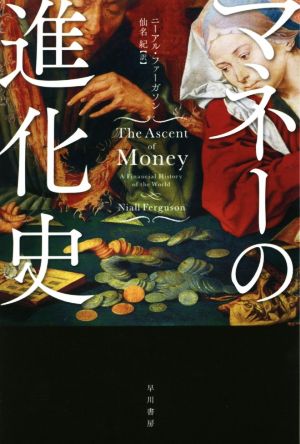マネーの進化史 の商品レビュー
金融学の学び始めに読むには少々難易度が高い本だった。 終章にて進化の過程を金融と生物の間で共通点を見出していた部分が、一番感覚的にスっと理解できた。
Posted by
人類の進化の裏側にはマネーの進化があったのだ. という本. 面白いけど,話の難しさと史実に忠実に沿うことで発生する話の展開や重要性の感じずらさが辛い... 似た本としてはこの本を解説してくれている野口悠紀雄の「マネーの魔術師」がおすすめ 金融は経済を円滑に回すための手段だっ...
人類の進化の裏側にはマネーの進化があったのだ. という本. 面白いけど,話の難しさと史実に忠実に沿うことで発生する話の展開や重要性の感じずらさが辛い... 似た本としてはこの本を解説してくれている野口悠紀雄の「マネーの魔術師」がおすすめ 金融は経済を円滑に回すための手段だったのに.いつのまにか金融が経済(ひいてはそれに参加する人々の生活)に影響しているんだなあとわかる. ミシシッピバブルが象徴的.それが複雑にシステム化・グローバル化された現代だと尚更だと言える. 日本の金融緩和政策は政府の債務を中央銀行に資産に付け替えることで,それはミシシッピ会社(フランスの経済をぶっ壊してフランス革命の遠因になった,金融緩和の父,ローが建てた会社)と同じことだと野口さんは述べている. 資産を守らねば. ===================== スイスの数学者 ダニエルベルヌーイ あるものの価値(value)は価格(price)ではなく効用(utility)によって決まる. ICO,ミシシッピ会社やエンロンとやってること変わらんな. ・無に金箔を貼り付けて夢を見させる ・夢(無)に魅了された人々がそれに投資する ・無を仕掛けた人サイド売り抜け,資金の使い込みをして鴨から金を搾り取る. ・夢が無であったことが露呈してバブル崩壊 ー>どうすれば防げる? ・相手の発言ではなくポジションを見る. サブプライムローン問題 不動産と株で価格の下落開始に9ヶ月の差 貧しさは金融業者の搾取ではなく、金融の仕組みがないことで生まれると言う主張→途上国の高利貸しが途方もない金利で金を貸す→金融包摂の価値はそう言うところにあるな インカ帝国 16世かに滅亡 "ピサロの一行にとって、銀が単に光って装飾用に使える以上の価値を持っていることが、インカの人々には不可解だった。"(当時ヨーロッパでは金銀は貨幣だった) "スペインの過ちは、貴金属の価値が絶対的なものだと思い込んでいたところにあった。カネの価値は、それを何と交換してもらえるかによって決まる。 供給が増えただけで、社会が豊かになるわけではない。" トークン=代用貨幣 昔は粘土の塊、今は銀行が発行する紙切れ カネとは信仰に近い信頼 金属がカネなのではない。信用を刻印されたものがカネなのだ カネが世界を回しているわけではない。実際に回っているのは、おびただしい数の人間であり、物資であり、サービスだが、それを可能にしているのはマネーだ。 サブプライム問題=債券の証券化 近代戦争の背後に金融あり.兵站戦 通貨のインフレ= 通貨の供給量が生産力を上回っている状態 通貨のパワー=生産力/通過供給量
Posted by
ユダヤ人はなぜ金融業に多いのか?なるほどそう言うことかと答えてくれます。マネーといってもキャッシュ(現金)の歴史ではなく、金融全般の歴史となっている。キャッシュはもちろん、債券、株、不動産証券化商品などの金融商品の歴史や貨幣そのものの歴史にも触れることができます。
Posted by
数ある経済史や経済人類学の本は多数あったが、これはとても読みやすい本である。最新の「リーマンショック」にも触れつつ、古代の貨幣社会までもを論じている。利子の起源や債券の起源など、保険の起源など具体例を挙げつつ解説する。 我々はマネーを憎みつつも、マネーから離れられない状況に来てい...
数ある経済史や経済人類学の本は多数あったが、これはとても読みやすい本である。最新の「リーマンショック」にも触れつつ、古代の貨幣社会までもを論じている。利子の起源や債券の起源など、保険の起源など具体例を挙げつつ解説する。 我々はマネーを憎みつつも、マネーから離れられない状況に来ていることを痛感した。マネーのない社会を最初に触れているが、即殺し合いの社会になり、男性の六割が戦闘で死に、女性の略奪が横行する社会になるという。そんな世に、もう戻れない。 後半では、著者の市場に対して非常に冷めた目で論じている。それを昨今の金融市場の混乱、ヘッジファンドの抬頭に翻弄される各国政府・・・それに対する処方箋は、すぐに出るものではないようだ。情報に対して人間は必ずしも合理的判断を下すことが出来ず、主観やマジックに踊らされやすい、ということを彼は看破して、本を終えている。
Posted by
結構なボリュームですが、金融の世界の幅広さ、面白さを感じ取ることができます。 まぁ(解説で野口悠紀雄さんもおっしゃってましたが)正直ちょっと難しいので、ちゃんと理解するなら複数回読んだ方が良いのかなという感じ。 株式には第3章が割かれていますが、その黎明期(なぜ生まれたのか?)...
結構なボリュームですが、金融の世界の幅広さ、面白さを感じ取ることができます。 まぁ(解説で野口悠紀雄さんもおっしゃってましたが)正直ちょっと難しいので、ちゃんと理解するなら複数回読んだ方が良いのかなという感じ。 株式には第3章が割かれていますが、その黎明期(なぜ生まれたのか?)や初期のバブルについて詳しく書かれていて、人間ってヤツは昔も今もしょうもない「錬金術」を使ってきたんだなぁとあきれつつも、考えさせられます。 グローバリゼーションについて書かれた第6章は、少し荒唐無稽な話という体で「米中戦争」の可能性について触れつつ、歴史から得られる教訓として「①グローバリゼーションが進んで安定的に見える状況でも戦争は起こりうる」「②平和が続くと衝突のシナリオは想像しにくくなる」「③現状に満足した投資家が危機に襲われると、市場は激しく崩壊する」という3点を挙げて警鐘を鳴らしています。 昨今のアメリカの状況を見ると、なんだか笑えません。。リーマンショックの最中くらいの本なので、最新の状況を踏まえるとどんな書きぶりになるのやら。 他にも債券、保険、不動産等、まぁ金融の世界って広いなぁと感じる本でした。決して読みやすくはないけど、類書の中ではまだ読みやすい方かも。
Posted by
マネーの進化史。公債、株、保険、デリバティブ、不動産etc.それぞれの金融商品がどのように生まれたのかを面白く分かりやすく書いてある良書。入門には丁度良い難易度だと思います。金融の世界は奥が深いですね。
Posted by
専門知識がない人間でも理解しやすい本。 入門書には最適。 リーマンショックの詳細な記述があれば、と感じる。
Posted by
500頁超の大部だが、マネーにまつわる4000年の歴史を紐解くには、それでもまったく紙幅が足りないだろう。その証拠に、本書には数式がひとつしかでてこない(ブラック・ショールズによるオプションの価格決定式 p.439)。 さすがにこれだけ分量があると、ざっと一回読んだだけではぼん...
500頁超の大部だが、マネーにまつわる4000年の歴史を紐解くには、それでもまったく紙幅が足りないだろう。その証拠に、本書には数式がひとつしかでてこない(ブラック・ショールズによるオプションの価格決定式 p.439)。 さすがにこれだけ分量があると、ざっと一回読んだだけではぼんやりとアウトラインが見えてくるだけ。が、これが大変おもしろい。 人類史の動かした大きな歴史上のイベントの陰には、いつもそれを駆動する巨大な資金を融通する仕組みや人間が存在してきた。 ともすれば「陰謀論」とくくられてしまいそうではあるが、戦争と帝国主義の裏で金融の仕組みは巧妙に進化してきたことが、歴史的事実として提示されていく。 いまでは当たり前になった金融の仕組み(国債、社債、保険、不動産売買)のすべては、一握りの強欲な天才の頭の中で生まれた野望の落とし子だといえるだろう。 暴落や恐慌を生まれるのは、それらを国際的に売買する仕組みが確立されて、市場が大衆に解放されたのちの話。時折飛来するブラック・スワンによって、世界は混乱の渦の中へ何度も突き落とされることになる。 群集心理、また自然界の営みはいとも簡単に、そして不合理な理由で“専門家”の思いもしない振る舞い(のちに計り知れない衝撃)を市場にもたらす。投資が、投機のリターンをインセンティブとするかぎり、市場の熱狂はいつか終わるのだ。 金融のシステムは生き物のように進歩と交代を繰り返しながら少しずつ前には進んでいる、と著者はいう。ただ、現代を生きる人間は、いまださまざまな認知バイアス(p.472)から、過去の金融史から判断の種を探すことができないでいる。 まだ大丈夫、たぶん自分だけは大丈夫。あのような参事は二度と起きない。根拠なき、または見せかけの根拠に基づいた人々の投機熱は、市場と実体経済の乖離を限界まで広げていく。 大衆を熱狂に連れ出すのは、不確実性を確からしく見せる「よそおい」だ。不確実性は成功の物語によって希釈され、上等な生地のスーツに身を包んだバブルの使者があなたのもとに訪れる。 あとは誰が一番最初に降りるのか? チキンレースは続いていく。 何度でも同じ過ちを繰り返す人類は、特に金融市場においては欲にほだされた集団的健忘症患者に見える。 あとがきで野口悠紀雄氏は、 「マネーがあるから人間が貪欲になるのではない。人間が貪欲だから、それがマネーの挙動に現れるのだ。「マネーがなくなればユートピアが実現する」などという考えは、単に幼稚であるばかりでなく、危険なものである」(p.502) と書く。 マネーを一般に「交換を媒介する信用価値」とするならば、これは人類史上有数の大発明だ。同じく、規模の大きな生産活動を実現するための投資市場も、人類に豊かさをもたらす福音だった。 問題なのは、技巧をこらして「金で金を生んでやろう」と人々を駆り立てる投機マインドだ。結局のところ、市場を破壊しするのは人間の強欲だ(まぁ、つまるところ当たり前の話)。 倫理観を失った投機家と、良心を忘れた利子生活者(ランティエ)は、賢いようでいて醜く哀れに見える。 最後に1節引いておきたい。 「金融市場は人類を映す鏡であり、私たちが自分自身や自分たちを取り巻く資源をどのように評価しているかをつねに示している。 人類の欠点が、美徳と同じようにあからさまに映ったとしても、それは鏡のせいではない」(p.494) よく考えよう、お金は大事だよ。でもお金の歴史について学べば、もっと大事なものが見えてくるかもよ。
Posted by
- 1