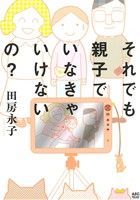それでも親子でいなきゃいけないの? コミックエッセイ の商品レビュー
色々な人の話あり、作者の話あり。 浄化しないと食べられない、という人の気持ちは ちょっと分かります。 何だかこう…気持ち悪いというか このままだといけない気分になるのが。 人に回して食べてもらう、という手もありますが 多分それをするには、さらに罪悪感が産まれて できないのだろう...
色々な人の話あり、作者の話あり。 浄化しないと食べられない、という人の気持ちは ちょっと分かります。 何だかこう…気持ち悪いというか このままだといけない気分になるのが。 人に回して食べてもらう、という手もありますが 多分それをするには、さらに罪悪感が産まれて できないのだろう、と思います。
Posted by
親子に関する違和感、体験や考えがまとめられたコミックエッセイ。 親に対するヘイトを口にすると「いくら嫌いでも苦手でも、育ててくれた親なんだから!」と説教してくる人いますよね。そういう風に言えるのってきっと真っ直ぐに育ってきた方で、純粋に羨ましいしすごいなと思います。 私の親はたぶ...
親子に関する違和感、体験や考えがまとめられたコミックエッセイ。 親に対するヘイトを口にすると「いくら嫌いでも苦手でも、育ててくれた親なんだから!」と説教してくる人いますよね。そういう風に言えるのってきっと真っ直ぐに育ってきた方で、純粋に羨ましいしすごいなと思います。 私の親はたぶん毒親ではなかったけれど、それでも私はなぜか小さい頃から家族という枠にずっと居心地の悪さを感じていて、高校卒業後すぐに実家を出て現在に至るまで両親、きょうだいとは滅多な理由がない限りは距離を置いて過ごしている。 だから、家族を嫌いであること、家族と関わらずに生きていくことを認めてくれるこんなエッセイがあると心底救われる気がします。 それでも親子でいなきゃいけないの?そんなことはない。 "毒親"は、決して親を罵るための蔑称ではない。病名でもない。 あくまでも子供が自分と親を切り離して考えるための言葉であって、誰かに判定してもらうものでもなく、自分の「つらい」という気持ちを基準に決めていいんだ。
Posted by
いやぁ、ヒドい。ウチの母親もかなりなものだけれど、ここまでひどくはない。こういう親御さんに育てられた人達は、一刻も早く自立出来るようになって、自分らしく生きることが出来るようになって欲しい。
Posted by
自分が壊れるまで、親子関係を続けなくてもいいのです というメッセージ。「母がしんどい」人たちは 親の過去の悪行を「許さない」人じゃなくて 「許して許して許しまくった挙句 限界を超えてしまった」人たちなんですよね
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「うちの母ってヘンですか?」の続編、今回も強烈な毒親オンパレードです。しかし、「毒親」としてテレビ等で簡単に消費されてしまう現状への違和感や、田房さんの母親再会など、それ以外のコンテンツも盛りだくさんです。田房ファンならぜひご一読を。
Posted by
一巻完結。 『母がしんどい』その後のエピソードと、 作者が同じ悩みを抱える方々を取材した、 人それぞれ様々な形の『毒親』話を収録。 様々な形があれど、少しでも共通する部分は必ずどこかにある。 一般人には伝わらない『毒親』の辛さを皆で共有し、対処法を学ぶ。そんなエッセイ漫画。
Posted by
同著『母がしんどい』(http://booklog.jp/item/1/404602884X)後日談。 母との関係や、出版後の読者からの反応、マスメディアや識者との対談を通して得たことをまとめている。 また「毒親」という言葉の認知を広めた人々のお一人である著者が、「毒親」という言...
同著『母がしんどい』(http://booklog.jp/item/1/404602884X)後日談。 母との関係や、出版後の読者からの反応、マスメディアや識者との対談を通して得たことをまとめている。 また「毒親」という言葉の認知を広めた人々のお一人である著者が、「毒親」という言葉が本来の意図が伝わっていなかったり、異なる方向に使われたりしている点も言及されていた。 断片的な情報に留まっているのは、著者自身もまた進行形で模索しているためだろう。(母娘関係にしても) 母との関係に重点が置かれていた(置かざるをえない訳だが)ものが、父の存在にも眼を向けている。 読んでいて思うのは、「父親の不在」だ。存在感が無い。 それは『ドラえもん』にも現れていたか。のび太とママの関係の暗い面だ。 世の中の男性は、自身の男性原理やさらに発展させた父性原理をどう育てるか、考えたことがあるだろうか? 家族の在り方についても考えさせられてしまうが、このコミックでは布石に留まる。 「家族」など幻想で、お互いにお互いの事など所詮気に留めておらず、思い込みの世界で生きている事が示唆されている気がした。 著者の家庭をこう言ってしまうのは本来、憚れるかも知れないが……機能不全にもかかわらず、ステレオタイプな“家族感”だと思い込み、それに振り回されている。 そしてこれは、どこの家庭でも起こりうる事だとも思う。
Posted by
- 1