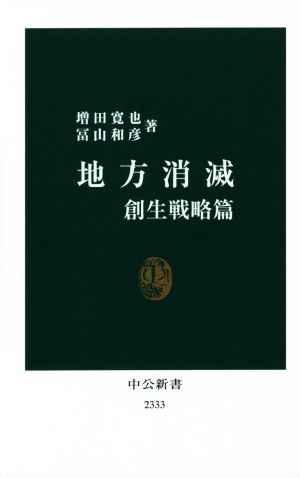地方消滅 創生戦略篇 の商品レビュー
冨山和彦が好きで読んだのだが、全体的に薄くて既知の内容が多いという印象。 地方が消滅する最たる理由は人口流出だが、それによりインフラ維持もできず、土地に留まる理由が弱化していく。農業や観光業のように土地に留まる産業が活性化すれば、それに付帯した事業が持続されるが、そもそも人口減...
冨山和彦が好きで読んだのだが、全体的に薄くて既知の内容が多いという印象。 地方が消滅する最たる理由は人口流出だが、それによりインフラ維持もできず、土地に留まる理由が弱化していく。農業や観光業のように土地に留まる産業が活性化すれば、それに付帯した事業が持続されるが、そもそも人口減で農業離れしていくと、後は観光業頼みとなっていくが、そこでの外資の役割については、慎重な判断を要する。この本に書かれるが、雇用の中身を地元の人に聞くと、清掃とかリネン業務とか、年収100万〜200万円という仕事が中心で、他のより高い収入を期待できる仕事は、季節労働者を増やしたり、外部から雇用されるようだ。 先の都知事選で石丸候補が東京一極集中の解消による地方活性化を説き、都知事なのに地方を活性化させるというロジックの複雑さに疑問を感じた有権者も多いと聞く。過密問題を解消するのは良いが、ネットワーク効果を損なえば収入が減り、中途半端に地方に分散させたことで却って日本全体のコストは増す。 地方は最早潔く諦めるべきとの論者もいるが、やはり考えるべきは、海外に移管不可能な、土地の制約における産業の合理化や集中についてを考え直す事かと思う。資本主義のロジックに従うならば、ある種の区画整理というか、地方単位でのM&Aが進むことで、撤退する地方も出て来て、それがために集中投資できる地方が生まれるという考えだ。 いや、そんなことは全くこの本に書かれている事では無く、私の独り言。ちなみに本書では、地方発のイノベーションとか、大学の役割とか、自動運転やドローンなどの連結するテクノロジーについて触れている。確かに、いずれも重要な事だ。
Posted by
前著の第二弾です。 具体的にどのようなプロセスで、どのように人口維持をするべきかがまとまっています。 と同時に誤った解釈も載っており役立ちます。
Posted by
少子高齢化による「人口オーナス」の克服には、「選択と集中」と「生産性の向上」が欠かせないことが、豊富な事例と筆者らの経験から詳述されている。
Posted by
「地方消滅」のスピンオフ。 すべての自治体がグローバル社会で戦う必要はない。ローカルにはローカルのサイズ感と稼ぎ方がある、という切り口。 ローカルに差別的、との評価もあるようだが、地域それぞれでいいじゃん、というのは実はこの数年のバズワードである多様性の議論でもあるんだよなあ。
Posted by
地方創成に関して、とても良い議論が展開されていると思います。専門的なテーマになるので万人向けの本ではないですし、2015年のほんなので少し古さを感じるところがありますが、このテーマに興味を持っている方には是非、読んで頂ければと存じます。
Posted by
図書館で借りて軽く読了 メモすべき部分の要約 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【自分の意見なし(ややネタバレ)】 まず、全体の現状としてブラック企業の蔓延がある。かつては雇用のために低賃金でも価値があったが今は人手不足なので雇用が減っても問題ない。white...
図書館で借りて軽く読了 メモすべき部分の要約 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【自分の意見なし(ややネタバレ)】 まず、全体の現状としてブラック企業の蔓延がある。かつては雇用のために低賃金でも価値があったが今は人手不足なので雇用が減っても問題ない。white企業が推進されていくべき。地方固有の現状としては会津若松市は福島県というだけで放射線の条件は仙台よりも被害が少なかったはずが人が来なくなっている。このような人口減少をうけての現状があるが、これからの展望として人手不足が逆に「必要は発明の母」というように介護ロボットや自動運転やその他創意工夫のアクセラレータとなると考えられ、例として東京大学と東北大学の東日本連合や高齢者が元気なうちに地方回帰されて地方での経営の訓練させることをしていくことが挙げられる。 その際「小さな東京」にならないようにすること、キャッシュレス化を進めることにきを付けるべきである。事例として金沢市は新幹線開通で東京派閥になったが、福井への開通による影響を踏まえ固有性をかんがえていくべきということがある。宮崎県のシーガイアは東京化の失敗例。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 現状の例外として会津若松市があり、人で不足による議会の倦等を防ぐため夜間議会で傍聴者を増やすなど議会改革に熱心である。県議会市議会などに行ってみたくなった。
Posted by
特に東北における地方創生のビジョンが具体的で面白い。疑問点もあるけど、現代日本の東京地方における問題について細かく分析している。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読み終わって時間がたってしまったためはっきり覚えていない。 しかし増田寛也の「地方消滅」が超話題になったけど、その後に冨山和彦との対談本を出していたのは、正直言ってしらなかったな。 ふたりのそれぞれの本を補足したような対談だったけど、反抗心からすれば、「それができれば苦労しないよね!」と思わないでもない。 しかしたとえ理想論だとしても、「どうなるんだろうねぇ」と諦観するのではなく、「政策遂行と経営遂行の現場で目前の現実問題に対峙する一方で、全国的かつ長期的な視点で鳥瞰的に問題の構造を分析、理解」することは大事なんだろう。
Posted by
2020.1.21 6 よかった。ローカルからグローバルへ。地方の強さ。強み。 人手不足で生産性向上の下地ができた。一次産業は規制するところと緩めるところ。 簿記の凄さ。ブラック企業の淘汰。年収をあげていく。
Posted by
【ノート】 ・著者の一人である増田氏による前著「地方消滅」が総論的なものであったのに対して、本書はかなり具体的に踏み込んだものになっている。 ・本書は知事経験者である増田氏と、東北で経営者として活躍している(らしい)冨山氏との対談形式になっている。このためか、地方自治における実...
【ノート】 ・著者の一人である増田氏による前著「地方消滅」が総論的なものであったのに対して、本書はかなり具体的に踏み込んだものになっている。 ・本書は知事経験者である増田氏と、東北で経営者として活躍している(らしい)冨山氏との対談形式になっている。このためか、地方自治における実例や弊害についての言及が具体的で分かりやすい。例えば「必要なのは共働きで500万稼げる仕事(冨山 P37)」や、「首長が変わると議会がガラリと変わる(増田 P89)」などという発言はかなり具体的。また、悪しき平等主義のため、余裕があると「選択と集中」を実行することができない、というのもリアルなご意見。「北海道の農業は(略)可能性が開けている(増田 P49)」というのは道民としては嬉しい発言だが、あくまでも「可能性」だからね。 ・中でも、例えばコンパクトシティという考え方について、日本では移住を強制できるわけではないとし、そのような強制移住ではなく、高度経済成長時代に拡散し過ぎた人口分布を適正値に戻すことによって、人口減少を前提として組み込んだ自治体の在り方を住民と共に作り上げていくというのは大事な提言であり、今後の日本の行く末をわがこととして考える時に、かなりの説得力を持つと感じた。ちなみに、コンパクトシティ政策が進んだ場合、近年顕在化している野生動物の侵食は拡大すると考えるべきだろう。 ・自分にとって最も印象深かったのは増田氏の次の発言。「地方創生の戦略を考える上で、私が一番増やしたいと思っているのは、地域の大学が核になって、地域が本当に求めているニーズを汲み取り、解決する仕組みをつくることですね。(P156)」ただ、これを可能にしようと思ったら今の文科省の制御は変えていかないと実現は困難。 ・実はこの本については、最近、大変お活躍(誤植じゃないよ)の増田氏が、対談形式という執筆の労を取らなくてよい形式で好きなことを放談してるんだろうということで軽視してたのだけど、対談ゆえに読みやすく、それでいて随所に二人の知見がキラリと輝いているといった印象で、自分としては読む甲斐のあった本でした。
Posted by