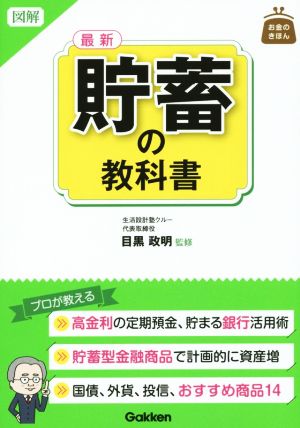図解 最新貯蓄の教科書 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
貯金をふやすために、家計の どこを削るべきか、銀行や信金別 定期預金や手数料などの比較や、保険の種類や活用法、投資や株・外貨、事例別貯蓄戦略などがわかりやすく書かれている本だった。 10年前(2015年)に発行された本だったが、内容は、今どきメディアなどが言っていること(先取り貯金やiDeCo、NISAなど)と ほぼ同じことがかいてあり、驚いた。 本の情報は古いが、メディアなどで ある程度知っていたため、読みながら心の中で訂正しつつ、自分の家計をふりかえりながら今後のことについて考えることができた。 投資や株・外貨、NISA、iDeCo、保険などは、全く興味がないし、したいとも思わないため、その部分は、とばして読んだ。
Posted by
貯蓄の仕方を話していく本 最後の方の生活費例は参考になる、金融商品あまりいいのないよなあ 貯まる仕組みを作る、家計簿で確認、固定費見直し、 銀行:メインとサブ、手数料 金融商品:国債、社債、投資信託、インデックス、 ライフイベント:結婚式、住居、車、養育費 住居10、食費・外食...
貯蓄の仕方を話していく本 最後の方の生活費例は参考になる、金融商品あまりいいのないよなあ 貯まる仕組みを作る、家計簿で確認、固定費見直し、 銀行:メインとサブ、手数料 金融商品:国債、社債、投資信託、インデックス、 ライフイベント:結婚式、住居、車、養育費 住居10、食費・外食5、光熱費1.5、娯楽2、保険1.5、生活用品等1、通信1.5、被服2.5
Posted by
割と細かく項目ごとに分けて図も豊富に説明されていたので、仕組みや流れなどがわかりやすかった。 色々と種類がありすぎて訳がわからない…と思っていた各種金融商品の違いも、なんとなくわかるようになってきた…ような気がする。 あと、巻末のケーススタディ解説は参考になった。 --- メモ:...
割と細かく項目ごとに分けて図も豊富に説明されていたので、仕組みや流れなどがわかりやすかった。 色々と種類がありすぎて訳がわからない…と思っていた各種金融商品の違いも、なんとなくわかるようになってきた…ような気がする。 あと、巻末のケーススタディ解説は参考になった。 --- メモ:公社債投信@98p:一般的には「長期公社債投資信託」のことを指す メモ:投信のリスク@116p:債権<株式、国内<海外 メモ:地方債@102p メモ:投信のコスト@121p:長期投資する場合は販売手数料よりも信託報酬に注意 メモ:コストの低い投信@127p:アクティブ型<インデックス型<ETF メモ:確定拠出年金@136p:運用益非課税、所得税、住民税の軽減など、税制上のメリットあり メモ:NISAの対象@147p:預貯金や公社債投信、個人向け国債などには利用不可 メモ:子育て世代のおすすめポートフォリオ@185p:普通預金25%、定期預金25%、個人向国債(変動10年)40%、投信(国内債権型)10%
Posted by
- 1