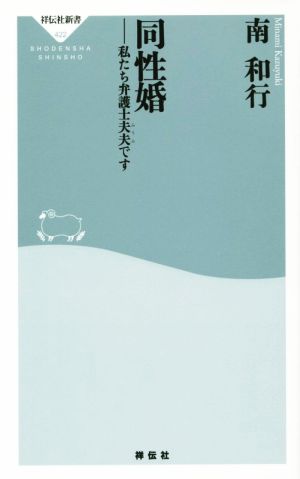同性婚 の商品レビュー
性的少数者のために新たな権利や法律を作るのではなく、元々同じ人間として既に権利や法律の下にいることを社会が認識するのが必要だろう。 何故同性愛者だからと枠外に出されなくてはならないのか。そもそも結婚制度とは何か、などを考えさせられた。
Posted by
ゲイの弁護士カップルの一方の人が書いた本。同性婚が法律的に認められることを求めて、日本の法律とか法律を取り巻く社会のあり方に一石を投じている感じかな。 自分としては、同性カップルも異性カップルを同じような権利を行使できるようになればいいとは思うけど、それが結婚というものに集約され...
ゲイの弁護士カップルの一方の人が書いた本。同性婚が法律的に認められることを求めて、日本の法律とか法律を取り巻く社会のあり方に一石を投じている感じかな。 自分としては、同性カップルも異性カップルを同じような権利を行使できるようになればいいとは思うけど、それが結婚というものに集約されていくのは何だかなと思っている。利便性とか考えると、現状では結婚ということになってしまうのはわからんでもないけど、それが残念。同性カップルにせよ、異性カップルにせよ結婚しなくてもお互いを信頼して一緒に生きていけるようであればいいと思うんだけど、甘ちゃんかしらん。だから、結婚なんて制度がなくなってしまえばいいと思うし、戸籍とかも現日本の結婚制度への縛りになるものとしてなくなってしまえばいいと思っている。 この本も最終ゴール、勝ち取るべき権利が結婚・婚姻に向かっているようなんだけど、この本の最後の最後のところで、著者とパートナーとパートナーの未成年被後見人と著者の母親の4人で著者の兄とその妻と息子のところへ行き、みんなで遊んだ一日のことが書かれていて、それがすごくいいなと思った。血とか法律とかの結びつきなんてどうだっていいじゃないか。気の合う者、そのときなじむ者どうしが自由につながれるほうが理想だな。
Posted by
この手の本は必要だと思いつつ、どうしてもモヤモヤしてしまうことが。 それは、マイノリティ同士のカップルだと、パワーカップルばかりがメディアに出てきてしまうこと。構造上仕方がないとわかっていても、モヤモヤしてしまう。 なんとなく、弁護士とか美容師とか大学教授とか医師とか、手に職系(...
この手の本は必要だと思いつつ、どうしてもモヤモヤしてしまうことが。 それは、マイノリティ同士のカップルだと、パワーカップルばかりがメディアに出てきてしまうこと。構造上仕方がないとわかっていても、モヤモヤしてしまう。 なんとなく、弁護士とか美容師とか大学教授とか医師とか、手に職系(かつ、一般的に比較的「高給」と考えられている職業)でないとマイノリティとしては生きていけないような感じになってしまうのであれば、やはり社会としては不健全だと思う。 こうした「手に職」系にマイノリティが多いように思えてしまうのは、それらが職業的にチームプレイでなく個人プレーが可能であり、それがゆえに同調圧力が低いコミュニティに属しているから可能になっている側面は無視できないように思う。そうした、同調圧力の低い、個人プレーが可能な手に職系に付かないと、自分のアイデンティティが脅かされてしまうのであれば、マイノリティの人々の職業選択の自由が侵害されているのであって、由々しき問題であるように思う。 どんな性別でも就きたい仕事に就けて、子どもが欲しければもうけることができて、日本もそんな社会になればいいなぁ。 憲法の問題は重要だけど、この本での議論も含めて、まず憲法を活用してみることが日本社会のあらゆる場面では必要な気がする。この本の話とは関係ないけど、日本にも憲法裁判所があったらいいのにね。
Posted by
P14「同性婚を考えると言う事は、男女とは何か、結婚とは何か、家族とは何かを考えることである。」 P 44「私はせめて、小学校中学校、高校での教育の中で、世の中には同姓愛者が存在すると言うことをきちんと知ることができればよかったのにと思う。自分は教科書には載っていない存在だと思...
P14「同性婚を考えると言う事は、男女とは何か、結婚とは何か、家族とは何かを考えることである。」 P 44「私はせめて、小学校中学校、高校での教育の中で、世の中には同姓愛者が存在すると言うことをきちんと知ることができればよかったのにと思う。自分は教科書には載っていない存在だと思い、湧き上がる自然な気持ちを否定するしかなく、自分で自分を認めるまでにずいぶん回り道をしてしまった事は残念だ。」 P110「一方で、法令データ提供システムの法令用語検索で同性愛あるいは同性と検索してみても、該当するデータはありませんと表示される。」 P115「2人の愛情は結婚のきっかけとして必要かもしれない。しかし、結婚には、カップルを中心とした家族として周囲から承認され、保護されると言う社会的な効果もある。」 p127 「民法772条は「子供が生まれる枠組みこそが結婚である」と言う家族モデルを提示する。しかし、この民法772条が提示する家族モデルから外れた家族は、家族として法律上保護されず、個人としての存在すら認められないと言う困難を抱えている。」 P1 137「同性カップルの家族、あるいは同性カップルと子供の家族が法律上保護されるとき、つまり同性婚が法律で認められる時こそが、家制度の最後の名残である民法772条の役割が終わる時なのではないかと考えている。」 150「少なくとも(同性カップルが子育てをする)と言う事実が、子供を不幸にするのではない。「子供は不幸に違いない」と言う人々が、子供を不幸にするのだ。子育てをしている同性カップルの家族の巡り合わせを肯定する社会、多様な家族のあり方をうけいれられる社会こそが、子供を幸せにするのだ。」 162ページ「クリントンが演説の冒頭で「all human beings are born free and equal in dignity and rights」つまり「全ての人は、生まれながらにして自由かつ平等に尊厳と権利を受けている」と述べた事は、同性愛者の人権は特別なものではないと言う考えを端的に示すものである。」 163ページ「LG BTの課題の解決は、「少数者も権利を認める」ことではなく、「もともと同じ権利がある」ことを前提に、人権保障を阻む障害を除去する視点でなければならない。この視点はLG BTの当事者が抱える困難を社会的課題として解決する場面にとどまらず、同性カップルの家族としての権利を法律上の同性婚の制度として認めるかどうかにおいても忘れてはならない視点だ。」 167ページ「憲法24条1項が、封建的な家制度のもとで女性の自由や人権が奪われていたと言う実情を背景に、婚姻における女性の自由な意思決定と家庭内における男女の平等を希求して制定されたからに過ぎない。」 169ページ「憲法24条1項が「両性」と言う言葉を用いていることだけを持って、同性婚を積極的に禁止する趣旨だと声高に唱える事は、そもそも憲法が個人の人権を保障する存在であることに反する。」 182ページ冒頭「この条例(渋谷区のパートナーシップ制度」)は、行政と言う公権力が、同性愛者を含めLG BTすなわち性的少数者が社会で生活していると言う事実と、当事者が偏見や差別に脅かされていると言う実情を認め、偏見や差別を打破するのは当事者の努力や行動ではなく、むしろ当事者を取り巻く人々や社会の意識が変わることによるべきと宣言するものである。」 187ページ「しかし形や異性愛者であることを当たり前に生活してきた異性愛者にとっては、異性愛者しか存在しないことを前提に形成された社会は、生きやすくそして自身の性自認について立ち止まって考える必要もない社会である。」 188ページ冒頭「葛藤を抱いていない人(異性愛者)の無理解は、罪ではない。」
Posted by
帯文:”自分らしく生きたいすべての人へ。同性愛者が幸せに生きる社会は、「あなたらしさ」が大切にされる社会です―木村草太(憲法学者)” ”私は、ブームをブームで終わらせず、社会の当り前のこととする試みとして、「同性婚」について語ろうと思う。” 目次:はじめに、第一章 私たち弁護士...
帯文:”自分らしく生きたいすべての人へ。同性愛者が幸せに生きる社会は、「あなたらしさ」が大切にされる社会です―木村草太(憲法学者)” ”私は、ブームをブームで終わらせず、社会の当り前のこととする試みとして、「同性婚」について語ろうと思う。” 目次:はじめに、第一章 私たち弁護士夫夫です、第二章 同性愛者からの法律相談、第三章 結婚・家族とは何か、第四章 同性婚と憲法24条
Posted by
LGBTを理解して 認めなければ間違った方向に 向かい社会から排除され 人権が失われていく… これからの家族の新しい在り方 の幸せなモデルの先駆者となった 勇気ある南、吉田弁護士に拍手です。 少子高齢化が進み、日本はかつて 味わったことのない社会になりつつ あります。 確かにLG...
LGBTを理解して 認めなければ間違った方向に 向かい社会から排除され 人権が失われていく… これからの家族の新しい在り方 の幸せなモデルの先駆者となった 勇気ある南、吉田弁護士に拍手です。 少子高齢化が進み、日本はかつて 味わったことのない社会になりつつ あります。 確かにLGBTはなるものではなく 時間をかけて気付くものですし… 性的嗜好と性自認は治療法がありません。 それにしても読み始めると止まらず 小説のような面白さがありました。 かく言う僕も本当のところはわかり ませんが…女っぽい男ですし… 気持ちの上ではわかっていたつもり で…本当はゲイなのかもしれません。 (惚れるのはいつも男性です。) それでももがき続けてきたことから ようやく救われたような… 安心感がありました。 どうしてかなぁ、多分、何もかも 弱者の立場に立ってくれているから だと気付きました。 唯、これだけは言わせてもらいます。 同性愛の性行を想像、歓喜、 表現するからヤラシーのであって この弁護士夫夫は心で何時も 繋がっているという硬い絆が あると言うことを… 忘れないでおいてほしい。
Posted by
著者の来歴の章はおもしろかったし、憲法や少子化と同性婚についての話もなるほどなあと興味深く読めたが、いまいち本として面白くない。他の方のレビューにあるように「なんで一冊の本にまとめたの?」ってところだろうか……。 別の本のレビューで私は「LGBTが利用されてもかまわない」と言っ...
著者の来歴の章はおもしろかったし、憲法や少子化と同性婚についての話もなるほどなあと興味深く読めたが、いまいち本として面白くない。他の方のレビューにあるように「なんで一冊の本にまとめたの?」ってところだろうか……。 別の本のレビューで私は「LGBTが利用されてもかまわない」と言ったが、この本を読み終えたあと、ああそれだと、性的少数者はいつまでも"消費される側"でしかないのか……? と思ったりした。笑いの種として、萌えのネタとして、一時のコンテンツ止まりになってしまうのではないか。つまりLGBTがオワコンとしてまた忘れ去られてしまう時をも許容することになるのではないか。それは困るな。「LGBTブームをブームで終わらせない」という言葉の意味を改めて感じる。
Posted by
法律で整備された日常に生きていると、見落としてしまうこと。同性パートナーの生活において、どこに問題があるのかを理解できた。「きのう何食べた?」との併せ読みで、より近い問題と感じられるかも。 ダ・ヴィンチのレビューきっかけ。
Posted by
夫夫(ふうふ)二人とも弁護士。 「きのう何食べた?」を読んでいる人は驚かないだろうことがたくさん書いてあります。 「きのう何食べた?」を読んでいても驚くのは、同姓婚カップルの子育てについてです。 自然に子どもに恵まれるということのない同姓婚だけれど、本来的には異性婚で不妊のカップ...
夫夫(ふうふ)二人とも弁護士。 「きのう何食べた?」を読んでいる人は驚かないだろうことがたくさん書いてあります。 「きのう何食べた?」を読んでいても驚くのは、同姓婚カップルの子育てについてです。 自然に子どもに恵まれるということのない同姓婚だけれど、本来的には異性婚で不妊のカップルと状況は変わらないはずなのに、子どもを望む人がいること自体無視されています。 同姓婚の人は子育てをあきらめていると勝手に思っていた自分に、自分の想像力のなさに、驚きました。 生物学的には自分の子でなくても、パートナーと一緒に子育てをしたいとまじめに望む人がいるなら、生みの親の庇護が受けられない子どもを育ててもらえるわけで、個人の幸せと公共の福祉が共に実現するいい方法だと思います。
Posted by
男2人で「結婚」し、大阪で法律事務所を立ち上げたという弁護士が、法律における婚姻関係のあり方を整理し、法律では保証されていない同性カップルの権利について論じたもの。 同性云々について考える前に、法律の役割やあり方についてまず考えさせられた。「そもそも憲法は、個人を尊重し、あら...
男2人で「結婚」し、大阪で法律事務所を立ち上げたという弁護士が、法律における婚姻関係のあり方を整理し、法律では保証されていない同性カップルの権利について論じたもの。 同性云々について考える前に、法律の役割やあり方についてまず考えさせられた。「そもそも憲法は、個人を尊重し、あらゆる人の人権を尊重するために存在する」(p.168)といった部分や、「あまねく人権保障とあらゆる個人の尊重を希求する憲法の価値」(p.171)、といった部分が、本書で展開される法律の議論の大元となっていることが分かった。憲法24条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」の「両性」が、女性の権利を向上させるための文言である、というエッセンスを汲み取る行為が重要であるというのも分かった。 ただ結局は「自然の摂理」や、自民党幹事長の谷垣氏の「伝統的価値観」を持ち出すまでもなく、同性婚の是非は社会全体の感情の問題に帰結する訳で、そのような中で法律の役割とは、「たとえ誰かが個別に非難し傷つけてこようとも、『大丈夫、あなたたちの家族の存在は法律でちゃんと認められていますよ』ということ」(p.148)、というのはなんか心許ないなあ、と思った。たとえ法律で色んな権利が認められても、当事者の人たちにとって、カミングアウトをしたことによる不利益を被り、心理的なダメージも大きくなるのではないか。著者は「葛藤を抱いていない人の無理解は、罪ではない」(p.188)というが、あまりに寛容に過ぎる感じがする。時間が解決するものなのか、よく分からないが、憲法24条の「両性」のエッセンスを汲み取らないといけないくらいには女性の権利が当時と比べて向上している現在のように、今後「社会全体の感情」が変わっていくことがあるのかもしれない、と思った。(15/08/21)
Posted by
- 1