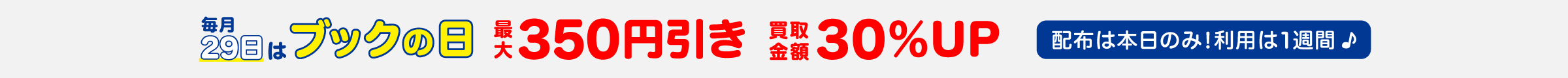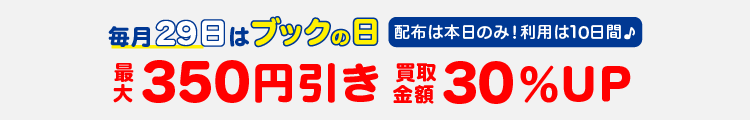初等数学史(下) の商品レビュー
原書名:A HISTORY OF ELEMENTARY MATHEMATICS 第3篇 近世の初等数学(算術;代数;幾何学と三角法;数学教育に関する近代的運動)
Posted by
近世編はヨーロッパを中心として進んでいく。中世において三角関数が登場したにも関わらず、ルネサンスを迎えるまではただ金勘定のための技術でしかなく、しかも卑しい物として扱われていたためむしろ衰退してしまっていたというのには驚かされる。その一方で17,18世紀には負数、虚数、複素数、...
近世編はヨーロッパを中心として進んでいく。中世において三角関数が登場したにも関わらず、ルネサンスを迎えるまではただ金勘定のための技術でしかなく、しかも卑しい物として扱われていたためむしろ衰退してしまっていたというのには驚かされる。その一方で17,18世紀には負数、虚数、複素数、無限級数などが一度に開花したのも驚きである。残念ながらなぜこのように急激な発展をしたのかについては直接触れられていないが、一つには数学という学問が広く学ばれるようになったことが原因だろうこと思う。近代教育の祖であるペスタロッチの名が度々登場し、教育制度についての考察にかなりのページを割いていることから著者もそのように考えていることが伺える。
Posted by
- 1