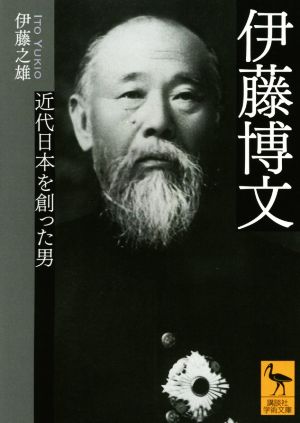伊藤博文 近代日本を創った男 の商品レビュー
伊藤博文及び明治の近代国家創設を知るための必読書だと思う。当時の書簡の遣り取りを掘り起こし、事実関係を丁寧に整理しており、網羅性の観点からも秀逸。また、全般的に分かりやすい。 特に伊藤博文のネガティブな評価を覆す思いが意図としてあり、彼の真意を理解することで、改めて彼の功績を評価...
伊藤博文及び明治の近代国家創設を知るための必読書だと思う。当時の書簡の遣り取りを掘り起こし、事実関係を丁寧に整理しており、網羅性の観点からも秀逸。また、全般的に分かりやすい。 特に伊藤博文のネガティブな評価を覆す思いが意図としてあり、彼の真意を理解することで、改めて彼の功績を評価することができる。 以下引用~ ・こうして木戸は、大蔵省・民部省という最重要官庁の次官から局長にあたる中枢ポストに、大隈・伊藤・井上馨という三人の腹心を送り込んだ。 ・(大蔵省時代)渡米中の伊藤大蔵少輔(次官クラス)等は政府に条約改正の準備を強く促していた。しかし、日本は欧米のような法律も制定しておらず、新しい有利な条約を結べる状況にはなかった。 ・伊藤は君主に主権があり、それが立法部・行政部・司法部に委任される形になるが、君主はみだりに委任を取り消せない、と憲法で規定し、君主権を制約する憲法を作った、と主張している。 ・(伊藤が西郷従道を参議に推挙するに関して)伊藤は、実力者の岩倉右大臣と連携を保ち、長州の盟友井上馨や山県ら長州派を固め、西郷従道や松方を通じて薩摩派にも影響を及ぼせるようになったのだった。 ・シュタインの説明は、君主権は神から授かったものであり、君主は専制的に行動してもよいという考え方を否定するためにできた考え方で、当時のヨーロッパの君主制についての最先端の学説、君主機関説であった。伊藤はシュタインとの会談で、その趣旨を理解できたのである。これで、伝統的に天皇専制(天皇親政)が行われていない日本に、その実態にあった憲法を作るための糸口がみえてくた、と伊藤は喜んだのである。 ・伊藤がシュタインから最も影響を受けたその教えは、(1)行政権が優位であるべきだが、行政権・君主権・議会の権限の三権が緊張関係にあることが望ましい(君主権と言えども制限されるべき)、(2)憲法はその国の固有の歴史を反映したものであるべきだ、(3)歴史は変化するので、憲法の運用や制度も変化していくことが自然であること、等である。 ・天津条約の締結の交渉に関して、清国行の際に、天津領事であった29歳の原敬を見出したことも、大きな副産物だった。 ・伊藤が憲法政治を定着させることが可能であったのは、(1)明治天皇の信頼を得、薩摩系の有力者とすら協調できる明朗な人柄、(2)英語力や中国・日本の古典などに裏付けられた法律や経済・歴史などに対する深い洞察力と西欧の規範への理解、(3)現実主義の立場から内政や外政を処理する実務能力と、「剛凌強直」な生活による政治への決断力、などがあったからだった。 ・(伊藤体制の凋落)日清戦争後に、山県有朋を盟主とする山県系官僚閥が形成されたことである。 山県の狙いは、専門家集団としての陸軍が、なるべく政府から干渉されない形で自立することだった。 ・伊藤は、薩長や藩閥になるべくこだわらない形で、新しい近代国家を作ろうと尽力した。1893年、第二次内閣の時に文官任用令と文官試験規則を公布したのは、それを象徴している。 ・伊藤と明治天皇がいなくなったことで、二人が作った明治憲法の改正を推進する人物がいなくなってしまった。また、日清・日露の両戦争に勝ったため、天皇の死後、偉大な明治天皇が発布した憲法としての権威がつきすぎ、改正を発想することすら政治的に危険になった。 ・イギリスにも2ヶ月も滞在して調査したように、伊藤は議会の権限の弱いドイツモデルに固執していたわけではなく、議会の権限が強いイギリスモデルも将来の視野に入れていた。 伊藤のリーダーとしての資質は、(1)しっかりとした学識にもとづき、長期的な展望を持っており、(2)また当時の日本が置かれていた現実の厳しさもよくわかっていた、(3)それにもかかわらず、現状の厳しさに絶望しない楽天的な性格を持っていて、強い決意で、しかも現実的な手法で問題を一歩一歩解決していったこと、にあるといえよう。このような伊藤博文と日本の近代の歩みの中に、厳しい状況にある現代の日本を改革していくにあたって、政治家などのリーダーや私たちの生き方がどうあるべきか、というヒントが見出せるように思えてならない。 奇妙なことであるが、伊藤の伝記を書く作業を進める中で、安重根の人柄を知るにつれ、立場こそ異なるものの、正義感や意志の強さ等、伊藤のそれと似ている面が多いことがわかってきた。そのため、伊藤の暗殺者である安重根に、信念に生きた人間として、伊藤と共通する親しみすら感じる。本書が、伊藤博文や日本の近代化を理解するためのみならず、日韓や東アジアの相互理解と永続する連携のための一助になれば、幸いである。
Posted by
初代総理大臣として内閣制度を創設し、みずから中心となって大日本帝国憲法を制定しながら、木戸孝允や岩倉具視らの間をたくみに世渡りして出世した「軽佻浮薄」な人物、あるいは、旧憲法によって民主化の道を狭め、韓国では民族運動を弾圧した権力者、といったイメージで語られてきた伊藤博文。著者が...
初代総理大臣として内閣制度を創設し、みずから中心となって大日本帝国憲法を制定しながら、木戸孝允や岩倉具視らの間をたくみに世渡りして出世した「軽佻浮薄」な人物、あるいは、旧憲法によって民主化の道を狭め、韓国では民族運動を弾圧した権力者、といったイメージで語られてきた伊藤博文。著者が、歴史学の最新成果をふまえて、伊藤の全生涯と「剛凌強直」たる真の姿を描き切る、決定版評伝。
Posted by
山口県光市にある、伊藤博文記念館を訪問した事を機会に、読み始める。記念館にある伊藤の愛用品を眺めつつ、遠い、明治という時代を思う、なかなか大変な時代であったのでは、と。またこの本も結構の大著、読むのも大変です。
Posted by
明治時代について現在が見渡すとき まず江戸からの維新の成功と 第二次大戦に至ってしまった失敗との区切りがある 日本の歴史に残る大宰相が政治活動をするのに意見の違う他者を斬る時代から現在への転換は 成功であり 現在の自分が歴史の現代に対して分けて見えるのが敗戦であるから もっとも...
明治時代について現在が見渡すとき まず江戸からの維新の成功と 第二次大戦に至ってしまった失敗との区切りがある 日本の歴史に残る大宰相が政治活動をするのに意見の違う他者を斬る時代から現在への転換は 成功であり 現在の自分が歴史の現代に対して分けて見えるのが敗戦であるから もっとも江戸のまま第二次大戦に至るさまを思い描けないのと同じく 負けていなかったため現在と歴史の区切りをつけられないようすを想像してみるのも難しい 成功と失敗はなぜ生じたのか 何が生じせしめたのか 明治の歴史はどうであったのか 例えば責任はだれにあるか 普通選挙がなかったことを理由にわれわれでないと皆がいうのか お上のすることに理由はないのか ただ自らにかなうあたりしかありえないのか 現実をいやいや見つめるならば 日本にはどうやら明確に成功と失敗があるので その差を個々人の庶民信念としてあげつらわねばならない 隣の国やその隣の国やその周囲の国や お偉方やその周囲やそこに利益を関する周りやそのあたりにいるわれわれも 見て見ぬようではいられない ひとつひとつの行動を取り上げていってそこに良し悪しをつけていって それを歴史の成功と失敗に結び付けられるのか 人間の知性が処置できる分を過ぎているように思えるけれども それが歴史に学ぶことでもある
Posted by
伊藤博文の成し遂げた事績を考える内容を含む本を、読んだことが無い訳ではないが…正直、伊藤博文に関しては、個人的には「小中学生の頃に手にした、小遣い銭の千円紙幣に在った肖像画」というイメージの以上でも以下でもない…が、色々と「新しい状況への対応?」という現代のような時代であるからこ...
伊藤博文の成し遂げた事績を考える内容を含む本を、読んだことが無い訳ではないが…正直、伊藤博文に関しては、個人的には「小中学生の頃に手にした、小遣い銭の千円紙幣に在った肖像画」というイメージの以上でも以下でもない…が、色々と「新しい状況への対応?」という現代のような時代であるからこそ、伊藤博文のような先人の事績や人物が見直されるべきなのかもしれない。 或いは本書は、「伊藤博文という先人との新たな出会い」を演出してくれる存在だ。お薦めである!!
Posted by
1500822 中央図書館 かなり稠密に伊藤の生涯を述べている。明治維新を実際にもたらしたのは西郷木戸大久保の元勲なのだろうが、日本を真に国際社会に直面しうる「国家」に育成したのは、伊藤の役割が大きかったであろう。周旋の才、英語の素養?、明治天皇との関係など、コミュニケーション能...
1500822 中央図書館 かなり稠密に伊藤の生涯を述べている。明治維新を実際にもたらしたのは西郷木戸大久保の元勲なのだろうが、日本を真に国際社会に直面しうる「国家」に育成したのは、伊藤の役割が大きかったであろう。周旋の才、英語の素養?、明治天皇との関係など、コミュニケーション能力、バランス感覚、胆力などが素晴らしかったのに違いない。
Posted by
- 1