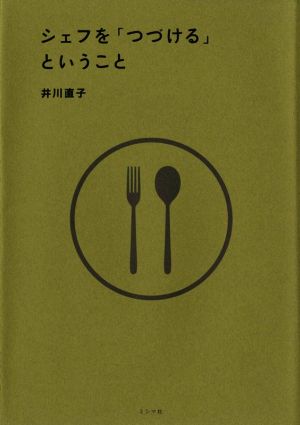シェフを「つづける」ということ の商品レビュー
たくさんの料理人の、それぞれの道。 十人十色、と言いますが、まさにそれ。 その職に就いたきっかけは様々で 続けようとした気持ちも様々。 何があろうと、何が起ころうと 最良だと思う道を見つけたいな、と。
Posted by
幅さんが2015年のドキュメンタリーで1番オススメと推薦した本。内容はイタリアに修行にでた料理人に10年後改めて取材をするというもの。自分の料理を追求し続ける人、料理のビジネスを楽しむ人、日本でもイタリアでもなくシンガポールで働く人、病気で倒れてしまう人と様々な料理人がいる。それ...
幅さんが2015年のドキュメンタリーで1番オススメと推薦した本。内容はイタリアに修行にでた料理人に10年後改めて取材をするというもの。自分の料理を追求し続ける人、料理のビジネスを楽しむ人、日本でもイタリアでもなくシンガポールで働く人、病気で倒れてしまう人と様々な料理人がいる。それぞれの生き方の中で厳しい飲食業界の中、「続ける」
Posted by
つづけていくことがいかに難しいか つづけるからこそ意味が出てくるのか この本に出てくるシェフたちは、ただ口々に 好きだから、これしかないから、つづけてこれた、ただそれだけだ と語っている。そこには驕りも謙遜もなく、ただの事実を述べてるんだと思う。 つづけていくこと、自分にはなにが...
つづけていくことがいかに難しいか つづけるからこそ意味が出てくるのか この本に出てくるシェフたちは、ただ口々に 好きだから、これしかないから、つづけてこれた、ただそれだけだ と語っている。そこには驕りも謙遜もなく、ただの事実を述べてるんだと思う。 つづけていくこと、自分にはなにがあるかな。
Posted by
「つづける」に括弧が付けられていることが読後にぐっとくる。 もちろんシェフたちの話なのだが、それ以上に「つづける」に重きがある。 だから飲食業には縁のない私にも、刺さることば、沁みることばの数々。 新年にふさわしい、静かな、強い一冊。
Posted by
タイトル通り、10年以上シェフを続けている人たちのお話。始めることは簡単だけど、続けることは難しい。本書には続けるためのモチベーションや思いがしっかりと書かれているので、弱気になったときに効きそうな気がします。行きつけのお店にいったとき、目の前の一皿がさらに愛おしくなりそう。早く...
タイトル通り、10年以上シェフを続けている人たちのお話。始めることは簡単だけど、続けることは難しい。本書には続けるためのモチベーションや思いがしっかりと書かれているので、弱気になったときに効きそうな気がします。行きつけのお店にいったとき、目の前の一皿がさらに愛おしくなりそう。早く行かなくちゃ。
Posted by
バブルが弾けた2000年頃、料理界ではイタリアンが大ブームだった。若き料理人は競って、イタリアで修行し、その経験を日本へ持ち帰った。そんな多くの料理人をイタリア時代から定期的に取材していた外食ライターが彼らの今を記す。 本書に登場するのはタイトルにある通り、シェフをつづけている...
バブルが弾けた2000年頃、料理界ではイタリアンが大ブームだった。若き料理人は競って、イタリアで修行し、その経験を日本へ持ち帰った。そんな多くの料理人をイタリア時代から定期的に取材していた外食ライターが彼らの今を記す。 本書に登場するのはタイトルにある通り、シェフをつづけている現役の料理人ばかり。ここまでたどり着くのに山も谷もあったが、今では自分の店を経営している。 ほぼ成功者ばかりの登場にちょっと期待はずれ。冒頭でイタリアの実績は日本でほとんど評価されない、と著者が述べているので、もうちょっと意外性のある人物を紹介するものだと思っていた。例えば、イタリアで修行したけど、今は料理から離れて、銀行マンや作家やホームレスやヒモになりました。というような人物。 期待した波瀾万丈な人生ドキュメンタリーではなかったが、「つづける」ことの苦しさ、美しさは伝わる。
Posted by
15人のシェフの10年前と今を書いた話。 全員の共通は「つづける」ということ。 迷っても、立ち止まってしまったとしても、そこでやめるのではなく、つづけてきた結果。 つづける、ことの大切さと難しさを感じた。
Posted by
かつてイタリアで取材した日本人シェフの10年後を訪ねる。 イタリアのレストランは、厨房のドアを開ければ日本人コックがうじゃうじゃいる、という時代があったそうだ。 つまり、「イタリアで修行をしてきた」というポジションも珍しいものではなくて、イタリア帰り飽和状態。 10年あまり...
かつてイタリアで取材した日本人シェフの10年後を訪ねる。 イタリアのレストランは、厨房のドアを開ければ日本人コックがうじゃうじゃいる、という時代があったそうだ。 つまり、「イタリアで修行をしてきた」というポジションも珍しいものではなくて、イタリア帰り飽和状態。 10年あまりで景気の変動もあった。その間シェフたちはどうしていたのか。 オーナーシェフであるかそうでないか、食事をするときに気にしたことはほとんどない。けれど、本書を読むと、料理人にとって経営というのが大きな難関であり、向く人と向かない人がいることがよくわかる。 経営にしても、料理そのものにしても、こうしたい、これをやってみたい、という気持ちがなければ継続するのはむずかしいのだ。それを、七転八倒しながら続けてきた人たちの話。中には、急に倒れて車椅子生活になってしまった人もいる。けれど、その人もシェフをつづけている。 僕も毎日料理をしているが、シェフというのは家庭の料理をつくるのとは、まったく、まるっきり違うのだ。なにか、敗北感。がんばろう。
Posted by
2003年のイタリアには、「どんな小さな村のレストランの厨房にも日本人がいる」くらいに多くの若者がイタリアで修行をしていたそうです。その時に取材した若きシェフ達のその後の10年を追ったドキュメンタリー。「10年で奇跡 30年で伝説」と帯にあるように、飲食の世界はそれほど厳しい。中...
2003年のイタリアには、「どんな小さな村のレストランの厨房にも日本人がいる」くらいに多くの若者がイタリアで修行をしていたそうです。その時に取材した若きシェフ達のその後の10年を追ったドキュメンタリー。「10年で奇跡 30年で伝説」と帯にあるように、飲食の世界はそれほど厳しい。中には諦めて別な道を歩んでいるひとたちもいるのでしょう。都会で一流店を構えるひと、田舎でその土地の食材を活かした料理を追求するひと、中国やシンガポールといった異国でのイタリア料理の発展に心血を注ぐひと。まったく別の生き方を余儀なくされたひと。 さまざまなシェフ達の生き方に、その道を究めることの難しさとその先にある喜びを教えられた気がする。 しかしこれほどまでに他国の料理を熱心に学び、このレベルで自国に持ち帰るのは善くも悪くも日本人くらいなものではないかと思うのですが、他の国ではどうなんでしょう。「○○人がつくった××料理」って、やっぱり一段下に見られると思うんですよね。すごいことだと思います。
Posted by
丹羽郡の車いすのシェフ伊藤さんの章は特にしみた。 他のシェフもみんなそうだけど、強い。負けない。くじけない。 いや、負けたりくじけたりもするけど、そこで終わらないってことなのかな。 で、10年。 10年で9割の飲食店が閉店していく中でそれでもその場にいつづけようする気持ちがひしひ...
丹羽郡の車いすのシェフ伊藤さんの章は特にしみた。 他のシェフもみんなそうだけど、強い。負けない。くじけない。 いや、負けたりくじけたりもするけど、そこで終わらないってことなのかな。 で、10年。 10年で9割の飲食店が閉店していく中でそれでもその場にいつづけようする気持ちがひしひしと伝わってくる。 なんていうか、無駄に肩に力をいれて「がんばってるんだ!一生懸命なんだ!負けるもんか!」って怒涛の前進をしていると何か壁にぶち当たった時なかなか立ち直れないのかもしれない。 眼の前に壁があったら、それを壊すだけが進む方法じゃなくて、例えば少し下がって壁のどこかに穴が開いてるかもしれないと全体を見てみる、とか、遠回りでもぐるりとまわりこんでみるとか、仲間を連れて来て階段を作るとか。 そういうあれこれを柔軟に考えられる強さってのが必要なんだと思った。 いやぁ、「シェフ」に限らずいろんな職業に置き換えて読むと、誰もがいろいろ考えさせられると思う。 「つづける」こと。この大変さをしみじみと。
Posted by
- 1