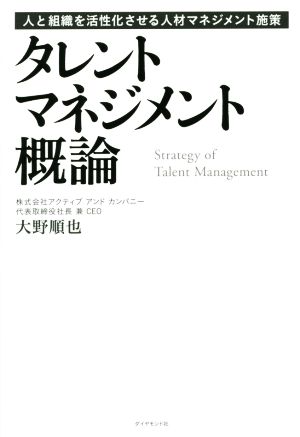タレントマネジメント概論 の商品レビュー
これからタレマネシステムに携わるため読んでみた。とても勉強になった。今後も繰り返し読んで血肉としたい。またタレマネに関するお薦め書籍があれば教えてほしい。
Posted by
タレマネについての基本を学べる一冊。 個人が会社に従う主従関係からのロイヤリティ向上ではなく、個人と会社が対等な関係のもとエンゲージメントを高めていくことがこれからの人事部門には求められていく。 その上でタレントマネジメントは非常に重要な考え方であり、タレマネ事業を行うものだ...
タレマネについての基本を学べる一冊。 個人が会社に従う主従関係からのロイヤリティ向上ではなく、個人と会社が対等な関係のもとエンゲージメントを高めていくことがこれからの人事部門には求められていく。 その上でタレントマネジメントは非常に重要な考え方であり、タレマネ事業を行うものだけでなく、人事領域に関わる方はぜひ一読して欲しいと思う。 タレマネは、人事だけでなく、現場マネージャー、そして何より従業員個人の意識が変革されて初めて実現されるものであり、その実現は簡単なことではないが、実現できた際には多大な効果を発揮する力を秘めている。
Posted by
タレントマネジメントを広い視野で見てかいている本。 ひいては人事・組織というものを表現してあり、 経営者、人事、MGRといった人を扱う方には是非読んでいただきたい一冊。
Posted by
【タレントマネジメント概論---人と組織を活性化させる人材マネジメント施策】 ・タレマネ事業部の皆さんはよくご存知の内容で恐縮ですが、奥村が不勉強なため忘れぬようPICKUP(今更ながら、顧客先で使える内容がちらほらあるような・・・) ・ポイントは以下 ①タレマネ...
【タレントマネジメント概論---人と組織を活性化させる人材マネジメント施策】 ・タレマネ事業部の皆さんはよくご存知の内容で恐縮ですが、奥村が不勉強なため忘れぬようPICKUP(今更ながら、顧客先で使える内容がちらほらあるような・・・) ・ポイントは以下 ①タレマネジメントの歴史と日米の違い ②"人事"の呼称の変化 ③人事と管理職に求められる"パラダイム変換" ④人材を輩出するアイデア! ⑤労働人口が減少し続ける現代における会社の役割 ■①タレマネジメントの歴史と日米の違い ・これは歴史的観点の話 ・タレントという概念は、2001年頃マッキンゼーがサクセッションプランをうまく進めるためにマネジメント人材を育成する計画概念として生み出した表現 ・アメリカは今後も人口が増え続けると思われるが、日本は反対に減少していく。その背景の違いにおいてアメリカと同様の概念でタレントマネジメントを考えるべきではない。(職があるのに人がとれないのが日本!) ■②"人事"の呼称の変化 ・こちらも勉強のために記載 ・人材マネジメントは以下の概念で進化している L②-1:パーソネルマネジメント・人事労務管理・・・人はコストであり、管理/監視しなければ怠けるので、以下に無駄なく使うか L②-2:HRM(ヒューマンリソースマネジメント/人的資源管)・・・人は他の経営資源(モノ・カネ・情報)の活用を左右する重要な人的資源として育成する、またやる気を引き出して"使う"対象 L②-3:HC(ヒューマンキャピタル)・・・人は消費する資源(リソース)ではなく、個人の能力を磨くことでリターンを得られる人的資源(キャピタル) ②-1、②-2までは、会社が主であり従業員は従という「主従関係」 ②-3において、初めて従業員が会社を変える主体となる可能性をもった L②-4:タレントマネジメント・・・会社と従業員が対等である概念 ・転職の際になぜなのかと不思議だった実例としては、例えばBIG4のファームでは、PwC、KPMG、EYはHRMという表現をつかうが、DeloitteはHCという表現を使う。Deloiiteに限って、社内の人事コンサル組織はHCという(面白い!) ・ちなみに、 「ロイヤルティ」・・・②-1、②-2のように主従関係の上に成り立つ考え 「エンゲージメント」・・・②-3のように、会社と従業員が「同等の関係」のうえに成り立つ ■③人事と管理職に求められる"パラダイム変換" ・今後人が減っていき、転職がより当たり前になるご時世における人事と管理職の新しいあり方が求められる ・人事は給与計算や採用などのルーティンワークは本当に大切であるという大前提のもとで、それらから目を移し、経営者の示す方向性を誰よりも理解し、その戦略を実現するための人材を社内で育成し、作り上げる仕組みを整えていかねばならない ・マネージャーは「タレントマネジャー」として、中長期、長期的に"会社にとって必要となる人材を育成する"という視点にたった業務にアタマを切り替える必要がある。(業績管理や進捗管理がタスクではない!) ・上記を謳っている理由は明確で、それだとリテンションが保てない時代だからである ■ ④人材を輩出するアイデア! ・これは大切だと思う!ぜひうちでも提案したい! ・マネジャーとして優秀な人材を部外に出すことは痛手であるし、一時的に業績も下がりうることはやりたくないのは当然。ならば、部署で最も手放したくない人間を放出した事自体を評価する全社の評価システムがあると良い ・個人的には、対象者のハイパフォーマー度合とその対象者が部に貢献した利益/価値を何かしらで定量化し(とても難しそうではあるが)、その定量化した数値をもって部やマネジャーの評価とするのはどうかと思う。加えて、放出した人が次の部署に移ってからのパフォーマンスをもって、対象者を部署移動させた部やマネジャーの最終評価としてはどうか? ■⑤労働人口が減少し続ける現代における会社の役割 ・大企業でも潰されてしまう時代、以下が求められるか 【個人】その会社では何を身に着けることができるか/身につけさせてもらえるのか(転職が大前提) 【会社】個人にどのような能力を身に着けさせることができるか/いかに選ばれる会社となって個人のタレントと業績を同時にマネージするか (奥村)
Posted by
2015年40冊目。 「仕事が先、人は後」という業務の形ありきのたった人事を、「人が先、仕事は後」にし、人の能力が発揮できることを前提とした業務形態を形成していくのがタレントマネジメント。 紹介されている「設計」「活用」「開発」「運用」のステップを、とにかくまずはなぞってやって...
2015年40冊目。 「仕事が先、人は後」という業務の形ありきのたった人事を、「人が先、仕事は後」にし、人の能力が発揮できることを前提とした業務形態を形成していくのがタレントマネジメント。 紹介されている「設計」「活用」「開発」「運用」のステップを、とにかくまずはなぞってやってみたいと思った。 制度全体を見渡す人事担当の他に、各部署のそのメンバーのタレントマネジメントを行うタレントマネジャーを置く、という発想もぜひ取り入れたい。 「人材」という概念の扱われ方の歴史的変遷も概観されていて勉強になった。
Posted by
労働生産性を上げるための施策として挙げている、 タレントマネジメント。 そもそも難易度の高い取り組み(手間がかかる)だが、 実現すると人材配置の最適化だけでなく、 個人のキャリア形成の活性化を実現することが出来る。 組織として取り組むのは勿論のこと、個人としても取り組むべき内容...
労働生産性を上げるための施策として挙げている、 タレントマネジメント。 そもそも難易度の高い取り組み(手間がかかる)だが、 実現すると人材配置の最適化だけでなく、 個人のキャリア形成の活性化を実現することが出来る。 組織として取り組むのは勿論のこと、個人としても取り組むべき内容。 最近転職活動している割には、 自分が何が出来る・何が得意といったことをアピール出来ない人が多いが、 それは自己棚卸が出来ていないことの象徴で、 =将来組織として仕事をしていくときにやりづらい人とも判断出来る。 それは、自己棚卸が出来ていない=組織で働くときに、 チーム編成されづらい=一緒に仕事しづらいに繋がるため。 若干大げさ感はあるが、あながち間違ってはいない。 あくまで個人的な感想ではあるが、 色んな経験が分かることは大切なことだが、 それよりもどんなことに興味があるのか? どんな性格の人なのか?が分かることのほうが タレントマネジメントとしては大切なのかなと感じた。 【勉強になった内容】 ・2011年から翌2012年にかけてタレントマネジメントに 用いるシステムのパッケージライセンスは19.9%伸びている。 これはパッケージが伸びただけであり、浸透したわけではない。 システムを導入するだけで実現する仕組みではないから。 ・日本でタレントマネジメントが必要な理由 ①人口構造が変化し、労働人口が減少 ②サービス産業の隆盛 ③情報産業・IT化の急伸 ④グローバル競争 ⑤ダイバーシティ、ワークライフバランス、 トータルリワードが浸透 →"量"から"質"が問われるようになってきた ・2036年には第2次ベビーブーム世代が定年を迎え、 1人の高齢者を2人以下で支える時代が待っている。 2060年には1人に対して1.3人で支えるとの試算も出ている。 定年を70歳に引上げても、1.7人で支えなければならない。 ・タレントマネジメントの目的 短期: 組織ニーズに対する人的資産の最適化 人的資産から新しい事業機会や解決策を生み出す 中長期: 人的資産の育成、新たなタレントの創出 ・ビジネスで必要とされる能力 ①資質・適性 ②価値観・考え方 ③行動特性 ④スキル ヒューマンスキル、テクニカルスキル、コンセプチュアルスキル ⑤知識・経験 職務経歴で分かるのは、経験とスキルの一部くらいで、 後はそれ以外のところ(例えばコミュニケーション)から しか分からない。 ここを見える化することは極めて価値が高い。 とはいえ、経験、スキルでさえ横断的に把握する術が無い。 これらが可視化されれば、どこで活躍出来そうな人なのかを 横断的に共有することが可能となり、人材交流の活性化が期待出来る。 ・タレントを開発する際のポイント ①アウトプットの場を設ける ②失敗を許容する ・タレントマネジメント実現のためには、 設計・開発を担う人と活用・運用を担う人を分けるべき。 これはプログラムとプロジェクトマネージャーの役割分担に 近いところとも言える。 ・タレントマネジメント推進のためには、 各部署がそもそも何をやっているのかを知る必要がある。 それにより、各部署で必要なタレントが定義出来、 必要な人材が定義出来る。 ・優秀な管理職ほど、優秀な部下を外に排出している。 ・文書や資料が可視化されたところで使い道が少ない。 それよりも人材そのもののタレントを可視化すべき。 特にサービスや企画等マニュアル化しづらい部門では、 誰が何を出来るかを知ることのほうが重要。 ・組織活性化=個人(スキル×マインド)×環境(仕組み×取り組み) 個人について見えているのはスキル部分でマインド部分は ほとんど見えていない。 ※スキル:経験や知識 マインド:意欲や意思、行動特性 どちらも向上させる必要があるが、源泉となるのはマインド。 このマインドが見えるようになることが組織活性化に繋がる。 合わせて環境整備も大切。チャレンジする機会を作り上げることで、 経験値が上がり、新しいアイデアやサービスを生み出しやすくなる。
Posted by
- 1