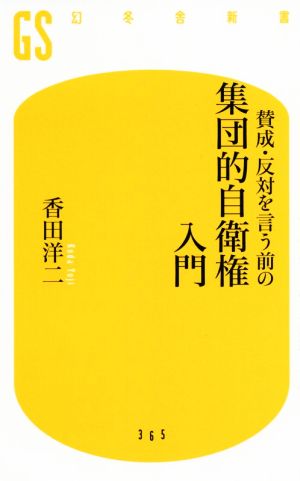賛成・反対を言う前の集団的自衛権入門 の商品レビュー
元海上自衛隊高官による集団的自衛権に関する解説本。専門家だけあってわかりやすい。現場で経験してきた苦労話が参考になった。 「日本のように「憲法の制約により集団的自衛権の行使はできない」と最初から結論づけられていると、何が自分たちの国益に見合う最適な行動なのかを判断することがで...
元海上自衛隊高官による集団的自衛権に関する解説本。専門家だけあってわかりやすい。現場で経験してきた苦労話が参考になった。 「日本のように「憲法の制約により集団的自衛権の行使はできない」と最初から結論づけられていると、何が自分たちの国益に見合う最適な行動なのかを判断することができない」p19 「明文化はされていませんが、次の3つの用件が満たされなければ、自衛権の行使は認められません。(国際慣習法)①急迫不正の侵害があること ②ほかにこれを排除して、国を防衛する手段がないこと ③必要な限度にとどめること」p22 「ドイツはアフガニスタンの(対テロの)戦闘で敵を撃滅する一方、約10年間に及ぶ戦いで、54人の戦死を含む犠牲者を出しました。もちろん、戦死者は出ないに超したことはありませんし、ドイツ社会としても戦後初の犠牲者を出したのは大変つらいことでした。しかし、そうやって現場でショルダー・トゥ・ショルダーで戦い、血と汗を流してくれる国に対しては、やはり強い信頼感が生まれます。実際、私がアメリカで接した安全保障関係者たちは、総じてドイツへの敬意と信頼感を抱いていました。日本も資金面では対テロ戦争に貢献しましたが、どちらが同盟国として頼もしいかは明らかでしょう」p103
Posted by
著者は元海将で、自衛艦隊司令官も務めた人。 集団的自衛権行使容認の主張のための一定の論理性はもちろんあるが、それよりも、現場でのソ連海軍との対峙から、インド洋での給油時にイージス艦を派遣するかどうかの問題に立ち会ったりとか、9.11のときのキティホーク護衛とかを自衛官として体験し...
著者は元海将で、自衛艦隊司令官も務めた人。 集団的自衛権行使容認の主張のための一定の論理性はもちろんあるが、それよりも、現場でのソ連海軍との対峙から、インド洋での給油時にイージス艦を派遣するかどうかの問題に立ち会ったりとか、9.11のときのキティホーク護衛とかを自衛官として体験した身からの、集団的自衛権を行使できないことへの憤懣からくる思いみたいなのが興味深い。 海自には特に集団的自衛権行使容認を求める声が多いと聞くが、海自が経てきた道をみるとそれも少し納得できると思った。 元自衛官の本には、在職中の思いなどから現在の安保政策とか政治についてああだこうだというものも多いけど、そのなかでも比較的現実的に議論を進めている印象。 主張の上手さとかは他の本に譲るところがあるかもしれないが、行使容認派の元自衛官の、現在の安全保障環境に対する焦りと憂いの思いを知るという点では好著かと。
Posted by
冷戦時代には、抑止による武力行使を伴わない安全保障が、逆説的な意味での戦争となり、エイジにおける情報収集が、安全保障上の行為の大半を占めるようになった。今や軍隊の任務の大部分、例えて言えば95%は平時の情報収集であり、抑止が崩れた際の軍事行動である実際の戦闘行為のウェイトは、5%...
冷戦時代には、抑止による武力行使を伴わない安全保障が、逆説的な意味での戦争となり、エイジにおける情報収集が、安全保障上の行為の大半を占めるようになった。今や軍隊の任務の大部分、例えて言えば95%は平時の情報収集であり、抑止が崩れた際の軍事行動である実際の戦闘行為のウェイトは、5%程度と考えてよい。
Posted by
日本が集団的自衛権の行使を容認することで日米の接着力が強まれば、それ自体が中国への抑止力として働く。 自衛隊の能力が高まった以上、もはや日米の軍事的な協力関係は机上の話ではない。それは実質を伴った本格的な軍事同盟。 そもそも中国がハイペースで軍拡を続けているのは冷戦時代のソ連のよ...
日本が集団的自衛権の行使を容認することで日米の接着力が強まれば、それ自体が中国への抑止力として働く。 自衛隊の能力が高まった以上、もはや日米の軍事的な協力関係は机上の話ではない。それは実質を伴った本格的な軍事同盟。 そもそも中国がハイペースで軍拡を続けているのは冷戦時代のソ連のようなアメリカと方を並べる軍事大国を目指しているから。 冷戦時代、中国とソ連の間には長大な国境線があったが、ソ連が崩壊して、中国は複数の国家と接することになった。 アメリカは絶対に日本を見捨てることはない。
Posted by
- 1