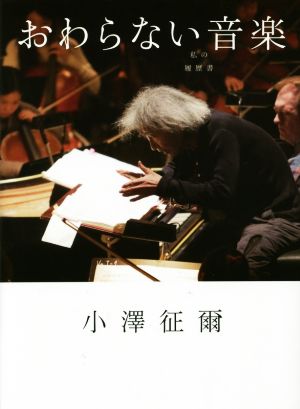おわらない音楽 の商品レビュー
日本人指揮者の中で最も素晴らしい人だと言っても過言ではないでしょう。 「世界のオザワ」と言わしめるその音楽は、海外の有名な指揮者にも劣らない。 才能に溢れた人なのだろうと想像していたが、思ったより泥臭い人生で個人的に好感が持てた。 音楽に向ける姿勢は見習うべきものがある。
Posted by
新聞記事をまとめたものだから、150ページほどで字も大きく、写真も多い。記述は駆け足だが、小澤征爾の精力的な活躍を垣間見ることができた。 1967年、バーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニックの創立125周年の記念で武満徹に委嘱した「ノヴェンバー・ステップス」を小澤の指揮...
新聞記事をまとめたものだから、150ページほどで字も大きく、写真も多い。記述は駆け足だが、小澤征爾の精力的な活躍を垣間見ることができた。 1967年、バーンスタインがニューヨーク・フィルハーモニックの創立125周年の記念で武満徹に委嘱した「ノヴェンバー・ステップス」を小澤の指揮で初演し、大成功をおさめた。その後のトロント交響楽団の演奏が録音されている。 1968年に日本フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者に就任したが、楽員と親会社との衝突により、1972年に解散した。最後の定期演奏会で指揮したマーラーの交響曲第二番「復活」は、力のこもった演奏だった。 斎藤秀雄が亡くなった十年後の1984年にメモリアルコンサートを大阪と東京で開き、モーツァルト「ディヴェルティメントK136」などを演奏した後、「サイトウ・キネン・オーケストラ」としてヨーロッパを演奏旅行した。 1995年、サントリーホールで32年ぶりにN響を指揮し、ロストロポービッチとともにドヴォルザークのチェロ協奏曲を演奏した。 2002年、ボストン交響楽団の音楽監督として最後の定期演奏会でマーラーの交響曲第九番を指揮した。 一音一音に気迫がこもり、大きなうねりを作り出すすごい演奏だった。
Posted by
https://yasu-san.hatenadiary.org/entry/20140906/1409986692
Posted by
小澤征爾追悼コーナーより 一度生で聴いてみたかったなぁ 教科書でもよく出てくるから、CDなどではよくお世話になっているのだけど 「僕はもっともっと深く、音楽を知りたいのだ」 シビレますね プロと言うよりは、道を追求する人という感じ
Posted by
2024.2.11 市立図書館 ちょうど十年前(2014年1月)に日経新聞に掲載された「私の履歴書(全三十回)」に加筆・修正したもの。訃報を聞いて、追悼読書の一冊として借りてみた。 2009年に病気が見つかり、仕事はキャンセルを余儀なくされ闘病・療養・休養に時間を取られてしまっ...
2024.2.11 市立図書館 ちょうど十年前(2014年1月)に日経新聞に掲載された「私の履歴書(全三十回)」に加筆・修正したもの。訃報を聞いて、追悼読書の一冊として借りてみた。 2009年に病気が見つかり、仕事はキャンセルを余儀なくされ闘病・療養・休養に時間を取られてしまったが、その時間のおかげでうまれたのが村上春樹との対談本やこうして来し方を振り返った文章だった。 ここでは、自分一人では音ひとつ出せず人の力に頼らざるを得ない指揮者として、どんな人たちに支えられてきたか、歴代のその恩人たちを紹介する形で人生を綴っている。「僕の音楽武者修行」などこれまでに読んだ著作でもすでに感じていたことだが、小澤征爾(一家)はとても運がいいというか、周りの支援者に常に恵まれている。いまの若い人が読んだら現実離れしたファンタジーのような気もするんじゃないだろうかというほど。もちろんこれは本人の目から見た世界で、客観的な現実はまた別にある可能性はあるが、ご自身はその幸運をじゅうぶん自覚してそれを音楽の形で返していこう、また次代に伝えていこうという気持ちで最後まで頑張っていたことが伝わってくる。八十を前にしてまだまだ音楽の勉強や教育に貪欲だったのに、心身がそれについて行けなくなってしまったのはさぞ悔しいことだったかもしれないと思いながら本を閉じた(90代になっても指揮台に立っているブロムシュテットやジョン・ウィリアムズなどをみるにつけても…)。 読みやすいので一晩で読み終えた。巻末に年譜がついていて、さまざまな追悼談話や他の本を読むとき参照できるのが助かる。
Posted by
「小澤征爾 指揮者を語る」を読んだ後で、重複している部分が多数あった。一気読み。 小澤征爾さんはいろんな人から愛されて、助けられて今の地位を築き上げた。 彼から学びたいところは、行動する時に良い意味で逡巡が無い。人生はあっという間なのだから、私もそうありたいと肝に銘じて本を閉じる...
「小澤征爾 指揮者を語る」を読んだ後で、重複している部分が多数あった。一気読み。 小澤征爾さんはいろんな人から愛されて、助けられて今の地位を築き上げた。 彼から学びたいところは、行動する時に良い意味で逡巡が無い。人生はあっという間なのだから、私もそうありたいと肝に銘じて本を閉じる。
Posted by
☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB16369022
Posted by
淡々と書いてあるけど、きっとすごく努力したんだろう。自分の譲れないところは突き進む。父親の存在が大きい。
Posted by
中学生のころ『ボクの音楽武者修業』を読んだ。重なる部分もあるが、その倍以上の時の経過と出来事が編まれている。当時ではあまり気を留めなかったが、友人たちが絶妙なタイミングで現れ、全力で小澤征爾を応援・援助する場面がかなり多いと感じた。若いころからカリスマ性・類まれな才能・努力できる...
中学生のころ『ボクの音楽武者修業』を読んだ。重なる部分もあるが、その倍以上の時の経過と出来事が編まれている。当時ではあまり気を留めなかったが、友人たちが絶妙なタイミングで現れ、全力で小澤征爾を応援・援助する場面がかなり多いと感じた。若いころからカリスマ性・類まれな才能・努力できる能力を持った指揮者といえよう。 とはいえ、万事順調なのではなく、N響の件、短大留年の件、意外にも斎藤秀雄と「何となくまだぎくしゃく」(p.86)していた件、など色々な出来事が紹介されている。ただそれらを過ぎると宿命だったかのように、新たな道が開かれ、こう劇的に物事が運ぶものなのか、と思ってしまう。三島由紀夫が自決した日に、自信の父親の葬儀があったということも全く普通でない。 最後の「これからも音楽の勉強を続けたい。おそらくどれだけ時間をかけても終わりはないのだろう。僕はもっともっと深く、音楽を知りたいのだ。」、という一文に感銘を受けた。とうに指揮者とか職業音楽家という次元ではなく、ただ純粋に音楽と向き合うという姿のみが残った「存在」があるだけだと強く感じた。
Posted by
小澤征爾(1935年~)氏は、満州国・奉天市生まれ、桐朋学園短期大学卒、2002~2010年にウィーン国立歌劇場音楽監督を務めた世界的な指揮者。文化勲章受章。主な称号は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団名誉団員、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団名誉団員、ボストン交響楽団桂冠音...
小澤征爾(1935年~)氏は、満州国・奉天市生まれ、桐朋学園短期大学卒、2002~2010年にウィーン国立歌劇場音楽監督を務めた世界的な指揮者。文化勲章受章。主な称号は、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団名誉団員、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団名誉団員、ボストン交響楽団桂冠音楽監督、セイジ・オザワ松本フェスティバル総監督、新日本フィルハーモニー交響楽団桂冠名誉指揮者等。 本書は、日本経済新聞の「私の履歴書」に2014年1月に連載された半生記で、小沢征爾が世界のオザワとなっていった疾風怒涛の79年の、数々のエピソードが写真と共に綴られている。 私が小沢征爾の名前を知ったのは、既にボストン交響楽団の音楽監督を務めていたときであり、ブザンソン国際指揮者コンクールでの優勝や、その後のカラヤンとの関係、ニューヨーク・フィルでのバーンスタインとの出会いと活躍等は、本連載(本書)で初めて知ったが、小沢氏が、若い時期から、その節目節目でとても大きな出会いがあり、その機会を活かして成長し、世界のオザワとなったことがよくわかる。 現在86歳。日本、いや、世界の音楽界のために長生きしていただきたい。 (2014年9月了)
Posted by
- 1
- 2