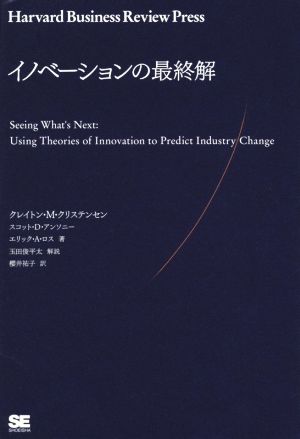イノベーションの最終解 の商品レビュー
「イノベーションのジレンマ」「イノベーションへの解」に続きクリステンセン教授のイノベーション3部作読了。ただ前2作よりも難解で消化するのに読解力が必要で、今の自分には難易度が高い。まとまった時間を作ってジレンマから通して精読したい。
Posted by
「イノベーションのジレンマ」「イノベーションへの解」に続く三部作の最終作だそうです。読んでいません。
Posted by
良い理論ほど実践的だ、とはよく言われるが使いこなせるだけの読解力が要求される。 使いこなすためには、自分のもつ事例で研究しなくてはならない。これらが私の率直な感想だ。幸いクリステンセン教授の扱ったメインの事例が情報通信業界なので、とても有意義だった。 新しい技術潮流で格好の事例を...
良い理論ほど実践的だ、とはよく言われるが使いこなせるだけの読解力が要求される。 使いこなすためには、自分のもつ事例で研究しなくてはならない。これらが私の率直な感想だ。幸いクリステンセン教授の扱ったメインの事例が情報通信業界なので、とても有意義だった。 新しい技術潮流で格好の事例を見つけたので、研究してみたいと思う。 経営学理論の教科書としては最高だと思う。論旨の構造が洗練されていて、変化のシグナル、競争のバトル、戦略的選択、環境要因を含めた影響分析の有機的な関係性の論じ方は、やはりハーバードがトップレベルの大学なんだなぁと感じさせる。ちょっと難解すぎたり、アメリカに偏っている感も否めないので、4つとしておこう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
◆イノベーションの主要な概念 ①破壊的イノベーションの理論 ②資源・プロセス・価値基準の理論 ③ジョブ理論 ④バリューチェーン進化の理論 ⑤経験の学校の理論 ⑥創発的戦略の理論 ⑦動機付け/能力の枠組み ◆概要 既存の企業と新規参入企業の社内外環境の違いから、既存企業がハイエンド向けの持続的イノベーションに囚われると同時に、新規参入企業が、ローエンド向けの破壊的イノベーションに取り組むのかを、更に航空機、教育、医療、通信、半導体業界の事例から、理論と対応指針を解説 ◆考察 ・組織の判断は資源・プロセス・価値基準に則って合理的になされるからこそ破壊的イノベーションが生まれるスキが生じてしまう。 ・一見合理的な判断材料の中には、顧客の要求は考慮されないことが多い。 ・エンジニアとして、①VC高度化、②剣と盾の追求、③ステークホルダーとの連携したビジネススキームの仕組みを作る力が求められる ・イノベーションとそれを具現化するためのバリューチェーンの高度化も必須。 ・変化のシグナルを察知するだけでは片手落ち。それをスピーディに機会に変えることができる組織が生き残る。 ◆第一歩 VC高度化のビジョンの具体化
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
クリステンセン氏のイノベーションシリーズの最新巻 読んでいて、事例の分析に感じる部分が多く、読んでいて興味をひかれる部分が少なかった 事例集から参考程度に調べるには良い本かもしれないが 読み物としては少し退屈に感じた
Posted by
破壊的イノベーションは、新しい価値提案を実現するものだ。破壊的イノベーションには、新しい市場を生み出すもの( 新市場型)と、既存市場を大きく変えるもの( ローエンド型)の二種類がある。ローエンド型の破壊的イノベーションが起こるのは、既存顧客が使いこなせる価値に比べて、製品・サービ...
破壊的イノベーションは、新しい価値提案を実現するものだ。破壊的イノベーションには、新しい市場を生み出すもの( 新市場型)と、既存市場を大きく変えるもの( ローエンド型)の二種類がある。ローエンド型の破壊的イノベーションが起こるのは、既存顧客が使いこなせる価値に比べて、製品・サービスが「性能過剰」になり、したがって高価になりすぎたときだ。
Posted by
クリステンセンといえば、「イノベーションのジレンマ」が有名である。前から気になっていたので、本書と共に借りてみた。「イノベーションのジレンマ」のページをめくってみたが、事例が古いからか、個人的には全く食指が動かなかった。本書も10年ほど前に書かれたものなのでそれほど新しくはないが...
クリステンセンといえば、「イノベーションのジレンマ」が有名である。前から気になっていたので、本書と共に借りてみた。「イノベーションのジレンマ」のページをめくってみたが、事例が古いからか、個人的には全く食指が動かなかった。本書も10年ほど前に書かれたものなのでそれほど新しくはないが、通信業界の事例など興味深いテーマが含まれていた。 終章の結論がコンパクトにまとまっていて良い。 「本書ではイノベーションの理論を使って業界の変化を予測する方法を詳しく述べた。第一章から第三章までは、わたしたちの分析プロセスの要旨を説明した。このプロセスは、三つの反復的なステップからなる。 一 変化のシグナルを探す。業界の環境変化や、無消費者、満たされない顧客、過剰満足の顧客を新しい方法で獲得しようとしている企業を示唆するシグナルはないだろうか。 二 競争のバトルを評価する。競合企業の経営状況を把握し、非対称性の剣と盾をもっている企業を探す。 三 破壊のプロセスを正しく実行できるチャンスを増やす、または減らすような、重要な戦略的選択に目を配る。 各章の結論には、それぞれのステップを実行する際に役立つ質問を列挙した。… 第五章から第八章までと第十章では、この分析的プロセスを用いて教育、航空、半導体、医療、通信の各業界の未来についての洞察を得た。各章の研究から得られた一般的な教訓を挙げた。… 本書の最も重要な教訓は、当然ながら破壊的イノベーションと関係がある。特に重要な教訓を四つ挙げよう。 一 破壊とはプロセスであって、一過性の出来事ではない。 二 破壊とは相対的な現象である。ある企業にとって破壊的なイノベーションが、別の企業にとっては持続的なイノベーションになるかもしれない。 三 異質な技術や急進的な技術が破壊的なイノベーションとは限らない。 四 破壊的イノベーションは、ハイテク市場だけのものではない。破壊はどんな製品・サービスにも起こるし、国家経済間の競争を説明することもできる。」 「破壊的な製品・サービスのイノベーションは、無消費と競争するか、消費を新しい状況にもたらすことで、新しい市場を創出できる。」 「ほとんどのイノベーションは、破壊的イノベーションではない。最も重要で最も収益性の高いイノベーションの多くは、良い製品・サービスをよりよくする持続的イノベーションである。一般に持続的イノベーションを先導するのは、既存企業だが、『成功』を正しく定義すれば、新規参入企業でも持続的イノベーションを成功させることはできる。」 「新規参入企業と既存企業にとっての適切な市場進出戦略が変化するのは、過剰満足が生じ、インターフェースがモジュール化を促すような形で変化するときだ。」 これ以外にも、今の業務でも思い当たる節がいくつもあり、非常に参考になった。
Posted by
クリステンセンのイノベーション3部作の3作目。 タイトルは「最終解」となっているが、内容的には、1〜2作から連続していて、業界が今後どういう競争状態になるか、破壊的イノベーションが起きやすいかどうかを予測するための方法論とそれに基づく予測という感じ。 内容的には、このシリーズ...
クリステンセンのイノベーション3部作の3作目。 タイトルは「最終解」となっているが、内容的には、1〜2作から連続していて、業界が今後どういう競争状態になるか、破壊的イノベーションが起きやすいかどうかを予測するための方法論とそれに基づく予測という感じ。 内容的には、このシリーズは、だんだん難しくなっている感じがして、かつ真面目な積み上げ的な分析に思えてします。 なんだか、ポーターの分析を読むときに感じる疲れがある。 タイトルに惹かれるが、クリステンセンの本としては、最後に読んでよかったなと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「イノベーションのジレンマ」からはじまり、「イノベーションの解」と続き、それらのシリーズ最終巻となるのが本書。 「イノベーションのジレンマ」では破壊的イノベーションからどのようにして自身の身を守るか、そして「イノベーションの解」では、逆に破壊的イノベーションを使って、既存企業にいかにして戦いを挑めばいいのかが述べられていた。 本書では、外から業界全体や、その業界内で何が起きているのかを解析、そして予測するために、理論を用いる方法を詳しく解説しています。
Posted by
実際は「最終章」として書かれた本ではないそうですが、名著の「イノベーションのジレンマ」を読んだ後に読むと、つながりがよくわかります。アンケートを実施することばかりに注力して、稚拙な分析をもとにをエビデンスだと言い張られそうな時、または、理論をベースに未来を見たいと思ったら、おすす...
実際は「最終章」として書かれた本ではないそうですが、名著の「イノベーションのジレンマ」を読んだ後に読むと、つながりがよくわかります。アンケートを実施することばかりに注力して、稚拙な分析をもとにをエビデンスだと言い張られそうな時、または、理論をベースに未来を見たいと思ったら、おすすめです。 違う訳の本もありますが、「ジレンマ」から読む方は、こちらの訳を読む方がいいと思います。
Posted by