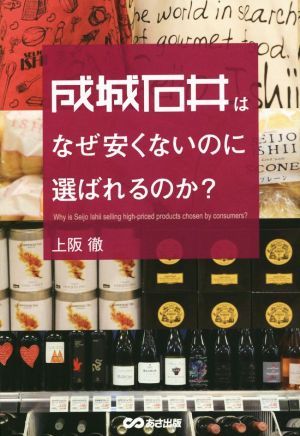成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか? の商品レビュー
良書。結構気づきが、ありました。というか、もっと基本に立ち返ってやるべきことがたくさんあることに今さらながらに気づかせてくれました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「生産者が一生懸命に作っている事をしっかり理解することが大事」「会社や店の都合なんてお客様には関係ない」「売れないのはお店のせいではない。本部のせい。」などなど、とっても共感出来る職場だと感じました♪普段はお惣菜コーナーでしか買い物しませんが、今度はちょっとじっくり店内を散策してみようと思います☆
Posted by
p101 (惣菜)ちょっとほかのスーパーではお目にかかれない本格的な料理 p105 ほとんどが本当に手作りされている 多品種少量生産ですから大きな機械をいれてしまうと逆にコストがかかってしまいます メニューもどんどん変わっていきますから p117 今の小売業では日持ちさせるた...
p101 (惣菜)ちょっとほかのスーパーではお目にかかれない本格的な料理 p105 ほとんどが本当に手作りされている 多品種少量生産ですから大きな機械をいれてしまうと逆にコストがかかってしまいます メニューもどんどん変わっていきますから p117 今の小売業では日持ちさせるためにいろいろなものが使われている でもそれはだれのためなのか。お客様のためではないということに気づく必要があると思うんです 販売する人たちがいかに日持ちさせて効率よくビジネスができるかということではないでしょうか 保存料が使われていなければ賞味期限は短い 保存料が入っていないんだもの、短い期間で売るしかないんだよね、という考え方に変わっていかないといけない
Posted by
読んでみて、改めて成城石井に行きたくなりました。店員さんに商品のストーリーを聞いてみたくなりました。値段やブランドではなくいいものをお客さんに届けたいっていう心意気とそれを実践できる文化が素敵だなと思いました。
Posted by
営業先の担当業界が一瞬飲食・小売になったので一読。 インタビューを元にまとめたもので、ビジネス書ながら具体的でわかりやすい。 ・マニュアルがなく、顧客それぞれに合わせた対応を行う ・商品それぞれのストーリーを理解することで価格相応の価値を持たせる ・「高級スーパー店と呼ばれたく...
営業先の担当業界が一瞬飲食・小売になったので一読。 インタビューを元にまとめたもので、ビジネス書ながら具体的でわかりやすい。 ・マニュアルがなく、顧客それぞれに合わせた対応を行う ・商品それぞれのストーリーを理解することで価格相応の価値を持たせる ・「高級スーパー店と呼ばれたくない」という強い思い などから、なぜ成城石井が愛されるのか、そのブランディングが少し理解出来た。
Posted by
1.成城石井の創業者の石井良明さんの本の隣にあったので、思わず購入しました。 2.先日自分が読んだものは、創業者の石井氏がどのような歴史を経て、成城石井をここまで大きくしたのかということが述べられていました。それに対してこの本は、外部の人が当時の社長である原昭彦さんに協力を依頼...
1.成城石井の創業者の石井良明さんの本の隣にあったので、思わず購入しました。 2.先日自分が読んだものは、創業者の石井氏がどのような歴史を経て、成城石井をここまで大きくしたのかということが述べられていました。それに対してこの本は、外部の人が当時の社長である原昭彦さんに協力を依頼し、石井氏が離れた後の成城石井の物語が書かれています。 社員を大切にするためにはどのような経営が良いか。また、顧客に徹底的に向き合うことが成城石井の強みだということ。さらには、基本的な事がなぜ大切なのかと言うことが書かれています。 書いてあることは、至ってシンプルで、人を大切にしていくためにはどうすればいいのかということです。成城石井では、顧客にしろ、従業員にしろ、会社を作り上げているのは彼らで、コミュニケーションこそが成長の基盤となっています。これがどのように実践されているかが詳しく述べられいる本です。 3.最初に、成城石井を立ち上げた石井氏の本を読んだ後にこの本をんだので、経営者目線と外部からの目線と、2つの視点で読むことができました。そこで思ったのは2つです。1つは、顧客に徹底的に向き合うということです。石井氏が常に気にしていたことを、今もなお貫かれているため、会社の成長が止まらないのだと思いました。効率化に目を奪われず、顧客が求めているものを非効率ながらも自分達の力で提供していく姿は勉強になりました。もう1つは、石井氏が今の成城石井に対してどう思っているのかが気になりました。この本を読むと、成城石井の社員さんはひたむきに努力を続けたにも関わらず、石井氏は会社を売却しました。石井氏が悪いとかいう問題ではなく、石井氏の中で何か思うことがあったのではないかと思い、気になってしまいました。 また、この本を読むのであれば、石井氏が書いた「成城石井の創業」も同時に読むことを勧めます。
Posted by
霑第園縺ォ縺ゅj縲√°縺、縲√→縺ヲ繧よオ∬。後▲縺ヲ縺?◆縺後?√◎繧後?蜻ィ蝗イ縺ォ縺雁コ励′蟆代↑縺?°繧峨?√¥繧峨>縺ォ閠?∴縺ヲ縺?◆縲ゅ%縺ョ譛ャ繧定ェュ繧薙〒縲∬??∴縺梧隼縺セ縺」縺溘?ゅ◎縺ョ蠕後?∝セ捺擂繧医j雜ウ郢√¥騾壹>縲∬イキ縺?黄繧偵☆繧九h縺?↓...
霑第園縺ォ縺ゅj縲√°縺、縲√→縺ヲ繧よオ∬。後▲縺ヲ縺?◆縺後?√◎繧後?蜻ィ蝗イ縺ォ縺雁コ励′蟆代↑縺?°繧峨?√¥繧峨>縺ォ閠?∴縺ヲ縺?◆縲ゅ%縺ョ譛ャ繧定ェュ繧薙〒縲∬??∴縺梧隼縺セ縺」縺溘?ゅ◎縺ョ蠕後?∝セ捺擂繧医j雜ウ郢√¥騾壹>縲∬イキ縺?黄繧偵☆繧九h縺?↓縺ェ繧翫∪縺励◆縲 蟶ク縺ォ縺雁ョ「讒倥?譁ケ繧貞髄縺?※縺?k縺雁コ暦シ丈シ夂、セ縲
Posted by
買収などの負の側面にも触れており、提灯記事と言うよりもファンの礼賛本という感じ。非常にごもっともなコンセプトなのだが、それが近年の拡大路線と矛盾しないのかがよくわからない。都心の成城石井はかなり品揃えが似通っていて各店舗の特徴が出ているかというと疑問な気がするのである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
見た目が必ずしも味につながるとも限りません 赤牛の肉はサシがほとんど見えない でも脂が少ないわけでなく 種類とえさが違うんです 自信をもって赤牛を売ります → 顧客のいろんな好みに応えるために 肉の個性を出していく (p36) 成城の始まりは都内屈指の高級住宅街 世界でいいものを見てこられた目の肥えた方々の 視線にさらされ続けてきた 食も本物志向 高くていいものは当たり前 それをいかにお値打ちで出せるか 商売としてはこれが問われたわけです どうやって応える どうやって考え続ける (p27) 各店舗には 肉の知識を持つ担当がいて 熟成させて 一番の食べごろの状態のときお客様に提供 (p38) 成城石井は値段が高い と言われることもあります ただストーリーをきちんとお伝えして こだわった生産者がいて それを理解して こだわって売ろうとする私たちがいて それでも本当に高いんでしょうか? ということは問うてみたいんです 成城石井のお客様はそれをご理解くださっている (p43) 本当においしいものを提供する それが一番大事 おいしいものを食べちゃうと もう戻れないんです お客様が増えたということは それだけ おいしいものを求める人が増えてきたということ (p44) 成城のお客様に 肩肘の張ったコミュニケーションに ならないよう お客様が見ておられるような世界を 従業員に見せる取り組みもありました サービスをされる側になって 初めてわかる求められるサービス を知ろうという努力 (p51) 小売りで結果を出そうとすると 簡単なことは 安いものを並べること それなりに売れるが短期的にはです 結果は出ても信頼を失ってはダメです 当たり前のことを 当たり前にすることが どれほど難しいか 商売の基本であるにも関わらず 認識している人は少ないのではないんでしょうか? だから 基本がしっかりできるよう 数値化して追いかけていく 毎日それをやり続ける できないとわかっているからこそ できる仕組みを考える (p69) 産地を季節にずらしていくことで安定供給 日本列島を横断しながら 有機野菜を仕入れていく (p82) バイヤーは世界に出張 戻ってきたら報告会で SABCの4段階で評価 自分の家族や子供に食べさせたいか 安心安全のこだわりが これ程高まっているという中 果たして世の現状はどうか (p110) 安かろう悪かろうに 人々は疲れてしまった ちょっといいものが欲しい 特別変わったもの そんな時に成城石井(p121) スタンスは過去と全く変わっていない 変わったのは世の中で 周囲の小売りは簡単には追いつけない
Posted by
副社からの宿題本をw ちょうどリブランド事業に取り組んでいる当社にとって、ブランドとは?をしっかりと考えさせてくれる本でした。 成城石井さんへの感想としては、バックグラウンドをしっかりと語れる物を販売出来るって幸せだなーと思いました。 全てではないにしろ、そういった想いの...
副社からの宿題本をw ちょうどリブランド事業に取り組んでいる当社にとって、ブランドとは?をしっかりと考えさせてくれる本でした。 成城石井さんへの感想としては、バックグラウンドをしっかりと語れる物を販売出来るって幸せだなーと思いました。 全てではないにしろ、そういった想いのこもった商品を販売できるってのは、販売員の醍醐味やと思います。 って、本を読んだだけの人に思わせられる人材育成を上手くしているんでしょうね。 ただ、こういった本は良いトコだけ切り取ってということもあるので、実際働くのとは別かも?! 一度行ってみたいし、お惣菜は是非食べてみたいと思いました!
Posted by