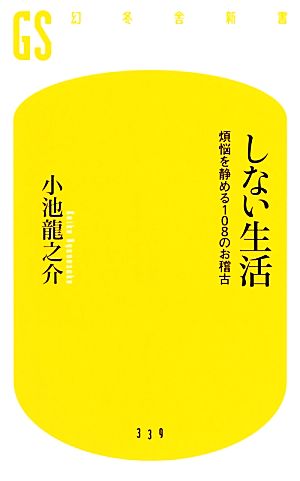しない生活 の商品レビュー
煩悩、、自分の感情に対しての向き合い方を学べる1冊。 感情に対して内省 腹が立つ、、はて?なぜであろう。 あちらさんのミスに対して、腹が立っているのか。 よくよく考えると、ミスをしてはいけないのか? 自分もミスをすることがあるのに、人のミスは許せないのだろうか。。 というふ...
煩悩、、自分の感情に対しての向き合い方を学べる1冊。 感情に対して内省 腹が立つ、、はて?なぜであろう。 あちらさんのミスに対して、腹が立っているのか。 よくよく考えると、ミスをしてはいけないのか? 自分もミスをすることがあるのに、人のミスは許せないのだろうか。。 というふうに、分析していく。深めていく。 感情的になっていても、物事を俯瞰でみることができれば少し落ち着くことができる。 悩みを人に話したり、ノートに書き出すことで気分が変化するように。 感情は物事をきちんと把握できていないことから、さらに不安や恐怖をつのらせてしまう。 自分がどういう状況で、なぜこの感情となったのかを改めて考えてみよう。 じつは私も交通マナーがなっていない輩が、絡んできたことがある。無性に腹が立ったが身内もいたため、その場では頭を下げた。しかし眠れないほど、イライラしつづけた経験がある。 だが何も失ってはいないこと、自分のプライドが傷つき腹が立っていたことを内省し少し落ち着くことができた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
プライドの煩悩。後輩から懐かれるとか、女性から素敵と思われるとか、丁重に扱われるとか。自分で自分の価値を認めていることができれば、プライドの煩悩に悩まされることはなくなってくるのではないか。 どの選択肢がより得か考えてしまう。ちっぽけな得を求めてケチな欲望に心乱れるその間に精神や時間を消耗してしまう。ちょっとくらい損してもと思える寛容さが必要。 自分の心でさえ状況が変われば大きくぶれる。他人の心のブレにも寛容でありたいもの。 自分のことをわかってほしいという煩悩。SNSでの投稿も自分の価値を周りに判ってほしがっている。匿名掲示板での批判の書き込みも、うまく批判できる自分、物事がわかっている自分をわかってほしがっている。他人はその人自身にしか興味がないのだ。 正義感の煩悩は突き詰めると、世の中が公平であることの期待である。自分の行ったコストに見合う行動・犠牲を相手に期待している。メールの返事や好意のお返しなど。逆に、相手からダメージを受ければそれが相手に公平にダメージを受けるべきという正義感が復讐。悪を懲らしめる正義感すらも煩悩。世の中は不公平であることを認めることで、寛容に 自分の優先順位が低いことに腹を立てるのはとても恥ずかしい。 自分が隠している感情を認めよう。情けなかったり、卑小だったり、カッコ悪いものも含めて。自分の本心が自覚しにくくなって心の回路が狂ってくる。つらいのに元気だと思い込む必要はない。自分の気持ちを認めることで楽になる。 欲望、怒り、愚かさの煩悩。他人をコントロールしたがる欲望を手放せればもっと楽になれる。 相手から良い扱いを受けて自尊心をくすぐられた時こそ注意。次にそうでなかったときに乱降下の原因にもなる。良い扱いを受けた時こそ、この扱いも一時的なものだと思えるといい。 結果を重要視する責任倫理と、動機を重要視する心情倫理。心情倫理で考えた方が心は穏やかでいられる。 誰しも価値観を否定されると心地が悪いもの。心に浮かんだ「でも」「しかし」をこらえることで、無用な闘争に巻き込まれなくて済む 自分のことを正確に理解させたいという欲望は厄介なもの。プライドの煩悩も大きく影響している。何かあった時に労わるような言葉をかけてくれたときも、全然平気でしたとか慣れているからとか。帰るように言ってくれた時も遊んでいるだけですからとか。。。相手のいたわりの気持ちを大事にしたい。 弱者が自分の自尊心を保つために、逆の価値観でルールを作ることはよくあること。道徳とかモラルとか正義とかという言葉でデコレーションされていることも多い。それ自体の価値を認めることができれば 渇愛と呼ばれる自己中心的な思惑によって、世の中をありのままに見れなくなっている。物事には善も悪もないのに自分の都合で善悪をつける 自我イメージを持つことを仏教では有愛といい手放すことを進めている。自我イメージをもつと、そうでない情報などに自我を脅かされる。心は諸行無常であるから、その時は自信満々でもそうでない自分に苦しむという面もセットで抱え込むことになる。自分はどういう人間というイメージを手放そう。そうすれば他人からのからかいもかわしていける 何かの想いにとらわれているときも、よく観察してみると途中でそれ以外の感情が現れることに気付くはず。それでも脳は強い感情のみを記憶して弱い感情を塗りつぶすので、その思いにとらわれている自我イメージを強く持ってしまう。しかし、途中で現れたそれ以外の感情があったことを見つめなおすと、心が無常なことに気付くことができる どうでもいいことでの不毛な争いを避ける。自分の考えを保留して相手の考えに寄り添える余裕を 議論を応じる者はここにはいない 「こうありたい自分」は苦しみしか生まない。そうあれない自分に苦しむか、そうなれても心が慣れてしまってより多くを求めて苦しむか。そうじゃなくてもいいという余裕で存在欲求を緩めると楽になる 自分の心も完全にコントロールすることはできない。完全に怒りを鎮めることもできないし、幸せな状態を目指してもそれは無理。幸せはふと感じるもの。 自分が守る戒めは、自らが守るべきものであって、他人に押しつけてはいけない 社会とは違う基準で自分を評価できる価値観で自らを正当化しようとしてはいないか。そういう動機自体は否定しないが、それでもって執着をしたり、他人を見下したりするのはあさましい。 仏典すら絶対に正しいものではない。絶対に正しいものなどない。狂信的にはなってはいけない 優越感、劣等感、同等感は捨て去れ。対象は、他人はもちろん、自分も。 苦しみも一度認める。それで初めて乗り越えられる。無理して平気なふりをしなくていい。
Posted by
自分の気持ちも、人の気持ちも、人の自分に対する評価もそれにに対する自分の感情も、その全ては諸行無常。 移ろい変わって当たり前。とらわれないことで楽になる。 なにかを「しない」ことも心がけと訓練が必要。 読みやすくて腑に落ちやすかった。 実践が何より大事。
Posted by
困ったときこそ次々と手を打ちたくなるもの。もがいて混乱するよりも、ただ内省すること、心の有り様を客観的に見直すことで心の平穏を取り戻す。それにも訓練が必要なのだと思う。仏教をはじめとする宗教にそういった知恵を学ぶことができる。
Posted by
感想 ToDoリストを捨てる。なにをすべきかではなく、なにをしないか。意識的に何かをしないことは難しいかもしれない。煩悩を捨ててスッキリ生きる。
Posted by
小池さんらしい文体で書かれた本です。項目ひとつが大体見開き1ページととてもライトで内容は少し物足りなくも感じましたが、隙間時間にちょこちょこ読んで、ハッと背筋を正すのに丁度よさそうです。
Posted by
面白かったと思う。 自分に当てはまる部分もたくさんあり、苦しむことが多いからこそそれに対処する方法を考えるのではなく苦しまない方法を考える。 また自分の心に余裕がなくなったら読みたいと思う。
Posted by
東大の教養学部で西洋哲学を専攻した現役の住職による有難い講話... というよりは、人生を穏やかに生きるためのちょっとしたコツ。迷い・不安・怒り... 人の心が乱れたこんな状態を仏教では「煩悩」と呼ぶのだが、その煩悩を追い払うための方法を伝授する。情報と「つながり過ぎない」・周囲に...
東大の教養学部で西洋哲学を専攻した現役の住職による有難い講話... というよりは、人生を穏やかに生きるためのちょっとしたコツ。迷い・不安・怒り... 人の心が乱れたこんな状態を仏教では「煩悩」と呼ぶのだが、その煩悩を追い払うための方法を伝授する。情報と「つながり過ぎない」・周囲に対して「イライラしない」・自分に「言い訳しない」・他人と「比べない」など、人間の煩悩と同じ数・108項の短い話で目覚めさせてくれる。本書は。『心を保つお稽古』というタイトルで朝日新聞に連載されたエッセイをまとめた一冊で、放っておくとコロコロと変わって乱れまくってしまう「心」を楽にしてくれる。
Posted by
・一番強い欲は、自我だったんですね^^; そう言われてみると、ちっぽけな自分を少しでも大きく見せようと懸命に背伸びしている自分がいるんですけど、直ぐふくらはぎがつって、踵をついてしまうんですよね… 先に読んだ、アルボムッレ・スマナサーラ氏の『ブッダが教える 執着の捨て方 (だ...
・一番強い欲は、自我だったんですね^^; そう言われてみると、ちっぽけな自分を少しでも大きく見せようと懸命に背伸びしている自分がいるんですけど、直ぐふくらはぎがつって、踵をついてしまうんですよね… 先に読んだ、アルボムッレ・スマナサーラ氏の『ブッダが教える 執着の捨て方 (だいわ文庫 B 176-4)』に書かれていた内容と似ている。小池龍之介さんも、頻繁にブッダの言葉を引用していますが、ルーツは一緒なんでしょうね。もしかしたら、アルボムッレ・スマナサーラ氏の著書も、読んでいらっしゃるかもしれませんね。 アイタタ―とか、ガーンとか、ご住職としては相応しくない言葉が使われているので、変だなぁ~と思っていたのですが、ウィキペディアで調べてみたら、小池龍之介さんは『坊主失格(2016)』という本で「物心ついたときから、いつも淋しく満たされず、多くの人を傷つけてきました」と告白されてるような経験があるみたいですね。 だから、この本に書かれていることは、師が弟子に灌頂を与えるような語り口でなく、同じ尊厳を持つ人間同士の対話のように対等な感じがするのでしょう。読者は、失敗談に支えられた煩悩を静める方法に納得するのです。 普通、欲って言ったら、物欲だと思ったら、一番強い欲は、自我だったんですね^^; そう言われてみると、ちっぽけな自分を少しでも大きく見せようと懸命に背伸びしている自分がいるんですけど、直ぐふくらはぎがつって、踵をついてしまうんですよね… 高野山の宿坊でいただいた精進料理は、とても美味しかったのですが、人間は、動物性のたんぱく質を摂らないと、やっぱり体調を崩してしまう人ですかね?だとしたら、僧侶らしく戒律を守って生きることは、とても大変なことですね(^^ゞ
Posted by