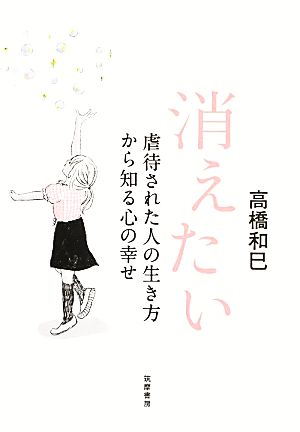消えたい の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
例えがとっても分かりやすく、文章全体読みやすかったです。 被虐者はうつ病と診察されることが多いが、ほとんどの場合薬物療法は効かない。認知行動療法さえ効かない。 著者のクリニックでは、患者のうつの原因になっている家族との関係を思い返させながら、医師(著者)とのカウンセリングを通して症状が改善していくかんじ。 発達障害と被虐児は、行動や仕草が似ている場合があり、時に混同される。 被虐児に、親とのつながりの大事さを意識させるのは負担になる。 被虐であっても必然的に親の愛を求める。年月が経ち親元を離れ、親からの愛など存在しなかったと自覚するのが生きづらさから解放される方法。 そのうち読み返すとおもう。
Posted by
私もふとしたときに、「消えたい」と思うことがある。死にたい、じゃない。消えたい。このまま消えられたらなと。検索したらこの本を見つけた。 私は親から虐待というものは受けていないと思うのだが、、、、どうなんだろう。
Posted by
虐待を受けて育った人はそもそもの心理的メカニズムが違うことを取り上げた本。例えば、普通のひとは「死にたい」というが、虐待を受けてきたひとは「消えたい」という。どちらも医学的には希死念慮の一言でまとめられるが、その意味する文脈は全然違う。死にたいというのは、こうありたいとかこうして...
虐待を受けて育った人はそもそもの心理的メカニズムが違うことを取り上げた本。例えば、普通のひとは「死にたい」というが、虐待を受けてきたひとは「消えたい」という。どちらも医学的には希死念慮の一言でまとめられるが、その意味する文脈は全然違う。死にたいというのは、こうありたいとかこうしてみたいなど自分の人生を生きてきた人がうまくいかなくなってしまったときにいう言葉。それに対して、消えたいというのは、そもそもの「生きている」という前提がない。生きられなかった人生を歩んできて、今までに生きてきたという実感を感じたことがない人が疲れたときにいうのが「消えたい」。 よくよく考えてみれば、虐待を受けてない人と受けた人では心理的機構が全然違うのは当たり前だが、いままでの心理学やカウンセリングの本でそれを明確に指摘している本を読んだ記憶がないような気がする。著者自身も数ある理論は正常に育ってきている人を前提に構築されているので、被虐待者の治療にはこれらの治療理論や治療のアプローチがまったく効かないと語っている。 非常に興味深い本だった。
Posted by
美味しく食べて、ぐっすり眠れて、誰かと気持ちが通じる――これが幸せであった。彼女は文字通り生命の危機から生き延びたサバイバーであった。幼子であることを踏まえれば大病や災害から生還した人々よりも稀有(けう)な存在だ。幸せとは当たり前のことなのだろう。もともとは「仕合わせ」と書いた。...
美味しく食べて、ぐっすり眠れて、誰かと気持ちが通じる――これが幸せであった。彼女は文字通り生命の危機から生き延びたサバイバーであった。幼子であることを踏まえれば大病や災害から生還した人々よりも稀有(けう)な存在だ。幸せとは当たり前のことなのだろう。もともとは「仕合わせ」と書いた。 http://sessendo.blogspot.jp/2015/09/blog-post_23.html
Posted by
黒バス脅迫犯の最終意見陳述を読んで興味を持った本。被虐待児だった人の心理はもちろん、普通の人の人格形成に関しても分かりやすい文章で書かれている。事例も多く勉強になり、ぼんやりイメージしてたものが脳に定着した。 余談)ワシもそこそこ人に相談をされることはあって、生き方の話になるとた...
黒バス脅迫犯の最終意見陳述を読んで興味を持った本。被虐待児だった人の心理はもちろん、普通の人の人格形成に関しても分かりやすい文章で書かれている。事例も多く勉強になり、ぼんやりイメージしてたものが脳に定着した。 余談)ワシもそこそこ人に相談をされることはあって、生き方の話になるとたいていするのが「自分の身の回りに三箇所、逃げ場を作っておくこと」という話しなのだが、本書でされている「安心の確保」ってテーマを浅くすればそれに行き着くな、と思った。経験則も、案外馬鹿にならない。
Posted by
自分の感情が揺れ動いた本の1冊です。 この本は理論書とは違い、実際に虐待を受けてきた人の体験や回復までの過程が書かれています。 そのため、被虐待者がどのように過ごしてきたのかをイメージしやすいかと思います。 「虐待を受けてきた人と受けていない人が別の世界に生きている」というこ...
自分の感情が揺れ動いた本の1冊です。 この本は理論書とは違い、実際に虐待を受けてきた人の体験や回復までの過程が書かれています。 そのため、被虐待者がどのように過ごしてきたのかをイメージしやすいかと思います。 「虐待を受けてきた人と受けていない人が別の世界に生きている」ということを、虐待を受けてきていない人はなかなか感じにくい感覚なのかなと感じました。 ただ、虐待を受けてきた方にとっては別の世界に生きている感覚は強く持っていて、だからこそ生きづらさを感じる部分もあるのかなと思いました。 この本を読んで、虐待を受けてきた人たちとのかかわり方だけでなく、すべての人とのかかわりにおいて「自分の当り前が他の人にとっての当り前とは限らない」ということを再認識させられました。 「死にたい」は、生きたい、生きている、を前提としている。 「消えたい」は、生きたい、生きている、と一度も思ったことのない人が使う。 この言葉がとても印象的でした。
Posted by
感情が人に正気を与える。 私の愛はきっと、理解することの中にある。 私は、もしかしたら人間にはなれないかもしれない。どこまでいっても、人とのつながりを当たり前に享受している人間たち(普通の人たち)の隙間をさまよう人(異邦人)でしかいられないかもしれない。 それでもただの生き物...
感情が人に正気を与える。 私の愛はきっと、理解することの中にある。 私は、もしかしたら人間にはなれないかもしれない。どこまでいっても、人とのつながりを当たり前に享受している人間たち(普通の人たち)の隙間をさまよう人(異邦人)でしかいられないかもしれない。 それでもただの生き物として、自分が存在しているこの世界を見てやろうとしながら、生きていくとはできるだろうか。 自分の存在を感じながら、人間であることを放棄したら、人として生きられる? 大変な労力をかけてまで、どうして物語が生み出され、語り継がれてきたのかを、本当に理解できたように思う。 物語を語るというのは、世界を説明するということ。世界を説明するというのは、世界と語り合って、世界を理解するということなんだ。世界を説明する言葉、物語が増えるたびに、世界は広く豊かになる。 多分、アメリカインディアンに関する本だったと思うが、高校生の頃に、「雨が降る理由を10通りの言葉で説明できるようになりなさい」という文章を見つけた。それは簡単なことではない。でもやり遂げたら、その時こそ本当の知恵を手に入れているだろう、と。そんな主旨だったように記憶している。その通りだ。 わからないことがひとつある。この本の中には、自分の問題が未解決なのに結婚生活を営んでいる人がたくさん出てくる。どうしてそんなことができたのだろう?人間のふりをした結果なの?
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自分自身が両親・父方の祖父母から虐待をされて育ってきた身で現在、心療科で治療中のため、治療の役に立てばと思って手にとって読んでみた。私自身も「死にたい」ではなく、「消えたい」と言ってるため、やはり虐待をされてきた人間に共通する言葉なのだろうと感じた。虐待に関してはいろいろ思うところがある。傷つけられるのはいつも子供なのだと思ってしまった。
Posted by
かの黒バス脅迫犯が逮捕後、本書を読み、大いに目を開かされたというので、どんな本だろうと思って読んでみた。 著者は、虐待を受けながら育った人たちを多く診ている精神科医。 彼らのことを著者は「異邦人」と呼ぶ。 虐待を知らない私たちとは、まったく異なる次元を生きているからだ。 また、...
かの黒バス脅迫犯が逮捕後、本書を読み、大いに目を開かされたというので、どんな本だろうと思って読んでみた。 著者は、虐待を受けながら育った人たちを多く診ている精神科医。 彼らのことを著者は「異邦人」と呼ぶ。 虐待を知らない私たちとは、まったく異なる次元を生きているからだ。 また、それゆえに「異邦人」に対する治療やカウンセリングは、一般的なうつ病患者などに行うようなものでは通用しないばかりか、かえって逆効果になることもあるのだという。 しかし私は不思議だった。 「あなたの抱えている生きづらさは、虐待を受けてきたことによるものなのですね」と事実を告げ、それを受け止めることによって、回復の道をたどる例がいくつも紹介されていた。 たしかにそれは大変なショックだろうし、それだけ大きな意味があることだと思う。 けれどそれによって「異邦人」たちの実生活は、本当にそんなに変わるのだろうか? 要は、言葉だけで人は救えるのか?ということなんだけど…。 そんな疑問は、所詮興味本位でページをめくった人間の戯れ言なのかもしれない。 なぜなら、Amazonのレビューを見たら「自分も異邦人でした」という切実なコメントがあふれていたから。 それを見て、少しハッとした。
Posted by
最近、「死にたい」というフレーズが脳裏によぎって困っていたけれど、思春期には、日記に「消えたい」とよく書いていたことを思い出しました。 高橋先生の文章は誠実で思いやり深い人柄が伝わってきます。とても、丁寧な本だと思います。
Posted by
- 1
- 2