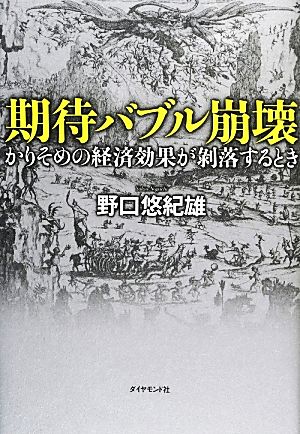期待バブル崩壊 の商品レビュー
最近、パソコンが高い。海外生産あるいは海外からのパーツ調達が多いため、円安の影響をもろに受けた結果である。発電用燃料の輸入とエレクトニクス製品の輸入の増加により、物価の円安感応度が近年とみに高まっている。反面、円安で増益になる企業は限定的であり、全体としては今もなお賃金は下降傾向...
最近、パソコンが高い。海外生産あるいは海外からのパーツ調達が多いため、円安の影響をもろに受けた結果である。発電用燃料の輸入とエレクトニクス製品の輸入の増加により、物価の円安感応度が近年とみに高まっている。反面、円安で増益になる企業は限定的であり、全体としては今もなお賃金は下降傾向にある。消費者物価は上昇し、ますます労働者の生活は貧しくなっている。財界に賃上げを呼びかけるもさしたる効果もない。賃金は個々の企業が決めるのではなく労働市場が決めるものであれば当然の帰結である。企業の売り上げが伸びなければ労働需要は増えないし賃金も上昇しない。日本の就業構造は大きく変化している。まずはその現実を見つめなおさなければならない。賃金問題は産業構造の問題。賃金の高い製造業の縮小は新興国の工業化によるものであって、いかなる先進国もこの状況を覆すことはできない。政府が緊急に実施すべきことは円安を抑えて実質賃金を上げること。日本再興戦略に欠けているのは縮小する製造業にかわって日本産業の中心となる産業をどうするのかという視点。製造業を中心とする発想からの脱却を図らなければならない。成熟経済における成長戦略は投資より消費。サービス産業は国際競争力が低く国際収支は恒常的に赤字であるという現実。これにどう取り組んでいくのかが日本浮沈の重要な鍵となる。
Posted by
ユーロ危機は再燃する可能性がある。 トルコ、インド、ブラジル、南アフリカ、インドネシアの通貨は信用が低く、ふらじゃいるファイブと呼ばれてきた。 経常収支が黒いか赤字ではなく、資本収支の黒字を計座億できるような信頼を獲得しているか。
Posted by
「アベノミクス」が失敗であることを豊富なデータで論証している書である。 本書は、報道での経済動向を聞く時に新たな視点を提供してくれる良書であると思えた。 なるほど専門家はこう評価するのかと、いちいちうなづく思いがしたが、はたして事実は本書のように推移するのだろうか。
Posted by
出張移動中に読了。 主張はこれまでと変わらず、 ・アベノミクスは期待された効果を発揮してはいない ・異次元金融緩和によりマネタリーベースをじゃぶじゃぶにしてもマネーストックはほとんど増えていない。金利はむしろ上昇した。企業の設備投資は増えていない。 ・日本国債バブル崩壊の危険性を...
出張移動中に読了。 主張はこれまでと変わらず、 ・アベノミクスは期待された効果を発揮してはいない ・異次元金融緩和によりマネタリーベースをじゃぶじゃぶにしてもマネーストックはほとんど増えていない。金利はむしろ上昇した。企業の設備投資は増えていない。 ・日本国債バブル崩壊の危険性を政府は認識しなければならない。 ・経済成長策において、製造業を主体に考えた輸出立国モデル、設備投資牽引モデルはもはや日本においては成り立たない。 ・企業の利益が増えても賃金は上昇しない。 ・日本経済の活性化に向けては、消費を主体に考えた政策と、産業構造の転換を図るしかない。 等々といったところか。 Q&A形式での章だて(節だて)となっており、読みやすい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自分はこれまでアベノミクスの効果効用について、とても疑問を抱いていた。円安が進み、輸出企業の利益が増える、賃金がUPという循環が報道されているが、本当にこのやり方が国際競争力という点で、正しい方向なのか?ということが疑問だった。円安で製造業の利益が増えたように見えるが、本来、為替が変動してみせかけの利益が増えることは、企業にとってあまり良く無いと考えている。というより、たかが円安が進行しただけで、こんなに株高になることが、自由資本主義にかなっていることなのか? この本は、そんな疑問に答えてくれる良書だと思う。 一つの結論は、もう日本は貿易立国で無いということを認識することである。私の世代は、学校なので、「日本は貿易立国であり、そのお蔭で経済発展をしている」と教えられている。すなわち、今後も日本が貿易立国であるということを信じさせていることである。 アベ首相は、「円安で日本国内に製造業が戻った」と言っているが、この本を読めば、日本に製造業が戻ることはあり得ないことが理解できると思う。自分も製造業の現場にいると、つくづくそう感じる。 日本のこれからの産業構造を考えるには、とても参考になる一冊である。
Posted by
- 1