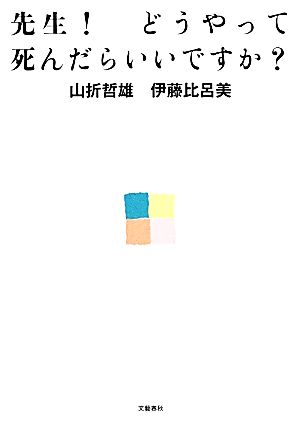先生!どうやって死んだらいいですか? の商品レビュー
お互いが相手のボールを丁寧に返す対談ではなく、相手の話から思いついたしたい話をする、というタイプの対談に感じた 良い悪いではなく お二人のことを知っていればより楽しく読めるのか 性について真面目に語る本にであえたのは収穫か
Posted by
「先生!どうやって死んだらいいですか?」山折哲雄・伊藤比呂美著、文藝春秋、2014.02.15 198p ¥1,680 C0095 (2021.09.29読了)(2021.09.28拝借) 【目次】 まえがき 伊藤比呂美 Session1 性をこころえる 食欲と性欲の切っても...
「先生!どうやって死んだらいいですか?」山折哲雄・伊藤比呂美著、文藝春秋、2014.02.15 198p ¥1,680 C0095 (2021.09.29読了)(2021.09.28拝借) 【目次】 まえがき 伊藤比呂美 Session1 性をこころえる 食欲と性欲の切っても切れない関係 欲望を満たしつつ、快く死んでいきたい 「翁」の表情は日本の老人の理想 仏像はみな若々しい ほか Session2 老によりそう 木石のように生きる 乾いた仏教、湿った仏教 国を誤らせた五七調 短歌が苦しみを軽減する Session3 病とむきあう 創造的な病 「気配の文化」と「告知の文化」 「思いやり」のあいまいさ Session4 死のむこうに 骨を噛む ひと握り散骨のすすめ 儀式抜きで生きていけない 残された者の側からの決めつけ ほか あとがき 山折哲雄 ☆関連図書(既読) ・山折哲雄 「日本の仏教と民俗」山折哲雄著、NHK市民大学、1989.10.01 「親鸞をよむ」山折哲雄著、岩波新書、2007.10.19 「『教行信証』を読む」山折哲雄著、岩波新書、2010.08.20 ・伊藤比呂美 「今日 Today」伊藤比呂美訳・下田昌克絵、福音館書店、2013.02.15 (アマゾンより) 出産、子育て、閉経、両親の介護と死を経て、忍び寄るのは自らの老い。 生きることを真正面から見つめ、格闘してきた詩人・伊藤比呂美が、宗教学者に「老い方」と「その心構え」を訊きにいく。
Posted by
山折氏と伊藤氏の対談という設定自体が面白い。 山折氏がたじたじしているのが伝わってくる場面があり、なかなか楽しく読みました。 死生観の話しは興味深かったです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
人間、食べられなくなったら枯れるように死んでいく。 これが一番自然だと思う。 近藤誠氏と通じるものがあった。納得。 日本人の遺骨信仰は独特なのかぁ。 お墓についても考えさせられた。
Posted by
生きることは無常観との闘いですね。 普段、儀式なんかは気にしない方ですが、何かに自分の心を乗せるとき、 何かに入り込む時は儀式が大事な役割を果たすことに気がつきました。
Posted by
【両親の介護を経て、忍び寄るのは自らの老い】生きることを真正面から見つめ、格闘してきた詩人・伊藤比呂美が、宗教学者・山折哲雄に問いかける、「老いを生きる知恵」。
Posted by
山折先生と伊藤比呂美さんの公開対談をまとめたもの。「性・老・病・死」の四つのセッションに分かれている。 正直言って「性」のパートはピンとこなかった。お二人の話もすごくかみ合ってるとは言いがたい。性の話は本当に微妙で、そうだよね!と思うものってとても少ない。個人の性意識っていうの...
山折先生と伊藤比呂美さんの公開対談をまとめたもの。「性・老・病・死」の四つのセッションに分かれている。 正直言って「性」のパートはピンとこなかった。お二人の話もすごくかみ合ってるとは言いがたい。性の話は本当に微妙で、そうだよね!と思うものってとても少ない。個人の性意識っていうのは、もちろん文化に大きく規定されるけれど、個の幻想なのだからして(私は岸田秀さんの唯幻論信奉者です)そういうものなのだろうと思う。 俄然面白くなってきたのは、「老」のパートから。今の日本は、老いを醜く弱くなることととらえ、強迫症的に若く行動的にふるまおうとするアメリカのありように似てきている。また、合理主義的思考が行き渡り、死後の世界のイメージを持たなくなったので、死への恐れから逃れられない。伊藤さんが、死に向かう自らの父を見つめて最も苦しんだのは、その恐怖、孤独のいかんともしがたいことだったという。 ここで持ち出されるのが、「短歌的叙情」であるところが面白い。モンスーン気候ならではの湿り気たっぷりの日本風土には、短歌の五七調がしっくりくるのだと山折先生は言う。古来日本人は死に際して和歌を詠んできた。「死を前にしたとき、この世からあの世への識閾を越えるために、和歌のリズムは重要な役割を果たしていると考えられます」 特攻隊員も和歌を残して死んでいった。戦後、五七七のリズムを「奴隷の韻律」として否定する所から現代詩は始まった。五七調は日本の伝統的価値観を支える韻律であったのだ。(だから全共闘の演説は五五調で、それゆえ広く訴える力がなかった、という先生の説にはかなり納得) もちろん、それは一度は否定されなければならなかったものであることに間違いはない。詩人である伊藤さんが「やっぱりたたっ切ってしまわなきゃならないものだったと思う。あれがある限り先に進めないという思いがあって」と言うとおり。その伊藤さんも、お経のリズムにたどり着いた。 繰り返す季節と人の生とを重ね合わせて一生を見つめるという生き方、死を「イメージトレーニング」していくことの手立てとして、短歌の、あるいはそれに代わるものの韻律が有効なのではないかという考え方には、なにかとても心惹かれるものがあった。 他にも「儀式・作法」について(「儀式抜きでは私たちは一日も生きていけない」)、「安楽死」について(「日本には自殺文化が埋め込まれている」)などなど、興味深い話が次々出てくる。山折先生の著作そのものを読んでいるより、よくわかったような気になるのが対談の妙だろう。
Posted by
- 1