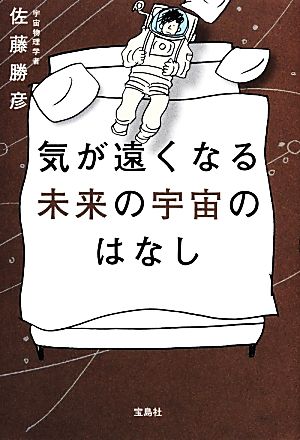気が遠くなる未来の宇宙のはなし の商品レビュー
宇宙物理学者である著者が24個の未来予想をもとに宇宙の未来について予想していくもの。 SF小説『タウ・ゼロ』から考えるタイムトラベルのはなし、次の氷期のはなし、北極星が移動するはなしや超大陸のはなし、太陽系の未来や銀河系の未来、宇宙の未来についてなどがあった。 最初は物語を読むよ...
宇宙物理学者である著者が24個の未来予想をもとに宇宙の未来について予想していくもの。 SF小説『タウ・ゼロ』から考えるタイムトラベルのはなし、次の氷期のはなし、北極星が移動するはなしや超大陸のはなし、太陽系の未来や銀河系の未来、宇宙の未来についてなどがあった。 最初は物語を読むように読めたのだが、宇宙全体の話になると物理の話が多くなり、さらっと読むには辛かった。 著者は巻末に知的生命とは生きる意味を考える存在であるとし、だからこそ宇宙について未来について解き明かそうとするのではないかと語っていた。 知りたいと思えるのは知的生命であるからこそで、地球の未来について宇宙の未来についてこれからも考察されていくのが楽しみだなと思った。
Posted by
宇宙の未来にまつわる記述を読んでいるうち、気がつくと、地球を離れた視点に浮かび上がっているこの感覚。さっきまで、地球に隕石が当たるとか太陽がそこまで膨れ上がるとか、恐怖を掻き立てる話だったのに、陽子が崩壊するとかブラックホールがその質量を減らすとか、もう。ぎりぎり想像が及ぶ、千年...
宇宙の未来にまつわる記述を読んでいるうち、気がつくと、地球を離れた視点に浮かび上がっているこの感覚。さっきまで、地球に隕石が当たるとか太陽がそこまで膨れ上がるとか、恐怖を掻き立てる話だったのに、陽子が崩壊するとかブラックホールがその質量を減らすとか、もう。ぎりぎり想像が及ぶ、千年万年のスケールを凌駕しだすから、いよいよ無感動になるのかしら。しかし、この「気が遠くな」って無になる感じ、嫌いになれないのである。記述を読み終わるなり令和の御世に帰ってきて、おもむろに猫の喉を掻いてやる不思議。
Posted by
ホンタナ(http://hontana.info/ )にて配信中: 紹介回: https://bit.ly/3cC9gp4 感想回: https://bit.ly/2EKUCzk
Posted by
宇宙の入門書として知らないことをたくさん書いてくれている。読んでいるうちに楽しくなってくる。 短いコラム的な文章だから読みやすく、知らない人に向けて噛み砕いて話しているのでありがたい。 宇宙だけでなく科学の話は入門書でもいきなり専門的な言葉が出てくることがあるから読み進むのがしん...
宇宙の入門書として知らないことをたくさん書いてくれている。読んでいるうちに楽しくなってくる。 短いコラム的な文章だから読みやすく、知らない人に向けて噛み砕いて話しているのでありがたい。 宇宙だけでなく科学の話は入門書でもいきなり専門的な言葉が出てくることがあるから読み進むのがしんどいことが多いのだけど、この本は短章の積み重ねだから読みやすい。
Posted by
『眠れなくなる宇宙』シリーズの第三弾は、未来がテーマ。1,500年後から始まって数億年後まで、地球・太陽・宇宙の姿をインフレーション理論の第一人者が予想する。第一弾、第二弾同様、語り口は優しくやわらかく、難しい話も分かりやすい例えを使って語ってくれるので、宇宙への夢がどんどん広が...
『眠れなくなる宇宙』シリーズの第三弾は、未来がテーマ。1,500年後から始まって数億年後まで、地球・太陽・宇宙の姿をインフレーション理論の第一人者が予想する。第一弾、第二弾同様、語り口は優しくやわらかく、難しい話も分かりやすい例えを使って語ってくれるので、宇宙への夢がどんどん広がる。 ワタシは常々、人類が順番に宇宙船に乗って地球やその他の星を外から見たら、世界で起きている内戦や紛争のかなりのものがなくなるのでは、と思っている。そして、『眠れなくなる宇宙』シリーズを読むたびにその思いを強くしている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
こういう距離的にも時間的にも遠くの話には圧倒される。太陽も地球も寿命があって、死期が確定している。ずっと未来の話だけど、無限ではなく有限。そのとき人類はもういないんだろうなとか、そのとき生きている生物がいるとしたらそれでもなんとか生き延びるのだろうかとか、想像を遥かに超えている。引っかかった話としては、 ・地磁気の反転は一気に起きるのではなく、だんだん地磁気が弱くなっていってそのあと反対向きの地磁気が出現する ・今はこぐま座α星が「その位置」にあるように見えるから北極星と呼ばれるけれど、過去、そして未来の時間では見かけの位置がずれるので別の星が北極星となる ・月が今はちょうどいい位置、大きさであるのために起きている皆既日食がいずれは起きなくなるということ ・月はだんだん遠ざかっていて、今後公転速度が下がっていって、地球から見ると登ったり沈んだりしなくなって、いつも同じ位置に見えるようになる(地球の反対側からは見えなくなる)ということ など。 新幹線で読んでいたのだけれど、宇都宮から乗ってきたスーツ姿の若手サラリーマン(営業?)が私の隣に座るなり、ビールを飲みながらスマホでゲームをやりだして、ずいぶん世界が違うなと思った次第。
Posted by
佐藤勝彦氏のシリーズ三冊目。タイトル通り、想像すると気が遠くなりそうな、太陽系を含めた宇宙の向かう先の話。宇宙は収縮するのか、膨張するのか、はたまた相転移して子宇宙、孫宇宙が誕生するのか、まだ答えの見えない難しい専門的な内容がわかりやすく章だてて書かれている。 宇宙の終わりを考え...
佐藤勝彦氏のシリーズ三冊目。タイトル通り、想像すると気が遠くなりそうな、太陽系を含めた宇宙の向かう先の話。宇宙は収縮するのか、膨張するのか、はたまた相転移して子宇宙、孫宇宙が誕生するのか、まだ答えの見えない難しい専門的な内容がわかりやすく章だてて書かれている。 宇宙の終わりを考えることは宇宙の始まりを考えること、そして物質がどのように誕生したのか探求すること。 長崎訓子さんの素敵なイラストも含めて楽しめるシリーズでした。
Posted by
~の理論にしたがえば、~億年後の宇宙は~となる。テクノロジーの進化によって未来予想が大きく変わる。宇宙の悠久な時間からすれば、人間の人生など瞬きするほどでもない。地球の消滅、宇宙のビッグクリンチ、物質の消滅などを心配するのは杞憂ではあるが、遠い未来を思いをはせるにもってこいの本...
~の理論にしたがえば、~億年後の宇宙は~となる。テクノロジーの進化によって未来予想が大きく変わる。宇宙の悠久な時間からすれば、人間の人生など瞬きするほどでもない。地球の消滅、宇宙のビッグクリンチ、物質の消滅などを心配するのは杞憂ではあるが、遠い未来を思いをはせるにもってこいの本である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本当に気が遠くなるような未来のはなし。個人的にはエネルギーの塊みたいに思われている太陽の最期が読んでて悲しくなった。まぁ、61億1000万年後って人類存在していないんだろうけど。 あと、2013年のロシアに落ちたチェリャンビンスク隕石でも結構衝撃だったのに、恐竜をも滅ぼした隕石の破壊力の凄まじさたるや…。恐ろしいな。
Posted by
先の「眠れなくなる宇宙のはなし」に引き続いて読了した今回の「気が遠くなる未来の宇宙のはなし」でしたが、後述する最後の夜(章)の著者の佐藤さんのお話が、まさに私がかねてから想像というか(妄想でしょうか!?)これこそが究極の人類の目標ではないかという記述がありました。最初の「眠れなく...
先の「眠れなくなる宇宙のはなし」に引き続いて読了した今回の「気が遠くなる未来の宇宙のはなし」でしたが、後述する最後の夜(章)の著者の佐藤さんのお話が、まさに私がかねてから想像というか(妄想でしょうか!?)これこそが究極の人類の目標ではないかという記述がありました。最初の「眠れなくなる~」も同様でしたが、佐藤さんの丁寧な解説というか解説を超えた分かり易い語り口で、最初から最後までどんどん引き込まれます。それでも内容としては、既に読んでいる他の最新宇宙論に出てくるマルチバース論や加速膨張する宇宙の最後の空虚な姿などは、最近のハードSFの土台にもなっているものです。 何度か他の本でも読んでますし、ハードSFにも出てくる姿なのですが、膨張しきった宇宙の最後が素粒子すらも存在しない終わり方というのは何とも寂しいものです。しかし、本書には現在ではまだ解明されていないダークマター(ダークエネルギー)が今後の大統一理論の鍵を握るということで、かつてのニュートン力学に対する相対性理論のようなインパクトがあるのではと予想しています。それであれば現在の宇宙論で予想されている宇宙とはまた違った終わり方となる可能性の方が高いですね。 最初の「眠れなくなる~」であったように、古代の人々からは想像もできない宇宙の姿の変化があったわけですから、この際の長い人類の歴史の中でどんどん宇宙の姿、しいては宇宙の未来も書き換えられる可能性の方が高い気がしています。 それはそれとして、佐藤さんが最新の理論や世界の学者の論拠として紹介しつつ述べられている最終夜(最終章)での、人類の未来の可能性には共感と共にポジティブで今の人類が生きる意味、究極の目標としての存在意義を感じます。今後の100年、1000年スケールで太陽系、10万年スケールでは銀河系にその活動域を広げるという話や、地球型生命体であるタンパク質の殻を破って宇宙型生命体に自己進化するなどという話は、学者というよりかはどこかのハードSFの話のようなのですが、これらも一つの可能性として不可能ではないのでしょう。 最終章は、この本のテーマというか主題である宇宙の終末とは一歩離れた感のある異色な感じではあるのですが、佐藤さんの宇宙論入門であるこのシリーズ3部作(実は2部目にあたる本はまだ読んでないのですけれども)にある宇宙論の意義、しいては人間の存在意義を探求する学問の一つとしての想いがよく伝わってきます。人間進化にある「1万年前の心」のままという話も納得させられると共に、非常に興味深いです。 本書の中でも宇宙の終末の形に関わらずに、孫宇宙、子供宇宙への生成や脱出の可能性など、まるでバクスターシリーズのジーリー顔負けのテクノロジーの話が出てきます。それもこれもこの先、1,000年、10万年単位で人類が存続できるのであれば、夢物語ではないのでしょう。そんな意味でも、「1万年前」のメンタリティーで生き続けている人類が存続できるかどうかの瀬戸際の時代というのは、あながち大袈裟でも無いのかも知れません。 そんな中で、たびたび話題に出る宇宙の物理理論(宇宙のグランドデザイン)に纏わる「人間原理」の理屈などは、ちょっと難解な感じでピンときませんし、毎年のように新発見もある量子物理の世界ですから、このジャンルの本にはしばらく目が離せそうにありません。 最後に「知的生命とは「生きる意味」を考える存在」という一文が、本当にじんと来る言葉です。人類が存続する限り、宇宙も存在し続ける、そんな相互関係があるようなロマンスを感じました。
Posted by