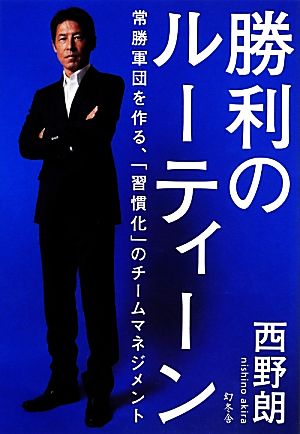勝利のルーティーン の商品レビュー
西野さんの社会人サッカー選手になってから、名古屋の監督になるまでの自伝 監督としての考え方が主に語られています。個人的な感想は、見た目と違ってかなり頑固な人だな〜です笑
Posted by
西野監督の監督としての経歴が分かる内容。 ヴィジョンとスタイルが必要。 過去の経験より、 超攻撃的なポゼッションサッカーという スタイルを目指すことになった。 毎日のトレーニングや生活リズムの習慣化を 積み重ねていくことで、 クオリティを上げていく。 気が付けば目標を達成...
西野監督の監督としての経歴が分かる内容。 ヴィジョンとスタイルが必要。 過去の経験より、 超攻撃的なポゼッションサッカーという スタイルを目指すことになった。 毎日のトレーニングや生活リズムの習慣化を 積み重ねていくことで、 クオリティを上げていく。 気が付けば目標を達成していたということになっている。 以上
Posted by
西野さんがこれからグランパスでどのような采配を見せてくれるのかの手がかりをつかむというよりは、これまでの経歴をおさらいができてよかったという感じかな。 懐かしい選手の名前も出てきたりして、そういう面ではおもしろく読むことができました。
Posted by
”サッカー監督にはヴィジョンが必要だ” サッカー監督に限ったことではないと思うけど、すごく大切なことだとオイラも考える。チームを率いる人にそれがなければ、行き先を見失っていずれ空中分解してしまうだろう。ヴィジョンを持つ→実現可能な目標設定をする→毎日のトレーニングや生活のリズムを...
”サッカー監督にはヴィジョンが必要だ” サッカー監督に限ったことではないと思うけど、すごく大切なことだとオイラも考える。チームを率いる人にそれがなければ、行き先を見失っていずれ空中分解してしまうだろう。ヴィジョンを持つ→実現可能な目標設定をする→毎日のトレーニングや生活のリズムを習慣化する→気がつけば目標を達成していた、ってすごくシンプルだけどこれができないからみんな苦労してるんだよなぁ。オイラが思うに、最初のヴィジョンが要なんじゃないかと思う。サッカーチームで例えると、もちろん勝つことがいちばんだけど、どんな戦い方をするのか、どんな勝ち方や負け方をするのか、などなど監督のヴィジョンが明確であればあるほど、最短距離で近づいていくんだろう。きっと個人においても一緒だ。どんな人になりたいか、って聞かれて人物名で答える人はきっと個人のヴィジョンが明確だろうな。チームでも個人においても、やりたいことがはっきりしていてそれに向かって真っすぐな姿を見てまわりの人も応援したくなるんだよなぁ。
Posted by
ワールドカップでの活躍を見て、興味を持ったので読みました。サッカーの監督としての思いやこだわりを知ることができました。
Posted by
西野監督がガンバ大阪を指揮して実践した「ポゼッションサッカー」 とにかくボールを持ち続けて失点のリスクを未然に防ぎ、前に前にボールを運び続け攻め続けるサッカー。 試合終盤、例えリードしていたとしても、前に進み続ける攻撃的サッカー。 その信念・ヴィジョンは明確であり、それをチームに...
西野監督がガンバ大阪を指揮して実践した「ポゼッションサッカー」 とにかくボールを持ち続けて失点のリスクを未然に防ぎ、前に前にボールを運び続け攻め続けるサッカー。 試合終盤、例えリードしていたとしても、前に進み続ける攻撃的サッカー。 その信念・ヴィジョンは明確であり、それをチームに定着させるためには長いスパンでのチーム育成が必要であり(つまり短期間で解任されるのはたまらん、と。)、長期政権を任せてもらえたからこそガンバでそれを成し遂げられた、と。 2018W杯では本番直前にナショナルチームの監督に就任することとなり、短い準備期間の中でのチーム作りを強いられ、ポーランド戦では世界中から批判を浴びたボール回しも断行し(西野監督自身が最も不本意だっただろう。この本を読んでわかった。)、結果として見事GL突破に繋げた。 西野監督に心からBravo。 同郷。さいたまが生んだスター。 あと、驚いたのは、監督というのはここまで選手とのコミュニケーションの仕方に気を遣う職業なのか、と。 繊細なコミュニケーションをする上でも代表監督は同じ言語で意思疎通できる日本人監督がやはりよいのかなぁ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ヴィッセル神戸やガンバ大阪で指揮を取った西野監督の著書。自身の監督業経験を交えつつ、そこで感じた監督に必要な力量、選手を伸ばす・チームを強くするための苦労など、監督と言う視点でしかわからない話が多く、ためになった。 スタイルを貫く・チームを次のステージに押し上げることの難しさと重要性は、メディアや選手からも理解されない・誤解されることもあるくらい伝わりにくいものなのだと思う反面、それを生きがい・職業としてまい進していく著者の姿には感嘆するばかりだった。
Posted by
前著的な位置づけになるだろうか「攻め切る―指揮官西野朗の覚悟」では、フォトブックのような形であったが、本書は西野氏の執筆となっている(もちろんGwかもしれないが) 内容は4章構成で、1章は監督に3つの必要な能力として、洞察力、コミュニケーション力、想像力を挙げている。2章では、...
前著的な位置づけになるだろうか「攻め切る―指揮官西野朗の覚悟」では、フォトブックのような形であったが、本書は西野氏の執筆となっている(もちろんGwかもしれないが) 内容は4章構成で、1章は監督に3つの必要な能力として、洞察力、コミュニケーション力、想像力を挙げている。2章では、監督の采配とフロントを含めたチームマネージメントについて、3章では主にG大阪監督時代の采配、補強などがメインだが、オリンピック監督時代、柏監督時代などを含めてコンセプトの大切さを説いている。4章は、神戸監督のシーズン途中就任、解雇、日本代表についての考えを述べている。 西野氏と言えば、オリンピックドン引きサッカー、柏時代のこれからというときの解任、G大阪の攻撃サッカーなどがあげられると思うが、本書では意外にいろいろとバランスをとろうとしている姿が興味深かった。しかし、神戸でカウンターサッカーが払拭できなかったように、伝統や選手の癖はなかなか抜けないのも事実だと思う。その意味では、G大阪時代は相思相愛のよい時代だったとも感じた。 また、いろいろと練習メニュー等を変化させるよりも、変化させないことのルーティーン化によって、安定化を求めていることもわかった。この仕事は結果がすべてなので、何がよいかは結果がすべてを物語るのだろうが、いろいろ考えての西野スタイルだったんだと思った。 2014年は、久しぶりに久米GMと名古屋の監督としてタッグを組む。西野式のスタイルがどのようになるのか、注目していきたい。
Posted by
- 1