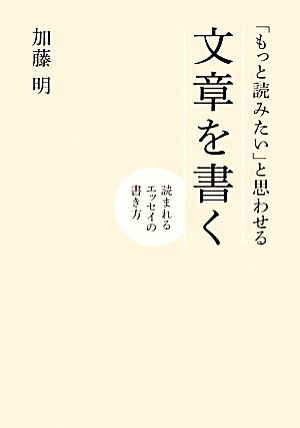「もっと読みたい」と思わせる文章を書く の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本のここがオススメ 「読まれないエッセイには、価値観の転換がない場合が多い。筆者の物の見方、価値観を変えた感動や驚き、発見がない。だから書き始めと書き終わりで、書き手の物の見方や価値観はほとんど不変のままです。あるのは気分、感情の変化ぐらい」
Posted by
役に立ちました。 以前学んだ起承転結について、詳しく記載されており、 再度学び直すことができた。 大学の同窓会誌にエッセイの募集があり、ほんしよもさんこあにさせてもらったか。 ---------- 以前、下記の本を参考にしようと思ったが、 羊頭狗肉の様な本で大いに失望した...
役に立ちました。 以前学んだ起承転結について、詳しく記載されており、 再度学び直すことができた。 大学の同窓会誌にエッセイの募集があり、ほんしよもさんこあにさせてもらったか。 ---------- 以前、下記の本を参考にしようと思ったが、 羊頭狗肉の様な本で大いに失望した。 辻 真先 旅のエッセイ教室―地球の書き方、歩き方 ------------ でも、今回の本は書名と中身が一致しており、求める内容が記載されていたので満足だ。
Posted by
文章を書く上での「起承転結」を意識することの重要性が書かれている。 エッセイ教室で教鞭をとる著者による、生徒が実際に書いたエッセイを例に挙げての文章指南となっているため、エッセイを書く人には良いかも。
Posted by
冗談なのかどうか分からないが、上から目線の表現が気になる。「言うべきこと」と「言いいたいこと」の区別をつけずに記述されているため、随所で気がそがれる。
Posted by
皆が勘違いしているが、赤の他人が書いた文章なんて、誰も最後まで読んではくれないものなのだ。では、どうすれば最後まで読んでもらえるおもしろい、「もっと読みたい」と思ってもらえる文章を書くことができるのだろうか。週刊朝日編集長、朝日新聞論説委員をつとめた著者が実例をもとに、読む人の心...
皆が勘違いしているが、赤の他人が書いた文章なんて、誰も最後まで読んではくれないものなのだ。では、どうすれば最後まで読んでもらえるおもしろい、「もっと読みたい」と思ってもらえる文章を書くことができるのだろうか。週刊朝日編集長、朝日新聞論説委員をつとめた著者が実例をもとに、読む人の心を惹きつけるエッセイの書き方を手ほどきする。 このように誰からでも見てもらえる形で本の感想を綴っていることもあり、読みやすい文章を書くコツを知ることができれば…と思い、本書を手に取った。 最後まで読まれる文書を書くために、表現力や語彙力よりもすぐに習得できる技、それはたった二つ。「起承転結」で文章を組み立てることと、深く掘り下げ色々な角度から切り込むことができる「ネタの鉱脈」を持っておくこと。この二つのポイントを、著者が講師を務めたカルチャーセンターの文章講座の生徒の実例を数多く引用しながら、丁寧にわかりやすく解説してくれる。 「起承転結」なんて小学校で習うような基本的なことだが、実際に文章を書く際に意識したことがあっただろうか。「起承転結」に沿った構造にするだけで、文章のわかりやすさは劇的に変わってしまうことが、文章講座の生徒が書いたエッセイからも理解できる。本書では起・承・転・結それぞれに、具体的にどのようなことを書けばよいのか、どのような順で考えれば書きやすいか等も解説してくれている。他にも、読まれないエッセイの構造や、気をつけるべき表現技法についても説明してくれている。 文章を通して伝えたいことがあっても、余分な話が多すぎたり、時間の流れがばらばらだったり、日本語としてわかりにくい文章だったりすると、読み手には何が言いたいのか伝わらないだけでなく、エッセイの途中で放棄されてしまう可能性もある。少し考えて文章を組み立てるだけで読み手の反応を変えることができるのだから、本書で紹介されたポイントはぜひ覚えておきたい。
Posted by
エッセイの書き方指南書。作文は自己満足、エッセイは読み手を意識して書く。起承転結を意識して書く。作者は週刊誌の編集長を勤めたこともあり、エッセイ講座も開いている。その受講者のエッセイを例として使われており、分かりやすくエッセイ見本集としてもおもしろい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
新聞の広告で見て、気になったもので購入。 読み進めていくうちに興味深いものがいっぱいでした。 筆者は週刊朝日編集長・朝日新聞論説委員を歴任という経歴。 朝日カルチャーセンターの新宿教室で「編集長のエッセイ教室」の講師を務め、定年退職後は「夜のエッセイ塾」を始めたとか。 講義の内容をまとめたものと思われます。 「読まれるエッセイ」を前提に書かれている。 どれもこれも理論的に提示されてて、ストンと胸に落ちてくる。 内容をメモしながら読了した。 重要なのは「起承転結」だと言うこと。 その組み立てと、切り口が左右する。 注意点として「読まれないエッセイの構造を知ろう」の章は耳が痛い。 反対に「読まれるネタの発掘法」は、なるほどと思う。 何にしても、物事をいろんな方向から見て、どんなアイデアでもキャッチできる感性を持たねばならないということだろう。 書き始めに、ちょっと悩んでいたので、この本を読んでよかったと思った。
Posted by
「起承転結」を意識して書く! 「読み手」を意識する! 一番書きたいことは、「転」で書く! 会社のブログを、週一回担当して書いている。 少しでも、読んでもらえるような文章を心がけたい。 とりあえず、明日アップ予定の文章を、 「起承転結」を意識して、書き換えてみた。
Posted by
エッセイは起承転結で書く。その中でも最も書きたいことを転に配置する。起と承は、転への導入で利用する。これだけでも文章が苦手だった私にとっては、かなり有用な情報だった。もちろんこれ以外の型もあるが、まずはこの型で練習することによって、基本が身に付いてくると書かれている。守破離の考え...
エッセイは起承転結で書く。その中でも最も書きたいことを転に配置する。起と承は、転への導入で利用する。これだけでも文章が苦手だった私にとっては、かなり有用な情報だった。もちろんこれ以外の型もあるが、まずはこの型で練習することによって、基本が身に付いてくると書かれている。守破離の考え方と同じだったので、とても共感できた。分かりづらい部分も例をたくさん紹介することで、感覚的に理解させてくれる。 現在はこの通りにいろいろ練習中。起承転結で書いて転に書きたいことを持っていくだけで、随分と文章が安定するのがわかる。他にエッセイのための書籍を知らないが、エッセイを書くならおすすめできる。
Posted by
- 1