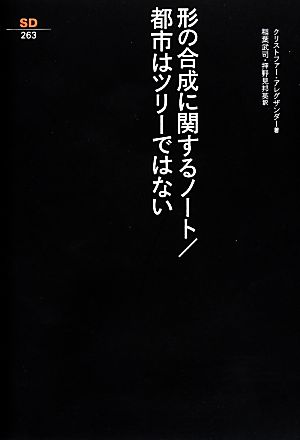形の合成に関するノート/都市はツリーではない の商品レビュー
ハーバードの心理学講義 にでてきた。建築について「デザインはそこに住む人々の根源的な欲求にこたえるものでなければならないと考えた」とのこと。
Posted by
アレグザンダーの博士論文である「形の合成に関するノート」は、今日ではソフトウェア開発の文脈で触れたほうがその価値を理解しやすいかもしれない。 制約条件の中で最良の解を目指すという前提。 変化それ自体を是とし、必ずしも正解のみが正しいとしない考え方。 それぞれの変数が直交性をもつ...
アレグザンダーの博士論文である「形の合成に関するノート」は、今日ではソフトウェア開発の文脈で触れたほうがその価値を理解しやすいかもしれない。 制約条件の中で最良の解を目指すという前提。 変化それ自体を是とし、必ずしも正解のみが正しいとしない考え方。 それぞれの変数が直交性をもつように分解してゆくプロセス。 本文にあるこれらエッセンスからは、変化に適応するためには高い変更可能性を持った設計であることが求められる、という事実が浮かび上がってくる。 ソフトウェアに限らず、物事の本質ではあるのだろう。しかし実体のあるものがもてる変更容易性には限界がある。だからこそ、この考え方はどこまでも変更容易性を高められる(であろう)ソフトウェア開発の文脈で広く受け入れられたのだろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ステークホルダーが多種多様なデザインを経験や勘ではなく数学的に解き明かし体系化するとどうなるかということについての研究を綴ったものである。 建築家であるクリストファー・アレグザンダーは慶應大学SFCの井庭崇教授によるパターン・ランゲージから知った。パターン・ランゲージ自体には数学的な要素は皆無なのだが、本書では都市のデザインにおいて複数の検討課題が生じている場合に、どれをどのように説いていくのか、その関係性と優先度を数学により求めるということがテーマになっている。 個人的には後から見たらたしかにそうなる的なアプローチであり、判断に迷った場合の参考程度にはなるだろうが、この数学だけを信じて検討を重ねるのには無理があると言わざるをえない。数学に落とし込む前にどのように事態をとらえ、どうありたいのかみたいなところは数学ではなく、あくまでもそれを検討している人物の「センス」すなわちどこまで深く考えが及んでいるのかということズバリだからだ。 とはいえアプローチは面白い。
Posted by
- 1