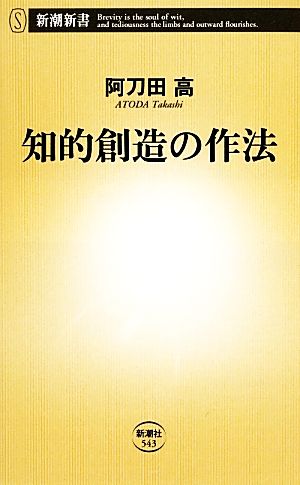知的創造の作法 の商品レビュー
40年以上前にナポレオン狂を読んでから、ブラックユーモアや「知っていますか」シリーズなど、いくつか読んできたので、著者が大切にしてきたことなどがすんなりと入ってきた。 ■臨界というのは決定的な情況よりまだほんの少し手前のような気がしてしまうのだ。臨海、臨月、臨床...臨界も限界に...
40年以上前にナポレオン狂を読んでから、ブラックユーモアや「知っていますか」シリーズなど、いくつか読んできたので、著者が大切にしてきたことなどがすんなりと入ってきた。 ■臨界というのは決定的な情況よりまだほんの少し手前のような気がしてしまうのだ。臨海、臨月、臨床...臨界も限界に近づいているが化学反応にまだ余裕があるような気がしてならない。でも臨界はもう事故そのものなのである。 →同感。これに限らず、名前と中身が一致していないものが時々ある。最近いくつかの本を読んで、それを感じた。 ■ユーモアは笑いを生むことも多いが、それは副産物であり、本当の価値は日常の中でべつな見方をすること、そういう脳味噌を持っていること、そう考えるのが正しい。→副産物だけを目指すのはやめよう。 ■あまりに行き届いた詳しいメモは、後になって、かえってそれに高速されてしまうため、結果がよくないようです。→発想、創造の余地を残しておく。
Posted by
短編小説家である阿刀田高さんのアイデア本を読みました。 ◆読んだきっかけ 阿刀田さんのことは知らなかったのですが、池上彰さんと佐藤優さんの共著『僕らが毎日やっている最強の読み方』にて、古典などの教養をかいつまんで上手に教えてくれる作者として紹介されていました。そこで『シェイク...
短編小説家である阿刀田高さんのアイデア本を読みました。 ◆読んだきっかけ 阿刀田さんのことは知らなかったのですが、池上彰さんと佐藤優さんの共著『僕らが毎日やっている最強の読み方』にて、古典などの教養をかいつまんで上手に教えてくれる作者として紹介されていました。そこで『シェイクスピアを楽しむために 』などを購入する過程で見つけたのがこの本でした。 ◆作者について ・本書の時点(2013)で70歳超え ・本書によると、アイデア満載の短編小説を900本も書いたらしい (見える幽霊ではなく、匂う幽霊の話など) ・旧約聖書、新訳聖書、コーランのダイジェスト本が人気 ◆読書レビュー 70歳を超えて、こんなに簡潔でおもしろい文章を書けるというのがまずすごい!文章からもっと若い人を想像して読んでいました。本を読む前に著者の年齢までは調べていませんでしたので… でも、なるほど、「つとに知られている」のような、懐かしい(古風な?)言葉がときどき出てきます。「つきづきしい」という言葉は初めて知ったので調べたところ、阿刀田さんの口癖なのでしょうか、他の本にも頻出するそうです(※)。 ※他ブログ参照 http://www.ytv.co.jp/michiura/time/2013/07/post-1777.html >p15 夫婦愛などもつきづきしい >p48 比喩的なダイジェストとしてつきづきしい >p52 飲酒主義を要約してつきづきしい 「たけだけしい」と語呂が似ていますね。「似合っている」といった意味だそう。 阿刀田さんのアイデア作成メソッドは、私なり表現すれば、 知識+目的+個人(着目の仕方)→アイデア 著者の知識に著者なりのダイジェストをすると、古典は次のように解説できるとのこと。 >p25 >旧約聖書はイスラエルの建国史 >新約聖書はイエス・キリストの伝記 >コーランは偉い親父の説教 アイデア発想はセレンディピティ次第。セレンディピティとは、努力すると現れる「棚からぼたもち」のこと。 いろいろな知識や既存のものを着眼点を変えて組み合わせるという彼の手法は、他の人も書いているアイデア作りの王道ですが、それを小説に発展させているのが新鮮でした。 ◆この本の影響 阿刀田さんのアイデア小説の発想秘話を読んでいると、自分でも何か話やネタを書きたくなってきてしまいます。そこで、子どものおもしろい行動と自然界の生き物を結びつけた話or図鑑を考えてみました。0歳だったうちの息子は誰もいないところへ向かって「いないいないばあ」をしていたのですが、そういう虫とかいないかな、って(笑) また、今まで苦手としてきた分野の知識・教養にも興味が出たので、阿刀田さんの「知っていますか」シリーズを読んでいくことにしました。 ◆関連して読みたい本 ・『ニッポンの大問題 池上流・情報分析のヒント44』 作中で紹介された書籍の中から。 「進次郎にみるプレゼン力」の章がおもしろそう。 ・『明日物語』 著者が紹介した『発明の母』が収録されている本。 ・『シーシュポスの神話』 ・『サン・ジェルマン伯爵考』 ・『新編 算私語録』 画家で絵本も描いている方です。 ・『ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉』 先日読み終わった『不死細胞ヒーラ』の関連本としてAmazonでチラチラ見かけていました。まさかここでつながるとは。 ・『旧約聖書を知っていますか』 ・『新約聖書を知っていますか』 ・『コーランを知っていますか』 ・『ギリシア神話を知っていますか』 ・『交通事故学』 本に挟まっていたチラシより。 ◆すでに読み始めた関連本 ・『シェイクスピアを楽しむために』 ・『ロウソクの科学』
Posted by
・知識をダイジェストし、そこからアイディアを生む ・ダイジェストに当たっては、そのまんま縮めるのではなく、ポイントだけを強調し、大胆にはぶき、自分なりの奇型をつくる
Posted by
40年以上、900編以上の作品を生み出し続けている作家の思考的作法。 小説を書くということ意外にも充分に役立つ考え方のコツです。 こういう本を読むとなんとなく創作意欲みたいなものを掻き立てられて小説なんかも書きたくなってきます。 でも本を読むのは好きだけど書くとなると別モノなんで...
40年以上、900編以上の作品を生み出し続けている作家の思考的作法。 小説を書くということ意外にも充分に役立つ考え方のコツです。 こういう本を読むとなんとなく創作意欲みたいなものを掻き立てられて小説なんかも書きたくなってきます。 でも本を読むのは好きだけど書くとなると別モノなんですよね~。 久しぶりに阿刀田高の小説でも読んでみようかな。
Posted by
小さいとき短編小説を読んで怖かったので、それ以来読んでなかったりする阿刀田高さんの小説。今読むともしかしたら小さい頃わからなかったブラックユーモアや更に背筋をぞくっとさせる恐怖感が感じられそうなのでまた読んでみようと思う。特に「知っていますか」シリーズは。今更ながらもっと本を読め...
小さいとき短編小説を読んで怖かったので、それ以来読んでなかったりする阿刀田高さんの小説。今読むともしかしたら小さい頃わからなかったブラックユーモアや更に背筋をぞくっとさせる恐怖感が感じられそうなのでまた読んでみようと思う。特に「知っていますか」シリーズは。今更ながらもっと本を読めばよかったと後悔先に立たず。あと死ぬまでいったい何冊の本を読めるか、そして活かせるか。本編は読書の必要性、ただし「曖昧さ」が発想を豊かにするということ。思い立ったらメモ。これは人生のどの場面でも当てはまる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
最後は少しダレてしまって斜め読みになったが、気に入ったところを抜粋: ・ダイジェスト そのまんま縮めるのではなく、ポイントだけを強調し、大胆に省き、自分なりの奇型をを作ること、これをつねに念頭に置いてほしい。ゆめゆめ縮図を描こうとしてはならない。 ・街のダイジェスト フィレンツェを訪ねた時。まず真っ先に小高いミケランジェロ広場に案内してくれた。・・・見事に眺望できる。・・・町の詳細はダイジェストの後で、ゆっくりと一日をかけて鑑賞することとなった。 ・一番おもしろいトピックスから入る。 ・とにかく私なりに解釈して、短くして分かりやすく伝えること、信ずることに賭けること、賭けに負けたら、そのダイジェストはただのくず、つねにその覚悟が必要だろう。 ・電通の大社長・吉田秀雄の「鬼十訓」 1.仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。 2.仕事とは、先手々と働き掛けていくことで、受け身でやるものではない。 3.大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。 4.難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。 5.取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。 6.周囲を引きずり回せ、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる。 7・計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。 8.自信を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚みすらない。 9・頭は常に全回転、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ、サービスとはそのようなものだ。 10.摩擦を怖れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未練になる。 ・ユーモア チャーチルのユーモア 「イギリス労働党の創始者はだれか」 「コロンブスだな。出発の時にどこへ行くかも知らず、着いた処が何処かもわからず、しかも全部他人の金でやったのだから」 ・はじめに言葉ありき 英語はthe Word。大文字で始まるWordは神のみ言葉=自然の摂理?
Posted by
「ナポレオン狂」をおそらくライブで読んで以来の… 1979年に直木賞を受賞した「ナポレオン狂」をおそらくライブで読んで以来の長いながいお付き合いです。透明のソフトカバーがかかった本だったような気がします。 仕事で「創造」という言葉にかかわりを持つようになり、「創造」と名のつく...
「ナポレオン狂」をおそらくライブで読んで以来の… 1979年に直木賞を受賞した「ナポレオン狂」をおそらくライブで読んで以来の長いながいお付き合いです。透明のソフトカバーがかかった本だったような気がします。 仕事で「創造」という言葉にかかわりを持つようになり、「創造」と名のつくこの冊子を選んだところ、なんとびっくり、阿刀田さんの新書でした。自身の頭の中やアイデアノートの中に「何かごちゃごちゃしたところ」を溜めておいて、そのアイデアの井戸から新しいものを紡ぎだす彼の方法について、いささか文学的に述べられています。もしかしたらこれは科学ではないのかもしれません。でも、ワタシ自身の発想法に照らしてもうなずけるところの多い冊子でした。 阿刀田さんはやっぱりショートショート!これは、春はあけぼのと同じくらいつくづきしいと思います。
Posted by
ややノウハウ的な要素も入ったエッセイ、と捉えると、情報のふるさとか、網羅性の無さとかは気にならない。
Posted by
あまり中身をよく見ずに、書店で題名に惹かれて衝動買いしたのだが、題名の内容については、本書のどこにも書かれてはいない。 自著の短編作品の紹介(宣伝)と、自慢話ばかり。 こういう著作を、「題名詐欺」とでも言うのだろう。
Posted by
物事をダイジェストして捉える、という1章の内容は濃い。 ただ、後半に行くほどダラダラとした語りになっていき、段々面白味が薄れていく一冊。 なんだか一冊分も書ききれるだけの人をきちんと選んでないような、ある種編集者の怠慢を新書には最近感じているが、この本もそんな部分が多少感じられ...
物事をダイジェストして捉える、という1章の内容は濃い。 ただ、後半に行くほどダラダラとした語りになっていき、段々面白味が薄れていく一冊。 なんだか一冊分も書ききれるだけの人をきちんと選んでないような、ある種編集者の怠慢を新書には最近感じているが、この本もそんな部分が多少感じられたのが残念。 新書のハズレ率って人によると思うが、どうも半々くらいのイメージがあるほど、つまらない本が多い気がする。この本は面白いとつまらないの中間点ぐらいと思う。
Posted by
- 1
- 2