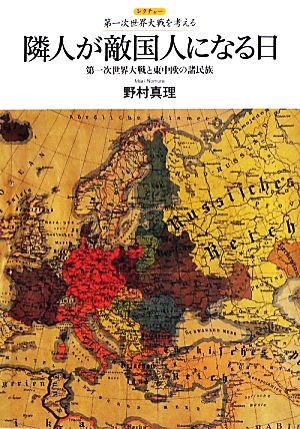隣人が敵国人になる日 の商品レビュー
最初に、第一次世界大戦時における東部戦線の扱いについて書かれている。「オーストリア=ハンガリーとセルビアの戦闘がどのように展開し、どのように決着したのか、これに答えられる人がどれほどいるだろうか。」たしかに、よくわからない。 そして本書の主たる舞台はガリツィアである。これもよく...
最初に、第一次世界大戦時における東部戦線の扱いについて書かれている。「オーストリア=ハンガリーとセルビアの戦闘がどのように展開し、どのように決着したのか、これに答えられる人がどれほどいるだろうか。」たしかに、よくわからない。 そして本書の主たる舞台はガリツィアである。これもよくわからない人が多いと思う。少なくとも私はまったく詳しくない。 ガリツィアは現在のウクライナ南西部にあたる一地域である。本書の舞台となる第一次世界大戦時はオーストリア領だった。この舞台で血に塗れるのは、現在のポーランド人、ウクライナ人、ユダヤ人である。 あとがきに書かれている「日本、日本人、日本語の三点セットの成立に何の疑問も感じず、国家や国籍など意識しないで過ごせる日常は幸福ということだろう。」というか一文は、本書を読み終えたあとだと考えさせられるものがある。国家や国籍、言語さえも、あらかじめ与えれた自明のものではないということ。そして、自明でないがゆえに、血で血を洗うような凄惨な歴史があったということ。 なかなかしんどい話だが、あまりよく知られていない歴史なだけに(そもそもガリツィアを専門とする学者自体が少ないそう)、興味深かった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ガリツィアは、ポーランド分割でオーストリア領になった地域で、西側にポーランド人、東側にウクライナ人が多く住む。更に点在するユダヤ人が人口の3割強を占めた。 こういう土地に民族主義をぶつけたらどうなったかが本書である。 語られるような悲劇は、「おわりに」で言及されるように、近代国民国家の形成期に主導となった国々に、「この辺に居てフランス語喋ってワインとチーズな人達」や「あのあたりのドイツ語を話すビールとソーセージのプロテスタント」みたいな、比較的(あくまで比較的‼︎)言語と宗教と民族にバラツキがなかったがために、境界の確定方法があまり考慮されなかったのが発端で、「ちょっと待て、ウチはヒンズー教徒と仏教徒が半々だわー」みたいな国が噛んでたら、事態はだいぶ違ったか。 スケールはだいぶ違うが、出生地と本籍地と育った所と現住所が違う私、関心を持たずにいられないんである。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
野村真理『隣人が敵国人になる日 第一次世界大戦と東中欧の諸民族』人文書院、読了。一次大戦とは、独仏の直接対決と戦後の民族自決の印象から、帝国から国民国家へ歴史に見えるが、そう単純ではない。帰属意識も疎らな多民族混淆地域の東部戦線では「隣人が敵国人になる」日であった。 言語や宗教の異なる諸民族が複雑に入り組む東中欧。いまだに国民国家を想像できないでいる民衆が存在する。ゆるやかな連合としての帝国の崩壊は、民族自決と国家形成の理念を掲げつつも、多様な人々を置き去りにすることになった。 EUの成立、グローバル化の進展は、国民国家の意義を逓減しつつある。国家=民族である必要はなかろうが、民族であることと、国民であることから置き去りにされる歴史を振り返る本書は、近代とは何かを教えてくれる。知られざる歴史に分け入る一冊。
Posted by
- 1