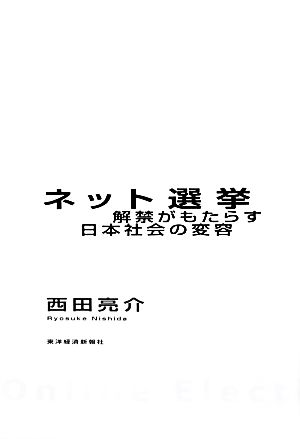ネット選挙 の商品レビュー
ネット選挙の一般的な認識としてあった「若者の投票率が増える」をしっかりと論理的に否定し、今後のネット選挙の展望についてわかりやすくかかれた書籍であると感じた。
Posted by
内容は2、3ページにまとめて書いてしまえる薄さで、特に目新しい論考もない ネット選挙について話題になっていたようなネタをそのまま深く弄らずツギハギした感じで、出版時のネット選挙に関する空気を伝える事だけには意味があるのかもしれなき
Posted by
本質は「均質な公平性」のもとでの競走から、「斬進的改良主義」の価値観を政治に取り込むこと。情報技術と政治の距離を近づけ、その豊かな可能性を引き寄せ得る。 しっかり考えてくれている人、に期待します。
Posted by
「制度だけでなく、これは思想の問題だ!」気鋭の社会学者が説く『ネット選挙』という事象。僕自身は今までさして興味は正直無かったのですが、これを読んで一体どういう事が起こっているかを改めて知りました。 2013年の参議院選挙から解禁となった『ネット選挙』新聞などを見ていると...
「制度だけでなく、これは思想の問題だ!」気鋭の社会学者が説く『ネット選挙』という事象。僕自身は今までさして興味は正直無かったのですが、これを読んで一体どういう事が起こっているかを改めて知りました。 2013年の参議院選挙から解禁となった『ネット選挙』新聞などを見ていると「親子で学ぶネット選挙」というような特集が組まれているのを散見することがありますが、僕は正直、あまり関心が無かったのかもしれません。 ここでいう『ネット選挙』とは選挙活動にネットようのコンテンツ。具体的にはツイッターやフェイスブック等のソーシャルメディアということになるのでしょうが、先日テレビのニュース番組を見ていて、ある国会議員が四苦八苦しながらツイッターを使っていたり、ブログに自分の所属する党の『裏事情』を書きすぎて執行部からお灸をすえられた議員もいるとかという話が流れておりました。 本書にするされているのはそもそもネット選挙とは何なのか?という根源的な話や、巷でもよく言われている 「お金がなくても政治家になれる」 や 「ネットで見た候補者の発信に触発されて、若者が選挙に行くようになる」 なんていうことが本当に起こるのか? さらにはネット論壇などでよく言われている 「この情報化社会にインターネットの使用を禁止するなんて、時代遅れもいいところだ!」 に至るまで多角的な角度から語られているということと、豊富なデータが提示されており、これ一冊読みきることができれば『ネット選挙』という事象についてほぼ正確に把握できるのではないでしょうかというのが僕の読後感でございました。 しかしツイッターをよく活用している「ツイッター議員」はなぜツイッター議員であろうとするのか?にはじまる様なネット社会の思想を政治の中に取り込むことによって何が変わってくるのか?ということも論じられていてとても面白かったです。 こういった話は立場によって意見が異なるかと思いますが、本書はすぐ読めますし、「ネット選挙って何?」という方には一読をオススメしたいと思います。
Posted by
「理念なき解禁」を超え、日本の政治を「斬新的改良主義」へ―。トライ&エラーを繰り返しながら、ブラッシュアップしていく政治。そこでネット選挙運動の真価が問われるのか。そんな政治を見てみたい。ありがとう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
テレビなどの新しいメディアの選挙運動への利用は認められてこなかったが、なぜネット選挙だけ認められるのか? 「お金がかからない」、「若者の投票率が上がる」という言説は合理的な根拠に乏しい。 理論なきネット選挙解禁は意味がない。まずは「インターネット」という世界の価値観の共有やそれを政治に取り入れる際に起こりうる変化を議論するべきである。 インターネットは政治家と国民の距離の遠さを縮め、政治を透明化できる可能性がある。ただし、ネットは手段のひとつで、従来のメディアや選挙活動を含めた総合的な議論が必要である。 ということが書いてありました。
Posted by
2013年通常選挙が国政として初のネット選挙運動解禁となった。それを受け、ネット選挙とは何なのかを論じた本書。 しかし内容は我々が思い描いた景色ではない。 西田亮介氏はこのネット選挙解禁を「理念なき解禁」と断じる。我が国でのネットによる選挙という概念が生まれて20年。その歴史...
2013年通常選挙が国政として初のネット選挙運動解禁となった。それを受け、ネット選挙とは何なのかを論じた本書。 しかし内容は我々が思い描いた景色ではない。 西田亮介氏はこのネット選挙解禁を「理念なき解禁」と断じる。我が国でのネットによる選挙という概念が生まれて20年。その歴史を紐解きながら、公選法とネットのあり方が如何に相入れないかを明らかにする。 ネット選挙にまつわる“誤解”を実証しながら巷にあふれる俗説を切ってゆく。自分自身も勘違いをしている部分があった。ネット選挙を解禁したところで、若者の投票率は上がらない。西田氏は海外の事例からそれを証明している。 このような個別の事例から見えてくるのは、政治家を選ぶための投票の在り方…理念への疑念である。「公平性の重視」から「漸進的改良主義」への変化を見据えて。。 この著作は今回迎えたネット選挙の解説に留まらない。つまりこれは未来にも読まれるべき書であるということだ。 何故ならば、ネット選挙でもたらされるべき、国民と政治の関係は、この選挙では無残にも達成されることはなかったからである。 如何に政治家が「しょうもない話」しかしないかが可視化されただけの選挙だったのである。 我々はネットによって、政治家と政策論議をしたいのである。オープンに双方向に… これが達成されるまではこの書は目標として掲げつづけられるべきであるし、仮に達成されたならば、この書は歴史の書へと変わるだろう。
Posted by
2013年参議院選挙から、ネット選挙が解禁されます。歴史的背景、海外比較などがわかりやすく、まとめられています。結局、理念なきネット選挙活動解禁では、広告代理店やPR会社が儲かるだけではないか、と私も考えていたので、見解は一致。やはり、政策の中身が大切で、前職ならば、実績報告まで...
2013年参議院選挙から、ネット選挙が解禁されます。歴史的背景、海外比較などがわかりやすく、まとめられています。結局、理念なきネット選挙活動解禁では、広告代理店やPR会社が儲かるだけではないか、と私も考えていたので、見解は一致。やはり、政策の中身が大切で、前職ならば、実績報告まで含めた活動を展開して欲しいです。今、読むべき一冊だと思います。
Posted by
ネット選挙導入までの経緯と論点についてコンパクトにまとまった一冊 ネット選挙導入によって劇的に情勢が変化することはない ただ、今まで何となく見えにくかった政治家が近く見える契機は得たといえる この点では同時に、各政治家や閣僚の主張等を聞く機会から「問題発言を聞く機会」も増えるこ...
ネット選挙導入までの経緯と論点についてコンパクトにまとまった一冊 ネット選挙導入によって劇的に情勢が変化することはない ただ、今まで何となく見えにくかった政治家が近く見える契機は得たといえる この点では同時に、各政治家や閣僚の主張等を聞く機会から「問題発言を聞く機会」も増えることになり、マスコミに次ぐ権力監視機能が付与されたともいえる ただし、それらの情報が増えてもマスコミだけに頼らず自ら学び、批判し、対案を考えたり、他の選択肢を探る努力を多数がしなければ政治は変わらない。 「◯◯党に任せれば大丈夫」が多数意見になれば、世の中はさらに悪い方向に進む。 以下、メモ 公職選挙法 →金権政治の防止 戦後紙は高かった→文書図画の細かな制限 アメリカ→表現の自由重視 「選挙コストが下がる」 日本共産党が2007年に政党交付金使途報告書を調査 自民党の2001〜2005 テレビCM等に使う宣伝事業費が約2割、136億8900万円←764億円中 SNSやHPは開設はタダかも知れないが、運用コストも去ることながらコンテンツを充実させるには多額の費用がかかり、素人では無理→コンサルや広告代理店に流れる金は多い 「投票率が上がる」「多様な民意の反映」 投票率と人口ボリューム 2012年 20代1391万人 60代1838万人 これに近年の投票率を掛け合わせるとそもそもの20代の人口を超える(2009年の衆院選49.45%:84.15%) ネット選挙解禁でも年長世代の利害重視は変わらない 2012年衆院選は38% Twitterの魅力、双方向性と情報伝播性 過半数の議員が活かしきれてない
Posted by
意識したわけではないが、タイムリーな1冊。そもそもネット選挙ってなんだっけ?という素朴な疑問を、その成立過程から俯瞰できる1冊だと思う。著者の述べるように、ネット選挙は新しい政治スタイルの始まりかもしれない。そんな側面も見ながら今回の選挙に参加したいですね。
Posted by
- 1
- 2