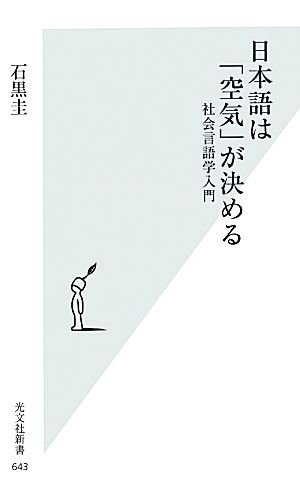日本語は「空気」が決める の商品レビュー
カテゴリ:図書館企画展示 2015年度第1回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」 第1弾! 本学教員から本学学生の皆さんに「ぜひ学生時代に読んでほしい!」という図書の推薦に係る展示です。 木下ひさし教授(教育学科)からのおすすめ図書を展示しました。 開催期間:...
カテゴリ:図書館企画展示 2015年度第1回図書館企画展示 「大学生に読んでほしい本」 第1弾! 本学教員から本学学生の皆さんに「ぜひ学生時代に読んでほしい!」という図書の推薦に係る展示です。 木下ひさし教授(教育学科)からのおすすめ図書を展示しました。 開催期間:2015年4月8日(水) ~ 2015年6月13日(土) 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペース ◎手軽に新書を読んでみよう 1938年に岩波新書が創刊されたのが新書の始まりです。 値段も分量も手ごろな新書は「軽く」見られがちなところもありますが、内容的に読み応えのあるものも多くあります。気に入った著者やテーマで探してみるとけっこう面白い本が見つかるものです。広い視野を持つために、興味や関心を広げるために新書の棚を眺めてみましょう。刊行中の新書を多様な角度から検索できるサイトもあります。(「新書マップ」) ◇新書で日本語を知ろう 分かっているようで分からない日本語。まずは知ることですが、難しく考えず日本語の本を読んで親しんでみましょう。大切なのは気持ちですが、誤解を招かない表現もまた大切です。大学生として、社会人として知っておいて損がないのが日本語の知識です。
Posted by
文法的な言葉の正しさを重視するあまり片隅に追いやられている「言葉のふさわしさ」。 生きた言葉が存在するのは人と人とがコミュニケーションを行う社会そのもの。社会の中で言葉がどのように使われているのか。これを知ることにより初めて言葉の真の姿が見えてくる。貴様、御前もかつては敬語。言葉...
文法的な言葉の正しさを重視するあまり片隅に追いやられている「言葉のふさわしさ」。 生きた言葉が存在するのは人と人とがコミュニケーションを行う社会そのもの。社会の中で言葉がどのように使われているのか。これを知ることにより初めて言葉の真の姿が見えてくる。貴様、御前もかつては敬語。言葉の正しさは時代の変遷とともに大きく変わりゆく。言葉として決して正しくなくとも、時と場合によっては最もふさわしい言葉となることは、しばしば我々が日常経験すること。形式にとらわれることなく、おかれた場面で、空気を適切に読み、どのように言葉を選び使うかが最も重要だということである。
Posted by
「はじめに」のところで、日本語ネィティブに向けて書かれる本は「正しさ」より「ふさわしさ」の問題であるべきだ、と書かれている。例えばクレヨンしんちゃんが母親のことを「みさえ」と呼ぶのは「正しい」けど「ふさわしい」か?など。なるほど、と思って読み始めたけど、副題が示すようにこの本は「...
「はじめに」のところで、日本語ネィティブに向けて書かれる本は「正しさ」より「ふさわしさ」の問題であるべきだ、と書かれている。例えばクレヨンしんちゃんが母親のことを「みさえ」と呼ぶのは「正しい」けど「ふさわしい」か?など。なるほど、と思って読み始めたけど、副題が示すようにこの本は「社会言語学入門」で、社会言語学というのはかなり広い範囲をカバーしているようなのでどうしても網羅的になり、タイトルから期待したような内容が深められている、という感じではなかった。 いくつかおもしろいと思ったことを書き留めておく。 *ポライトネスは日本語の「丁寧」と似た意味を持った言葉だが、「友好性」という意味が含まれている点が違う。ポジティブポライトネスは相手との距離を縮め、相手に親愛の情を伝えようと努める。一方、ネガティブポライトネスは相手との距離を取り、相手を尊重するという態度である。行き過ぎたポジティブポライトネスはなれなれしく映り、行き過ぎたネガティブポライトネスはよそよそしく映る。適度な距離はその人の性格により、また状況によって異なる。(p.111-113) … 確かに。 *「あなた」という表現がなぜ失礼と感じられることがあるのかという説明にも納得。(p.169-172) *ツッコミの機会は逃さず、かならずツッコむ。それが大阪弁の会話のお約束。(p.218) … うん、これはニフティの英会話フォーラムで話題になったことがあったなぁ。「大阪ではボケとツッコミができひんかったら生きていかれへん」と。 *「言語の喪失」の可能性について(p.248)。 …日本ではアイヌ語を始めいくつかの言語が消滅の危機にさらされているとユネスコにより指定されているとのこと。しかし日本政府、世論などはそれに無関心であることが指摘されている(p.249)。… 著者の言っておられることはもっともだと思うけど、現実の生活で使用頻度の少ない言語を維持していくのはやはりとても大変なことだとは思う…
Posted by
社会言語学ってこういう話なのか。 語用論とかテクスト分析とかとごっちゃになっている。 わかりやすいし面白いとは思う。
Posted by
社会言語学は、言葉選びの科学、と一言で言ってのける明快さが魅力。 社会言語学という、おそろしくその扱う領域が広い学問が、何となく一冊で概観できるような気になる。 最近話題の方言コスプレの話や、方言漢字、バイリンガル教育、危機言語のことまで、本当に幅広い。 社会言語学は、まだ日本...
社会言語学は、言葉選びの科学、と一言で言ってのける明快さが魅力。 社会言語学という、おそろしくその扱う領域が広い学問が、何となく一冊で概観できるような気になる。 最近話題の方言コスプレの話や、方言漢字、バイリンガル教育、危機言語のことまで、本当に幅広い。 社会言語学は、まだ日本では緒に着いたばかりの学問領域なのだとか。 この先、どのように進展していくのだろうか。
Posted by
サブタイトルにあるように学問の入門書。非常に読み易く学問に大変関心を感じる。なぜ言葉づかいが場面により変わるのか。敬語だけではなく、環境(社会)との関係、相手との親疎、距離感により言葉が変わるとは毎日のように感じること。それをポライトネス理論というという解き明しは痛快!。「俺、僕...
サブタイトルにあるように学問の入門書。非常に読み易く学問に大変関心を感じる。なぜ言葉づかいが場面により変わるのか。敬語だけではなく、環境(社会)との関係、相手との親疎、距離感により言葉が変わるとは毎日のように感じること。それをポライトネス理論というという解き明しは痛快!。「俺、僕、わたし・・・」などの一人称の使い分けなどをドラえもんの登場人物のキャラから説明するのが楽しい。若者語の特徴①断定を避けるぼかし表現が多い、②強調する程度副詞の発達、③気持ちを伝える形容詞の多用、④テンポを速める略語が多い、⑤共感を持って相手の話を受け止める表現の豊富さなどの解説は確かに!と納得。「言葉選びの科学」という表現、その場「空気」に合わせた適切な言葉選びのセンスを磨く!というお奨めはぴったり。
Posted by
「日本語は「空気」が決める」を本棚に登録しました。/ http://booklog.jp/item/1/4334037461 日本語の使い分け(人称代名詞の「おれ」、「ぼく」、「わたし」など)はどういう場やどういう人と話しているのかという「ふさわしさ」によって決まることを多くの...
「日本語は「空気」が決める」を本棚に登録しました。/ http://booklog.jp/item/1/4334037461 日本語の使い分け(人称代名詞の「おれ」、「ぼく」、「わたし」など)はどういう場やどういう人と話しているのかという「ふさわしさ」によって決まることを多くの例から説明した1冊。 話す相手によって、無意識に使う言葉(丹後弁、関西弁、標準語)が変わる私にとってはとても興味深い内容でした。
Posted by
□内容 なぜ、方言はうらやましがられたり、馬鹿にされたりするのか。『となりのトトロ』のサツキとカンタの会話から、何が分かるのか。あの人はなぜ自分のことを「オレ」と言ったり「ぼく」と言ったりするのか。ママと呼んでいたのがかあさん、おふくろ、母親、と変化するのはなぜか。状況に合った敬...
□内容 なぜ、方言はうらやましがられたり、馬鹿にされたりするのか。『となりのトトロ』のサツキとカンタの会話から、何が分かるのか。あの人はなぜ自分のことを「オレ」と言ったり「ぼく」と言ったりするのか。ママと呼んでいたのがかあさん、おふくろ、母親、と変化するのはなぜか。状況に合った敬語が使えるようになるにはどうしたらよいのか…。学校では教わらない、でも、一番「伝わる」日本語とは…?「生きた言葉」と、環境(社会)との関係を科学する―「ことばの社会学」の入門書。 by アマゾン □感想 『文章は接続詞できまる』でも感じたが、なにか物足りない。各章の最初と最後を読めば主要はわかる。タイトルやトピックのネーミングも上手だ。けれども、何かが足りない。それってなんだろう。 社会言語学の入門書というように、網羅(といっても、社会言語学の本は読んだことはない)しているが、広く浅くというものだ。 興味深いのは次の3つ。 話し手は、親しさを示したい場合は相手の言葉遣いに合わせ、反発を感じる場合は相手の言葉遣いを合わせない傾向がある。それを分析するのがアコモデーション理論である。p.115 →本書では帰省したら「関西弁」、子どもには子どもにあった「話し方」、外国人にはできるだけわかりやすい日本語で話そうとする、ということを「言葉遣い」としている。後述したのは親しくしたい、というものもあるがマナーや思いやりということもあるだろう。 たしかにm親しくしたい場合、(意識したことはないが)自然と相手にあった言葉遣いをしている。また相手の使う「言葉」を使って話をしようとする。これも結構あるのでは? 英語は性差別語(sexist language)だと言われることがある。例として、chiairman,policemanなどmanを用いたり、actor/actress, waiter/waitressのように男が基本形で女が派生形だったりする。これらに対して性中立語にする動きがある。 これらに対して社会的な反発がある。問題は言葉にあるのではなく、差別意識にある。言葉の言い換えに終始しても意識を改革しないことには根本的な解決にならない。その言葉が相手を侮蔑するかどうかは文脈によって決まることが多く、文脈を無視して表面的な言葉の使用だけを問題にしていいのか、という意見もある。 でも、言葉は自分でいうことは許されても人から言われると傷つく。例えば、「おれ、デブだからさ」と自分でいうのと、「お前、デブだな」と人からあらためて言われるのとでショックを受ける。pp.211-214 →うーん。もう少し書いてほしい。誰かこれについて話しましょう。 同じ意見文を書いてもらった場合でも、国によって色が出る。韓国人は身近なことについて引きつけて自分が感じたことを大切にするのにたいし、中国人は身近なことを書いても最終的には一般化して、経済・社会・文化といった大きな枠の中で教訓的に取り上げる傾向がある、ドイツ人の文章は飛躍が少なく、接続詞などで丁寧に理論を追っていくのにたいし、フランス人の作文は表現に凝る印象があり、批判的な見方を忍ばせる傾向がある。 どこまでが言語の問題で、どこまでが文化あるいは教育の問題かわかりにくいところはあるが、書き手の言語的・文化的背景が反映されていることはたしかだ。 pp.214-219 (まっちー)
Posted by
- 1
- 2