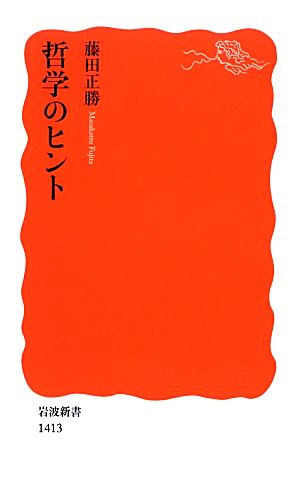哲学のヒント の商品レビュー
哲学って、めっちゃハードル低いように見えてめっちゃハードル高いように見えて実はめっちゃハードル低い、、、みたいなことを触れるたびに毎回思う。 結局身近な問いを大事にしようっていうけどいざ学ぼうとすると超むずいみたいな。
Posted by
「生」「私」「死」「実在」「経験」「言葉」「美」「型」の8つのテーマについて、哲学的な立場から考察をおこなっている本です。 著者は、西田幾多郎などの日本の哲学者についての研究で知られており、本書でも西田をはじめ和辻哲郎や田辺元、三木清といった思想家たちに言及されています。西洋哲...
「生」「私」「死」「実在」「経験」「言葉」「美」「型」の8つのテーマについて、哲学的な立場から考察をおこなっている本です。 著者は、西田幾多郎などの日本の哲学者についての研究で知られており、本書でも西田をはじめ和辻哲郎や田辺元、三木清といった思想家たちに言及されています。西洋哲学をメインに哲学の諸テーマについてわかりやすく解説している本を期待する読者には、あるいは違和感をおぼえる内容かもしれません。 著者は本書の「序章」で、哲学は普遍的な内容をもつのか、それともそれぞれの文化圏におうじた個性をもつのか、という問いを提起し、異なる文化的背景をもつ思想が相互に対話をおこなう場所として、哲学という学問を理解するという考えかたを語っています。プラトンやデカルトといった西洋哲学とは異なる入り口から、哲学という普遍的なテーマにアプローチする道筋があるということを示しているという意味で、興味深い哲学入門だと感じました。
Posted by
●いくつか哲学に関する本を読んで思ったのは、同じ哲学者やその著書のことを述べているのに、解釈や受け取り方に違いが見られる、といったこと。哲学というものは、普遍的な倫理を追求することが目的の一つと認識していたが、哲学の目指す普遍性の手強さを実感した。
Posted by
生、私、死、実在、経験、言葉、美、型の各章に分かれてそれぞれの主題に関する哲学について語っている。古今東西とは言っても、日本の哲学の紹介に重きが置かれているようである。この本は読みやすいが、さてそれぞれの原典を読むにはかなり敷居が高いような感じがする。
Posted by
2018.6.22読了 高校倫理も真面目に受けてこなかった人間なので、成人を前に「哲学」というジャンルに触れてみようと思った。 新書なので身構えたが、語り口は易しく入門書らしい。 しかし、正直第4章あたりから目が滑って理解が追いつかなかった。リベンジしたい。 p3 「哲学を...
2018.6.22読了 高校倫理も真面目に受けてこなかった人間なので、成人を前に「哲学」というジャンルに触れてみようと思った。 新書なので身構えたが、語り口は易しく入門書らしい。 しかし、正直第4章あたりから目が滑って理解が追いつかなかった。リベンジしたい。 p3 「哲学をするのはカムチャツカにいてもできる」 p46 人間は、死と不幸と無知を癒すことができなかったので、幸福になるためにそれらのことについて考えないことにした。 p132 言葉…①考えるため、表現するための道具 ②ものは言葉によって分節される p73 無常観 西洋:根底には移ろわぬ永遠なるものがある 東洋:背後には何もなく、虚しさがどこまでも深い
Posted by
「哲学」の入門書を探している人にとっては良い。哲学に触れるうえで主要となるカテゴリー別に問題提起がまとめられている。一度目は精読するのではなく、流し読みをして、二度目に興味のある章を精読しました。 哲学者の言葉を数多く引用しており、良書。 「私」の定義の部分が少し難解だった。。。
Posted by
古今東西の思想家の言葉をたどりながら、そこにひそんでいる哲学のヒントを取り出して見せてくれる本。 伝統的な思索の紹介にもなっています。 著作を読んだだけで、深くまでその思想が理解できずにいたパスカルと九鬼周造が取り上げられていると知って読んでみました。 哲学者たちの思想をクリア...
古今東西の思想家の言葉をたどりながら、そこにひそんでいる哲学のヒントを取り出して見せてくれる本。 伝統的な思索の紹介にもなっています。 著作を読んだだけで、深くまでその思想が理解できずにいたパスカルと九鬼周造が取り上げられていると知って読んでみました。 哲学者たちの思想をクリアにわかりやすく解説してくれているため、つかえることなく読み進められます。 まず、「倫」というのは「ともだち」「なかま」という意味であり、仲間の関係を規定したルールが倫理だという定義から入ります。 人のあるべき道だと思っていましたが、もっと社会的な意味を帯びたものでした。 パスカルが著書『パンセ』で、幾度となく「気晴らし」(divertissement)という言葉を使うのは、気がついていましたが、人は、一人で何もしないでいれば、必然的に 自分自身に向きあい、自己を直視しなければならなず、それは非常に恐ろしいことだから、気晴らしに身を投じるのだという解説を読み、ようやくパスカルの言わんとすることが分かってきた気がします。 また、九鬼の『いきの構造』はなかなか難解ですが、「いき」を媚態、意気地、諦めという三つの特徴で構造化していると、端的に表現していました。 東洋と西洋で語られる「無常」とは別の性質のものだとも説かれています。 西洋の無常は、プラトンの「イデア」のように永遠なものに支えられたもので、東洋の無常は、永遠なるものは見られないとのこと。 それは、一神教と多神教の違いに通じるところかもしれません。 別の所では、日本で仏教が人々の間に受け入れられ、深く浸透していったのは、仏教の理論が情緒と深く結び付いたからだとしています。 外国の思想家も登場しますが、全体的には日本哲学への入門編としてまとめられています。 さまざまな人のエピソードが紹介される中で、ジョットが無造作に手で円を描き、それが完全な円だったためにヴァチカンのサン・ピエトロ大聖堂ファサードのモザイク画に任じられたという話が印象的でした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
藤田正勝『哲学のヒント』岩波新書、読了。哲学と聞けばどこか浮き世離れしたイメージが強いが、アリストテレスがいうように、哲学は日常生活の中に根がある。本書は、生活者の視点、言葉から、根源的思索--哲学的に考えてみること--を誘う哲学エッセー。非常に読みやすい考えるヒント集。 著者はドイツ観念論と日本思想史の専門家。全編に渡り、京都学派「臭」は否めない。しかし、日本思想を「哲学」の次元で語り直すことには成功している一冊か。「生きた哲学は現実を理解し得るものでなくてはならぬ」(九鬼周造)の一つの見本となろう。
Posted by
懐かしい哲学。 西田哲学はずっとわからなかったけど、今もわからない。 小冊子で再び「純粋経験」 それでもわからない。 「生きるとは何か」 哲学の基本を語っていただいた。 どんなに分厚い本を読んでも、まだまだわからない。 だからこそ、哲学は永遠なのかもしれない。
Posted by
著者の藤田正勝さんは、京都大学卒業。だからだと思うが、西田幾多郎や田辺元に関する著作も多い。 彼の哲学に対する姿勢は明確だ。「はじめに」にも、「あとがき」にも書いてあるが、「哲学の問いは、ボクたちの日常生活や経験と深く関わっているものでなければいけない」ということだ。九鬼周造の...
著者の藤田正勝さんは、京都大学卒業。だからだと思うが、西田幾多郎や田辺元に関する著作も多い。 彼の哲学に対する姿勢は明確だ。「はじめに」にも、「あとがき」にも書いてあるが、「哲学の問いは、ボクたちの日常生活や経験と深く関わっているものでなければいけない」ということだ。九鬼周造の言葉を借りれば、「生きた哲学は現実を理解しうるものでなくてはならぬ」となる。 たとえば、「善とは何か」、「美とはなにか」、「生とはなにか」、「存在とはなにか」、「死とはなにか」。もちろん大きな問題だが、誰だって考えたことはあるだろう。だが、この本で一番印象に残るのは、ボクにとって「言葉とはなにか」だった。 ■私たちの思索は、私たちがそのなかで生まれ育った文化や伝承の枠のなかでなされるものです。そこでは言語が大きな役割を果たします。 ■井筒俊彦は、コーランの分析を通して、道徳的観念が時間・空間を越えて普遍的であるというのは一つの思い込みであるとはっきり主張しています。道徳的キータームの意味内容は「言語コミュニティーごとの人間生活の具体的現実の只中において」形成されると主張している。 ■私たちは日本語なら日本語、ドイツ語ならドイツ語、それぞれの言語によって、いわば一つの連続体である知覚対象を独自の仕方で分節しているわけです。私たちが使う言葉に応じて、それぞれの仕方で近く対象に切れ目が入れられるといってもいいでしょう。 ■世界の見え方、あるいは世界のあり方に言葉は深く関わっています。その世界の見え方、あり方は言葉によって織り成された世界理解の枠組みとして、私たちのうちに蓄積されます。私たちが日々行う経験には、この世界理解の枠組みが関与しています。私たちの経験には言葉が深く関与しているのです。 ■私たちの具体的な経験の中で使われる言葉はすべて、背後のこの「ふくらみ」を持っています。(中略)経験と言葉のあいだには、先ほど述べたように、超えがたい大きな間隙があります。しかし、私たちはその「ふくらみ」を手がかりにして、この間隙を飛び越えることができます。 最後に書いてある田辺元のことばも大きな共感を呼ぶ。「哲学は自分が汗水たらして血涙を流して常に自分を捨てては新しくなり、新しくするというところに成り立つのです」。 悩みながら、ときに苦しみながら、実際の経験を経て新しくしていく自分。覚悟が必要な言葉だと思う。
Posted by
- 1