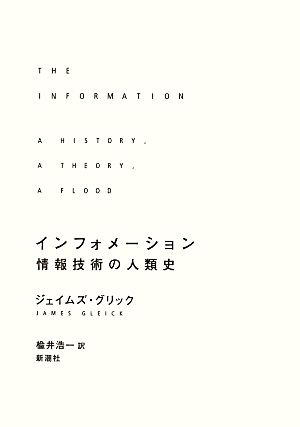インフォメーション の商品レビュー
《目次》 ・ プロローグ ◇第1章 太鼓は語る(符号が符号ではない場合) ◇第2章 言葉の永続性(頭の中に辞書はない) ◇第3章 ふたつの単語帳(書くことの不確実、文字の不整合) ◇第4章 歯車仕掛けに思考力を投じる(見よ、恍惚たる算術家を) ◇第5章 地球の神経系統(貧弱なる...
《目次》 ・ プロローグ ◇第1章 太鼓は語る(符号が符号ではない場合) ◇第2章 言葉の永続性(頭の中に辞書はない) ◇第3章 ふたつの単語帳(書くことの不確実、文字の不整合) ◇第4章 歯車仕掛けに思考力を投じる(見よ、恍惚たる算術家を) ◇第5章 地球の神経系統(貧弱なる針金数本に何が期待できようか?) ◇第6章 新しい電線、新しい論理(「これほど未知数であるものは、ほかにない」) ◇第7章 情報理論(「わたしが追及しているのは、ただの平凡な脳だ」) ◇第8章 情報的転回(心を築く基礎材料) ◇第9章 エントロピーと悪魔たち(「ものごとをふるいわけることはできません」) ◇第10章 生命を表わす暗号(有機体は卵の中に記されている) ◇第11章 ミーム・プールへ(あなたはわたしの脳に寄生する) ◇第12章 乱雑性[ランダムネス]とは何か(罪にまみれて) ◇第13章 情報は物理的である(それ[イット]はビットより生ず) ◇第14章 洪水のあとに(バベルの壮大な写真帳) ◇第15章 日々の新しき幸せ(などなど) ・ エピローグ(意味の復帰)
Posted by
本書は『The Information』史である。冒頭で述べられるようにクロードシャノンの「Bit(将来的にはQubitか)」の発明は、まさに人類に情報革命をもたらした。ニュートンが自然法則を言語化する偉業を成し遂げた結果、自然科学が飛躍的に発展・普及したように。 本書のカバー...
本書は『The Information』史である。冒頭で述べられるようにクロードシャノンの「Bit(将来的にはQubitか)」の発明は、まさに人類に情報革命をもたらした。ニュートンが自然法則を言語化する偉業を成し遂げた結果、自然科学が飛躍的に発展・普及したように。 本書のカバーする範囲は広く、太鼓や電信・電話など送達技術に留まらず、情報理論を成すエントロピーや派生したDNAや量子力学など多岐に渡る。他方でミームや乱雑性、情報過多といった情報に付随した概念も漏れなく取り上げている。 内容的には相当難解で500ページ超の大作だが、知的興奮満載の本である。
Posted by
【新しい媒体は必ず,人間の思考の質を変容させる。長い目で見れば,歴史とは,情報がみずからの本質に目覚めていく物語だと言える】(文中より引用) 身近な概念でありながら,その核心に迫るにつれて意味がぼやけてしまう「情報」という概念。その意味するところを丹念に追いながら,情報と人間の...
【新しい媒体は必ず,人間の思考の質を変容させる。長い目で見れば,歴史とは,情報がみずからの本質に目覚めていく物語だと言える】(文中より引用) 身近な概念でありながら,その核心に迫るにつれて意味がぼやけてしまう「情報」という概念。その意味するところを丹念に追いながら,情報と人間の関係を通史として描いた叙事詩的作品です。著者は,ピューリッツァー賞の最終選考作品を数々送り出しているジェイムズ・グリック。訳者は,ジャレド・ダイアモンドの作品などの翻訳を手がけた楡井浩一。原題は,『The Information: A History, A Theory, A Flood』。 500ページを超える大著かつ専門用語も頻出しますので読むのにかなりの労力を必要とする作品ではありますが,類書があまりないこともあり読後の達成感はなかなかのものでした。「情報の歩みを通して知る人間の思考の歩み」という観点でも大変勉強になった一冊でした。 こういう作品を翻訳で読めるというありがたさ☆5つ
Posted by
【由来】 ・はてなのブックマークメールでたまたま目についた。出たばかりだが、図書館にもあった。でも、読む本、たくさんあるのでまだ予約しない。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする...
【由来】 ・はてなのブックマークメールでたまたま目についた。出たばかりだが、図書館にもあった。でも、読む本、たくさんあるのでまだ予約しない。 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・
Posted by
太鼓の音で遠方と会話しようとするトーキング・ドラムの話からシャノンの情報理論、DNA、インターネットまで「情報」にまつわる博覧的な内容。 英語の場合、例えばQの次にはUが来るので、”QU"は”Q"に比べて冗長なだけ。こういうふうに、英語の場合であれば50%の...
太鼓の音で遠方と会話しようとするトーキング・ドラムの話からシャノンの情報理論、DNA、インターネットまで「情報」にまつわる博覧的な内容。 英語の場合、例えばQの次にはUが来るので、”QU"は”Q"に比べて冗長なだけ。こういうふうに、英語の場合であれば50%の冗長性が組み込まれており、シャノンによると圧縮できるということは情報の量が少ないということになる。これに対して今でも人の頭のなかで「理解」がされた時に情報が生まれるという心情的には同意したくなるような意見もあるが、それを乗り越えないと情報理論がなかなか腑に落ちない。 ・音声や歌、話しことばなど、人類によって生み出され、消費される情報はかつては消え失せるものであったが、今やすべてのものが記録され、保存されるようになってきた。コンピュータ時代の現代では特に顕著になってきており、これをもって情報による疲弊、痴呆化ということも言われているが、写真機が初めて出てきた時も同じようなことが言われていたらしい。 ・大半の論理演算にはエントロピー・コストがかからない。0が1になったり、1が0になる時、その情報は維持されるし、過程は可逆的でエントロピーが変えられることはない。情報が消去されるという不可逆的な過程の場合のみ熱が放射される。 ・情報、乱雑性、複雑性は基本的に同等のもので、この3つの強力な抽象概念は、人目を忍ぶ仲のごとく秘かに結びついている ・通信というものの本源的な課題は、ある地点で選択されたメッセージを、別の地点で精確に、あるいは近似的に再現することである(クロード・シャノン)
Posted by
巻頭のエピグラフは「通信の数学的理論」からの引用である。クロード・シャノンはこの論文で情報理論という概念を創出した。同年、ベル研究所によってトランジスタが発明される。「トランジスタは、電子工学における革命の火付け役となって、テクノロジーの小型化、偏在化を進め、ほどなく主要開発者3...
巻頭のエピグラフは「通信の数学的理論」からの引用である。クロード・シャノンはこの論文で情報理論という概念を創出した。同年、ベル研究所によってトランジスタが発明される。「トランジスタは、電子工学における革命の火付け役となって、テクノロジーの小型化、偏在化を進め、ほどなく主要開発者3名にノーベル物理学賞をもたらした」。ジョージ・オーウェルが『一九八四年』を書いていた年でもあった(刊行は翌年)。 http://sessendo.blogspot.jp/2014/05/blog-post_12.html
Posted by
陰翳礼讃を読んだ後なのかもしれないが、情報通信、電気通信の世界の本質を考えさせられた。また、筆者の新旧に渡る広い知識と視座の面白さが光るいい本だと思う。 シャノン、チューリング、フォン•ノイマンは、情報通信の分野では神様みたいなものだ。彼らがいたからその世界が開かれたとも言ってい...
陰翳礼讃を読んだ後なのかもしれないが、情報通信、電気通信の世界の本質を考えさせられた。また、筆者の新旧に渡る広い知識と視座の面白さが光るいい本だと思う。 シャノン、チューリング、フォン•ノイマンは、情報通信の分野では神様みたいなものだ。彼らがいたからその世界が開かれたとも言っていい。しかし、その論理は教わったし、今や情報化社会であり、あまりにも短すぎて見えなくなっていたものに、目を見開かせてくれた。当たり前、当然で片付けてしまい、本質を見失ってしまっていた。 また、この本には様々な事柄が引用されているがそのイメージのシンプルさ、エレガントさは読んでいてとても気持ちが良い。ダンジョン&ドラゴンズ、ポケモンなどを引用することで分かりやすい。 この本で感銘を受けたのは、高層ビルは情報通信技術があるから成り立つビジネスだということ。何を言っているかと言うと、仮に情報通信技術が無い場合はそれを全て人力による移動に頼ることになるがその場合、エレベーターなどの数が尋常ではなくなり、たちまち採算がとれない。つまり、情報通信は、高層ビル、果ては街や世界の在り方をも変えるチカラがあるということだ。 そういう意味ではあまりにも当たり前になっているとそのチカラを変に過小評価したり、過大評価してしまう。たまには、それをリセットすることは大事だ。この本はその点ではうってつけであると思う。
Posted by
文字の発明で論理的な思考を手に入れた人類が、電信、電話を経てコンピュータ、そしてインターネットで各個人が相互に繋がる世界へ、と「情報」の観点で人類史を再定義しなおした一冊。 まずは、真に偉大な発明はトランジスタよりもシャノンの情報理論、特に全ての情報をビットであらわすという概念...
文字の発明で論理的な思考を手に入れた人類が、電信、電話を経てコンピュータ、そしてインターネットで各個人が相互に繋がる世界へ、と「情報」の観点で人類史を再定義しなおした一冊。 まずは、真に偉大な発明はトランジスタよりもシャノンの情報理論、特に全ての情報をビットであらわすという概念なしにはここまでの世の中にはならなかっただろう、という考察から。ノイマン、チューリングといったおなじみの人たちとの関係や、当時の時代背景とあわせて理論が生まれるまでのお話だけでも読む価値あり(-_-) 次に、情報理論が他の分野に与えた影響について。生物化学はもとより、心理学にも大きな影響を与えて、認知心理学という分野が成立したってのは知らんかった。おおざっぱにいうと、外部の刺激→心のはたらき→外部に見える反応、うん、まんま入出力やね。 で、最後は量子コンピュータの話、そしてインターネットで各個人が繋がる世界を一つの生命体とみなすSFチックな考え方で〆、てわけでえらく壮大な一冊でした。いやー、これはホント読んで良かった。著者に感謝。
Posted by
現代では皆が口にする情報。だが、それを認識するのには長い苦闘の歴史があったことが語られる。現代と過去の人々の断絶は思ったより深い。 そして情報を使いこなしているように見える現代人ですら、情報の量すら定義できていない。複雑性と単調の間にある”意味”を持った構造とは一体なんなのだろう...
現代では皆が口にする情報。だが、それを認識するのには長い苦闘の歴史があったことが語られる。現代と過去の人々の断絶は思ったより深い。 そして情報を使いこなしているように見える現代人ですら、情報の量すら定義できていない。複雑性と単調の間にある”意味”を持った構造とは一体なんなのだろう? より深く情報を理解できるようになったとき、人類はどこに向かうのだろう?見届けることができるだろうか。
Posted by
壮大な試みではあろうが破綻している 広大な領域を統合しようとしているが、サイモン・シンやマクルーハンなどの論考に付け焼き刃で追いつけるはずもなく この分厚さで予想されるほどの値段あたりの情報量は、それほど多くはありません
Posted by
- 1
- 2