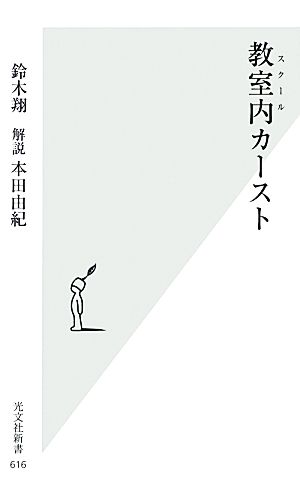教室内カースト の商品レビュー
インタビュー部分を読むだけで内容的にはわかる。熟読はしなくてもよさそう。 あとがきとかまとめ部分から、著者の過去の様子が伝わってくる。思い入れのある研究なんだろうと思う。 教室インタビューは教師の意見にあまり賛成できなかった。どちらかというと強者に有利、ひいきな意見だと思う。
Posted by
教室のなかで自然発生的につくられる序列、スクールカーストにいかに対応していけるか。 ある程度序列ができてしまうのは仕方ないことなのかもしれない。それでも、お互いがお互いの良さをちゃんと認識して、尊重し合える、そんなクラスをつくりたいと思う。 そんな決意で、読みました。
Posted by
生々しい内容だった。 我々が思っている以上に教室の権力関係は敏感でかつ深刻である。 近年ネット上ではよく使われる「スクールカースト」について社会学的手法から分析を試みた本である。 いじめは「暴力系いじめ」と「コミュニケーション操作系いじめ」の2つに分類され、前者は警察を持ち込めば...
生々しい内容だった。 我々が思っている以上に教室の権力関係は敏感でかつ深刻である。 近年ネット上ではよく使われる「スクールカースト」について社会学的手法から分析を試みた本である。 いじめは「暴力系いじめ」と「コミュニケーション操作系いじめ」の2つに分類され、前者は警察を持ち込めばどうにかなるが、後者はそうはいかない。それはスクールカーストと「コミュニケーション操作系のいじめ」は密接に結びついているからである。 権力関係でなりたつスクールカーストに生徒は抗することはできない。なぜなら、それに抗した生徒は、より下位のスクールカーストに落とされてしまう可能性があるからである。そのため、粛々とスクールカーストを認めるしかないのだ。生徒側から見たコメントで面白かったのが、「教室内の上位カーストの仲が良ければ良いほど」、もしくは、「クラスの結束が強ければ強いほど」よりカーストのヒエラルヒーが強まってしまうことだ。 この研究で目を引いたのは、スクールカーストを教師側がどう思っているか、である。教師側はスクールカーストを権力関係として捉えているのではなく、いわば「生きる力」の能力ヒエラルヒーとして捉えているのだ。だから、積極的にスクールカーストを肯定してしまう。 この生徒側の消極的なスクールカーストへの従属と、教師の積極的な肯定によって、スクールカーストは維持される。 これは、クラス替えだとか、同一学区内の進学ではなかなか変えられない。 学校制度自体をどうにか変えないとならないのだ。 スクールカーストの研究はまだ始まったばかり。 いじめ問題を一掃するには、より一層の研究が待たれる。 これ以降の研究にも期待したい。
Posted by
内容は、基本的にインタビュー・アンケートの内容を要約して次へ、要約して次へ、の繰り返しに過ぎず、問題への踏み込みがあまりにも浅い(著者も認めていますが)。 一番問題だと思うのは、インタビューのスクリプトの使用を承諾した教師が、著者の知人の20代男性教師4人しかいないこと。さらに...
内容は、基本的にインタビュー・アンケートの内容を要約して次へ、要約して次へ、の繰り返しに過ぎず、問題への踏み込みがあまりにも浅い(著者も認めていますが)。 一番問題だと思うのは、インタビューのスクリプトの使用を承諾した教師が、著者の知人の20代男性教師4人しかいないこと。さらに言えば、下位スクールに居た私の嗅覚が「こいつら全員、学生時代は上位カーストに居た」って言っている(多分あっている)。こんなインタビューじゃ正しい現状把握は不可能。 しかしスクールカースト、リア充/非リア(こういう言い方は本の中では一回もしていませんが)の構造に焦点を当てた研究っていうのは今までなかったわけで、パイロットスタディとしてかなりの意義があるんじゃないかとは思う。この分野の研究をひたすら進めていただきたい。
Posted by
一九八四年生まれの、めちゃくちゃ若い著者の本。 けっこう厚い本で研究っぽい小難しい本なのかなあと思いきや、とても読みやすい。 基本的に、インタビューのあとに著者がそのまとめをしてくれているので、さらに読みやすくまとまっている。 スクールカースト、確かにあるよなあ。 読んでる途中、...
一九八四年生まれの、めちゃくちゃ若い著者の本。 けっこう厚い本で研究っぽい小難しい本なのかなあと思いきや、とても読みやすい。 基本的に、インタビューのあとに著者がそのまとめをしてくれているので、さらに読みやすくまとまっている。 スクールカースト、確かにあるよなあ。 読んでる途中、ほんまに「そうそう!」とひざを打つような話題が多く、同世代の友達とこのテーマについて話しているような、そんな感覚に襲われた。 しかし、最後に著者から今のところの対策を提示されているのだが、それが「学校という場所を絶対だと思わなくていい」「学校に行かなくてもいい」というものに留まっていたのが残念。 なにかほかに、学校にいくひとたちがしあわせになれるような、そんな学校のあり方ってないもんやろうか、と思う。
Posted by
前掲の『桐島、部活やめるってよ』が面白く感じていたところに書店で発見し購入。タイトルのスクールカーストを現状把握した本を今まで読んだことがなく、自分の中高時代と現在も大きな変化はないものであると感じた。 第五章の教師側からのところで、一部教師が「スクールカーストの上位層=能力があ...
前掲の『桐島、部活やめるってよ』が面白く感じていたところに書店で発見し購入。タイトルのスクールカーストを現状把握した本を今まで読んだことがなく、自分の中高時代と現在も大きな変化はないものであると感じた。 第五章の教師側からのところで、一部教師が「スクールカーストの上位層=能力がある。下位層=能力がない」と言っているが、あまりにも短絡的ではないだろうか。 確かにそういう面があるのは分かる。とするのであれば、解説で本田由紀氏が述べているように、同じメンバーで同じ授業を受けるという息苦しい満員電車的な学校の制度を変え、大学のように授業選択性によりクラス以外との生徒の接触機会を増やすとともに、学校以外での居場所感を得られるような制度が必要だ。能力がないのではなく自己肯定感が得られないから下位層になってしまうのではないだろうか?他者に包摂されているからこそ新しいことにも挑戦できると思うのであるが・・・。現在社会は他者への承認提供ができないほどの余裕がなく、同調圧力に晒されているということなのだろうか・・・
Posted by
「平等」なはずの教室の中に、「多様性」をうたう社会であるはずの教育の現場に厳然たる序列、スクールカーストは存在する。スクールカーストの実態とはどのようなものなのか。また、生徒から見たスクールカーストと教師から見たスクールカーストはそれぞれの目にどのように映っているのかをまとめる一...
「平等」なはずの教室の中に、「多様性」をうたう社会であるはずの教育の現場に厳然たる序列、スクールカーストは存在する。スクールカーストの実態とはどのようなものなのか。また、生徒から見たスクールカーストと教師から見たスクールカーストはそれぞれの目にどのように映っているのかをまとめる一冊。現状把握に適か。 問題の画期的な解決策などあるわけがないので、最後に書かれたそれぞれの立場に向けた呼びかけはこれが限界、と思いながらもぱらぱら本論をめくってみるとえぐられるものがある――のは、おそらくカースト上位の人間にはあまり考えられないことなのであるように思う。わっかるかなあ、わっかんねーんだろうなあ。そんな事を思いながら読んでいた。現状把握には適。
Posted by
精神的な、ヒトから見えづらいいじめをそれ単体でとらえるのは困難という現状がある中で、いじめを生む構造からアプローチするというのは、興味深かった。これからどんどん検証が進んでいき理論として精緻化されていくことを期待している。
Posted by