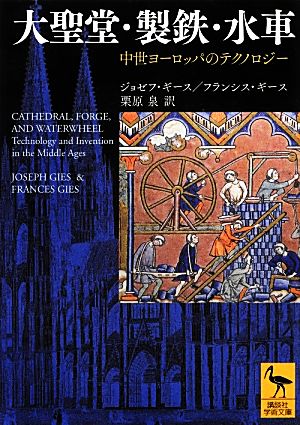大聖堂・製鉄・水車 の商品レビュー
テクノロジーの発達から見た中世1000年史についての本。本書のスタンスとして,中世の技術進歩は地道な積み重ねによると,プラス方向に捉えている。
Posted by
中世ヨーロッパの技術史の解説本。表題からわかるように多分野の技術を扱っている。また単に技術の変遷を辿るだけではなく、そういった技術革新が起こった要因にまで触れている。専門家でなくとも読みやすい。原著に記載されていたであろう註や参考文献のリストが省略されているところは残念。
Posted by
ヨーロッパ中世の科学技術史。商業制度も扱っているので、社会史と大きく捉えてもいいかなと。 それにしても、初期は中国から取り入れたモノが、後期には逆に輸出できるように、西洋と東洋で技術の差が埋められ、遂に逆転まで起きてしまうとは。 社会の技術への受け止め方や、宗教思想が技術の発展を...
ヨーロッパ中世の科学技術史。商業制度も扱っているので、社会史と大きく捉えてもいいかなと。 それにしても、初期は中国から取り入れたモノが、後期には逆に輸出できるように、西洋と東洋で技術の差が埋められ、遂に逆転まで起きてしまうとは。 社会の技術への受け止め方や、宗教思想が技術の発展を後押しするか堰き止めるか、で後世の社会がヨーロッパを規範として出来上がった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
中世は黒歴史じゃない。人類がテクノロジーに目覚める夜明けのような明るい時代なのだ。って感じの教養が身につく。 ネーミングが銃と病原菌と鉄を題材にしたあの歴史書をパックリしているけれど、中身が全然違うから、むしろ真似なくてもいいのにってくらいいい内容だと思うんだけどなぁ。広く浅く学んだ高校生世界史の内容を深めるのにとても良い。テクノロジーのテーマ史ってのがやっぱ面白いよな。 これを読むと中国父さんはやはりすごいな。なんでもヨーロッパに先んじている感じある。よくヨーロッパが産業革命を起こして、アジアを追い越すことができたなって感じ。それも中世の頃にしっかりとテクノロジーの機運を世の中で高めたからなんだな。 いくらキリスト教が科学の進歩を妨害しても、人類はテクノロジーの魅力には勝てなかった。加速するテクノロジー。その代表が、水車による動力。製鉄による道具の品質向上。そして大聖堂をつくるなど宗教がテクノロジーの需要を生み出していた社会背景。
Posted by
そうか、中世が暗黒の時代ってのは古い迷信だったのか!確かに、奴隷が主な動力源の世界よりも水力(縦型水車)と火力(炭)が主な動力源の世界の方がマシだよなあ。そして、欧州がイスラム圏やアジアに対して技術的、経済的に劣っていた状態から逆にリードを奪ったのがまさに中世だったのか!中世があ...
そうか、中世が暗黒の時代ってのは古い迷信だったのか!確かに、奴隷が主な動力源の世界よりも水力(縦型水車)と火力(炭)が主な動力源の世界の方がマシだよなあ。そして、欧州がイスラム圏やアジアに対して技術的、経済的に劣っていた状態から逆にリードを奪ったのがまさに中世だったのか!中世があったからこそ、(良くも悪くも)今の世界情勢があるのかと再認識
Posted by
読了せず。 最初の10ページくらいで「わー教科書」ってなった。 うーん。これを超えれば面白くなるのかなぁ。
Posted by
あまり読ませるタイプの語り口ではない。興味深い内容なんだけど。中国の技術が進んでいたことが印象的。だけど覇権はヨーロッパにあった不思議。中国からヨーロッパへの海洋貿易が起きなかったのは謎。
Posted by
暗黒の時代と考えられてきた中世ヨーロッパにも大きな発展があったことがわかる。開拓による農業の発展が自治の仕組みを産み、繊維業が発達したことでコンパーニャによる商業が発展した。12〜14世紀のルネサンスを経て、15世紀には工業の発展し始めることが見えてくる。 5世紀から南下し始め...
暗黒の時代と考えられてきた中世ヨーロッパにも大きな発展があったことがわかる。開拓による農業の発展が自治の仕組みを産み、繊維業が発達したことでコンパーニャによる商業が発展した。12〜14世紀のルネサンスを経て、15世紀には工業の発展し始めることが見えてくる。 5世紀から南下し始めた氷河が反転し、7世紀までにはブリタニア、ガリア、北海沿岸低地、ゲルマニアで収穫が増えた。西洋文明の中心は、カール大帝(在位768-814年)の時代までに地中海から北ヨーロッパの平原へ移った。 奇襲と交易を繰り返したヴァイキングは、やがて交易に比重を置くようになり、東ヨーロッパやロシア各地に広がる商業帝国を建てた。ヴァイキングは、川の反対側を上ってきたイスラム商人と出会い、毛皮や奴隷、武器、琥珀を売り、イスラムの絹や香料、銀貨を買い入れた。 「アラブ人による翻訳の時代」は、アッバース朝第5代カリフのハールーン・アッ=ラシード(在位786-809年)の治世下に始まり、ギリシャの古典を買い集めて翻訳した。 10世紀以降、干拓や灌漑、森林伐採などによって、かつてほとんど人の住んでいなかった北西ヨーロッパは様変わりした。10〜11世紀の間に人口増加による土地の再分化が進み、開放耕地制農業が始まった。小作人は何人かで協力して森林や沼を切り拓き、区画に分けられた。小作人たちは、自治の仕組みを作って協力して農作業を行うようになり、重い犂の登場によって協力の重要性が増した。 ヨーロッパは、奴隷や獣皮などの後進地域の低級品を輸出していたが、11世紀には布地や金属製品を輸出できるようになり、1200年には高級ウール地、条鉄、銅の延べ棒、道具類、武器、甲冑を輸出するようになった。 フィボナッチは、1202年に「算盤の書」を執筆してインド数字を広めた。インド数字は、14世紀の後半までにローマ数字や計算盤に取って代わった。 シチリア島の木綿産業はノルマン人征服者がアラブ人から受け継ぎ、12世紀初めにはポー川流域が生産の中心となった。絹織物の生産も12世紀にイタリアで始まった。14世紀に亜麻打ち機が発明され、紡ぎ車が導入されて、亜麻布の生産が飛躍的に増大した。亜麻布の生産が増えた結果、ぼろを使った紙の生産が増大し、価格が下がり、市場が拡大した。 布作りの拡大の伴って、13世紀に家族が出資して経営参加するコンパーニャが盛んになり、次第に一族以外もメンバーとして受け入れるようになった。この仕組みによって、商人は各地に代理商を配置して支店を置くようになり、毛織物だけでなく、様々な商品を扱うようになっていった。事業が複雑化するにつれて、記録管理の手法も発達し、1340年には複式簿記が考案された。14世紀のフランドルの織物の町では、時計が職人たちの労働時間を知らせるようになり、商人たちが町を支配する道具となった。 14世紀にはフランスの森林面積はカール大帝の時代の半分以下に、イングランドでは11世紀の記録より3分の1減った。 イングランドでは、荘園管理者が黒死病を生き残った小作人たちに過酷な賦役を課したため、小作人の反乱が起きた。15世紀を通じて、農奴は自由を買い取ったり、税の支払いを拒絶して、農奴の枷から解放されていった。放棄された耕地は牧草地として利用され、家畜が増えて肥料も増え、収穫量が増えた。労働集約型の単作穀物栽培から、土地集約的な牧畜や果物・野菜栽培に変わった。 15世紀にタービンの原理を利用したスクリューポンプが実用化され、鉱山の縦坑の排水に役立てられた。また、木製レールの上を動物に引かせて走る荷車が登場し、新たな精錬法が考案され、鍛冶屋でも水力を用いた道具が導入され、鉄や青銅の生産量が増大したため、大量の農具が安価に入手できるようになった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
J・ギース、F・ギース『大聖堂・製鉄・水車 中世ヨーロッパのテクノロジー』講談社学術文庫、読了。歴史家ギボンの中世観(中世を人類の歴史の「時間が止まった」「暗黒のような」時代)は俗説に過ぎないが、どのように彩り豊かな時代だったのか。本書は具体的なモノの変遷と暮らしの変化から辿る一冊。 ローマ帝国の崩壊から大航海時代までの千年。西ヨーロッパはゆっくりと時間をかけて「現代的な国家、現代的な社会の基礎」を築く。鍬や鎌といった道具から航海術に至るまで、その大きな要因がテクノロジーの発達である。 水車の登場は蒸気機関の発明まで主要な動力源であったが、その登場により、人々の食生活は大きく変わる。粥からパンへの変化は、道具や機械のとぎれることのない発達が人々の暮らしと考え方をかえていった経緯を明らかにする一例だ。 技術革新の背景には地球規模の技術伝播が欠かせない。技術の最も重要な供給源は中国。磁気羅針儀、火薬、紙だけではない。そして技術革新の原動力になったのがキリスト教の人間観とカトリックの修道院制度だと著者は指摘する。 技術の変遷を辿る本書は、ヨーロッパ中世が「暗黒時代」どころか人々が「直観と洞察力を働かせ、失敗と挑戦を忍耐強く繰り返し」ながら発展を遂げた時代であったことを明らかにする。年表と用語の背後の豊かさを再認識させてくれる。
Posted by
(130127読書中) ジャレド・ダイアモンドの「銃・病原菌・鉄」を彷彿とさせる。 暗黒の中世を、ヨーロッパ技術革新の時代と捉え直す。シトー会あるいは、ベネディクト会といった修道会の技術集蓄積に果たした役割は面白かった。また、ローマ帝国時代、人文学的な学問の発展を見た反面で、技術...
(130127読書中) ジャレド・ダイアモンドの「銃・病原菌・鉄」を彷彿とさせる。 暗黒の中世を、ヨーロッパ技術革新の時代と捉え直す。シトー会あるいは、ベネディクト会といった修道会の技術集蓄積に果たした役割は面白かった。また、ローマ帝国時代、人文学的な学問の発展を見た反面で、技術的な革新には、社会的にも経済的にも、ほとんど重要性が感じられていなかったという、論は、非常に参考になった。(塩野七生さんが聞いたら怒りそうな) 続く、、、。
Posted by
- 1