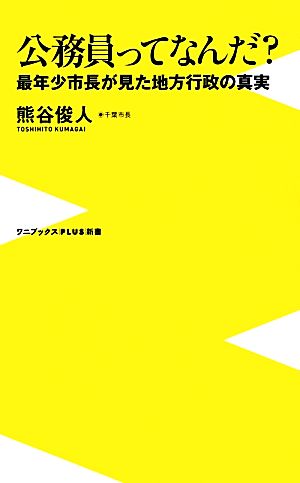公務員ってなんだ? の商品レビュー
世の中のバッシングに耐えながら地道に仕事をこなす公務員。そんな方々の心に届くトップの声である。 千葉市に8年ほど住んでいたが、市長以下市役所の中のことは一つもわからなかった…。世の中の役所というのはそんなものなのかもしれない。
Posted by
公的な機関で働く人にとってモチベーションをあげてくれる書。 また、自分が住んでいるまちにもっと関わりたいなと思える紹介でもある。 熊谷さんは頭のいい方で説得力のある文章を書かれるなあということがわかる。 折に触れて読み直したい。
Posted by
現役千葉市長による、バッシングでも擁護でもない、バランスのとれた公務員論。自らの実績紹介が多い気はするが、著者は若いが確かに見識のある政治家だと思う。公務員が住民のために力を発揮するためには、政治家のリーダーシップが重要であるということを感じた。
Posted by
熊谷市長は、民間企業で身につけた考え方を市政に活かして千葉市を良くしていこうと考えていることがよく分かった。 地方分権、さらには住民自治を目指して、市民が当事者意識をもって、身近な不便を減らすために物事を大局的に考えなければならないと思った。
Posted by
現役千葉市長である、熊谷俊人氏による著書。 当時全国最年少市長である著者は、財政の危機的状況である中、しかも前市長が汚職で逮捕されるというスタートという波乱の後に就任し、その信念をもって市長として職務にあたる姿が印象的です。 民間企業に就職後、市議会議員を経て市長となった著者は、...
現役千葉市長である、熊谷俊人氏による著書。 当時全国最年少市長である著者は、財政の危機的状況である中、しかも前市長が汚職で逮捕されるというスタートという波乱の後に就任し、その信念をもって市長として職務にあたる姿が印象的です。 民間企業に就職後、市議会議員を経て市長となった著者は、民間企業の経験をもとに、行政の考えの特異性、無駄のある部分を指摘しつつも、行政ならではの事情を理解しつつ対応策を論じている点は、単なる公務員批判本ではなく、建設的な主張だといえます。 著書の中では大阪市の橋本市長との違いも指摘していますが、熊谷市長の考え方はより現実的かつ実践的であると思います。 単なる公務員批判・行政批判をすることで、公務員と住民を敵対関係にしていまうことの無意味さ、地方分権を突き詰めていくと住民自治になり、そのためには公務員だけではなく、市民にも意識改革が必要であるという明確なメッセージは、将来の地方自治のあり方にとって、とても重要であると考えます。 <この本から得られた気づきとアクション> ・首長としての明確な目的と覚悟がよく表れていると思う。そのような期待に応えられる公務員であるべきだと感じる。 ・民間との違いを言い訳することを甘えだと指摘しているのはそのとおりだと感じる。官民の違いを踏まえたうえで、独自の考えに陥ってはならない。 <目次> 第1章 公務員は本当に無能なのか?―特殊な世界が生み出す市民とのズレ(そもそも「公務員」とはなんなのか? 公務員批判を拡大させた石肩上がりの終えん ほか) 第2章 市長と公務員の役割―私が決断した市政改革の幕開け(『脱・財政危機宣言』 “ハコモノ行政”の見直し ほか) 第3章 求められる公務員の意識改革―私と職員の向き合い方(公務員の意識の本質的な問題 民間とは違うという甘え ほか) 第4章 市民にも求められる意識改革―自分の街をもっとワクワクする街にしませんか?(燃えるごみを3分の1減らす真の目的 行政は市民のアドバイザー ほか)
Posted by
当時史上最年少で市長となった千葉市の熊谷俊人市長の、3年以上に及ぶ市政改革の軌跡と、公務員や市議会議員、市民がどうあるべきかを綴った書。 ここ最近で読んだ本の中でも特に影響を受け、自らが住む街のために自分はどうしたいのか、どうするべきなのかをとても考えさせられました。確かに、我...
当時史上最年少で市長となった千葉市の熊谷俊人市長の、3年以上に及ぶ市政改革の軌跡と、公務員や市議会議員、市民がどうあるべきかを綴った書。 ここ最近で読んだ本の中でも特に影響を受け、自らが住む街のために自分はどうしたいのか、どうするべきなのかをとても考えさせられました。確かに、我々市民は徴収された税金が如何に使われているかということに無関心である傾向があります。しかし、税金は、結果的に行政サービスとして我々に還元されます。ならば、何も知らないままメディアの論調に同調して思慮なく公務員を批判するのではなく、住民各人が市の「株主」としての意識を持ち、当事者である自覚を認識した上で市政に参画していくことが重要です(これは国政にも同じことが言えます)。そうすることで、街は更に住みやすくなり、快適な生活を営むことができるようになります。 本書は、以上のことを千葉市の実例を挙げながら分かりやすく紹介しており、千葉市民のみならず、全国の市町村に住む人々も必読の書であると断言できるものでした。
Posted by
元々千葉市の熊谷市長には興味があったし、公務員を目指している身でもあるので、読んでみた。 公務員を目指している身として、なかなか興味深い内容だった。例えば、「公務員の仕事は遅い」とマスコミなどでは言われて格好の批判の的になっているが、どうしてそうなってしまったのかや、民間と公務...
元々千葉市の熊谷市長には興味があったし、公務員を目指している身でもあるので、読んでみた。 公務員を目指している身として、なかなか興味深い内容だった。例えば、「公務員の仕事は遅い」とマスコミなどでは言われて格好の批判の的になっているが、どうしてそうなってしまったのかや、民間と公務員が、どのような点がどういう理由で異なっているのかを、市長が実際に見たり聞いたりしたことを交えながら分析している。 また、同時に、同じ革新的な市長でも、市役所の職員といかに協調しつつも、自分の思い描く理想を実現するかの難しさを赤裸々に語っており、面白い内容だった。 この本は、公務員とは何かを考えるのと同時に、市の政策についても考えるよいきっかけとなりそうだ。
Posted by
千葉市長当選時、最年少政令市長として話題になった熊谷俊人市長の著書第一弾。第二弾の「選挙ってなんだ?」を先に読んでいたので、こちらも読まないととは思っていたのだが、中々読めずに積んでしまっていた。時間が取れて読み始めたのだが、読むのに没頭してしまった。 「公務員」「役所」というと...
千葉市長当選時、最年少政令市長として話題になった熊谷俊人市長の著書第一弾。第二弾の「選挙ってなんだ?」を先に読んでいたので、こちらも読まないととは思っていたのだが、中々読めずに積んでしまっていた。時間が取れて読み始めたのだが、読むのに没頭してしまった。 「公務員」「役所」というとどこかマイナスなイメージがついてまわるこのご時世。公務員のイメージが変わるだけでなく、自分の生活態度から選挙参加の意志まで変わるような思いだった。 詳しい内容については是非本を読んでもらいたい。我が市の市長ということを除いても「公務員ってなんだ?」、「選挙ってなんだ?」の2冊は是非読むべき。
Posted by
「身近なことって実はあまり知らないんだな」 この本を読んでいて何回か思いました。 普通の生活の中で、自分と役所の関係性を考えることはあまりありません。 考える機会もありませんし、でも実はそこに大きな課題が内包されていることをこの本を通して思いました。 千葉市長の熊谷俊人市長が財...
「身近なことって実はあまり知らないんだな」 この本を読んでいて何回か思いました。 普通の生活の中で、自分と役所の関係性を考えることはあまりありません。 考える機会もありませんし、でも実はそこに大きな課題が内包されていることをこの本を通して思いました。 千葉市長の熊谷俊人市長が財政的にも、市民の信用的にも最悪という状況のなかで就任してから行った施策、そしてその施策にはどういう意図があるのか、また課題や想いといったものが書かれています。 とても、興味深いと思ったのは熊谷市長が就任した際に前体制の色を全部消すということをしなかったという部分。具体的には前体制の副市長を慰留した部分。 本書でも書かれているように、市長の周りを熊谷市長に近しい人で固めてしまった方が、新しいカラーを打ち出しやすいはずですし、改革もスムーズに行えるかもしれません。しかし、既存のベースを大事にし、職員の混乱が必要以上に大きくならないようにとの思いからのこのような行動に至ったそうです。この布陣を「最強布陣」と表現していたのも印象的でした。 この行動にも代表されると思うのですが、この市長は「縦軸」つまり、過去から未来への時間軸と「横軸」つまり職員同士、市民同士、自治体同士または役所と市民の人同士のつながりのバランスを非常によく考えているように感じます。この施策で未来がどう変わるのか、過去の何がいけなかったのか、そしてそれに対し役所はどういうアプローチで臨んで、市民にはどういう変化が求められるのか。施策の説明すらしっかりとされない自治体がある中で、この「縦軸」「横軸」をしっかりと考慮した熊谷市長の説明は非常に説得力を持っています。 市民と役所は「ギブアンドテイク」の関係です。私たちは税金というお金を預けて役所はそのお金で自治体の未来を明るくする。そして、私たちは享受する。だから、市民と役所はもっと積極的に歩み寄る関係であるべきなんです。でも、互いに疎外感があるのが今の現実… その関係性の変化に私たちの生活の向上のキーがあるのではないか、この本に言われた気がします。
Posted by
当時最年少市長として当選した千葉市長による著書。 前市長は汚職で失脚、財政的にも信用的にもどん底だった千葉市。 そこからの再建は並大抵のものではないと想像できます。 着実に一歩一歩前に進み、市民や市職員と対話を重ねる市長の書いたこの本は、読んでいてとても泣きたくなりました。 人...
当時最年少市長として当選した千葉市長による著書。 前市長は汚職で失脚、財政的にも信用的にもどん底だった千葉市。 そこからの再建は並大抵のものではないと想像できます。 着実に一歩一歩前に進み、市民や市職員と対話を重ねる市長の書いたこの本は、読んでいてとても泣きたくなりました。 人はきっと、人の強い想いに触れると心を動かされるんでしょうね。 本当に何度も泣きそうになって本を閉じました。 行政は市民を選べない。市民も大抵の場合、行政を選べない。 必然的に持ちつ持たれつ、ともに歩んでいかなければならない。 それなのに市民にはどこかお客様意識が、行政はいわゆるお役所と言われる融通のきかなさがあるように感じる。 そのどちらも根っこは同じで、市民にも「市の運営者」という意識が足りないし、市も情報開示を積極的にして理解してもらおうという姿勢が足りないのかもしれない。 課題を解決するには、まずは課題と認識しないといけないですね。 ともに歩みよることは、もちろん大事なことだけど、とても怖いことでもあります。 歩み寄って、わかってもらえなかったらどうしよう。批判されたらどうしよう。 それでも、歩み寄らないと何も始まらないし、これは私たち一人一人が考えなくてはいけないことですよね。 もっと市政に興味を持とうと思いました。 本書の、誰をも敵にしない市長の話の進め方、具体例をわかりやすく提示するプレゼン力に感銘を受けました。 執筆してくれてありがとういございます、と伝えたい気持ちでいっぱいです。
Posted by
- 1
- 2