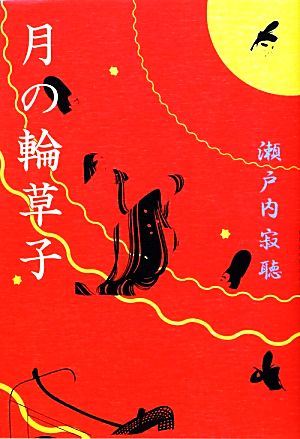月の輪草子 の商品レビュー
清少納言を主人公においてその一生を回想していきます 90歳になった清少納言が誰に聞かせるわけでもなく過去を振り返っているので、話が前後したり、同じようなことを何度も言っていたりと少し読みにくいと感じることもあるけれど、自分だけで振り返ると何度も話がいったりきたりとするだろうな...
清少納言を主人公においてその一生を回想していきます 90歳になった清少納言が誰に聞かせるわけでもなく過去を振り返っているので、話が前後したり、同じようなことを何度も言っていたりと少し読みにくいと感じることもあるけれど、自分だけで振り返ると何度も話がいったりきたりとするだろうなとリアルに感じられました 高校生の時に完全にタイトルと和紙を使ってるようなざらついたカバーに惹かれて購入 そこで初めて読んで以来、物凄く久しぶりに読み返してみて当時は理解できなかったところも理解できるようになってさらに面白く感じます
Posted by
隠居納言の回想調という体裁は取ってるけど、基本的には『枕草子』内の中関白家絡みのエピソードで繋いでいく構成は、冲方丁『はなとゆめ』と同じ。料理人が違うとこうも違う仕上がりになるのね〜、面白い。90歳過ぎても書き下ろし、素晴らしいです、寂聴さん。 納言の出仕し始めたのが正暦4(9...
隠居納言の回想調という体裁は取ってるけど、基本的には『枕草子』内の中関白家絡みのエピソードで繋いでいく構成は、冲方丁『はなとゆめ』と同じ。料理人が違うとこうも違う仕上がりになるのね〜、面白い。90歳過ぎても書き下ろし、素晴らしいです、寂聴さん。 納言の出仕し始めたのが正暦4(993)年、一条帝の時代が始まってからなので、それ以前の話(花山の出家とか)は人伝てだし、中関白家の雇われだからその外の世界の話も少なく。春宮(居貞親王、後の三条)周辺の話とかは全くなし。そりゃそうか。
Posted by
人間的なアクの強さが先行する清少納言だけれど、彼女が目撃した歴史の顛末があまりにも過酷で、少し見る目が変わった。負けた側に立つ人間の意地ともみれる枕草子の書き方は、逆をいえばとにかく切ないものだったということがわかる。瀬戸内寂聴だからこそ書ける、女としての定子、女としての清少納言...
人間的なアクの強さが先行する清少納言だけれど、彼女が目撃した歴史の顛末があまりにも過酷で、少し見る目が変わった。負けた側に立つ人間の意地ともみれる枕草子の書き方は、逆をいえばとにかく切ないものだったということがわかる。瀬戸内寂聴だからこそ書ける、女としての定子、女としての清少納言の苦悩がとてもリアルで、わかりやすくて、さすがと思った。
Posted by
(2014.11.17読了)(2014.08.30購入) 【日本の古典】 Eテレの「100分de名著」で『枕草子』が取り上げられたので、この機会に「小説清少納言 諾子の恋」三枝和子著、を読み、ついでにこの本も読んでしまうことにしました。 瀬戸内さんは、1922年生まれですので、こ...
(2014.11.17読了)(2014.08.30購入) 【日本の古典】 Eテレの「100分de名著」で『枕草子』が取り上げられたので、この機会に「小説清少納言 諾子の恋」三枝和子著、を読み、ついでにこの本も読んでしまうことにしました。 瀬戸内さんは、1922年生まれですので、この作品は90歳での作品となります。 Wikipediaによると、清少納言は、康保3年頃(966年頃) - 万寿2年頃(1025年頃)となっていますので、60歳ぐらいで亡くなっていそうなので、この本の語り手は、清少納言が乗り移った90歳の瀬戸内さんのようです。そのせいか、清少納言が自分のことを語っているようで、実は、瀬戸内さんが自分のことを語っていそうなところが随所に見受けられます。特に、清少納言が男性経験を語っている部分は、そのように思われます。 題名の「月の輪」は、清少納言が晩年を過ごした土地の名前のようです。 「小説清少納言 諾子の恋」と共通する話は、『枕草子』などに、書いてある話なのでしょう。父・清原元輔の落馬の話、「草の庵」の話、など。 『枕草子』の誕生については、中宮定子との会話の中から生まれたと推測しています。 和泉式部、道綱の母、等の話も出てくるので、いずれそちらの関連本も読まないといけなそうです。 ●性善説(38頁) 人間の性善説など信じたことはない。わたしのまわりは、いつでも仕様のない愚かな悪人でみちていたからだ。この世が善人ばかりで満たされていたら、なんと退屈なことだろう。 ●結婚は二度(65頁) 則光と別れて数年後藤原棟世と結婚した。棟世も摂津守で、わたしは受領の妻になった。棟世とは年の差が二十もあり、頼もしいけれど、面白味がなかった。 ●男と女(143頁) 愛しあっていると、言葉はいらない。顔を見ただけで、指の動きを追っただけで相手の心の要求が読め、より深い理解に到達する。 媾うという行為によって男も女も安堵し、相手の心をことばや文字以上に読みとることが出来るからだ。 ●常識(150頁) 大体、世間に伝っている常識なんていうものはすべて怪しい。あれを食べるな、これを呑むななどという健康法の常識も。実にいい加減なものだ。わたしは健康法をすべて無視して好き放題に暮らしているが、まだ死なないではないか。 ☆関連図書(既読) 「清少納言『枕草子』」山口仲美著、NHK出版、2014.10.01 「桃尻語訳 枕草子(上)」清少納言著・橋本治訳、河出書房新社、1987.08.31 「桃尻語訳 枕草子(中)」清少納言著・橋本治訳、河出書房新社、1988.12.20 「桃尻語訳 枕草子(下)」清少納言著・橋本治訳、河出書房新社、1995.06.30 「むかし・あけぼの(上)」田辺聖子著、角川文庫、1986.06.25 「むかし・あけぼの(下)」田辺聖子著、角川文庫、1986.06.25 「小説清少納言 諾子の恋」三枝和子著、福武文庫、1994.10.05 ☆瀬戸内晴美さんの本(既読) 「美は乱調にあり」瀬戸内晴美著、角川文庫、1969.08.20 「諧調は偽りなり(上)」瀬戸内晴美著、文芸春秋、1984.03.01 「諧調は偽りなり(下)」瀬戸内晴美著、文芸春秋、1984.03.01 「源氏物語の女性たち」瀬戸内寂聴著、NHKライブラリー、1997.11.20 「白道」瀬戸内寂聴著、講談社文庫、1998.09.15 「いよよ華やぐ」瀬戸内寂聴著、日本経済新聞・朝刊、1997.12.01-1998.12.13 「釈迦と女とこの世の苦」瀬戸内寂聴著、NHK人間講座、2000.04.01 「藤壺」瀬戸内寂聴著、講談社2004.11.24 「秘花」瀬戸内寂聴著、新潮社、2007.05.15 「日本を、信じる」瀬戸内寂聴・ドナルド・キーン著、中央公論新社、2012.03.11 (2014年11月17日・記) (「BOOK」データベースより)amazon 月の輪の庵で、九十を迎える清少納言は人生を振りかえる。心のうちに、甦るのは、幼い頃に死んだ母のことばと、お仕えした中宮定子のお姿だった。隆盛を極めた中関白家の衰退と権力をめぐる争い、中宮定子の悲劇。そして自分自身の結婚、離別、愛と性。華やかな宮中を生きぬいた女性の人生を描き、人の世の美しさをことばにした「枕草子」の創作秘話に迫る、瀬戸内寂聴の新たなる代表作。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
九十歳の媼となった清少納言がつらつらと過去を物語る。 浮かんでは消えるとりとめのない思考、記憶。時系列は行きつ戻りつし、若干の読みにくさはあるものの、清少納言と寂聴さんが 渾然一体となってそこに存在しているようで非常に興味深かった。「枕草子」に書かれたエピソードも時々出てくるけれど、それ以外の部分、夫や父とのやりとり、道長像、紫式部と源氏物語への評価、などが興味深かった。(←紫式部本人は大嫌いだけど、源氏物語は愛読してる、なんて、いかにも納言らしい。けど、そこには寂聴さん本人が顔を出しているのかな、ともw) あとがきには、「清少納言が書かなかった、定子の不幸な晩年、中関白家の没落」を小説家としていつか書いてみたかった、とあります。
Posted by
枕草子の訳本かと思っていたらそうではなく、90歳になった清少納言の昔語りでした。 もちろん枕草子が下地にはなっていますが、清少納言の晩年の様子や、結婚生活にも触れ、創作ながら楽しく読むことが出来ました。 平安時代の風俗や今風な恋愛観が寂聴さんに合ってるのかな、なんかわかりや...
枕草子の訳本かと思っていたらそうではなく、90歳になった清少納言の昔語りでした。 もちろん枕草子が下地にはなっていますが、清少納言の晩年の様子や、結婚生活にも触れ、創作ながら楽しく読むことが出来ました。 平安時代の風俗や今風な恋愛観が寂聴さんに合ってるのかな、なんかわかりやすいだけではなく無理がなくて読みやすかったです。 もともと源氏が好きなので、長いこと意味なくアンチ清少納言でしたが、山本淳子さんの本やこちらの本を読んだりしているうちに、気が強い清少納言が好きになり、定子のサロンの一員になったところを想像してみたりして、実在の人物だと物語とは違った楽しみ方があることを今頃噛みしめています☆ 清少納言のちょっと奔放な感じ、寂聴さんに似てる感じがする。 。
Posted by
まるで本当に見てきたかのような描写に圧倒された。 フィクションも混じっているようだけどもともと歴史に詳しいわけではないので気にせず楽しめた。よく知っていれば知っていたで面白いと思う。 当時の女流作家たちの作品をいま一度きちんと読みたくなった。
Posted by
何年ぶりかの寂聴さんの本&清少納言の物語ということで読んだ。 清少納言に関する物語はやはり少ないといえるので珍しさから。 気になったのは地の文で「神経」「プライド」「二、三分」という表記があったこと。どれ近代以降の概念じゃないかなと思うのですが。 もちろん『ジャパネスク』のよう...
何年ぶりかの寂聴さんの本&清少納言の物語ということで読んだ。 清少納言に関する物語はやはり少ないといえるので珍しさから。 気になったのは地の文で「神経」「プライド」「二、三分」という表記があったこと。どれ近代以降の概念じゃないかなと思うのですが。 もちろん『ジャパネスク』のように現代言葉を取り入れたものなら気にならないのですが、今回のように平安時代の時代小説を書いてるにしては目につきました。 無意識か、ねらってかはわかりませんが。 久しぶりに寂聴さんの文を読んで「かたいな」という印象を受けました。 ところどころに平安時代のそれぞれの人物の話が出てきて、正直どれも知った話だったので私は特に新しい発見はなかったです。 清少納言の語り方は、時間軸がわかりませんでした。これは老人だからということにまとめられてしまうのでしょうか。 「清少納言の性格」というのをやたらに意識して書いたような感じを受けます。 それが地の文にも表れていました。 清少納言と道長が関係を持ったというのは面白い設定ですね。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
世の中の移り変わりを詠った本。中関白家の栄華と、清少納言が描かなかった衰退の景色。女の因果や恨みや見栄や。色んな物が混じり合って、けれど彼女の名前は清少納言。悪びれず、あっけらかんとした文体に、只々引き込まれてゆきます。 寂聴さんの平安文学は、源氏物語などの口語訳も割と小説に近い形で訳されてありますが。 この本は口語訳というスタイルではない分、一層寂聴さんらしい味付けを楽しめる一冊となっています。
Posted by
ありそうで珍しい清少納言を主人公とした物語。 清少納言とその父親とのやり取りは独自性があって、興味深いです。 他方、中宮定子の悲劇については、どこかで読んだことがある印象です。 物語は、高齢になった清少納言が徒然なるままに思い出す記憶をなぞり、時系列が行ったりきたりします。 も...
ありそうで珍しい清少納言を主人公とした物語。 清少納言とその父親とのやり取りは独自性があって、興味深いです。 他方、中宮定子の悲劇については、どこかで読んだことがある印象です。 物語は、高齢になった清少納言が徒然なるままに思い出す記憶をなぞり、時系列が行ったりきたりします。 もっと清少納言を全面に出した物語であることを期待していたので、 全体的に少し物足りない感じがしました。
Posted by
- 1
- 2