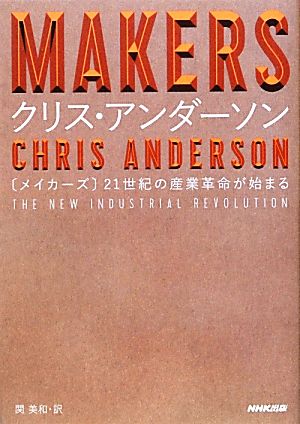MAKERS の商品レビュー
久し振りに読んでいてワクワクする本だ。モノづくりの可能性を指し示してくれる。ニッチな製造業が上手く立ち上げられる時代、ネットの力を感じる。
Posted by
「ロングテール」や「フリー」を著した栗須・アンダーソンの最新作。21世紀第三の産業革命などと話題になることが多いが、その正体は何なんだろうと疑問に思っていたことがクリアになった・・・ということはなく、やはり漠然としか分からない。デジタル・マニュファクチュアリングとパーソナル・マニ...
「ロングテール」や「フリー」を著した栗須・アンダーソンの最新作。21世紀第三の産業革命などと話題になることが多いが、その正体は何なんだろうと疑問に思っていたことがクリアになった・・・ということはなく、やはり漠然としか分からない。デジタル・マニュファクチュアリングとパーソナル・マニュファクチュアリングが一体となったときに、「もの作り革命」は起こるものらしい。ロングテールもフリーミアムモデルも、当時は何のことか分からなかったが今はよく分かるということを考えると、本書に書いてあることも数年後には当たり前になっているのか。 「メインフレームコンピューターしかなかった時代に、AT&TやIBMの精鋭達が集まってデスクトップコンピューターができたとしたら何に利用できるかを議論し、その結論に基づいて作ったのは、レシピを管理し、まな板を内蔵しているキッチンコンピューターであった。現在ノートブックやタブレットがどう使われているかを考えると、大手メーカーが想定していた使い方ではなく、ユーザーのニーズに基づいて開発製造されたものがほとんどである」ここから、個人がモノを作れるということの可能性とインパクトの大きさが何となく想像できる。自分たちを守るためのただ一つの盾は「コミュニティ」。ネットーワークから生まれる知の蓄積と進歩。アダムスミス「国富論」人は最も得意なことだけを行い、他の人が作るものと交換すべきだ。自動車はハードウェアからソフトウェアに近づきつつある。買った瞬間から劣化するのではなく、必要に応じてバージョンアップすれば良い。ビルジョイ(サンの恊働創業者)の法則「一番優秀な奴らはたいていよそにいる」オープンでイノベーティブな知見を取り入れようと思ったら、社内も同じ程度にオープンでイノベーティブでなければならない。人件費の安い地域での製造と、近くでの製造の比較は、性能、輸送コスト、製造のスピード、様式変更への対応など。レゴとブリックアームズの生態系。
Posted by
『ロングテール』『フリー』の著者による続編的な内容。 「フリー」による「モノ作りの民主化」が「モノのロングテール」を作り手側に生み出す、ということを実例 を挙げながら論じてんいる。デザインさえできてしまえばファブレスでよいことや、モノ作りの機械化により、人件費よりも流通コストや安...
『ロングテール』『フリー』の著者による続編的な内容。 「フリー」による「モノ作りの民主化」が「モノのロングテール」を作り手側に生み出す、ということを実例 を挙げながら論じてんいる。デザインさえできてしまえばファブレスでよいことや、モノ作りの機械化により、人件費よりも流通コストや安全コストの比重が相対的に高まっていくといった指摘も興味深い。
Posted by
図書館で借りた。気になってたけど、買うほどじゃないかなぁと思ってた。読んでみて、メイカーブームの意味が分かった。 ビットとアトムを繋ぐって書いてある通り、3Dプリンターやレーザー加工機が安く手に入ることが重要ではない。繋ぐためのネットワークやCADがネット環境さえあれば誰でも無料...
図書館で借りた。気になってたけど、買うほどじゃないかなぁと思ってた。読んでみて、メイカーブームの意味が分かった。 ビットとアトムを繋ぐって書いてある通り、3Dプリンターやレーザー加工機が安く手に入ることが重要ではない。繋ぐためのネットワークやCADがネット環境さえあれば誰でも無料で使えることが革命的。ネット環境があれば、家にいながらにして、ものづくりができるだけではなく、資金、アドバイス、バグ出し、改善案、市場調査、真のニーズの全てが簡単に手に入る。単品のものづくりのコスト減は、最後の後押し的な印象。 会社で食うに困らない働きをしつつ大量消費社会向け製品を作り、オフにメイカーの一員になってボランティア的にオンライン上で技術を提供しつつスキルアップしていけたら、最高。
Posted by
フリーミアム、の本を書いた著者の最新作。 インターネットが現実の物作りにまでこんなに影響を及ぼしていることを、明確に認識したことはなかったけど、確かに最近は3Dプリンタの価格がかなり下がってきていることを思い出した。
Posted by
ロングテールに比べると、ちょっと期待はずれ。 でも、面白かった。 3Dプリンター、3D CADもフリーで使える。 もののロングテールも始まっている。 クラウドファンディングで、資金調達もできる。 生産部門もネットで調達できる。 オープンソースで、作り上げることで、 研究開発の...
ロングテールに比べると、ちょっと期待はずれ。 でも、面白かった。 3Dプリンター、3D CADもフリーで使える。 もののロングテールも始まっている。 クラウドファンディングで、資金調達もできる。 生産部門もネットで調達できる。 オープンソースで、作り上げることで、 研究開発のスピードも速い。 本とか?と思うが、Wikiなどのようにフリーのコミュニティの協力さはまちがいない。 オープンソースをどうやって利益につなげるかは、 もう少し考えは必要。 クラウドファンディングは、資金調達の綿でも大事だが、 ニーズがあるのか同化の市場調査を兼ねることもありえる。 これで資金調達をできないてーまは成功しない。 ベンチャーキャピタルと違って、 支配権なども失わない。単に、最初の売上げを前借しているだけ。 清算の自動化が進むと、人件費の寄与度は下がる。 すると、発展途上国で生産する必要はなくなる。 → 先進国にも戻る。 巨大企業がなくなるわけではない。 あくまでニッチな物が増えるということ。 そもそもフリーなので、模倣者は歓迎。 それをも生態系に取り込むような。 先行者権限を最大限に活かす。 コミュニティーを構築し、サービスを保証する。 車のデザインを学ぶ人のほとんどは車メーカに就職できない。 その人たちの情熱を拾い集めるだけでよい。 クラウドファンディングと、コミュニティーを意識してみよう。
Posted by
わくわくして、わくわくして、もう逆戻りしない大きな時代の転換期のまっただ中にいる思わずそう思わされた。 ブログに感想書きました! http://shinojackie.blogspot.jp/2014/01/makers.html
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
○ワイアードUS版編集長でベンチャー企業の経営者でもあるクリス=アンダーソン氏の著作。 ○3Dプリンターの誕生の意義等を中心に、新たな“ものづくり”について、その主体やあり方に言及したもの。 ○インターネット、ソーシャルネットワークの普及が、“ものづくり”のあり方をこれほどまでに変えるという視点が興味深い。 ○技術の発達が全てではないが、アダム=スミスの言う「分業」が、現在はまだ過渡期であるんだなぁと、改めて感じた。単なるカスタマイズではなく、ニーズに応じたモノ(商品)そもそもの差別化・細分化が行われていくのだろう。 ○これからは、企業だけでなく、ひとりひとりが“メーカー”である(になれる)のだ。
Posted by
ものをつくる。本能に根ざした行為。大人になるにつれていつしかできない理由を探すようになり、ありものですませるようになって久しい。これまで趣味、ビジネスでのモノづくりの制約になっていたものが徐々になくなっていく世界が克明に描かれている。これまであきらめていたものを作ってみようかなぁ...
ものをつくる。本能に根ざした行為。大人になるにつれていつしかできない理由を探すようになり、ありものですませるようになって久しい。これまで趣味、ビジネスでのモノづくりの制約になっていたものが徐々になくなっていく世界が克明に描かれている。これまであきらめていたものを作ってみようかなぁと思わせてくれる一冊。
Posted by
人間の歴史が楽をしていい気分でいるためにはどうすればよいのか、を考えてきた歴史だとすると、このような「自分で選び取る」「カスタマイズする」というものはなかなかメインストリームにはならないだろう。もちろんこういったメイカー達はメインストリームになろうとしていない訳だけど、一旦消費者...
人間の歴史が楽をしていい気分でいるためにはどうすればよいのか、を考えてきた歴史だとすると、このような「自分で選び取る」「カスタマイズする」というものはなかなかメインストリームにはならないだろう。もちろんこういったメイカー達はメインストリームになろうとしていない訳だけど、一旦消費者になってしまった大多数の人々はやはり消費者以上のものにはなかなかなれないのでは、と思う。
Posted by