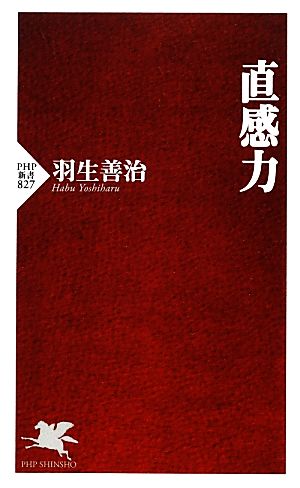直感力 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本で出会った素敵なフレーズが二つある。 一つ目が「短期的には否定的で、長期的には楽観的に考える」という文章だ。成長にはある程度、現状の自分には満足せず問題点を見つけなければならないが、そればかりに集中してしまうと全体すらも否定的に捉えてしまい、あたかも自分という人間が駄目なように感じてしまう。私は、ネガティヴはピンポイントで、全体ではポジティブで。を心がけたいと思った。 二つ目は「あえて考え込まない、自己否定ないことは、感情的にならずに冷静に判断し選択するというプロセスにおいて必要不可欠だと思っている」という文章である。私はてっきり考え込むことで冷静に判断できると思っていたし、「考え込む」ことが「冷静」を想起させるとまで思っていた。でもそうではない、一歩引いてフェアな視線で考えることが「冷静に判断する」ということらしい。
Posted by
知識や経験を積み重ねた上での直感。 闇雲に思い付きで考えて行動することではない。 経験があるからそ、直感として降りてくるという事なんだろう。
Posted by
内容は感覚的か論理的と問われれば明らかに前者で、ちょっと難しいところもあったけど著者は分かり易く表現するよう努めてくれたと思う。 野球でもゴルフでもそうだけど、その道に特化した人はそれで人生を例えるけど羽生氏も将棋で人生を見ている感があって興味深かった。
Posted by
世間からすごいと言われる人は皆共通する思考回路を持ってるんだなと思った 道のりを振り返らないっていうのは確かに大事 「これだけ時間をかけてやったのに…」っていう思考が成長を減速させるんだよね ✏論理的思考の蓄積が、思考スピードを速め、直感を導いてくれる ✏自分が学んでつくり...
世間からすごいと言われる人は皆共通する思考回路を持ってるんだなと思った 道のりを振り返らないっていうのは確かに大事 「これだけ時間をかけてやったのに…」っていう思考が成長を減速させるんだよね ✏論理的思考の蓄積が、思考スピードを速め、直感を導いてくれる ✏自分が学んでつくりだした「経験のものさし」によって、人は何かことに当たるとき、その時間の不安に耐えられるようになる ✏何を選ぶかは、選ばなかったことに対してどれだけ多くの創造力を働かせることができるかによると思う
Posted by
ものすごく期待して読んだんだけど‥言いたいことはわかった気がする。しかし、抽象的。抽象的。羽生さんの考えをふわっと触る本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
直感は本当に何もない所から湧き上がることはない。 もがき努力した全ての経験を土壌として、ある瞬間に生み出されるもの。ほとんどが無意識下で行われ、意図的に行っているのかが自分自身にもわからないようになれば、直感が板についたと言える。そしてそれを信じることで、湧いてきた直感が初めて有効になる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書の「はじめに」に、棋士は「直感」と「読み」と「大局観」の三つを使いこなしながら対局に臨んでいると述べ、そのうち「読み」については「計算する力といっても過言ではない」と述べている。「大局観」については、著書を読んでくれと言われている。そして、本書で「直感」について語ろうというのだ。 ただ、本書のタイトルは「直感力」であるが、それだけについて語られたものではなかった。将棋という勝負の世界全般について語られている。自身の期待としてはプロの棋士の直感というものがどういうものかを知りたかったので、それについて述べられた最初の二章くらいがとても面白かった。 第一章「直感は、磨くことができる」 「直感は決して先天的なものではない」という言葉から、「直感」は経験により得られるということだが、その得られるプロセスの説明が非常い興味深かった。 「地を這うような読みと同時に、その状況を一足飛びに天空から俯瞰して見るような大局観を備え持たなければならない。そうした多面的な視野で臨むうちに、自然と何かが湧き上がってくる瞬間がある。」 羽生さんと対談されたカーネギーメロン大学の金出先生の言葉も並べてみると面白い。 「それまでは毎回発火していた脳のニューロンが、その発火の仕方がいつも同じなので、そこに結合が生まれ、一種の学習が行われたということではないか」 「直感」といっても、それは膨大な思考の蓄積の中から生まれるものというイメージだ。昨日今日でふと直感力が身につく者でないことが分かる。 さらに、次のような言葉は、プロ棋士の「直感力」がいなかるものかを少しでも理解する手立てとなるように思う。 「つまり、直感とは、論理的思考が瞬時に行われるようなものだというのだ」 「もがき、努力したすべての経験をいわば土壌として、そこからある瞬間、生み出されるものが直感なのだ」 「湧き出たそれを信じることで、直感は初めて有効なものとなる」 「惑わされないという意志。それはまさしく直感のひとつのかたちだろう」 「将棋は、ひとつの場面で約八〇通りの可能性があると言われている。私の場合、その中から最初に直感によって、二つないし三つの可能性に絞り込んでいく」 「直感は、ほんの一瞬、一秒にも満たない短い時間の中での取捨選択だとしても、なぜそれを選んでいるのか、きちんと説明することができるものだ」 「直感を磨くには、多様な価値観を持つことだと思う」 次の第二章「無理をしない」では、冒頭に「余白がなければ直感は生まれない。リラックスした状態で集中してこそ、直感は生まれる」という言葉が紹介され、その意味について解説が加えられる。 「余白がある」ということは、「無駄がある」と同意のようだ。無駄とは「役に立たないこと」とか「間違い」とかを意味するようであるが、そういうことの経験も一定量を超えると、それが全体に対して有効になってくるという。「失敗は成功の母」の考えに近い。 リラックスした状態で集中する、その集中とはいかなるものか。 著者は、集中力を高めるトレーニングとして3つ挙げている。 ①何も考えない時間をもつ(その状態からスタートして、徐々に深く潜っていくのだそうだ)。 ②じっくりと一つのことについて考えをめぐらせる習慣を作ること。 ③時間と手間のかかる作業に取り組む(=集中力持続のために)。 すなわち、「集中力」もまた昨日今日で簡単に身につくものでないことが分かる。 無駄と思えることも、失敗も、多くの経験の蓄積を重ね、そういう取り組みの中でじっくりと一つのことについて考えをめぐらせたり、時間や手間をかけてでも取り組んでいくという地味な作業の集積の結果として、すぐれた「直感力」が獲得できるということになる。何事も真剣さを忘れず、経験を積み重ねよということだろうか。
Posted by
伝説の棋士、羽生善治の思考のエッセンスが凝縮された一冊。 将棋の話だけではなく、そこから得られた様々な対象についての洞察が記されている。読みやすく、こうした考えもあるのかと参考になる。良書。
Posted by
直感は、本当に何もないところから湧き出てくるわけではない。考えて考えて、あれこれ模索した経験を前提として蓄積させておかなねばならない。 という言葉が全て。 みんながいう直感てのは正しくなくて、経験値をためるしかない。行動しつづけて、そのために考えつづけた人しか直感は働かない
Posted by
なんだか難しい。羽生さんのような、日々難しい何かをたくさん考えているような人にならないと、わからない気がした。もっとわかりやすく書いて欲しい。私には、伝わらない。
Posted by