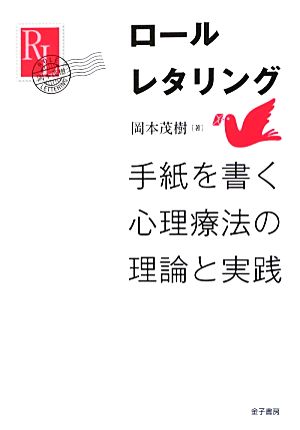ロールレタリング の商品レビュー
「悲しく辛い時にこそ無理してでも笑顔でいよう」と言われるけど、それは辛すぎて無理だと思っていた。そんなことしたら自分の心は壊れてしまうと思ってた。 この本を読んで自分が思っていたことは間違っていないと感じている。 悲しい時に笑顔でいて良いのは、しっかりとしたサポートが得られていて...
「悲しく辛い時にこそ無理してでも笑顔でいよう」と言われるけど、それは辛すぎて無理だと思っていた。そんなことしたら自分の心は壊れてしまうと思ってた。 この本を読んで自分が思っていたことは間違っていないと感じている。 悲しい時に笑顔でいて良いのは、しっかりとしたサポートが得られていて自分の負の感情を自分で認識して吐き出せている時に限る。 この本を読んで私はそう感じた。
Posted by
相手への手紙を書くことで自分の本当の心に気づくという心理療法。 ゲシュタルト療法との比較があっておもしろい。 一人ではできないところがちょっと残念である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2019年12月14日に開催された講座で,ロールレタリングの手法を紹介しました。 その勉強のために読んだ書籍です。 本書(主に第1部)を要約すると以下です。 ロールレタリング(ローレタ)とは,「自分から相手へ」の手紙を書いたり,ときには相手の立場になって,「相手から自分へ」の手紙を書いたりするなかで,さまざまな思いや感情を書くことによって,自分自身だけでなく相手のことも理解し,人間関係が改善していく技法(p.15-16)です。ローレタは「感情の吐き出し」によって様々な効果が生まれます。たとえば,①カタルシス効果,②自己理解,③他者理解,④自己受容と他者受容,⑤自己表現力の向上,⑥認知と行動の変化,⑦性格の変化などがあります。ローレタに取り組むためには,「書こうという気持ち」「抱えている葛藤を解決したい意欲」「感情を吐き出すための後押しをしてくれる支援者の存在」が必要です。これらを前提として,ローレタを実際に実施する際には「自分の言いたいことを書ける範囲で書く」「できるだけ紙とペンを使う」「話し言葉で書く」「自分から相手への手紙が基本」であることが述べられています。そのほかにも第1章では,ロールレタリングが理論的背景として交流分析が挙げられます(ただ,個人的感想ですが,この理論的背景のせいでロールレタリングの信憑性が低下しているように感じました)。第2部は筆者が携わった実際の事例です。第3部は事例を振り返りながら第1章で説明したことを改めて紹介し,集団指導や矯正教育でロールレタリングを活用する際の心構えが述べられています。 日本発祥の心理療法であるロールレタリング。洗練させる必要があるとは感じるものの,可能性を感じる手法でした。筆記開示との違いなども気になるところです。
Posted by
役割交換書簡法とは、「自分」と「相手」の二役を 演じながら、往復書簡のやり取りを繰り返し、自分の 立場から感情を訴え、相手の立場でそれを受け止めて 返信する過程で、自己洞察を深めたり、他者理解の 気持ちを生じさせることによる心理療法。 実例をもとに解説があり、参考になった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
直接自分に関わった人間に思いを語ることも、カウンセラーに打ち明けることも、考える以上に難しい。 しかし、本音を吐露したい相手に見せなくてする手紙を書くことで、気持ちが解消されるなら、少しは肩の荷が降りるのではないか。 実際に変化を見せる臨床例も掲載されている。 自分をそれに重ねあわせて読んでみると、カタルシス効果と同時に、自分を守りながら他者への共感を持つことが出来るように成るかもしれない。 精神科や心理カウンセリングにお世話になるほどでなくても、読んでみて得るものは大きい。
Posted by
- 1