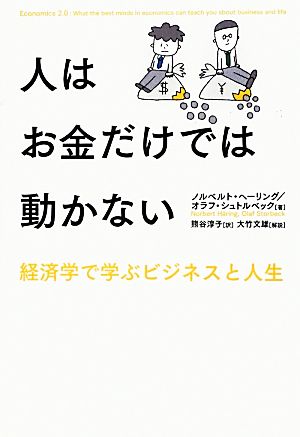人はお金だけでは動かない の商品レビュー
経済を回すわかりやすい道具であり、価値基準をつくるものとしてわかりやすい指標であるお金。しかし、世の中は、お金という物差で測れるものばかりではない。 そういうことを例を挙げながら書いている本。タイトルのわりに目新しさはない。
Posted by
不公正な行為に制裁を加えようと決断すると、報酬系の重要な部位が活発になる。 行動経済学的な考え方の事例紹介。
Posted by
題名からは行動経済学の本のようだが、そうではなく、最近の経済学の話題を広く浅く紹介する本。リーマンショックのサブプライムの仕組みとか、ステマの経済効果のような話も含む。 所々、訳に疑問がある。
Posted by
大竹文雄の解説では本書を絶賛していたが、期待したほどで面白くはなかった。同じ経済学の最先端を著した書物としては、先に読んだ「経済物理学の発見」の方が、よっぽど驚きの連続であった。いずれにしても、共通するのは、これまで経済学の大前提が覆されているということ。 ウェーバーのプロテスタ...
大竹文雄の解説では本書を絶賛していたが、期待したほどで面白くはなかった。同じ経済学の最先端を著した書物としては、先に読んだ「経済物理学の発見」の方が、よっぽど驚きの連続であった。いずれにしても、共通するのは、これまで経済学の大前提が覆されているということ。 ウェーバーのプロテスタントと資本主義の精神はあまりにも有名だが、裕福たらしめているのは、その精神ではなく、実は識字能力であったというもその一つ。
Posted by
やっぱり行動経済学は面白い。難解なことも平易な言葉とわかりやすい身近な事例で解説してくれるから親しみ易い。最近はこの手の本が増えてきて嬉しい(*´ω`*)
Posted by
タイトルに惹かれて読んだ本。人の経済活動が絶対値ではなく比較値で動く点がとても興味深い。ただ、全体的に経済学の本ではよく聞いた事例が並んでおり、目新しい内容は少ないかもしれない。
Posted by
人は心理、同意、共感によって動くというのがこの本を読めば理解出来ますし、ビジネスに活用できるチャンスの多さもわかります。
Posted by
経済政策というと、結局お金をどこにいくら使うかという話になってしまうが、人はお金だけでは動きませんよという多くの例を紹介しています。多くの文献を参照していることもあり、話の内容はスポー等の話からオークションの話まで、人が何を基準に行動を決めているのかを紹介しています。たとえば、テ...
経済政策というと、結局お金をどこにいくら使うかという話になってしまうが、人はお金だけでは動きませんよという多くの例を紹介しています。多くの文献を参照していることもあり、話の内容はスポー等の話からオークションの話まで、人が何を基準に行動を決めているのかを紹介しています。たとえば、テレビの視聴時間の長いは不幸に感じる傾向にある、教会に通う頻度と宗教信念の強い国は経済成長率が高い、リードされている段階で攻撃的な選手を投入すると得点できる確率は21%で失点は40%と高いなど。 この本で出てくる話は、収入の多さが人の幸せに結びつかない話ばかりで、人が満足感を得るには様々な要因があることがわかります。また、個人だけではなく、他の人が同時に満足できるかなど、満足感を得られるには、個人、家族、グループ、チーム、会社、国といったいくつものレベルでの考慮が必要であることもわかります。 最近の行動経済学の領域をわかりやすく、しかも特定の説に傾倒する書き方ではないので、読みやすくなっていました。お勧めの一冊です。
Posted by
レビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11410574822.html
Posted by
・行動経済学以外にも、幅広く最近の経済学のトピックを紹介。広く浅く経済学の最新動向を知りたい人に最適。 ・以下に気になった箇所を抜き出し。 第5章 すべては文化しだい ・先進工業国の間で、株式保有率が国によって大きく異なる理由を経済学者はうまく説明できずいた 株式保有率の...
・行動経済学以外にも、幅広く最近の経済学のトピックを紹介。広く浅く経済学の最新動向を知りたい人に最適。 ・以下に気になった箇所を抜き出し。 第5章 すべては文化しだい ・先進工業国の間で、株式保有率が国によって大きく異なる理由を経済学者はうまく説明できずいた 株式保有率の高い国 アメリカ、スウェーデン 株式保有率の低い国 ドイツ、イタリア、オーストリア →よく日本はアメリカより株式保有率が低い事が問題視されるが、株式保有率が低いことは特段珍しい訳ではないらしい。いつもアメリカとばっかり比較されるから、錯覚していた。 ・近年の調査で信頼が株式文化の違いに重要な役割を果たしていることが示された 株式保有率の高い国では、大企業への信頼度が高い 株式保有率の低い国では、大企業への信頼度が低い →信頼の無い所に、取引は生まれない 確かに日本でも、大企業への不信感は強いかも、なんか納得 第3章 労働市場の謎 ・「最低賃金を上げると雇用が低下する」という説は近年疑問視されている。 最低賃金の値上げによって、雇用が増加したという実証研究も(ニュージャージー州) ・知的能力は世代が新しくなる毎に10%増加する。(自分の子供は、親より10%頭が良い) ・異なる環境で育った双子の研究は、ほぼ一貫して知的水準の差が遺伝的に決まっていることを示している。 しかし、世代が下るにつれてどんどんIQが高くなることは、この結論と矛盾する。 ある世代から次の世代の間に遺伝子はごくわずかしか変化しないからだ。 →橘玲氏は、「IQ=遺伝子」説を支持しているみたいだけど、それに対する反証になるかも。 参考 ≫ 【書評】石川幹人『生きづらさはどこから来るか』 | 橘玲 公式サイト http://www.tachibana-akira.com/2012/11/5210 ・プロテスタント信者がカトリック信者より裕福なのは、優れた労働観(勤勉)の為ではなく、プロテスタント信者は聖書を自分で読むという教義の為に識字率がカトリック信者より高かったから。 第12章 スポーツ選手をモルモットに ・インセンティブの歪み(望まない副作用) 国際サッカー連盟(FIFA)のルール改定。ゴール数を増やし試合のスリルを高めるため、勝利チームの勝ち点を2点から3点に引き上げた。引き分けの場合はこれまでどおり1点。 →引き分けの試合は減り、シュートとコーナーキックは増えた。 しかし、ゴールが増えるという期待は裏切られた。先制点を挙げたチームは守備を固め、ファウル回数が増える結果に。 ・依頼人と代理人の関係(プリンシバル・エージェント問題) 審判は試合を公正に進めるためではなく、観客を喜ばすためにホイッスルを鳴らす。地元チームが1点負けていると、ロスタイムの時間が長くなる。スペインでは2分、ドイツでは30秒長くなる。 →イギリスではプロ審判員を導入したところ審判員の判断の質が目に見えて向上した。審判員の給与アップ(飴)と、誤審へのペナルティ強化(判定ミスが多いと停職処分)(鞭)。 第14章 最後の警告 ・経済学者も間違いを犯す スティーブン・レヴィットが2001年に発表した研究で、「アメリカの犯罪率が90年代から低下傾向にある一番の理由は、1973年に妊娠中絶が合法化された為」。 →ボストン連邦銀行の経済学者、クリストファー・L・フット、クリストファー・F・ゲッツは、レヴィットの計算が本文の計算手法から逸脱している事をつきとめた。ただしく計算しなおしたところ、「妊娠中絶が犯罪に対して選択効果をもつという説得力のある証拠は見つからなかった」。 ・再検証 アメリカン・エコノミック・レビューの規定では、著者は掲載論文の結果再現のためのデータ要請に応じる事になっていた。 しかし、1998年にマッカローとヴィノドが、実際に1つの号の全論文に対して、結果再現のためにデータとコードの提供を要請したところ、著者の半数はその義務を拒んだ。 →2003年にこの結果を発表すると当時アメリカン・エコノミック・レビューの編集者だったベン・バーナンキ(現在は連邦準備理事会議長)は、記録用としてデータとコードの提供を義務化した。
Posted by
- 1