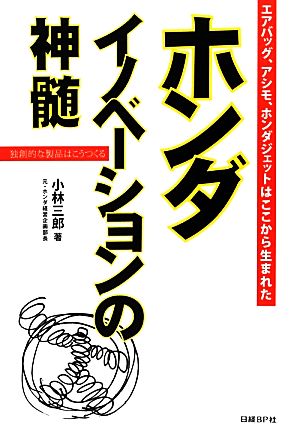ホンダイノベーションの神髄 の商品レビュー
面白かった。 最初はおっちゃんが悪態ついてるだけのように思えたけど笑 まぁ若者の気持ちを代弁してくれてると思えば良い気持ちいいかも。 オペレーションとイノベーションは全く異なるもの。今の会社のトップの方々はオペレーションでのし上がってきた人たち。故に失敗することがほぼ当たり前の...
面白かった。 最初はおっちゃんが悪態ついてるだけのように思えたけど笑 まぁ若者の気持ちを代弁してくれてると思えば良い気持ちいいかも。 オペレーションとイノベーションは全く異なるもの。今の会社のトップの方々はオペレーションでのし上がってきた人たち。故に失敗することがほぼ当たり前のイノベーションには消極的。 口ではイノベーションって謳うけど、、、 やりたいことができる会社っていうのはそもそもそういう社風なんだろう。 自分がやりたいことをやるには自分で企業するのが今の時代近道なのかもしれない。ハードルも低いのではないだろうか。 以下、印象的なシーン 1. 何度も感謝の言葉を受けた。〜技術者冥利に尽きるとはこのことだ。 →やっぱ誰かに感謝される仕事って幸福度高いよなぁ。 2. 食塩水の濃度を5秒で解くテクニックについて。 天秤を使った考え方。 →これ初めて知ったかも。小学生の算数の問題が1番難しいかもしれない。ここで言いたいのはコンセプトとアプローチがイノベーションには重要ということ(みたい) 3. 完璧な技術、製品はなく問題は必ずある →「あなたたちのシステムの問題点は何ですか」 これを発注先のエンジニアさんに聞いてみよう。 きっと嫌われる笑 ただここでちゃんと答えてくれる人は信頼に値するのかもしれない。 もっと言えば今後どうやって改善していくかを計画しているなら最高。 4. 心の中で「あなただからできなかったんだ。私なら絶対にやってみせるぞ」 →自分に言い聞かせます。
Posted by
イノベーションを成功させるためには、時間がかかる。 長い時間ぶれずにやるためには、強い気持ちが必要になる。 製品が出せても、世に浸透させる品質のためには、全てを深くやりきる必要がある。 ただこれはデジタル領域では、一つプラスがある気がする。 まず最初に出す。 早く出して世に問...
イノベーションを成功させるためには、時間がかかる。 長い時間ぶれずにやるためには、強い気持ちが必要になる。 製品が出せても、世に浸透させる品質のためには、全てを深くやりきる必要がある。 ただこれはデジタル領域では、一つプラスがある気がする。 まず最初に出す。 早く出して世に問う。 その上で、本当の成功までじりじりと詰めていくのだと思う。 (以下抜粋。○:完全抜粋、●:簡略抜粋) ○他社の話なんて聞きたくない。それは相対的な話にすぎない。あんたは今、ホンダの安全の方向性を決めているんだ。そのときになぜ他社の顔色を見るのか。なぜ自分たちがこうなりたいと、絶対的な価値を言えないのか(P.23) ●実はもう一つ、ホンダ流イノベーションの必須条件がある。技術者が高い志と強い想いを持つことだ。ホンダでは、技術者個人の自由と裁量に任されている領域が広い。技術者のやる気がなくなったら、いくら本質に根差した哲学があり、イノベーションの加速装置を備えていても全く役に立たない。(中略)だから、経営者や役員は、人づくりのために時間の三~四割を使う必要がある。(P.59) ○一週間や二週間で集めた資料が本質を議論する際に役立つわけがない。それよりも実際の体験を通じて身に付けた知識や、その人の価値観/人生観の方がはるかに重要になる。(P.69) ○「何でこんなに当たり前のことを延々と話すのだろうか」と思った瞬間、ハッと気付いた。「当たり前のことを徹底してやる」ことが本質だ、と。(P.161) ○40%の力があれば任す(P.202) ○思い付ける故障は必ず起こる(P.249)
Posted by
技術開発プロジェクトの立ち上げでとても参考になる。30年前と今でホンダもすっかり変わってしまったと言う人がいるのもよく分かった。
Posted by
筆者の熱量が伝わってくると著書だった イノベーションとオベレーションを明確に分ける イノベーションは全体の5%で良い 最後は情熱思い 著者の思い込みが激しいと感じる部分もあった
Posted by
ホンダで16年間に及ぶ研究開発の成果として、1987年に日本初のエアバッグの量産に成功した、小林三郎氏が、ホンダでイノベーションをどのようにして生んできたかを著している。 久しぶりに相当面白かった。三日三晩の合宿で徹底議論するという「ワイガヤ」などのエピソードはやっぱりホンダは違...
ホンダで16年間に及ぶ研究開発の成果として、1987年に日本初のエアバッグの量産に成功した、小林三郎氏が、ホンダでイノベーションをどのようにして生んできたかを著している。 久しぶりに相当面白かった。三日三晩の合宿で徹底議論するという「ワイガヤ」などのエピソードはやっぱりホンダは違うなあ、と思う半面、日々の業務への姿勢については、参考になる金言ばかりである。想いを持って、徹底的に考えるという当たり前のことの重要性が身に染みた。
Posted by
武沢氏の本を読んでホンダに興味でたので購入。アツい!!イノベーションしたくなる(?)こと請け負いのすばらしい一冊でした。イノベーションを生み出す組織となるための仕掛けは多々あれど、最後は「考え抜く」「熱意」「根性」みたいな、人間力勝負的な結論になっているところがとても好きでした。...
武沢氏の本を読んでホンダに興味でたので購入。アツい!!イノベーションしたくなる(?)こと請け負いのすばらしい一冊でした。イノベーションを生み出す組織となるための仕掛けは多々あれど、最後は「考え抜く」「熱意」「根性」みたいな、人間力勝負的な結論になっているところがとても好きでした。二度読みしたい本。
Posted by
ホンダは創業者が熱い天才だったので、いかにそのDNAを引き継ぐかを工夫されている。イノベーションを大切にしておるそんな会社でも筆者の取り組んだエアーバックは苦労の連続だったようです。そんな事例の取り組みが満載されている。 著者の切り口は、オペレーションとイノベーションに分けた際の...
ホンダは創業者が熱い天才だったので、いかにそのDNAを引き継ぐかを工夫されている。イノベーションを大切にしておるそんな会社でも筆者の取り組んだエアーバックは苦労の連続だったようです。そんな事例の取り組みが満載されている。 著者の切り口は、オペレーションとイノベーションに分けた際のイノベーションを貫きオペレーションに新しい価値を届ける困難の大きさ、しかしやりようによっては実現できる勇気を与えてくれる。ものづくりを経験した人なら大抵想像できる。 ホンダは、 開発がブレないように基本構想をA00と呼ばれる文章に集約された本質的な目標を定義する。いつ何時もA00に立ち帰れる様になっている。別の会社では、目標に指標がいつしか利益に変わることで色々な社会問題となっている。まさに他社はCSRで補強しないと横にそれるがホンダはA00がしっかり議論されていれが同じ様なことが起きない。 本田宗一郎の「理念、哲学なき行動は凶器である。行動なき理念は無価値である。」に基づき哲学を大切にされている。 三現主義(現場、現物、現実)で本質を見失わないような社風は保たれている。 近江商人の三方良しの技術者版ともいう3つの喜びなるものがある。「作って喜び、売って喜び、買って喜ぶ」また、人間尊重に基づき議論がしやすい環境をある。「自律、平等、信頼」である。
Posted by
ホンダの企業文化を知った。イノベーションはコンセプトで決まる。コンセプトとは、本質である。本質をワイガヤなどの議論やあらゆる思考で突き詰めることこそが重要なのである。そして最後は、情熱だ。情熱さえあれば、誰でもできる。
Posted by
ホンダでエアバッグの開発を主導し、16年に渡る苦闘の末、実用化を成功させた著者によるイノベーションの実践論。実は数年前、この著者の講演を拝聴した後に宴席をご一緒し、無謀にも議論を交わそうと挑んだところ、ホンダの流儀でコテンパンにやられて玉砕したことがある(苦笑)。 本書を読むと...
ホンダでエアバッグの開発を主導し、16年に渡る苦闘の末、実用化を成功させた著者によるイノベーションの実践論。実は数年前、この著者の講演を拝聴した後に宴席をご一緒し、無謀にも議論を交わそうと挑んだところ、ホンダの流儀でコテンパンにやられて玉砕したことがある(苦笑)。 本書を読むと、ホンダでは「ワイガヤ」などの草の根的な活動が全く形骸化することなく脈々と受け継がれ、それらが相互に連動しながら数々のイノベーションを生み出してきたことがわかる。つまり戦略論よりは運動論が中心で、マッキンゼーの「7S」の中の「ソフトの4S」で説明できそうだが、とはいえそのような一般論的な解説は、MBA嫌いの著者からすればそれこそ「バカヤロー」と一蹴されてしまうのだろう。 戦後〜高度成長期にかけて、数々のイノベーションによって経済的地位を確立した日本が、いつの間にかオペレーション重視に偏り、新たな価値を生み出すことが困難となっている現状に対し、著者は事業を通じて物事の「本質」を追求し続ける覚悟なくして、社会に価値あるイノベーションを生み出すことは不可能だと喝破する。何らかのノウハウを学ぶというより、本質を見失いがちな自分に気合を入れ直してくれる一冊。
Posted by
「本田宗一郎」の「哲学」の実践編、といった本。著者の経験を追体験しながら、どう考えていけばより意義のある仕事ができるか、ひいては面白い人生を送れるかといったことにつながるヒントをもらえる。
Posted by