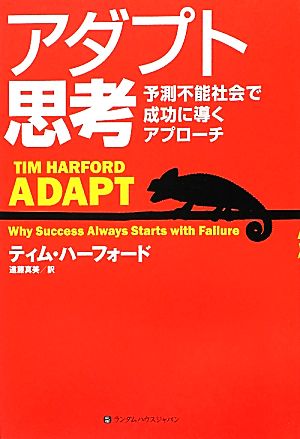アダプト思考 の商品レビュー
複雑な現代においては、トップダウンではなく、ボトムアップで思考錯誤しながら臨機応変に対応する思考の方が良いということを論じ、そのための進化のプロセスを示していく本。
Posted by
パルチンスキーの対処法は、3つの基本原則にまとめることができる。第一に、新しいアイデアを追求し、新しいことに挑戦する(変異)。第二に、新しいことに挑戦するときには、失敗しても大きな問題にならない規模でする(生存能力)。第三に、フィードバックを受けられるようにし、失敗から学びながら...
パルチンスキーの対処法は、3つの基本原則にまとめることができる。第一に、新しいアイデアを追求し、新しいことに挑戦する(変異)。第二に、新しいことに挑戦するときには、失敗しても大きな問題にならない規模でする(生存能力)。第三に、フィードバックを受けられるようにし、失敗から学びながら進む(選択)。 ソ連は、問題に対して多種多様なアプローチをとることを容認できず、何がうまくいって、何がうまくいっていないかを判断することもできなかった。ソ連のシステムには、変異と選択を生み出すことができず、適応能力がないという欠陥があった。中央の計画者には、現場の混沌とした複雑性は抜け落ちており、成功か失敗かのフィードバックが抑え込まれていた。 変異を阻む壁として、誇大性と一貫性へのこだわりがある。政治家や企業のトップは、自分が有能なリーダーであることを示すために大きなプロジェクトを好むが、失敗しても大きな問題にならない規模で行う原則に反する。商品もサービスも標準化すれば、すっきりして公平に思えるが、問題が解決されていないときや、問題が変化し続けている時には、様々なアプローチを試すことが最善の策になる。 化石燃料生産国の政府が、採掘・抽出された化石燃料に含まれる炭素1トン当たり約50ドル、二酸化炭素1トン当たり14ドル程度の税金を掛ければ、炭素税が市場価格に組み込まれる。ガソリン価格は1ガロン(4リットル)あたり12セント値上がりする。市場価格システムは巨大なアナログ式クラウド・コンピューターとして働く。 <考察> 変異を阻む壁としてあげられている誇大性と一貫性へのこだわりは、日本では耳の痛い指摘に思える。日本人は強いリーダーシップを好む傾向があるし、公平性に対する志向が強い。地方分権は進まないし、独自性は抑えられることが多い。画一的だと選択の力が働かないから、発展が望めない。多様性を許容し促す気風がないことが、日本が停滞している理由のひとつだろう。
Posted by
【要約】 ・生物(グッピーの例)のように、状況の変化に対応、アダプトしていく。 ただし、今の社会は複雑で密結合になっており、失敗の連鎖がドミノのように巨体で制御不可能なものになることもある。 よって、セーフクッションをはさみ、結合度合いをゆるめて複雑さを減らし、影響が限定的な...
【要約】 ・生物(グッピーの例)のように、状況の変化に対応、アダプトしていく。 ただし、今の社会は複雑で密結合になっており、失敗の連鎖がドミノのように巨体で制御不可能なものになることもある。 よって、セーフクッションをはさみ、結合度合いをゆるめて複雑さを減らし、影響が限定的な状態で失敗を繰り返していくのがよい。 【ノート】 ・何か当たり前のことしか言ってないような気もする。色々な実例は確かに示唆的ではあるが、それで?という感じ。ただし、成毛さんのブログを読むとちゃんと解説されてるので、これは自分との相性の問題か。 ・どうも経済畑の本はこれまでに面白く読めたことがなくて、ボヤッとしており、イマイチ相性がよくない。これはひとえに自分の不勉強に起因するのだと思うけど。 ・ちなみに「アダプト」と言われて思い浮かぶのは映画版スター・トレックの「ファースト・コンタクト」。エンタープライズ号の中で攻撃されたボーグが、その攻撃を学習して無効化した時にウォーフが「They adapted !」と叫ぶシーン。ボーグはアダプトしながら成長してきたんだな。ボーグやターミネーターの原型と言ってよいであろうF.セーバーヘーゲンの「バーサーカー」もそういうコンセプト。
Posted by
会社の執行役員が薦めていたので読んでみたが、なるほど、良い本である。 本書の主題である「アダプト思考」とは、実験的、試行錯誤的アプローチにより複雑な組織、システムを改善する方法である(という意味では、目指すところは、システム思考と同じであるが、アプローチはかなり違う)。つまり、...
会社の執行役員が薦めていたので読んでみたが、なるほど、良い本である。 本書の主題である「アダプト思考」とは、実験的、試行錯誤的アプローチにより複雑な組織、システムを改善する方法である(という意味では、目指すところは、システム思考と同じであるが、アプローチはかなり違う)。つまり、1.改善方法と、その効果の測定方法を考える。2.失敗しても、クリティカルなミスにならない程度範囲で1を試す。3.評価し、ダメなら1に戻る。うまくいけば、もっと大きい範囲で試す。というアプローチである。こういう書き方をすると非常に効率の悪いやり方に思えるが、決定論的に解決できない複雑なシステムに対しては、確かに有効な方法である。また、遅巧よりも拙速をモットーにするトヨタ改善方式や、最近主流のソフト開発スタイルであるアジャイルにも通じているメソッドである。
Posted by
認知的不協和に屈せず、失敗を認めて学び、修正(アダプト)せよ。詳細設計のトップダウンより、試行錯誤のボトムアップ。主旨はシンプル、事例が膨大。
Posted by
適応する。組織はどう学ぶ・現場。変異、選択、成功のルール・競争条件、デカップリング・疎結合。 新しいことに挑戦する、失敗しても命取りにならないように、失敗を認める・学ぶ。
Posted by
「強い者が生き残ったわけではない。賢い者が生き残ったわけでもない。変化に対応した者が生き残ったのだ。」この有名な一説は実は「種の起原」の中には見つからず出典が明らかでない。しかしアダプト思考というややわかりにくいタイトルの本を紹介するにはこの言葉から入るのが適当だろう。 adap...
「強い者が生き残ったわけではない。賢い者が生き残ったわけでもない。変化に対応した者が生き残ったのだ。」この有名な一説は実は「種の起原」の中には見つからず出典が明らかでない。しかしアダプト思考というややわかりにくいタイトルの本を紹介するにはこの言葉から入るのが適当だろう。 adaptを直訳すると「状況に合わせて変化する、適応する」とある。ちなみにadoptだと「養子にする」で題名見た瞬間にはいろんな考え方をパクれということかいなと思ってしまった。いやはや。 フィリップ・テトロックという心理学者が1984年から20年に渡って専門家の予測の限界について調べたところ、大学生よりは精度が高いが将来の予測には役立たずで、知名度の高い専門家ほど無能だというものだった。また1983年に「エクセレント・カンパニー」で紹介された43社の内2年後には14社が深刻な経営難に陥っていた。では若いダイナミックな業界の企業はどうか?倒産率はさらに高くなる。 経済学者のオームロッドが種の絶滅の記録と企業の絶滅とを比較したところいずれも絶滅の規模が2倍になると頻度は1/4になる同じ関係であることが証明された。さらに生物学の進化の数理モデルをあてはめ一部の企業を優れた計画者になれるようにした。しかし結果としては企業の存亡のパターンは計画は不可能というモデルにあたってしまうこの2つの研究から専門家は当てにならず、現代経済では優れた計画をたてるのはほとんど不可能ということが示唆されている。そこで、生き残るための手段が本書で提唱されている。それがアダプト=試行錯誤して適応することだ。 本書ではシビアな状況での試行錯誤の成功例、失敗例を紹介し基本となる3つのステップ「失敗を恐れずに新しいことを試す」、「失敗しても大きな問題にならないようにする」、「失敗したときにわかるようにする」を学ぶ。 イラク戦争はなぜ泥沼化したのか、軍の上層部の判断ミスよりもミスから学ぼうとせず適応することを拒否したのが決定的だ。一方最前線ではアルカイダの報復を恐れる市民は米軍に非協力的であったが地元の有力者と会話を重ね、治安の維持に努めた結果住民が米軍を信頼し始めた。これを進めたマクマスター大佐は上司を公然と無視しキャリアを棒に振っている。理想的な組織の原則にも軍での処世術にも反しているがイラクの状況には適合した。 予想もしない成功はどうやって生み出せば良いのだろう。マリオ・カペッキはアメリカ国立衛生研究所に3件の研究プロジェクトを申請したがうち1件はマウスのDNAの特定の遺伝子を変化させるというかなりハイリスクなものであった。カペッキは忠告を無視して予算をこの第3のプロジェクトにつぎ込みノーベル賞を受賞した。 確実なプロジェクトを推進するだけではなかなか大きなイノベーションは生まれない。確実で小さなステップと大きなジャンプの組み合わせが適応の戦略である。ただし一か八かになる前にうまく失敗するのがこつだ。
Posted by
複雑で急速に変化する世界において、確実な未来を予測することが困難になっている中、どのような方法で生き延びるかについて書かれた本。著者は、生物進化のプロセスである「アダプト(適応)」がカギだと指摘する。望ましい方向性が分からないのであれば、考えられる限りの実験をして、成功したものだ...
複雑で急速に変化する世界において、確実な未来を予測することが困難になっている中、どのような方法で生き延びるかについて書かれた本。著者は、生物進化のプロセスである「アダプト(適応)」がカギだと指摘する。望ましい方向性が分からないのであれば、考えられる限りの実験をして、成功したものだけを選べばよいということであるが、それでは失敗した個体はただの人柱になってしまうのか?この問いに対して、著者は「失敗しても大きな問題にならないようにする」「失敗が失敗であることを分かるようにする」ことで、失敗が個体にとっての致命傷にならないと説く。なんだか分かったようで分からない感じの本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アダプト思考(適応する能力)、むしろ積極的な適応能力を指す。 ここで覚えた単語、アダプト思考・ポピュリズム(大衆の意見を取り入れエリート層との対決を行う、大衆迎合主義)
Posted by
レビューはブログにて http://ameblo.jp/w92-3/entry-11317060220.html
Posted by
- 1