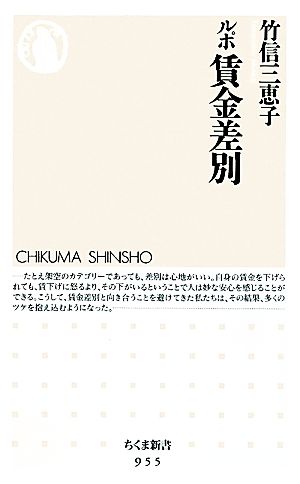ルポ 賃金差別 の商品レビュー
パート労働は、所詮夫の収入がある女性たちの仕事、生活費がいらない女性たちの小遣い稼ぎ。こういった位置づけが、非正規の低処遇に対する社会的抵抗を阻んできた。女性の家計補助だからと、仕事の内容を問うことなく容認されてきた非正規は、いまや、男性たちにまで広がっている。また、シングルマザ...
パート労働は、所詮夫の収入がある女性たちの仕事、生活費がいらない女性たちの小遣い稼ぎ。こういった位置づけが、非正規の低処遇に対する社会的抵抗を阻んできた。女性の家計補助だからと、仕事の内容を問うことなく容認されてきた非正規は、いまや、男性たちにまで広がっている。また、シングルマザーも男性ではない、新卒ではないというだけで低賃金で不安定な働き方を余儀なくされている。非正規は理不尽に特定のカテゴリーへ押し込められ、低賃金でも当然だというレッテルを貼られ、働く意欲や気力を奪われている。安くても当然の人たちを作ることにより企業は人件費を抑え、労組の組織率を下げ賃金交渉力を弱体化させた。正社員は正社員で、あの人たちよりもましだからと賃金抑制にも怒らない羊と成り果てた。高齢者の低賃金再雇用は労働ダンピングを加速させている。著者は警鐘を鳴らす。この状況を放置しておれば、必ずそのツケがまわってくる時が来ると。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
[ 内容 ] 同じ職場で同じ働き方をしていても、賃金に差が生じるのはなぜなのか? 労働者の三人に一人が非正規雇用となり、受け取る生涯賃金にも大きな格差が生まれている。 本書はアルバイト・パート・嘱託・派遣社員・契約社員など「働く人の賃金」に焦点を当て、現代日本の労働問題を考察する。 賃金というものさしから、いま働く現場で何が起きているのかを読み解き、現代日本の「身分制」を明らかにする、衝撃のノンフィクション。 [ 目次 ] 第1章 賃金差別がつれてきた世界 第2章 かけ替えられた看板 第3章 「能力」と「成果」の罠 第4章 労働と「ボランティア」の狭間で 第5章 「派遣」という名の排除 第6章 最悪の賃下げ装置 [ 問題提起 ] [ 結論 ] [ コメント ] [ 読了した日 ]
Posted by
日本社会は、同じ仕事でも、出身地・性別・採用形態・雇用形態と様々な線引きによって自在に賃金に差をつけられる賃金差別大国である。 同一価値労働同一賃金はよく聞く言葉だけれど、その意味の重要性を改めて認識しました。
Posted by
一章 2011年、元京都大学図書館の雇用職員らによる「くびくびカフェ」が閉鎖された。運営者の一人である井上昌哉さんは、就活に苦しみ、内定後も苦労している同級生の姿を見るうちに正社員としての生き方に疑問を抱き、非正規職員としての生き方を選択した。そこへ上司からの雇用形態差別ともとれ...
一章 2011年、元京都大学図書館の雇用職員らによる「くびくびカフェ」が閉鎖された。運営者の一人である井上昌哉さんは、就活に苦しみ、内定後も苦労している同級生の姿を見るうちに正社員としての生き方に疑問を抱き、非正規職員としての生き方を選択した。そこへ上司からの雇用形態差別ともとれる言動、突然の整理解雇通告という、「人を人として扱わない対応」に怒り、ユニオンを結成した。裁判にまで進展したが、「彼らの労働はあくまで家計補助的労働」と位置づけられ、裁判長(京大卒)からは「なんで京大を出た人間がそんな仕事を選択したのか理解出来ない」という趣旨の説諭を受けた。 自分用キーワード すかいらーくの過労死問題(店長という立場と、残業月200時間にも関わらず、契約社員のため同じ勤務年数の社員の八割しか給料を貰えていなかった) 釜田慧『自動車絶望工場』 公契約条例 職務評価(異なる仕事を比較するために行う)
Posted by
図書館で借りた。 就業の形態が正規か非正規かというのは、もはや身分制度として機能しており、職務内容とほぼ無関係に賃金が大幅に異なる状況を生み出している。ただ差がある格差ではなく、不合理なレッテルによる差別であると主張している。 短時間職員が京大を訴えた2011年の事例、女性職...
図書館で借りた。 就業の形態が正規か非正規かというのは、もはや身分制度として機能しており、職務内容とほぼ無関係に賃金が大幅に異なる状況を生み出している。ただ差がある格差ではなく、不合理なレッテルによる差別であると主張している。 短時間職員が京大を訴えた2011年の事例、女性職員の差別を訴えた兼松訴訟など、ルポだけに色々な人の体験が読めて現在の非正規を取り巻く状況が実感できる。 判決では原告の訴えを理解している部分があるけれど、なぜか敗訴していたり、裁判というものが分からなくなる。 読んでいて不思議なことは、過去につくられた「妻つき男性モデル」のような考え方に企業が縛られていて、そこに当てはまらない人たちが安く使われていることだった。 なぜ、妙なモデルをつくって給与を決めたのか、もう実体が崩れている考え方を変えようと思わないのか、仕事なのだから本書でも紹介されているような職務評価を行い仕事外の条件を持ち込まない評価をすべきではないか、と疑問がわいてくる。 職務評価は介護の事例が載っていたので参考になる。これだけ派遣や委託が一般化しているのだから公契約条例ももっと知られるべきものだと思う。
Posted by
何と言うか、この本の内容を考えると、どうして日本という国が今現在成立しえているのかよくわからない。 「正社員」か「非正社員」かという違いだけで、給与を始めとした各待遇で大きな差ができてしまうのはやはり差別と言っても差し支えない。 それらの間に、異なる仕事が割り当てられているのな...
何と言うか、この本の内容を考えると、どうして日本という国が今現在成立しえているのかよくわからない。 「正社員」か「非正社員」かという違いだけで、給与を始めとした各待遇で大きな差ができてしまうのはやはり差別と言っても差し支えない。 それらの間に、異なる仕事が割り当てられているのならまだしも、正社員と非正社員という雇用形態以上に、違いがあるとは言えない仕事を両者は抱えている。 それにもかかわらず、客観的な職務評価が成立していないため、恣意的な評価が賃金への直接的な評価となる。 また、この雇用形態の中には、女性蔑視ともいえる価値観が存在していることも忘れてはならない。 本書では、非正規雇用を女性がメインの働き手である「家計の補助的労働」と位置づけてきた結果、日本が労働環境、社会情勢の変化に全く対応できていない現状が浮かび上がる。 そこには、女性は「夫に養ってもらうもの」=経済的な自立水準まで賃金を上げなくても構わないという意図がある。 しかし、非正規雇用を「家計の補助的労働」としてしまったことで、彼らの賃金を基準にし、正社員の賃金抑制に転化するという働きも強まっている。 これらが最終的に行き着くところは、最低賃金すれすれの給与と、人間らしい生活を損なった働き方である。 最低賃金すれすれでは貯金も出来ず、いざというときに使えるお金もない。 貯金ができないのにもかかわらず、有期雇用だからという理由で年金などの支払いもできていないため老後の生活の見通しが立たない。 これから先、社会に出ていくにあたって是非一読しておいて欲しい本。 自分たちが置かれている、また、置かれるであろう社会の労働環境がどのような実態であるのか、考えさせられる一冊。
Posted by
女性であるとか、パート社員であるとか、採用区分が違うとか色んな「違い」を理由に、同じ労働をしていても差別がまかり通っている日本の労働市場の現状を書いたルポ作品。どの研究大会に出てもほぼ確実に雇用問題が議題に上がるような仕事をしてる身としては、とても興味ある内容でした。 この本を読...
女性であるとか、パート社員であるとか、採用区分が違うとか色んな「違い」を理由に、同じ労働をしていても差別がまかり通っている日本の労働市場の現状を書いたルポ作品。どの研究大会に出てもほぼ確実に雇用問題が議題に上がるような仕事をしてる身としては、とても興味ある内容でした。 この本を読んで思い出したことが二つ。一つは内田樹のブログ記事「大学統廃合について(http://blog.tatsuru.com/2012/06/25_1136.php) 経済界や政治家は「大学が増えすぎたから大学生がバカになった。なので大学を減らせ」と言うが、その裏には「大学が減って低学歴の労働者層が増えれば、国内で安く使える労働力が生まれてラッキー」という思いがあるのではないかという指摘。すごいな、資本主義社会(苦笑) もう一つは「女性の育休25%がノー 企業『取らずに退職を』」という調査結果。(http://www.47news.jp/CN/201206/CN2012062901001127.html) 差別はこのための布石なんじゃなかろうかと思う。
Posted by
正規労働者、非正規労働者の賃金の格差問題について。 欧米のように「同一価値労働、同一賃金の原則」がしっかりしておらず、曖昧な為に非正規労働者は正社員と同じ労働時間、労働内容であってももらっている賃金は約半分。 そのような低賃金労働者が年々増え続ける現実。 しかし派遣だから、パー...
正規労働者、非正規労働者の賃金の格差問題について。 欧米のように「同一価値労働、同一賃金の原則」がしっかりしておらず、曖昧な為に非正規労働者は正社員と同じ労働時間、労働内容であってももらっている賃金は約半分。 そのような低賃金労働者が年々増え続ける現実。 しかし派遣だから、パートだからとその低賃金を容認してしまう日本の社会の問題。 雇用の問題についてかなり興味がわいた一冊でした。 一度読んでみた方が良い。
Posted by
前から気になっていて、図書館にあったので借りてきた。 あと、働く若者論的なものに興味が出始めたので、目についたものをちまちま読んでいる→雇用問題について興味持つ→賃金問題について興味持つの流れでますますいろんな問題があることがわかってわけわからん状態に。 賃金に不満を持つ人たち...
前から気になっていて、図書館にあったので借りてきた。 あと、働く若者論的なものに興味が出始めたので、目についたものをちまちま読んでいる→雇用問題について興味持つ→賃金問題について興味持つの流れでますますいろんな問題があることがわかってわけわからん状態に。 賃金に不満を持つ人たちのおこした判例集みたいなかんじだった。 労組の仕組みとかやっぱ知ってるのと知らないのとでは大違いだなっておもった。
Posted by
日本の労働環境は、もはや、マスコミや評論家達がこぞって使う、賃金格差なんていう生易しい言葉では済まされない。著者が言うように、現代の労働環境はまさに「差別」であり、「身分制度」そのものと言っても大げさではない。この大きな社会問題に対して、この国の立法府は、まったく手を付ける気もな...
日本の労働環境は、もはや、マスコミや評論家達がこぞって使う、賃金格差なんていう生易しい言葉では済まされない。著者が言うように、現代の労働環境はまさに「差別」であり、「身分制度」そのものと言っても大げさではない。この大きな社会問題に対して、この国の立法府は、まったく手を付ける気もなければ、ましてや法を整備して改善する気はさらさらないようだ。このような事を放置すると、今に世界の先進国の中で、唯一、日本だけが、労働環境に関しては、国際的な人権問題に発展し各国から批判される状況に陥ってしまう可能性は否定できない。先進国、特にヨーロッパでは、同一労働、同一賃金が常識になりつつある現在、この問題を放置したままでは、未だ続く不況(デフレ経済)から永遠に脱することが出来ず、やがて、第3のうねりとも言える未来の新秩序(資本主義にかわるもの)から取り残され、「失われた30年」いや、もしかすると「失われた40年」と世界中の人々から揶揄されてしまう事だけは確かである、と…、私は強く感じるのである。
Posted by
- 1
- 2