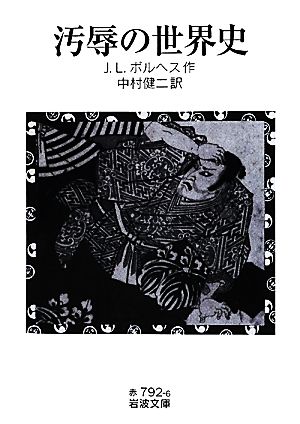汚辱の世界史 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ボルヘスのことが知りたくて読んでみた。 著名原話や史実を改変した変奏曲としての物語集。 アンチヒーローを扱っているが「汚辱」というほどのことはない。我らが吉良上野介の一編も登場する。 若い頃の初期作品ということで、ボルヘスの魔法の片鱗が見える。読んでいるうちにくるりと語り手が入れ替わるような感覚。 私としては著名原話や史実に関する知識が少ないため、かなり愉しみが減ったように思う。知識に溢れかえるボルヘスは嬉々としてパロディを書いたんだろうと想像する。
Posted by
悪党列伝、と思って読むと違和感があった。「悪党」と言い切りがたい登場人物もいるからだ。 ボルヘス自身の1954年版の序には、大乗仏教を引き合いに出して自分の作品を空無と例えており、さらに『表題の「汚辱」とは仰々しい言葉であるが、その響きと怒りの背後にはなんの意味もない。この本は見...
悪党列伝、と思って読むと違和感があった。「悪党」と言い切りがたい登場人物もいるからだ。 ボルヘス自身の1954年版の序には、大乗仏教を引き合いに出して自分の作品を空無と例えており、さらに『表題の「汚辱」とは仰々しい言葉であるが、その響きと怒りの背後にはなんの意味もない。この本は見せかけ以上のものではなく、かつ浮かびかつ消えていくイメージの連続以上のものではない。』とある。 ある人物についての描写といえば、普通よくありがちなのは、事実を時系列に事細かに描いたものが多いが、ボルヘスの作品ではそういった即物的な感じがない。具体的な人間についての話なのに、まさにイメージ、といった印象である。 これほどの恐ろしい人生でさえも、「イメージ」という抽象的な捉え方を余儀なくされると、どんな人間の一生も所詮は虚なのである、という感覚になっていく。 ボルヘスを読んでいると、暗くはないが、冷静だが同時に温かみもある不思議な客観的な虚無感に浸れる。
Posted by
ボルヘスの最初の短篇集、1935年。表題作は古今東西の7人の悪党=アンチ・ヒーローにまつわる物語。後半の「エトセトラ」は『怪奇譚集』『夢の本』にも通じる不可思議な掌編。 □ ボルヘスの書くものには、自己同一性の無化という主題がしばしば見られる。自己同一性を担保するはずの顔/名...
ボルヘスの最初の短篇集、1935年。表題作は古今東西の7人の悪党=アンチ・ヒーローにまつわる物語。後半の「エトセトラ」は『怪奇譚集』『夢の本』にも通じる不可思議な掌編。 □ ボルヘスの書くものには、自己同一性の無化という主題がしばしば見られる。自己同一性を担保するはずの顔/名前/起源がひとつに定まらずにずれていく。仮面による顔の隠蔽、偽名変名による宛先の逸失、迷宮による現在地の不定、鏡による原本の複製。以下の記述は、ボルヘス自身の世界観にも通じるのではないかと思う。 「我々の住む世界はひとつの過失、不様なパロディである。鏡と父親はパロディを増殖し、肯定するがゆえに忌むべきものである」(「メルヴのハキム」) さらに、ボルヘスの文学観としては、個々の「作者」というものですら不在であるかもしれない。その都度の読書行為がその都度の作品に上書きされそれをずらしていく。その運動の中で、「作者」だとか「原作」だとかいう観念は解消されてしまうのかもしれない。その運動の無限遠において、「読者」と「作品」の区別も解消されていく。それらみな、非時間的で超人間的な《永遠客体》に解消されていく。これは、ボルヘスが描こうとしている自己同一性の無化という事態と並行的ではないかと思う。世界も自我も作品も、その本源だとか同一性だとかという観念は、ただの幻像であると。 「自らの作品を書く勇気はなく、他人の書いたものを偽り歪めることで(時には正当な美的根拠もないまま)自分を愉しませていた臆病な若者――作品はすべてこの若者の無責任な一人遊びである」(「一九五四年版 序」) 「書物に署名するのはおかしなこと。剽窃の観念は存在しない。すなわち、あらゆる作品が非時間で無名の唯一の作者の作品であることが定められた」(「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」) □ 「学問の厳密さについて」が印象的だった。どのような寓意を読み取ろうか。 □ 「この本は見せかけ以上のものではなく、かつ浮かびかつ消えていくイメージの連続以上のものではない。まさにその理由で、それは楽しい読みものであるだろう」
Posted by
大人のための夜のロウソクの明かりの中で語られるような作品集。 人称も語り口もさまざまで、あざやか。 それぞれのアンチヒーローは劇的にも描けただろうに、なんともいえない等身大感。というか、あれ?という小ささだ。 それがかえってリアリティ、存在感を産んでいる。 メルヴのハキムがお...
大人のための夜のロウソクの明かりの中で語られるような作品集。 人称も語り口もさまざまで、あざやか。 それぞれのアンチヒーローは劇的にも描けただろうに、なんともいえない等身大感。というか、あれ?という小ささだ。 それがかえってリアリティ、存在感を産んでいる。 メルヴのハキムがお気に入り。
Posted by
ヤダーン、ウォモシローイ。学生の頃、授業のうまい先生がいると、教科は関係なくワックワックしながら授業を受けたものだが、それよ! 既にある伝記ものから、ボルっちがセレクトし編集。結構変化球つけてるらしいわ。 すっごいすまして真面目にインタビューとか受けながら、実は今すかしっぺし...
ヤダーン、ウォモシローイ。学生の頃、授業のうまい先生がいると、教科は関係なくワックワックしながら授業を受けたものだが、それよ! 既にある伝記ものから、ボルっちがセレクトし編集。結構変化球つけてるらしいわ。 すっごいすまして真面目にインタビューとか受けながら、実は今すかしっぺしてるし! みたいなねー、こういうの、好きだわあー。 積極的にボルヘス読んで来てなかったけど、これからはちゃんと読むわあー。
Posted by
【由来】 ・図書館でたまたま目についた 【期待したもの】 ・ 【要約】 ・ 【ノート】 ・吉良上野介だけ読んでみた。短編集で面白そう。 【目次】
Posted by
悪党列伝。吉良上野介の章が読みたくて。 どういう意図なのかわからないので間違い?を指摘するのは無意味かも。でもおもしろいので。 くつ紐を結ばされて屈辱とか、赤穂城で切腹とか。それも緋毛氈の上で…目出度い感じ?その上、大石間に合ってる⁈このときの腹切り刃物は、宝石を散りばめた短刀⁈...
悪党列伝。吉良上野介の章が読みたくて。 どういう意図なのかわからないので間違い?を指摘するのは無意味かも。でもおもしろいので。 くつ紐を結ばされて屈辱とか、赤穂城で切腹とか。それも緋毛氈の上で…目出度い感じ?その上、大石間に合ってる⁈このときの腹切り刃物は、宝石を散りばめた短刀⁈キラびやか! 吉良暗殺の密談は鏡をはめ込んだ四角い箱のある社殿。この辺、ボルヘスっぽい? 討ち入りで大石側9人死亡。息子、主税も死亡⁈吉良の隠れていた場所は銅鏡の裏。鏡、好きなんだね。 でもこれ、悪党吉良というより大石内蔵助が主人公でした。
Posted by
実在した世界の悪党や無法者を題材にした短編集。ギャング、詐欺師、女海賊など知らない人物ばかりで新鮮だった。日本人では吉良上野介が取り上げられている。アンチヒーローの人生はヒーローの人生と同様に、平凡ではありえず物語となる。エトセトラの中の「学問の厳密さについて」は、10行足らずの...
実在した世界の悪党や無法者を題材にした短編集。ギャング、詐欺師、女海賊など知らない人物ばかりで新鮮だった。日本人では吉良上野介が取り上げられている。アンチヒーローの人生はヒーローの人生と同様に、平凡ではありえず物語となる。エトセトラの中の「学問の厳密さについて」は、10行足らずの短い作品なのに印象に残った。
Posted by
世界悪人列伝といった趣きの掌編小説集。7人の人物の物語を扱うが、手法はそれぞれに少しずつ異なっている。これを読む契機になったのは、表紙にもなっている「不作法な式部官 吉良上野介」がどんなふうに描かれているかに興味を魅かれて。赤穂事件の全体像はともかく、細部では史実とも、また「忠臣...
世界悪人列伝といった趣きの掌編小説集。7人の人物の物語を扱うが、手法はそれぞれに少しずつ異なっている。これを読む契機になったのは、表紙にもなっている「不作法な式部官 吉良上野介」がどんなふうに描かれているかに興味を魅かれて。赤穂事件の全体像はともかく、細部では史実とも、また「忠臣蔵」ともあれこれと違っている。この事件はオランダ商館長ゴロウトによってヨーロッパに伝えられ、1871年の英語版をはじめ、ドイツ語やフランス語での出版もあった。内容は未見なのだが、おそらくボルヘスはこれらのいずれかによったのだろう。
Posted by
『ブロディーの報告書』の訳者鼓直氏によれば、本書におさめられた短編集は中途半端な出来らしい。 私的には『ブロディー〜』の短編より、こちらにおさめられた超短編のほうが、摩訶不思議で寓話的面白世界に満ちていて好み。 邦訳『汚辱の世界史』における目玉は、何といっても吉良上野介——傲慢...
『ブロディーの報告書』の訳者鼓直氏によれば、本書におさめられた短編集は中途半端な出来らしい。 私的には『ブロディー〜』の短編より、こちらにおさめられた超短編のほうが、摩訶不思議で寓話的面白世界に満ちていて好み。 邦訳『汚辱の世界史』における目玉は、何といっても吉良上野介——傲慢な式部官長だろう。 あのボルヘスが、日本人の大好きな(私は特に好きじゃないけど)『忠臣蔵』を取り上げているとなれば興味もひとしお、どうして手に取らずにいられようぞ(笑) 想像すら難しい遠い異国のいにしえの物語。武士たちの主君への忠義と悪玉への復讐劇——アルゼンチンが生んだ世界的文学者の目にはどう映っていたのか、考えるだけでも面白過ぎるじゃないか(笑) ボルヘスの“東洋”は中東中心だとそれまで思っていたので、吉良上野介もそうだが、中国の女海賊鄭一嫂の話も(もとネタは知らないが中国では著名なキャラなんだろう)興味深く読んだ。 取り上げられているそのほかの人物も、ビリー・ザ・キッド以外未知なので、もとの話を知っていればもっと楽しめただろうと思う。 そんななかで特に印象に残ったのは『メルヴのハキム』。 ボルヘス作品からもとネタを追究するのもまた楽し。
Posted by
- 1
- 2