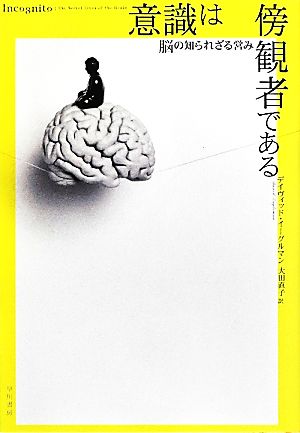意識は傍観者である の商品レビュー
「僕の頭の中に誰かがいる、でもそれは僕じゃない」とのピンクフロイドの曲「ブレインダメージ」の一節を第一章のタイトルに始まる本書、そこでは、科学の発展は従来からタブーを切り崩して新しい知見を得る、そのようにして私たちの脳には自分で意識できない無意識があることが発見されたとある。 そ...
「僕の頭の中に誰かがいる、でもそれは僕じゃない」とのピンクフロイドの曲「ブレインダメージ」の一節を第一章のタイトルに始まる本書、そこでは、科学の発展は従来からタブーを切り崩して新しい知見を得る、そのようにして私たちの脳には自分で意識できない無意識があることが発見されたとある。 そして、私たちの脳は、見ている現実を正しく認識していない反面、説明できないことでも認識可能であり、体を動かすことができる。脳の初期設定は遺伝子で行われており、脳内では差別主義と博愛主義など様々な考えが混在していると説き、人間は本当に自分自身を自分の意思でコントロールしているのかと症例などを引き合いに出し、犯罪者は本当に自分の意思で犯罪を起したのかと疑問を呈する。 終章では人間の意識は遺伝子と化学物質などを含む様々な環境で決定されると説くも、ある遺伝子を持っているともっていない人の10倍殺人犯が多いとの話に遺伝子で全てが決まるわけではないと認識、ある遺伝子とはY染色体と呼ばれ、それを持っているのは「男」と呼ばれるそうです(笑)。 最近読んだ脳化学系の本は自分の意思ではなく後付で自分の意思で行ったと記憶するとの立場をとったものが多い、本書も直接そのようには断言していないものの、結果的に後付けと解釈できるような論調となっている。もっともこのテーマではっきりと結論ずける研究者は今のところいません。
Posted by
いやー面白かった。脳に関する本を読むと必ず出てくるのが「自由意志」。果たして人間の行動には意志はあるのだろうか。そして犯罪を起こした人の行動というのは果たして本当に「自分」なのか。脳関連の本はよく読むがこの本は題材の取り上げ方が非常に面白い。内容的には小説や映画にしたら面白くなり...
いやー面白かった。脳に関する本を読むと必ず出てくるのが「自由意志」。果たして人間の行動には意志はあるのだろうか。そして犯罪を起こした人の行動というのは果たして本当に「自分」なのか。脳関連の本はよく読むがこの本は題材の取り上げ方が非常に面白い。内容的には小説や映画にしたら面白くなりそうなネタがいっぱいです。お勧めです。
Posted by
イーグルマン『意識は傍観者である』(早川書房、2012)を読む。 近年の脳科学の発展は著しく、これまでの常識がくつがえったり根拠なく経験則で語られていた事柄が理論付けられたりしています。 十余年前に教育を受けた身では、脳はシナプスで繋がった電気信号インターフェイスだ、という説...
イーグルマン『意識は傍観者である』(早川書房、2012)を読む。 近年の脳科学の発展は著しく、これまでの常識がくつがえったり根拠なく経験則で語られていた事柄が理論付けられたりしています。 十余年前に教育を受けた身では、脳はシナプスで繋がった電気信号インターフェイスだ、という説明でしたが、実は、これに加えて脳内物質による化学インターフェイスとしての動きもしておるとか。 たとえば世にいう「虫の知らせ」は無意識下で脳が作動しており、「意識」はあとで結果だけを知らされるCEO的な立場(傍観者)である、などの興味深い指摘。 あるいは、意識が行動を命じてから筋肉が動いて活動に至るのではなく、反射的に筋肉が動くと同時に、そこへの意味づけとして「運動を命じた」と知覚されるなど、障害の例、知覚、多くのケースに基づいて興味深い論及がなされています。 ヒトを客体として見る、という点で脳科学や進化心理学は実に興味深い分野です。テレビの通俗健康番組で、娘が父の体臭を嫌うのは進化史的に説明がつく、などの話が伝えられますが、これも最近の研究成果だそうで。 【本文より】 ◯生まれつき目が見えない人にも同じことが言える。彼らは何も失っていない。視界がなくなっている場所に暗闇を見ているのではない。視界はそもそも彼らの現実のパーツにはないのだ。ブラッドハウンド犬が感じる余分なにおいや、四種類の色覚受容体を持つ女性が感じる余分な色をわあなたが感じられないのと同じにすぎない。 ◯進化は入念にあなたの目、内臓、生殖器などを形づくってきた。ーそしてあなたの思考や信念の特性も。私たちは細菌に対抗する特異的な免疫防御を進化させただけではない。人類の進化史の99パーセントにわたって、狩猟採集民族だった祖先が直面した特殊な問題を解決するための神経機構も発達させてきた。「進化心理学」の分野は、なぜ私たちは、こういう考え方をして、ああいう考え方をしないのか、その理由を探る。 ◯最近、私の女だちの一人が月経による情緒変化で落ち込んでいた。彼女は青ざめた笑顔でこう言った。「あたしね、毎月二、三日は自分でなくなるの」。神経科学者の彼女はそのあとしばし考えて、こうつけ加えた。「それともひょっとすると、こっちが本当のあたしで、残りの二十七日間は実は他の誰かなのかも」。私たちは笑った。彼女はいかなるときも自分というものは体内の化学物質の総量で決まると考えて、臆するところがなかった。私たちが〈彼女〉だと思っているものは、時間平均バージョンのようなものであることを理解していたのだ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
唯物論の立場から意識を語る本。「このマシンに幽霊が入り込む余地はない(223p)」というように、かなり強力な議論展開。 著者は自由意志というものを認めておらず、我々の脳では常に雑多なアイデアが生成されており、自由意志だと思われているものも偶々選ばれたアイデアに後付の理由をつけているのにすぎないという。意識は端役にすぎず、雑多なアイデアが正反対の内容であった場合など、対立するシステムを仲裁する時に表に出てくるのみである。 動物に意識があるかどうか、も著者の立場からすると、こうした対立するシステムを統合できるかどうかで決めれば良い。たとえば、セグロカモメの巣の中に赤い卵を入れるとかもめは暴れだす。赤い色は鳥の中の攻撃性を刺激するが、卵の形は孵化行動を誘発する。その結果、カモメは卵を攻撃しようとすると同時に抱こうとする。このように対立するシステムを統合できない動物に意識はない。 自由意志がないとすると、犯罪行為はその有責性を問われるのか?反社会性は全ての人の中にあり、障害によって「脱抑制」が起こった結果が犯罪行為である。その「障害」が脳腫瘍であればその人は「非難に値されない」が、性格や薬物中毒の場合は「非難に値する」というのが現在の考え方。しかし、「障害」の検出力は科学の進歩とともに上がっており、将来的には技術の進歩によってより微細な「障害」も検出され得る。このように、技術の限界によって有責性が決まるという法制度はおかしい。犯罪行為そのものは脳の障害によって起こるのであり、判断すべきはそれが繰り返されるかどうかで、有責性を「問う」のは間違っている
Posted by
デカルトの「我思う故に我あり」の名言は残されているものの、現代脳科学上、「自分という意識」は脳機能の処理結果であって、それ自体で存在しているわけではない。意識や自由意志は脳のプロセスの、ただの傍観者なのである。 前半部は上記の説明、後半はそこからさらに踏み込んで、現在の法制度の話...
デカルトの「我思う故に我あり」の名言は残されているものの、現代脳科学上、「自分という意識」は脳機能の処理結果であって、それ自体で存在しているわけではない。意識や自由意志は脳のプロセスの、ただの傍観者なのである。 前半部は上記の説明、後半はそこからさらに踏み込んで、現在の法制度の話に発展する。人に自由意思がなければ、そしたら自由意思によって人は犯罪を犯すという法制度の大前提が崩壊してしまうのだ。脳科学の発展によって揺らいだ法制度の土台を強固にするためにも、人間の脳の仕組みにあった法制度改革が必要と主張する。
Posted by
面白かったです。全部を理解して読んでいたかは別にして、大変興味深いテーマだったので飽きずに読めましたし、和訳も分かりやすかったと思います。脳のことを考えるのは、私って何だろうと考えるのと通じるような気がします。タイトルの『意識は傍観者である』というのも、私ってなんだろうって考えて...
面白かったです。全部を理解して読んでいたかは別にして、大変興味深いテーマだったので飽きずに読めましたし、和訳も分かりやすかったと思います。脳のことを考えるのは、私って何だろうと考えるのと通じるような気がします。タイトルの『意識は傍観者である』というのも、私ってなんだろうって考えている私を意識した時点で傍観者なんだなぁと思うし、プロのアスリートの目標が考えないこと、つまり意識しないでも体が動く(素早い反応)ことというのもなるほどなぁと納得。それにしても脳って不思議ですね、まさしく小宇宙!
Posted by
無意識のことや、プライミング、習慣化のためにはなど切れ切れの知識として入ってきていたことが少し腑に落ちた感じかな。日々自分が見聞きしているものが自分を形成しているのなら、普段いかに過ごすかもたいせつということかな。 後半の自由意志と有責性や更生についてもいろいろ考えさせられる。
Posted by
ひとからどんな本?と聞かれると 意識は思ってるほど意識してないんだよ 会社のCEOみたいなもんだよ ってことを書いてる本だよぐらいにしか 説明できないぐらいの理解だけれども おもしろかった この面白さは ホンマでっかTVの面白さに とても似ている 衝撃的な学説を突き付けられ 裏...
ひとからどんな本?と聞かれると 意識は思ってるほど意識してないんだよ 会社のCEOみたいなもんだよ ってことを書いてる本だよぐらいにしか 説明できないぐらいの理解だけれども おもしろかった この面白さは ホンマでっかTVの面白さに とても似ている 衝撃的な学説を突き付けられ 裏づける実験や事例が提示される ちょっと違うのは 意識は傍観者であるというスタンスが 全編を貫いているから 体系的な理解が得られることか ひよこ雌雄鑑別師がどうやって学び判断するのか 人口知能の新しいありかたー多党制にする 虫のしらせについての説明 そんな面白すぎるテーマが次々と語られる ホンマでっかとおなじように ちょっと眉唾ものに聞こえ 他の研究者の意見も聞いてみたい気もするが それでも★5が相当な面白本 新しい判決のありかたについて 修正可能性に基づくという提言は 現在の日本なら 少年の可塑性に基づく要保護性を考慮した 保護処分に該当するだろうか 可塑性があれば年齢問わず保護的措置を行う ということだろうが 科学的に可塑性を判断できるようになるのは まだまだ難しいのではないか?
Posted by
われわれの行動や思考は「私」と思っている意識の あずかり知らぬ無意識の領域でその多くが決められて いる。今まで読んできた意識についての本の内容を 超えることはないが、一番わかりやすくまとめられて いると感じた。しかし、そのわかりやすさゆえに 唐突な感じで展開された最後の章、犯罪と...
われわれの行動や思考は「私」と思っている意識の あずかり知らぬ無意識の領域でその多くが決められて いる。今まで読んできた意識についての本の内容を 超えることはないが、一番わかりやすくまとめられて いると感じた。しかし、そのわかりやすさゆえに 唐突な感じで展開された最後の章、犯罪と法律に ついての記述は生理的に反感を覚える人もいるのでは ないだろうか。著者の言う通りだとも思うが、なかなか そうはいかないだろうなぁ。
Posted by
意識三部作としては、『神々の沈黙 意識の誕生と文明の興亡』ジュリアン・ジェインズ→『ユーザーイリュージョン 意識という幻想』トール・ノーレットランダーシュ→本書の順番で読むことを勧める。次にアントニオ・R・ダマシオへ進み、更に『人間この信じやすきもの 迷信・誤信はどうして生まれる...
意識三部作としては、『神々の沈黙 意識の誕生と文明の興亡』ジュリアン・ジェインズ→『ユーザーイリュージョン 意識という幻想』トール・ノーレットランダーシュ→本書の順番で読むことを勧める。次にアントニオ・R・ダマシオへ進み、更に『人間この信じやすきもの 迷信・誤信はどうして生まれるか』トーマス・ギロビッチ、『脳はいかにして〈神〉を見るか 宗教体験のブレイン・サイエンス』アンドリュー・ニューバーグ、ユージーン・ダギリ、ヴィンス・ロースを読めば理解が深まる。たぶん天才になっていることだろう。 http://sessendo.blogspot.jp/2014/04/blog-post_8.html
Posted by