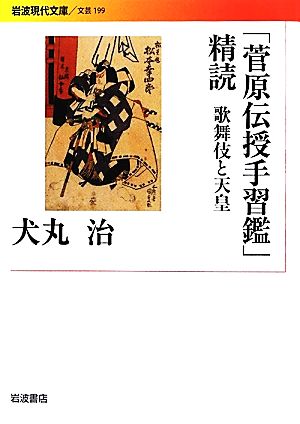「菅原伝授手習鑑」精読 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
資料を博捜しており、感心した。八瀬童子から梅王丸、松王丸、桜丸の三ツ子を着想したのではないかと説く。 読んでいて一つ疑問に思ったのは、駕籠丁と舎人は同じなのだろうか?また八瀬の資料も昭和の資料を引用していたりと、やや強引に思えた。
Posted by
『菅原伝授手習鑑』を通しで観劇しなくても、丁寧に読み取っていくと、いかなる内容であるか、リアルに伝わってくる。まさに「精読」である。 「歌舞伎と天皇」と副題がついているが、松王丸は八瀬童子をモデルにしたという仮説が、実証的に証明されてスリリングでもある。菅原道真の天神伝説を取り上...
『菅原伝授手習鑑』を通しで観劇しなくても、丁寧に読み取っていくと、いかなる内容であるか、リアルに伝わってくる。まさに「精読」である。 「歌舞伎と天皇」と副題がついているが、松王丸は八瀬童子をモデルにしたという仮説が、実証的に証明されてスリリングでもある。菅原道真の天神伝説を取り上げ、「聖と俗」の両極を結びつけるのは、天皇制の近代性に陥らないのが素晴らしい。
Posted by
題名の通り,菅原伝授手習鑑の精読本。 著者が歌舞伎に精通した人らしく,細かい点までその面白味を伝えてくれる。 「菜種御供」の七笑なんかは実際に見たことあるけど,この本を読んだ後にもう一度見ると,更に面白いと思う。 明治以降に加えられた改変点は,非常に気に入らないな。現...
題名の通り,菅原伝授手習鑑の精読本。 著者が歌舞伎に精通した人らしく,細かい点までその面白味を伝えてくれる。 「菜種御供」の七笑なんかは実際に見たことあるけど,この本を読んだ後にもう一度見ると,更に面白いと思う。 明治以降に加えられた改変点は,非常に気に入らないな。現代では江戸版と明治版どちらで演じられているんだろう。 八瀬童子と松王との類似点に関しては,どうだろうなあという感じ。作られた時代背景を鑑みると,道真を天皇に見立てたというのはあんまり腑に落ちないかなあ。 この本を読んで,更に自分の仮説を強化出来たので,満足です。
Posted by
・犬丸治「『菅原伝授手習鑑』精読 歌舞伎と天皇」(岩波現代文庫)は 正に副題通りの結語を持つ書であつた。そこに至るまでに「菅原」全5段をきちんと読む、これが書名の由来である。もちろん全5段といふか らにはこれは原作の浄瑠璃のことで、歌舞伎に取り込まれた場の説明はその従の位置に来る...
・犬丸治「『菅原伝授手習鑑』精読 歌舞伎と天皇」(岩波現代文庫)は 正に副題通りの結語を持つ書であつた。そこに至るまでに「菅原」全5段をきちんと読む、これが書名の由来である。もちろん全5段といふか らにはこれは原作の浄瑠璃のことで、歌舞伎に取り込まれた場の説明はその従の位置に来る。私は文楽の『菅原』をたぶん観たことがない。歌 舞伎に比べると文楽はほとんど観てゐないのだから、これは当然のことである。活字になつた『菅原』もあるが、これとても読んでゐない。私 の知つてゐるのは全体のごく一部、歌舞伎の「車引」「賀の祝」「寺子屋」、これだけである。Wikiには、歌舞伎では「人気のある場面が 単独で上演される事が多い。」とあり、そこに出ているのがこの三場であつた。歌舞伎の『菅原』しか知らないのならこれが普通といふことで あらうか。実際、「賀の祝」の頻度は少し落ちるが、「車引」と「寺子屋」は本当に人気狂言である。地芝居でも「車引」は良く上演される。 三兄弟と時平が客受けするからであらう。あの場で、時平の登場等でおひねりが飛んで声がかかるのは、大芝居では味はへない快感である。 ・その時平、最後は「賀の祝」で果てた桜丸八重夫婦に取り殺される(187頁)と知つた。舎人が菅丞相の遺恨を晴らしたわけである。これ は「一連の大内の天変地異で、天神すなわち道真は終始姿を現さず、桜丸夫婦が代行して」(同前)をり、「道真は既に神であるから、眷属桜 丸に思いを晴らさせる」(同前)といふことである。道真は神、正に天神であり、敵対する時平は「皇位簒奪者」(同前)である。歌舞伎では これが見えてこない。浄瑠璃を第一段から読むことによりこれが見えてくる。だからこそ「寺子屋」での「菅秀才の『無謬性』」(170頁) が指摘され、松王丸が一子小太郎の首を菅秀才の首と認めた「『奇跡』の構造」(171頁)が明かされる。それは「『奇跡』は常に聖者、す なわち天皇なり道真の上に発動されるものであり、下々はあくまでそのための生贄であるという構図」(173頁)である。本書の論旨に沿つ た明快な指摘である。だからこそ最後に「段外 『寺子屋』変容」といふ章がつく。この後半は「松王屋敷」である。忠臣蔵の本蔵下屋敷同 様、松王とその家族の苦衷を見せる場である。これは嘉永年間に京で上演されて以後も、小芝居では上演されてきたらしい。犬丸氏によれば、 これは「『死臭』漂う舞台」(204頁)であるといふ。なぜなら、ここには「『観てはいけないもの』を見せられたような、正視できない 『いたたまれなさ』がある。」(同前)からである。それはどこから来るか。武部源蔵の有名な台詞とは違ふ台詞の「荒涼たる光景が果てしな く拡大再生産されている。」(同前)ところから来るのである。これが時代の要請であり、その中心にゐたのが天皇であつた。逆に言へば、こ れが現在上演されないのは、小芝居がなくなつたといふ理由以上に、時代の変化によるといふことである。私はこれを観てゐないし、それ以前 に「菅原」全体を知らない。従つて、かういふ文脈で「菅原」を読むことができるのかどうかも分からない。それでも、例へば「寺子屋」に於 ける「『奇跡』の構造」は存在するのであらうと思ふ。さうとでも考へなければ、あれは理不尽この上ない。いくら虚構世界でもありうべから ざることであらう。絶対的な存在にすべてが奉仕する、この構図が、言はば共同幻想としてあつたればこそ「寺子屋」は物語として成立するの である。それを説明せねばならぬ時代となつた……問題はここに「死臭」が漂ふかどうかである。それを確認するのは精読しかないか……。
Posted by
明治と昭和の天覧劇を通して、歌舞伎の演目と天皇と赤子の不幸な時代を紡ぎだしているようです。 観なくても内容のすべてが、その背景、史実・・・もろもろが手に寄るように理解できました。 寺子屋がクライマックスで、登場人物の複雑な心境も理解できた。
Posted by
- 1