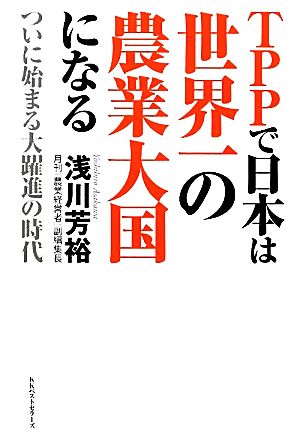TPPで日本は世界一の農業大国になる の商品レビュー
先ごろの講演会で購入。出版年から4年が経過しそうな本を売ること自体、イマイチ感があったが、やむにやまれぬ事情で購入。 書いてあることに、納得できないことはない。しかし、第5章は、まさに机上の空論。農協・全中などという組織がある中で、農協法廃止などあり得ない。鳴り物入りで始めた農...
先ごろの講演会で購入。出版年から4年が経過しそうな本を売ること自体、イマイチ感があったが、やむにやまれぬ事情で購入。 書いてあることに、納得できないことはない。しかし、第5章は、まさに机上の空論。農協・全中などという組織がある中で、農協法廃止などあり得ない。鳴り物入りで始めた農協改革も、種々の独占の一つ(監査)をようやく取っ払っただけだったのに。 前向きに言えば、時代を大幅に先取った提案ともいえる。できれば、農協がある前提で、あるいは農協解体のソフトランディングを踏まえて、もう少し現実味のある八策を提案してほしい。
Posted by
TPPと農業に対して批判する書籍が多い中、この本はTPPをきっかけに日本農業が世界一になるための戦略と可能性を示しています。最も印象的だったのが、農家さんの、TPPに対するポジティブな意見と、やる気でした。 九州大学 ニックネーム:たまこ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
チェック項目12箇所。本書はTPP賛成本でもなければ、ましてTPP反対本でもない、本書は実際にTPPを活用するための本だ、とくに日本の農業・食産業をいかに発展させるか具体論を示す実践本である。日本人が突如、モチモチ感のない米を好きになり、一斉に食べ始めることはありえない、それ以前に、全国すべての米卸からスーパー、レストラン、米屋、米加工業者が仕入れを一斉に外米に変える必要がある。日本人が食べる良食味の短粒種米市場は、世界のコメ貿易のなかで超ニッチ市場である、米国の97%のコメ生産者にとっては、これまで栽培したこともない特殊なコメなのである。「チャーハン米」「パエリア米」など、毎月のように世界中から多種多様な新米、コメ食品が陳列されるようになれば、潜在需要が引き出される、その結果、国内の生産者にとってもこれまで想像しなかったような新市場創出という相乗効果が生まれる。関税ですべてが決まるわけではない、最後に選ばれるのは品質であり、生き残るのは顧客のために技術を磨く志の高い農業経営者である。農協職員の多くが車や保険、宝飾品、着物の営業などのノルマを抱えている、農業に関係ない仕事は別会社がやればいい、むしろ、必要な事業活動は堂々と継続すればいいだけだ。農協が真に恐る事態はTPP協定(4ヶ国)12条に明記してある、「いかなる締約国も、地域区分に基づくか、全領域に基づくかに関わりなく、独占的サービス提供者の必要性、いずれの形であれその数の制限を採択、維持しない」、これが農協にいずれ適用されるかどうかだ。日本の農家人口はまだ多すぎるのである、人口に占める農業従事者比率は英国1.7%、米国1.9%、ドイツ2.2%、フランス2.9%に対し、日本は3.4%もいる、国が減反などの政策によって、趣味的農家を延命させ、事業意欲の高い成長農場が規模拡大する余地を妨げているからだ。日本農業が世界一になるには、今のうちから中国の巨大な”胃袋”市場を視野に入れておく必要がある。中国の農産物の輸入伸び率は517%でその額は米国、ドイツに次ぐ世界3位、すでに日本の輸入額を大きく上回る規模となっている。伸長する輸入品の多くは食品加工用である、一人世帯が増え、ますます自宅で調理しない人口比率は高まるばかりで、この潮流は絶対変わらない、この現実を農業サイドが直視しなければならない、生鮮市場の価値が高いか安いかで農業経営を論じても、未来はない、過当競争に明け暮れ、有望な市場を見逃すだけだ。米国ポテト協会では、日本の学校給食マーケット参入を目論見み、献立に影響力を持つ日本の栄養学の権威を米国に招待し、米国産ジャガイモの素晴らしさを畑から伝えていく、最近では、日本のファストフードやファミレスでのフレンチフライの市場が飽和してきたと見てとるや、コンビニや和食チェーンにも攻勢をかける、具体的なメニュー提案するにとどまらず、小売単価から利益額、準備するまでの時間と人権費まで算出し、いかにお店が儲かるか商談で提示する。「食りょの輸入が増えれば増えるほど農産物・食品の輸出は増える」、たとえば、世界一の小麦輸入国は「パスタの国」イタリアである、イタリアは輸入小麦をパスタに加工し、世界中に輸出しているのである。
Posted by
著者は、TPPを日本の農業にとって脅威ではなく、むしろ大躍進するための好機であると語る。本書ではまず、反TPP論者の主張の虚偽や日本の農業界を蝕む利権構造を徹底的に暴く。その論拠は、緻密なデータと農業の現場を歩き、生産者の声にじかに接している著者の豊富な取材に基づくもので、実に大...
著者は、TPPを日本の農業にとって脅威ではなく、むしろ大躍進するための好機であると語る。本書ではまず、反TPP論者の主張の虚偽や日本の農業界を蝕む利権構造を徹底的に暴く。その論拠は、緻密なデータと農業の現場を歩き、生産者の声にじかに接している著者の豊富な取材に基づくもので、実に大きな説得力をもつ。本書を開けば、いかに世間を賑わす「亡国論」が机上の空論であり農業の現状を無視したものであるか、そして農水省・農協を中心とする日本の農業界の構造がいかに農業の成長を妨げる要因となっているかを、つぶさに理解できるであろう。
Posted by
農業は全世界的に見れば、成長産業。その可能性を感じさせてくれる1冊。 前著が、主に日本の農業界の現状を述べていたのに対し、こちらはそれプラス著者の提案が具体的に述べられている。 その前に日本農家は黒字化を達成し、自立することが大事。
Posted by
初めて農業に関する本を読みました 全く知識のない分野だったのでかなりおもしろかったです やはり自由競争の促進がどの業界でも求められているのだと感じます 筆者はTPPに賛成でも反対でもないと書いていましたが、あきらかに賛成と感じました。 というのも自由化はとにかく必要だと思ってお...
初めて農業に関する本を読みました 全く知識のない分野だったのでかなりおもしろかったです やはり自由競争の促進がどの業界でも求められているのだと感じます 筆者はTPPに賛成でも反対でもないと書いていましたが、あきらかに賛成と感じました。 というのも自由化はとにかく必要だと思っており、それには法改正が必要、TPPはそれを包含してくれるというところに起因してるからだとおもう。 ものすごく農業に関心をもてました。でもこの本しか読んでないので少し正しいのか偏っているのか全く判断ができないので☆ヨッツです・・・
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
TPPというと、農業界は足並みをそろえて断固反対している印象を受けます。しかし、実際にまったく異なるということはご存知でしょうか。本書は、農業経営者サイドの視点から、TPPへの賛成意見を提出している異色の著書です。 意外なことかもしれませんが、農業とは全く関係ない「専門家」がTPPが締結されると日本の農業は壊滅すると警告をし、一方では、農業でしっかり事業を目指す農業経営者たちの中には、虎視眈々とTPP後の変化を狙ってビジネスチャンスを今か今かと待ち受けている方々もいるのです。むしろ、TPPを締結してくれたほうが日本の農業は発展すると考えている人たちもたくさんいるのです。 本書では、TPP後に起こると言われている、「日本米の9割が外米に置き換わる」「小麦が全滅する」「米国の陰謀説」などの悲観的な議論を、具体的な事例やデータをもとにしながら、すべて根拠薄弱なものとして切り捨てます。 むしろ、ほとんどの場合はTPPによる規制撤廃で、日本の農産物は世界中に輸出が拡大して、 農業が成長産業となり、雇用も産み出すと論じられています。なにより、第4章では、実際の農業経営者たちの生の声で、彼らがTPPに対してどのような考えを持っているのかを知ることができ、私たちがイメージしている農家とのイメージに違いに驚きを覚えるでしょう。 国内の農業を保護するためのもっともらしい理由としては、新興国での人口爆発による食料価格の高騰や、政情不安によって海外から食料が入ってこなくなるなどの食料安全保障が挙げられています。しかし、実際には、そのような緊急事態が起こるのであれば、なおさら質が高く、正常な価格の農産物を大量に作れる力をつけることが必要になるでしょう。 歴史上の食料飢饉で悲惨だった事例としては、19世紀にアイルランドで起きたじゃがいも飢饉がありますが、あの当時、飢饉で国民がバタバタ倒れている間にも、アイルランドからイギリスには、小麦を始めとした食料が輸出されていたのです。結局のところ、事実は食料が足りなかったのではなく、「食料を買うお金がなかった貧困」と「政府の失策」が問題でした。仮に食料自給が国内で十分になされていたとしても、政府に問題があったり、国民の所得に問題があれば、食料は手に入りません。統制と保護により、市場価格より高い食料が確保されていても、それが国民に行き渡るかどうかの保障はありません。 実際に、他国から食料がまともに輸入できなくなるほど世界情勢に問題がでる状況を想定したら、国内生産で充分に食料が確保できる状態になっても、あまり意味が無いことに少し考えれば誰でも気がつくはずです。というのも、日本はエネルギー資源の約96%を海外から調達しています。食料の輸入が厳しくなるような情勢になれば、まずはそれ以前に、エネルギー資源の確保が困難になります。 エネルギー資源がなければ、日本の工業、サービス業、あらゆる産業は立ちゆかなくなります。ビニールハウスの燃料から、耕運機の燃料まで、農業の生産もままなりません。仮に百歩譲って、国内の農産物が問題なく生産され続けていられるとしても、それを都市部に輸送する手段がありません。都市に住む人たちが、大挙してリアカーを引きながら、農村に向かう状況など、想定として現実的ではないでしょう。その意味では、「農産物がまともに輸入できない状況」はすでに、日本にとっては詰んでいる状態です。実際、先進国で、「食料安全保障」を自国ですべての食料を生産できる状態を目指すなどと考えている国はありません。荒唐無稽なのです。 TPPですべてがバラ色という立場を取るには、一人一人が真剣に問題の所在を考える必要ありますが、「守られるべき農業(?)」の立場から、「TPPが来ても構わない、政府がなにかをやろうとするのは大きなお世話」という意見がでることには、真摯に耳を傾ける必要があるでしょう。 この著書からは、政府や、経済界からの「TPP賛成論」や、農業、医療などの組織からの「TPP反対論」とは全く異色の世界が見えてきます。それだけでも必読といえる一冊です。
Posted by
250ページほどで構成されているが、原稿はこの倍あったというのだから驚く。しかもそれを2ヶ月で書き上げたというからさらに驚く。 そんな短期間でこれだけの内容を詰め込めているということは、常日頃より農業の問題点や改善点を考え、私案化できていることの表れ。図表はあまりないが、過去の...
250ページほどで構成されているが、原稿はこの倍あったというのだから驚く。しかもそれを2ヶ月で書き上げたというからさらに驚く。 そんな短期間でこれだけの内容を詰め込めているということは、常日頃より農業の問題点や改善点を考え、私案化できていることの表れ。図表はあまりないが、過去の歴史や多岐に渡るデータを駆使した説明は有無を言わさない説得力に満ち満ちている。この方の意見に意義を唱えても、すぐに論破されてしまうだろう。朝生テレビでTPP反対論者や農水省の役人とやりあってもらいたい。 農業は国が過保護にしなければならないような特殊な産業ではなく、第1次産業から第3次産業までたくさんある産業の中の1業種にすぎない。各産業が国に頼らず自助努力で何とかしようとしていることを農業もすべきであるというシンプルな話のはず。 それなのに、「農業は弱っている」とか、「補助金が与えて守るべきなんだ」となるのは、あまりにおかしな話しである。この本はその点をストレートにに見事に説明しきっている。その見事さは、読んでいて気持ちいいぐらい。 TPPの中の農業分野に関しては、この本を読めば本質まで理解できる。この本は、みんなが絶対読むべきである。そして、農業に対するわたしたちの先入観や思い込み、刷り込みをすべて砕け散らせて、認識を新たにするべき。 これを読んでもTPPに反対する農業関係者がまだいるとすれば、それは既得権益を死守したい人たち、現状維持に固執する人たち、自助努力という苦労から逃げたいだけの人たち、そして相も変わらず税金を補助金の名で搾取して楽をしようとする怠惰な人たちである。
Posted by
- 1