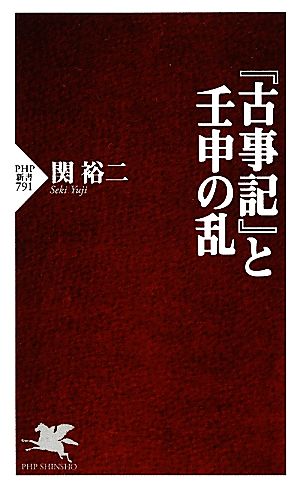『古事記』と壬申の乱 の商品レビュー
奈良への旅行に行く前に予習の一つとして。 教科書では数行の記載の事象も解説されると面白い。真偽はともかく、古代の人々も懸命に生きてきたんだなと思うと奈良にますます行きたくなった。
Posted by
関さんの本、15年くらい前に読もうとして(まだ中学生だった)難しすぎて断念したのです。 今回読めて良かった。 賛否両論ありまくりなんでしょうが、個人的に 古代史ってわからないことが本当に多いので、これくらい色々推理して色んな説を打ち出してもいいんじゃないかなと思います。 確かに教...
関さんの本、15年くらい前に読もうとして(まだ中学生だった)難しすぎて断念したのです。 今回読めて良かった。 賛否両論ありまくりなんでしょうが、個人的に 古代史ってわからないことが本当に多いので、これくらい色々推理して色んな説を打ち出してもいいんじゃないかなと思います。 確かに教科書で習う飛鳥時代ってキレイにまとまりすぎてて、んなわけねぇだろとは思う(笑)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
なぜ、ほぼ同じ時期に『古事記』(712)と『日本書紀』(720)というふたつの歴史書を必要としたのか。しかも『古事記』は新羅に好意的で、『日本書紀』は百済に好意的(反新羅)である。中国の歴史書は多くの場合、新王朝が前王朝を倒した正統性を明らかにするために記されていることを考えれば、当時の日本では、2つの王朝が争っていたと推測できる。 当時(7世紀中頃)の朝鮮半島情勢を見てみると、新羅、高句麗、百済が鼎立した三国時代。もともと、新羅、百済などから日本への移住者はおり、政権争いもあった(乙巳の変)。さらに、唐が新羅を支援して百済を攻撃し、百済が滅亡する(660年)あたりから、百済の遺民が大量に日本に入ってくる。 百済滅亡を機に663年、朝鮮半島の白村江で、日本・百済遺民の連合軍と唐・新羅連合軍との戦争が起き、日本は大敗し、唐・新羅に対する防衛強化が必要となる。このような外交政策の中で672年に生じたのが、壬申の乱である。天智天皇亡き後の天智天皇の弟(大海人皇子)と息子(大友皇子)の争いとされているが、663年の白村江の戦の延長線上で考えるべきであろう。つまり、天智天皇は舒明天皇と皇極女帝の間の子(百済系)であり、その息子である大友皇子(弘文天皇)は百済系である。しかし弟である大海人皇子(天武天皇)は蘇我系の高向王(壬申の乱の立役者)と皇極天皇の間の子(異父兄弟)であり、新羅系ということだ(p.144)。つまり壬申の乱は、新羅と百済の戦いが背景にある。勝って即位したのが新羅系の天武天皇である。 ふたつの歴史書がある理由について、『日本書紀』は、百済の王子である中臣鎌足を始祖とする藤原氏が、改革派である蘇我氏を排斥する一方、蘇我氏の功績を聖徳太子という架空の人物の功績にすり替えることで、一方的に蘇我氏(新羅系渡来人)を悪者にする立場で記されたものであるとする。一方『古事記』は、親新羅の天武天皇の勅命によるものであるが、その妻であり次の天皇である持統天皇以降が実は、百済寄りの政権であったため、『日本書紀』が正史として編集されることとなった。その一方、『古事記』は、新羅系の秦氏によって、その奉祭する神統譜を『古事記』に加条することによって、新羅系渡来人の正統性を訴えるために執筆された、とする。 この「2つの歴史書」の問題を当時の朝鮮半島情勢や渡来人と密接に絡めて検討をしている点には面白味を感じる。著者の推理により結論付けている点が多いのは確かであるが、資料万能主義に囚われた歴史観は、歴史上の勝者による一方的で独善的なものになりかねない。従って、隣国の動きや人間の情も入れつつ、批判的に見て、推理することも必要だと思うし、面白く分かり易い歴史観が提示されていると捉えてよい思う。
Posted by
関裕二先生 なぜだろう、読みづらいのに買ってしまう いつも中途半端にしか読めない 古事記偽書説を述べているが肝心な事が書いていない 712年に出来た古事記 713年風土記編纂命令で、720以降(忘れた)出来た出雲風土記 この出雲風土記の神話の数々が720年できた日本書紀には記載が...
関裕二先生 なぜだろう、読みづらいのに買ってしまう いつも中途半端にしか読めない 古事記偽書説を述べているが肝心な事が書いていない 712年に出来た古事記 713年風土記編纂命令で、720以降(忘れた)出来た出雲風土記 この出雲風土記の神話の数々が720年できた日本書紀には記載が無く、712年の古事記にはふんだんに記載ある 多氏が自分の家系を飾り立てるため、政敵が編纂した新撰性氏録にない独自の神を出した日本書紀より古い国選史書を偽っているに決まっているじゃないか なぜ書かない
Posted by
前に読んだ秦氏の本とかぶるとこあり。 通説ってのは、歴史の教科書みたいなことをさしてるのかな。 最近の古代史本だと、蘇我=悪みたいなのって少ない気がしますが。
Posted by
定説となっている内容とは違い、いい意味でのスキャンダル性に富んだ1冊。なるほどと頷ける部分も多々ある。この時代も海外との交流は頻繁にあった事実に改めて驚く。もう少しこの時代をお勉強しようかと言う気になった。
Posted by
日本の古代史の理解を深めたくて読んでみようと手にとりました。 なかなか登場人物の位置関係も複雑だし、そもそも歴史書は時の権力者による捏造や創作もあり、わかりずらい構造にあると思う。 上宮王家は架空とか、聖徳太子は蘇我入鹿の功績をすり替えるための皇族とか、色々な仮説を提示してお...
日本の古代史の理解を深めたくて読んでみようと手にとりました。 なかなか登場人物の位置関係も複雑だし、そもそも歴史書は時の権力者による捏造や創作もあり、わかりずらい構造にあると思う。 上宮王家は架空とか、聖徳太子は蘇我入鹿の功績をすり替えるための皇族とか、色々な仮説を提示しており、少し言いっぱなしの箇所も多く、もっと深堀が欲しいとこ。
Posted by
日本の古代史にはよくわからない曖昧モコとした部分が多いことは知っていたが、最近の研究はどのくらい進んでいるのかと思い本書を読んでみた。 しかし、相変わらず全くわかっていない様子が伺えてちょっとがっかりする思いを持った。 本書で扱っている「古事記」と「日本書紀」の内容の研究...
日本の古代史にはよくわからない曖昧モコとした部分が多いことは知っていたが、最近の研究はどのくらい進んでいるのかと思い本書を読んでみた。 しかし、相変わらず全くわかっていない様子が伺えてちょっとがっかりする思いを持った。 本書で扱っている「古事記」と「日本書紀」の内容の研究は「文献史学」というジャンルなのだろうが、昔からあまり進歩していないように思える。ほとんどが推測と憶測のようにも思え、新しい知見や考察があるようには思えなかった。 「古代史研究」や「古人類学」では、科学的調査方法の進化やDNA解析などにより、新たな世界を切り開いているように思えるが、「文献史学」はそうはいかないのだろう。あい変わらず旧態依然のまま、との感想を持った。本書は残念な本であると思う。
Posted by
大化の改新(本書では乙巳の変、645)から壬申の乱(672)かけての古代史は分り難い。本書を読んでも明解にならない。 例へば、大化の改新には弟の天武天皇は何故登場しないのか。天武天皇は壬申の乱では甥の大友皇子と戦ひ、姪の大友皇子の姉を妻(後の持統天皇)としてゐる。複雑怪奇である。...
大化の改新(本書では乙巳の変、645)から壬申の乱(672)かけての古代史は分り難い。本書を読んでも明解にならない。 例へば、大化の改新には弟の天武天皇は何故登場しないのか。天武天皇は壬申の乱では甥の大友皇子と戦ひ、姪の大友皇子の姉を妻(後の持統天皇)としてゐる。複雑怪奇である。 文章は筆者の主観的表現(「思えてならない」とか「思えて仕方ない」)が目立ち、読みづらい。 筆者は多作の様だが、本書だけとしたい。
Posted by
- 1