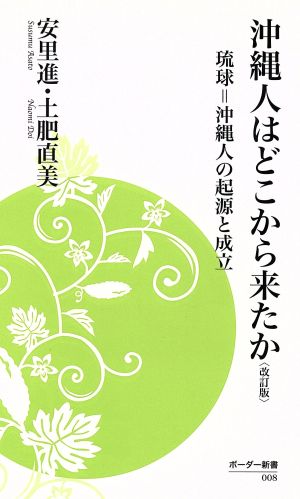沖縄人はどこから来たか 琉球=沖縄人の起源と成立 改訂版 の商品レビュー
考古学者・安里進と形質人類学者・土井直美が1997年に行った対談を1999年に書籍化、2011年に「増補版」として新書化したもの。著者二人による「対談以降の調査研究の進展」が加わり、情報を更新してくれている。 本書の内容は、「現在の沖縄人につながるグスク時代以降の人は、形質的に...
考古学者・安里進と形質人類学者・土井直美が1997年に行った対談を1999年に書籍化、2011年に「増補版」として新書化したもの。著者二人による「対談以降の調査研究の進展」が加わり、情報を更新してくれている。 本書の内容は、「現在の沖縄人につながるグスク時代以降の人は、形質的にも政治・経済・文化的にも日本からの強い影響のもとに成立した」という科学的な命題が基調となっている。これは「新たな日琉同祖論」の可能性をはらむものであるが、著者の一人である安里は「日本との関係のみを強調するだけではなく、貝塚時代や先島先史時代、朝鮮・中国のヒトと文化の影響についても考慮する必要がある」(p.156)と説く。日本本土と琉球・沖縄の間にある「同質性」と「異質性」、そのどちらに重きをおくかという価値観の問題ともかかわり、「沖縄ナショナリズムに根差した歴史観」との批判もあるとのことだが、個人的には安里氏の研究姿勢をお手本としたいと思う。 【港川人について】 1万8千年~1万6千年前の港川人と6000年前に始まる貝塚文化の間には1万年の空白がある。港川人絶滅説もある。対談当時は「港川人=縄文人の祖先」と考えられていたが、最近では、縄文人は北方系で、港川人にはつながらないという考え方が支持されるようになっている。 【グスク時代について】 新興経済大国・宋を中心とする「東アジア交易圏」の形成に伴い、日本商人が九州から琉球列島各地に押し寄せ、貝塚文化はグスク文化に転換していく。 日本からの影響は先島まで及び(高度な航海の技術と動機をもった人々がいたということ)、それまで互いに交流のなかった奄美・沖縄と先島が文化的に統合され、琉球文化圏が形成されていく。 貝塚時代人とグスク時代以降の人では、形質的にも大きな変化がみられる(体格が頑丈になり、中世の日本人に似た顔つきになる)。 この時期に日本本土から流入してきた集団の形質を受け継いだ人たちの人口が爆発的に増加する。
Posted by
- 1