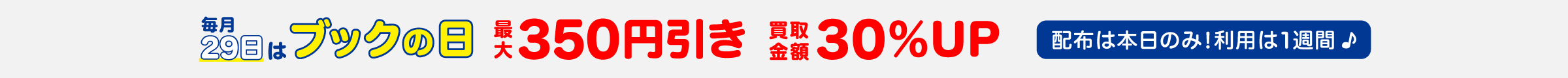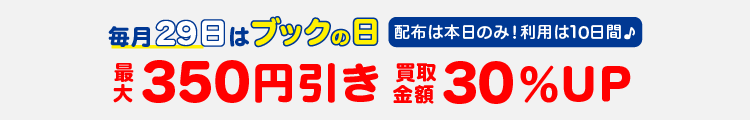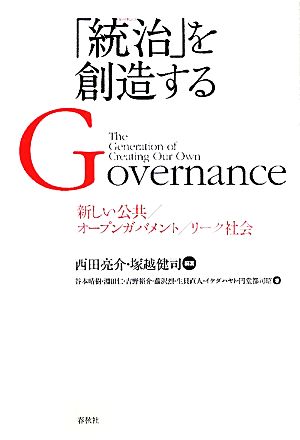「統治」を創造する の商品レビュー
オープンガバメントを理解したくて手に取る。 アメリカ、イギリス、ニュージーランドや日本の政府の取り組みの経緯などまとまっていてわかりやすかった。 改めてオープンにすることの意義を考えさせられた。 自分の仕事に生かしたい。そう思わせてくれた。 少し迷っていたことがクリアになった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
《第1章 eデモクラシー2.0―その可能性とこれからの日本政治 by 谷本晴樹》p37~ 「スマートモブズ(賢い群衆)」by ハワード・ラインゴールド:ITを利用して政治運動を行う市民たち。Cf. 『スマートモブズ―<群がる>モバイル族の挑戦』p42 Eg. 『オバマの作り方』 アメリカの政治学者ベンジャミン・バーバー 代表制民主主義「薄い民主主義(Thin Democracy)」 参加型民主主義「濃い民主主義(Strong Democracy)」 Cf. 『ストロング・デモクラシー―新時代のための参加政治』p44 マックス・ヴェーバー「政治とは情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっと穴をくり抜いていく作業である」『職業としての政治』p70 《第2章 政府/情報が開かれる世界とは―情報の透明化とリーク社会 by 塚越健司》p71~ 【ジャスミン革命における3つの「主体」】p92 ①一次情報発信主体 ②キュレーター ③情報拡声器としての主体 《第3章 「政治」概念はラディカルに変化するか―オープンガバメントが切り開く新しい社会》p119~ 「啓蒙とは何か。それは人間が、みずから招いた未成年の状態から抜け出ることだ。未成年の状態とは、他人の指示を仰がなければ自分の理性を使うことができないということである」カント『啓蒙とは何か』p131 《第4章 ハイエクの思想から読み解くオープンガバメント―情報化社会における市場と政府の役割》p147~ 【オライリーの「Gov2.0」】p158 旧来の政府=「自動販売機」 Gov2.0=バザール 「自動販売機モデルにおいては、可能なサービスについてのメニューは前もって決定されている。少数の売主(だけ)が機械に商品を入れておく能力を持っている。結果として、(ユーザーの)選択は制限され、価格は高くなる。対照的にバザールは、共同体それ自身が財やサービスを交換する場所である」 「カーリル(calil.jp)」:図書館蔵書検索サイト p289
Posted by
本著は情報技術の発展という社会的な情勢を前提とした現代のオープン・ガバメントに関する実践的思考についての論文集であり、それぞれの著者の経歴からも分かるようにその種々の論文における観点も非常に多様である。米国政府の状況の考察からオープン・ガバメントの前提としての情報開示の必要性を説...
本著は情報技術の発展という社会的な情勢を前提とした現代のオープン・ガバメントに関する実践的思考についての論文集であり、それぞれの著者の経歴からも分かるようにその種々の論文における観点も非常に多様である。米国政府の状況の考察からオープン・ガバメントの前提としての情報開示の必要性を説いたものもあれば、各国での法制に焦点をあてたものや、震災後の具体的な状況、あるいはオープン・ガバメントによって齎されるビジネス的利益などまで、そして個人的に経済学部生として興味深かったのだが、経済学者の観点からオープン・ガバメント的変化をハイエクの想定した社会全体の知識の蓄積という歴史の原動力と重ねて考察した論文までもあった。 しかしそういった諸々の立場からオープン・ガバメントの明るい可能性が語られながらも、目を引くのは淵田仁さんや円堂都司昭さんなどのオープン・ガバメントの限界を説く論文である。浄君が言っているように現在ではオープン・ガバメントの限界を説く主張の方が声が大きいといのは事実かも知れないと感じた。 三章で淵田仁さんはオープン・ガバメントの弱点は政治に主体的な個人が前提とされていることだと指摘している。しかし最終的にはこの弱点は避けるようなシステム的変革の提言はしておらず、好ましい事例としてあげている物もいまいちである点は少し不満足であった。 また九章「悪しき統治を想像する」において円堂都司昭さんは、『一九八四年』『すばらしい新世界』『われら』などのセックス・言葉が管理されたディストピア小説の系譜を辿ることを出発点としている。もはや使い古された方法論と思うかも知れないが、本論は単なる全体主義批判・社会主義批判・管理社会批判に留まることはない。『ドーン』『虐殺器官』『ハーモニー』などのゼロ年代のSFの思考実験を踏まえて「分人」「散影」「ディズニー的資本主義」「添加現実」などの概念に触れ、現代的な政治と人間における好ましいシナリオ・そうでないシナリオについて考察している。結論としては「人間が動物である部分と社会的な存在である部分の折り合い」が重要であるといったことなどを挙げている。芸術家は未来のアンテナである、というような事をマクルーハンが言っていたと思いますが、改めて小説・文学の先見性には驚くことがある。 何よりこの本の執筆陣は博士課程の院生も多くいて、自分達とそう歳の違わない人々であることに期待を抱かざるを得ない。
Posted by
【読書その53】3月11日の東日本大震災。その際に大きな役割を担ったtwitterやFacebookをはじめとしたソーシャルメディア。本書は、若手の研究者等がソーシャルメディアを活かした新たな統治のあり方について論じた論文集。先日読んだ「一般意思2.0」と同様、非常に刺激的だった...
【読書その53】3月11日の東日本大震災。その際に大きな役割を担ったtwitterやFacebookをはじめとしたソーシャルメディア。本書は、若手の研究者等がソーシャルメディアを活かした新たな統治のあり方について論じた論文集。先日読んだ「一般意思2.0」と同様、非常に刺激的だった。 政府はtwitterやFacebook、Youtubeなど、情報提供ツールを多様化させているが、それはあくまで「情報提供ツール」に留まるものだと思っていた。その中で文部科学省の「熟議カケアイ」という取組があるのは初めて知った。今後の仕事の仕方として参考にしたい。 また、東日本大震災復興対策本部で非常勤スタッフとして勤務された藤澤氏の論文の政府機関内で働いた上での感想は、そのように目に映るのかと考えさせられた。情報は開示されるだけではなく、それが市民に対して伝わっていることが大事。まさにおっしゃるとおりである。 最後に、最近こうしたソーシャルメディアの台頭もあり、自分と同世代の研究者等が活躍している。非常に心強いと思うし、期待したいし、嬉しい。
Posted by
IT社会のもたらす新たな”統治”の形を、「新しい公共/オープンガバメント/リーク社会」という3つのキーワードから提示する意欲作。 寄稿者の幅が広いという理由もあるが、理念的なことから実践的なことまで、そして法律からビジネスそして文学までカバーしており、政治・統治に関わる問題領域の...
IT社会のもたらす新たな”統治”の形を、「新しい公共/オープンガバメント/リーク社会」という3つのキーワードから提示する意欲作。 寄稿者の幅が広いという理由もあるが、理念的なことから実践的なことまで、そして法律からビジネスそして文学までカバーしており、政治・統治に関わる問題領域の広さと深さが体現されている。 上記の3つのキーワードは並置されているが、全体を通しての主軸は「オープンガバメント」であり、それを支える「リーク社会」と、それがもたらす「新しい公共」が付随的に論じられているという印象。 しかしながら、「オープンガバメント」という概念自体が新しく、浸透し切っていない段階において、うってつけの「オープンガバメント入門書」と言えると思う。 序章西田論文による現状の統治のあり方に対する問題提起からはじまり、第1部はオープンガバメントの導入となっている。 「オープンガバメント」とは何かと問われると、基本的には ・政府の持つ情報の公開(=政府のプラットフォーム化) ・それを利用して民間サービスが活発化、人々の政治参加が活発化 (=「新しい公共」の活性化) の2点に集約される。 ところが、概念の新しさゆえに、この2軸から枝葉のように伸びるメリット・デメリットが点在していて、それらを各論文が拾い集めていく。 谷本論文は「熟議」をひとつのキーワードとしつつ、純粋に政治の観点からオープンガバメントを吟味するのに対し、塚越論文はウィキリークスを題材に、情報公開に関わる正当性/正統性といった観点からオープンガバメントの効用を説いた。 一方で、淵田論文と吉野論文は、「オープンガバメント」の重要性を社会思想の点から裏づける。 淵田論文が東浩紀『一般意思2.0』の紹介に終わってしまっている点が少々残念だが、同書が文脈的に重要であるのことは間違いないのでやむをえないともいえる。というのも、谷本論文も文部科学省の「熟議カケアイ」を引き合いに出しつつ、インターネットを介したやりとりとリアルのやりとりの相乗効果に期待をかけているからである。この相乗効果に関しては、評者も民主主義の強化につながるものとして、可能性を求めるところである。 第2部はより実践的な側面に軸足を移す。 西田論文は寄付文化に、藤沢論文は東日本大震災への対応に、どのように「オープンガバメント」的なものが利用されたかを検証する。例が身近で非常に分かりやすい。とくに藤沢論文は、以前『思想地図β2』で読んだ津田論文と通底するものがあり、面白い。 その後、池貝論文が少し視点を変えてオープンガバメントと著作権の問題に視点を当て、さらにイケダ論文がビジネスの方向へ舵を切る。「オープンガバメント」のはらむ問題や可能性が、政治/統治にとどまらないことを示している点で、池貝・イケダの論文は重要である。 そして第3部に「もう一度考える」と称してぽつん、と入った円堂論文。 執筆者の幅が広いとはいえ、やはり文芸・音楽評論家は他と比べても異色である。 しかし、第1部・第2部が「オープンガバメント」による”「統治」の創造”を、ポジティブに、現在を中心に論じているのに対し、文芸を題材に、新たな動きをより慎重に、歴史的な経緯も絡めて論じていることに好感を持てた。ちょっと不思議な構成だが、悪くない。 というわけで、敬称略でざっと内容をさらってみた。 以下、個人的な感想を2点ほど述べたい。 1つは、「オープンガバメント」の前提となる情報の透明化がはらむ問題を、負の側面として検討して欲しかった。 今さら抵抗があるわけではないが、個人の嗜好・行動のすべての情報が集積されるようになる「プライバシーの消失」が、この手の論議にいつも気になってしまうたちである。 2つは、やはり新しい”「統治」の創造”に可能性を感じる点で非常に面白かったということ。 本を読んでみて、わたしの期待を最も端的に表しているのは、第6章藤沢論文の最終部分である。 「オープンガバメント」のもたらす政府の情報公開は、市民自らの手によるアジェンダ設定・熟議を可能とする。このことは、市民が自ら「政治/統治」という公共を担うことを可能にし、ひいては政府に自らの提案をつきつけ、動かしていくことを可能にする。議論の提示を待つのでは遅い、こちらから議論を引き出せ、ということである。これこそが民主主義の真骨頂であり、それは新しいけど古い。 動かし方は分かった。あとは「統治を逆回転」させるだけ――そんな段階に来ていると思うと、やりがいがあるし、面白いのではないだろうか。
Posted by
敬愛する藤沢烈氏@retzが著者の一人ということで読んでみた。新しいということもあり『一般意志2.0』の流れまでカバーしている。これは刺激的な本だ。政治に興味がありつつもそのシステムに違和感を持っている人は全員とりあえず読めばいいと思います。
Posted by
「新しい公共」「オープンガバメント」「リーク社会」と、最近よく聞くようになったキーワードを若手気鋭の実務家、研究者、アクティビストが実例を踏まえて説明してくれる、何ともお得な本。 若者にとって政治とは、何だか遠い密室で年寄りたちが決めているもの、、という認識がこれまでは一般的...
「新しい公共」「オープンガバメント」「リーク社会」と、最近よく聞くようになったキーワードを若手気鋭の実務家、研究者、アクティビストが実例を踏まえて説明してくれる、何ともお得な本。 若者にとって政治とは、何だか遠い密室で年寄りたちが決めているもの、、という認識がこれまでは一般的でした。しかし、それによって若者たちは不利益を被り続け、所得再分配が進まなかった結果、非正規雇用の増加や非婚化といった現象が発生し、少子化が進みました。 ソーシャルメディアの発達、東日本大震災の発生、政府組織への不信、、これらの要素が組み合わさって、新しい潮流が生まれようとしています。既存の政府組織の限界をソーシャルメディアを中心とした緩やかな連携が補完し、新しい公共としての役割を担う主体が登場する、統治構造の刷新です。 我が国においても、大多数の民主国家においても選挙によって選ばれた議員が政治を担当する間接民主制が採られています。けれども、IT技術の発達によって直接民主制が可能なのではないかという言説も見られます。実際に、原発の是非を問う住民投票を望む声も大きくなっています。 昔ながらの日本社会においては、家長制で家の主たるお父ちゃんの意見がその家庭の意見でした。村の寄り合いでは、男衆が集まって方針を決め、その集合体が村社会をつくっていました。そこから企業中心の契約社会へと変遷し、今また変革期を迎えているのです。 その萌芽は確かに至るところで見つけることができます。大阪では気鋭の首長が既存政党を凌駕する勢いで支持を伸ばし、まさに「オープンガバメント」で府と市という自治体統治構造の刷新を進めています。佐賀県武雄市では、Facebookを活用した市長が登場し、内外の支持者との直接対話を実現しています。 政治は自分たちの生活には関係ない、そんな悲観をしていた若者たちにとって、政治は随分と近いところまで降りてきました。自分たちの統治構造を創造するのか、それともまだ現実は変えられないと諦めるのか、私たちは大きな岐路に立っているのだと実感します。
Posted by
少なくともオープンガバメントに関心のあるかたは読んだほうがよさそうな本です。 「透明性」「政治参加」「官民協働」の3本柱とするオープンガバメントは、行政・市民・NPO・民間事業者等が公共空間の中でそれぞれの役割を果たし公共をつくりあげる「新しい公共」とも密接に関連しています。 ...
少なくともオープンガバメントに関心のあるかたは読んだほうがよさそうな本です。 「透明性」「政治参加」「官民協働」の3本柱とするオープンガバメントは、行政・市民・NPO・民間事業者等が公共空間の中でそれぞれの役割を果たし公共をつくりあげる「新しい公共」とも密接に関連しています。 ガバナンス論はずっと言われているように思いますが、「オープンガバメント」という新しい技術に基づく思想的根幹を取り入れて、まさに「『統治』を創造する」パワーとなるかが分かる―そんな本でした。 具体的には、序章で本全体のマップとラフスケッチを描き、第1章で、ソーシャルメディア等の影響による政治情報の流通形態の変化と公職選挙法との関係(間違いなくかなり大きな障壁のひとつ)、第2章で、ウィキリークスなどによるリークと情報の透明化との関係、またそこでの発信力と主体性との関係を示しています。 第3章で、意図的にかかわろうとしなければかかわれない政治状態を打破するための一般の人々の意見の集積がオープンガバメントの鍵になること、第4章では、ハイエクの思想(市場競争を生み出すプラットフォームを創ることが政府の役割)とオープンガバメントとの親和性が示されています。 第5章、第6章では、主に震災復興に係る社会参加の連鎖事例及びオープンガバメント事例の紹介・考察、第7章では政府情報と著作権の関係を整理しています(この「権利」と「義務」的な考え方の違いが根本的にオープンガバメントの進展度合いを規定している可能性があると思います)。 第8章はオープンガバメントを活用したビジネスについて記し、第9章はオープンに対置された監視的・悪しき統治を小説等から読み解いています。 全体的には、オープンガバメントを捉え直す意味でも、様々な分野の執筆者が横断的書かれていることが刺激的でした。その意味で、知識のインプットよりも本との対話を通じた思索的な深まりがある気がしています(その点、著者のみなさんの意図どおりだと思いますが)。また、この本から議論を生み出すという意味も、非常に意欲的だなぁと感じました。 ただ一点。良い内容の論考が多いだけに、逆に質の低い論考が過度に際立ってしまうのが残念なところではありました。さすがに本の論考はブログの記事ではないので、そのレベルのものは避けてほしかったです。 なお蛇足ですが、以前書いた若生のオープンガバメント関連の論考は以下のとおり。 「住民参加とオープンガバメントを活用した地方議会改革」 http://www.pppnews.org/files/research/2010/re2010_07_101025.pdf
Posted by
「統治」を創造する。この本を読んで考えたのは、創造と分配について。具体的に言えば、ケーキの例を挙げてみる。Open Government(以下OG)によって公開された情報を利用して、多くの人が参加して社会に多大に貢献するものが出来たとする。それは、ケーキで言えば、みんながデコレー...
「統治」を創造する。この本を読んで考えたのは、創造と分配について。具体的に言えば、ケーキの例を挙げてみる。Open Government(以下OG)によって公開された情報を利用して、多くの人が参加して社会に多大に貢献するものが出来たとする。それは、ケーキで言えば、みんながデコレーションしてすっごく美味しいケーキが出来るということだ。だが、それとは別に、そのケーキを分配するときには、みんながそれぞれの利益を主張するだろう(「若い人は栄養が必要なのだから」、「ケーキを食べるのは、老い先短い老人の楽しみ」だとか)。確かに、透明性のある情報が直接届くことで分配はさらに効率的にはなるだろうし(amazonのWish List的なマッチングシステムの開発や個人の行動記録など)、上に述べたみたいに元々のケーキの量も増えている。でもそれでもケーキは有限なのだ。OGは魔法みたいにゼロからイチを生み出す方法ではなく、今まで使われてこなかったものを効率的に使おうという発想だ(って自分は考えている)。とにかく、何が言いたいかっていうと、OGは現実的に今ウィキリークス以降の社会の中で考えられるベストの統治形態だと思うけれど、OGにすれば、なんでもかんでも解決するということではなくて、僕らの世代は自分たちの手で「統治」を創造していかなければならないんだってことを改めて考えさせられました。
Posted by
「統治」、「オープンガバメント」といった概念について哲学・社会学・経済学など様々な側面から書かれた論文集。 個人的には思想史的な流れをくんだ3章と4章、法哲学的見地を盛り込んだ7章が従来の興味と重なっているが、論者の多様性が自分のこれまでの観測範囲外からの面白い話が”良いノイズ”...
「統治」、「オープンガバメント」といった概念について哲学・社会学・経済学など様々な側面から書かれた論文集。 個人的には思想史的な流れをくんだ3章と4章、法哲学的見地を盛り込んだ7章が従来の興味と重なっているが、論者の多様性が自分のこれまでの観測範囲外からの面白い話が”良いノイズ”として紛れ込みやすくなっているので、一冊の本としてはお得な印象を持つ。 特に、これは「あとがき」で編者の塚越健司も書いているが、学者からビジネスの実務家、批評家など幅広いジャンルの書き手が名を連ねており、この一冊だけでもそれなりに多角的視座を取得できるような作りになっている。 例えば「震災時のソーシャルメディアによる有用性評価」という点では、5章は比較的良い方向で捉える一方、6章や9章では否定的に書かれている。そもそもネットが利用できる環境に”被災地”があったのかということについては、震災から少し経過した後で頻繁に語られるようになったが、この辺の評価の差も出自や視座の多角性を象徴しているように思う。 ただ、そのような良い点と表裏一体の話ではあるが、もう少し読み込んでみたいようなモノも中にはあり、これは今後の各筆者の活躍に依るところだと思う。 飽きっぽい性格だが一気に読めた。ただ、.reviewが事実上停止状態なのが個人的には悲しい。それは、.reviewという媒体そのものがオープンガバメント性を有した、これまでの評論系同人誌には無いものだと感じていたからだ。 本書の元は、その.reviewの勉強会だという。そのフィロソフィーは別な形で継承されることを(偉そうに)期待しています。
Posted by
- 1