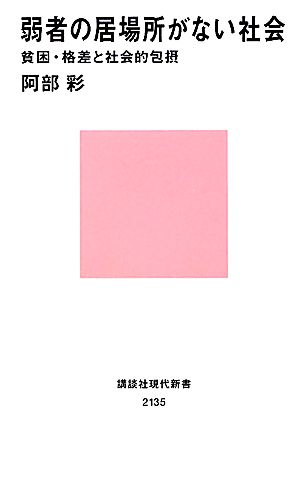弱者の居場所がない社会 の商品レビュー
社会から排除されないように努力をすべき、と考えられがちだけど、だれもが排除されないような社会を本来はつくるべきだというのが納得した。
Posted by
困難な環境に陥ることはいつ誰でも可能性がある。自分には関係ないと思わず、そのような環境に陥った時に手を差し出してもらえる社会の仕組が欲しいと心から思える内容だとおもいます。 ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www....
困難な環境に陥ることはいつ誰でも可能性がある。自分には関係ないと思わず、そのような環境に陥った時に手を差し出してもらえる社会の仕組が欲しいと心から思える内容だとおもいます。 ( オンラインコミュニティ「Book Bar for Leaders」内で紹介 https://www.bizmentor.jp/bookbar )
Posted by
自身に居場所や役割があること、頼ってくれる人がいることは金銭面での貧困を埋めるよりも(と同等に?)生きていくために大事。 社会の格差が大きいことは、それ自体が社会に悪い影響。他の階層の人たちへの憎悪大きくなり、平均余命は短くなり(ウェールズの富裕層はスウェーデンの富裕層よりも短命...
自身に居場所や役割があること、頼ってくれる人がいることは金銭面での貧困を埋めるよりも(と同等に?)生きていくために大事。 社会の格差が大きいことは、それ自体が社会に悪い影響。他の階層の人たちへの憎悪大きくなり、平均余命は短くなり(ウェールズの富裕層はスウェーデンの富裕層よりも短命)、貧しい層の政治参加がどんどんなされなくなる。 マタイ効果…持てるものはどんどん持つ、持たないものはどんどん持たない=格差はどんどん拡大していく 一般的な潮流。止めるためには、持てるものが自身の豊かさは自分の能力だけで作り出したものではないと自覚すること 職業訓練→スキルアップ→失業者を就労につなげる、という流れは、結局彼らの非就労を能力不足につなげる=自己責任論。能力が足りない人たちは、職業訓練によってお行儀が良い人にならなければいけないのか?
Posted by
貧困問題に対し、自己責任論という個人の問題ではなく、社会包摂という社会の責任を問うアプローチをしている。 また、格差は社会の中での人と人の信頼関係の低下と相関がある等、インクルーシブかつ格差のない社会の重要性がわかりやすく提示されている。
Posted by
統計を使った分析もさることながら、ホームレスのエピソードが印象に残った!統計的には格差と社会への信頼が相関していることが、エピソードからは、頼られることの重要性が理解できた。 ロビンフッド指数、マタイ効果について、さらに勉強。
Posted by
社会的排除という言葉を初めて聞いた。 格差は確実に存在している。けれど、弱者をないものとして社会の隅に追いやる状況は、この本が発行されて9年経った今でも変わらないんじゃないかと思う。 いくら暮らしが発展して便利になったからとはいえ、やっぱり人とのつながりは大切。誰かに認められるこ...
社会的排除という言葉を初めて聞いた。 格差は確実に存在している。けれど、弱者をないものとして社会の隅に追いやる状況は、この本が発行されて9年経った今でも変わらないんじゃないかと思う。 いくら暮らしが発展して便利になったからとはいえ、やっぱり人とのつながりは大切。誰かに認められること、自分の居場所があることが何より生きがいになるし生きる活力になる。でも貧困と格差がその人間らしさを奪ってしまう。私の周りに貧困者がいたらどうするだろう。もし自分がその立場になったらどうするだろう。考えるきっかけになった。
Posted by
昔は地縁、血縁が基盤であったが、いまは職縁の時代である。ゆえに失業はその縁を失うことであり、失業が長引けば友人付き合いも希薄になり、だんだん社会の周辺に追いやられてしまう。これを社会的排除と言い、対の概念を社会的包摂という。 日本の相対的貧困率は16%である。つまり6人に1人が相...
昔は地縁、血縁が基盤であったが、いまは職縁の時代である。ゆえに失業はその縁を失うことであり、失業が長引けば友人付き合いも希薄になり、だんだん社会の周辺に追いやられてしまう。これを社会的排除と言い、対の概念を社会的包摂という。 日本の相対的貧困率は16%である。つまり6人に1人が相対的貧困である。 では残りの84%はどうか。この84%の層には貧乏が蔓延している。 貧困は経済用語であり、貧乏は心の問題である。他者との比較から欠乏を感じるのが貧乏である。しかし、この84%の経済格差は小さい。この層は希望格差であろう。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2011年刊。現代日本の貧困・格差問題につき①貧困・格差の意味、②格差の与える社会的影響、③地震など自然災害による貧困を主題とする。①は既読感があるも、「社会的排除」、その中でも雇用からの排除(つまり失業)を、収入減と違う意味で格差問題の中核と見るのは興味深い。先の社会的排除論と②は、英国のリチャード・ウィルキンソン教授の著作(「格差社会の衝撃」等)を参照すべし。③は、震災後三年目に幸福度が急落し、震災直後の水準に陥るのは新奇。ただやはり本書は導入書で、阿部氏著の「子どもの貧困」程のインパクトには乏しい。
Posted by
貧困、格差という問題から一歩進んで、社会的排除という問題を捉えて、社会的包摂政策の必要性を説く。 データもありつつ、現場レベルの話もありつつで、あまり知らなかった貧困の実態が少しは見えてきた。
Posted by
貧困を学問的に追及すると、こうなるのね。貧困学入門。 貧困の定義、その測定の方法論、社会との関係、政策への反映のさせ方、等々単に貧困といっても色々な切り口があることを知った。 特に社会的排除と格差の理論はなるほど腹に落ちた。最も援助を必要とする人に基準を合わせれば皆が幸せな社会に...
貧困を学問的に追及すると、こうなるのね。貧困学入門。 貧困の定義、その測定の方法論、社会との関係、政策への反映のさせ方、等々単に貧困といっても色々な切り口があることを知った。 特に社会的排除と格差の理論はなるほど腹に落ちた。最も援助を必要とする人に基準を合わせれば皆が幸せな社会になる。情けは人の為ならず、と言うことか。 ただ格差是正の恩恵は目に見えにくいから負担とのバランスに社会の納得感が得られるだろうか?被生活保護者をナマポと呼んで差別する風潮が益々強くなっている現状を見ると、絶望的にならざるを得ない。日本人の民度はそこまで高くない。
Posted by