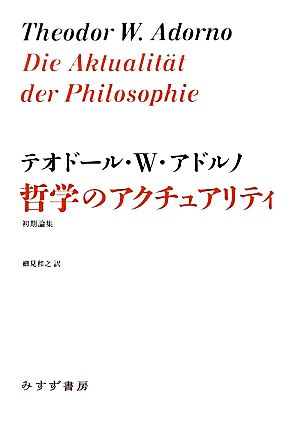哲学のアクチュアリティ の商品レビュー
「哲学のアクチュアリティ」や「自然史の理念」といった、アドルノの思考のモチーフを知る上で参考になる論述を中心に編まれたアンソロジー。上の2つの論考と「哲学者の言語についてのテーゼ」には、独特の唯物論理解に根ざす終生変わらなかったハイデガーやシェーラー的な現象学に対する批判と、ベン...
「哲学のアクチュアリティ」や「自然史の理念」といった、アドルノの思考のモチーフを知る上で参考になる論述を中心に編まれたアンソロジー。上の2つの論考と「哲学者の言語についてのテーゼ」には、独特の唯物論理解に根ざす終生変わらなかったハイデガーやシェーラー的な現象学に対する批判と、ベンヤミンの鍵概念である「星座的布置(Konstellation)」を自家薬籠中の物にしようとするアドルノの思想的格闘のあとが窺える。
Posted by
1920年代から1930年代初頭にかけて、ベンヤミンからの決定的な影響の下で思想形成を遂げつつあったアドルノは、みずからの思想を展開し、表現する足場をも築きつつあった。そのような初期アドルノの思考の足跡とともに、後年まで変わることのない彼の思考の構えとでも呼ぶべきものが本書には...
1920年代から1930年代初頭にかけて、ベンヤミンからの決定的な影響の下で思想形成を遂げつつあったアドルノは、みずからの思想を展開し、表現する足場をも築きつつあった。そのような初期アドルノの思考の足跡とともに、後年まで変わることのない彼の思考の構えとでも呼ぶべきものが本書にはある。ここに収められた講演や断章には、『存在と時間』の時期のハイデガーを批判しつつ、新たな唯物論を構想しようとするアドルノの哲学的な方向性とともに、シェーンベルクらの無調音楽を批判する批評の「反動的」動向に反撃しながら、真の「新音楽」の可能性を語る批評的言説の可能性を探ろうとする、彼の音楽批評ないし美学の方向性も示されているが、こうした方向性は、まず『本来性という隠語』や『否定弁証法』といった晩年の哲学的著作においても明確に貫かれている。また、本書に収められた音楽論は──最晩年の『美学理論』においては音楽に対する態度にいくらか変化が見られるとはいえ──、『新音楽の哲学』などの議論を先取りするものと言えよう。本書には、すでに雑誌に翻訳が掲載されている二つの講演、すなわちフランクフルト大学哲学科の私講師就任記念講演である「哲学のアクチュアリティ」とフランクフルトのカント協会で行なわれた「自然史の理念」に加え、初めて翻訳される「哲学者の言語についてのテーゼ」と「音楽アフォリズム」が収録されているが、1927年頃から10年にわたって書き継がれた、本書のおおよそ半分の量を占める「音楽アフォリズム」はさらに、アドルノの哲学と音楽美学が同じ視点から構想されていることをも示している。総体としての存在を問うことの不可能性を引き受け、その問いの欺瞞を批判しつつ、還元不可能な「意図なき現実」を言葉の「星座的布置」──アドルノがベンヤミンから引き継いだ概念である──のうちに浮かび上がらせようとする彼の哲学は、三和音にもとづく調和的な総体としての音楽の崩壊を引き受けながら、そうした音楽像にしがみつく言説を斥けて、新しい音楽の「暗号」を読み解き、その「破壊的」ですらあるような強度を、やはり「星座的布置」において受け止めようとする音楽論と軌を一にしているのである。このようなアドルノの思考の──ほとんど変わることのない──姿を、彼自身の言葉によって浮き彫りにしている点が、本書の最大の特徴と思われる。また、このような思考の媒体としての言語について、アドルノがベンヤミンの言語哲学の影響の下で、踏み込んだ省察を行なっていたことも、本書が伝えてくれることの一つである。「哲学者の言語についてのテーゼ」においてアドルノは、言語の本質を「名」と捉えるベンヤミンの発送を受け継ぎながら、言葉と事象の関係を恣意的に捉える立場を「観念論的」と批判し、歴史的な事象を唯一無二の仕方で言い表わす言葉を、崩壊した言語が真理を表わす言葉の「布置」を形成する可能性を追求しているのだ。「哲学のアクチュアリティ」においてはその場が、形式と内容が不可分に結びつく美的エッセイであり、そこでは「移ろい」のうちに自然と歴史が弁証法的に絡み合う──これが「自然史」ということである──さまをも捉えられうるという。このように語ることで、初期のアドルノは、ベンヤミンと新たな唯物論という共同戦線を張ろうとしていたのかもしれない。このような彼の行き方が、思考そのものを、またその媒体としての思考をどのように捉え直させるかを測るのは、読者に委ねられていようが、彼の行き方のうちに今日の思考に対する重大な問いが潜在していることは疑いえない。訳文は、一部の訳語の選択に疑問が残るとはいえ、非常に読みやすく仕上げられている。
Posted by
- 1