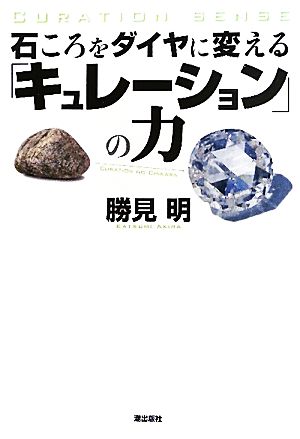石ころをダイヤに変える「キュレーション」の力 の商品レビュー
■キュレーション 1.「キュレーション」は、美術館や博物館で企画や展示に行うキュレーターに由来する言語で、既存のものの意味や価値を問い直し、それらを絞り込み、結びつけて新しい意味や価値を生み出すことを意味する。一言でいえば「編集」である。 2.キュレーションは次の3段階で構成され...
■キュレーション 1.「キュレーション」は、美術館や博物館で企画や展示に行うキュレーターに由来する言語で、既存のものの意味や価値を問い直し、それらを絞り込み、結びつけて新しい意味や価値を生み出すことを意味する。一言でいえば「編集」である。 2.キュレーションは次の3段階で構成される。既存の意味の問い直し(再定義)。要素の選択・絞り込み・結びつけ(新しい編集)。新しい意味、文脈、価値の生成(創発)。
Posted by
キュレーション:ある視点のもとで「情報を収集、分類し、共有する」こと キュレーションは次の3段階で構成される。 1.既存の意味の問い直し(再定義) 2.要素の選択・絞り込み・結びつけ(新しい編集) 3.新しい意味、文脈、価値の生成(創発) キュレーションの成功例としては、「懐...
キュレーション:ある視点のもとで「情報を収集、分類し、共有する」こと キュレーションは次の3段階で構成される。 1.既存の意味の問い直し(再定義) 2.要素の選択・絞り込み・結びつけ(新しい編集) 3.新しい意味、文脈、価値の生成(創発) キュレーションの成功例としては、「懐中電灯機能付き携帯電話」「羽のない扇風機」「iPhone」など。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【知のエコシステム(生態系)】 =環境から知を取り込み、放出していく中で、知と知がジグソーパズルのように結びつき、新たな知が生まれていく循環。 知識創造の場=プラットフォーム 自分たちを取り巻く環境=知の貯水池(多種多様な知が埋め込まれている)p37 【キュレーションとプラットフォーム】 世の中のさまざまな取り組みを「プラットフォーム」として想定し、そこに何を取り込むかを考えると、既存の枠に縛られない自由な発想ができる キュレーションとは「知識創造の場=プラットフォーム」上で新しい意味、文脈、価値を生み出すために行うp40 【キュレーションのプロセス】 ①既存の意味の問い直し(再定義のプロセス) ②要素の選択・絞り込み・結びつけ(新しい編集のプロセス) ③新しい意味・文脈・価値の生成(創発のプロセス) ビジネスや経営における価値観には「競争に勝つ」という、競合相手に対する競争優位性を目指す「相対価値」の追求と、自分たちの理想や思い、信念を大切にする「絶対価値」の追求があります。p74 知識創造理論では「暗黙知」と「形式知」があります。暗黙知とは言葉や文章で表現することが難しい主観的な知で、個人が経験に基づいて暗黙のうちに持つものです。思いや信念、身体に染み込んだ熟練やノウハウなどのは典型的な暗黙知です。一方、言葉や文章、データ等で表現できる明示的で客観的な知が形式知です。知識創造理論では、新しい知は個人の暗黙知に源泉があり、暗黙知から形式知へ、形式知から暗黙知へと相互に変換していくプロセスにより生み出されていくと考えます。そのプロセスを4つのモードでとらえ、各モードの呼び名を頭文字を取り、「SECIモデル」と呼びます。p82 【SECIモデル】 1. 共同化(S= Socialization)=現場で個人が獲得した暗黙知(思い、イメージなど)を共通の体験などを通じて互いに共有し、組織の暗黙知にする。 2. 表出化(E= Externalization)=暗黙知を言葉や図などで表現し、形式知(コンセプトなど)へ転換する。 3. 連結化(C=Combination)= 形式知と他の形式知を組み合わせ、一つの体系として新たな形式知を作りだす。コンセプトを具体化する設計や製品づくりがそれにあたります。 4. 内面化(I= Internalization)=製品づくりなど、新たな形式知をつくり出す経験を通じて、各自が新たな暗黙知を吸収し、血肉化していく。 最先端ビジネスは「再定義」から生まれる=再定義できない企業は生き残れないp154-155
Posted by
新たな成長曲線を描くためには事業の再定義が必要であり、このような考え方が今の自分には必要と思われた。 多くのケースを紹介した本。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
キュレーションの基本的な概念理解に役立つ本。 ポイントとして ・情報の絞り込み ・受け取る側が再構築する ・キュレーションによって「こんなもの・サービスが欲しかったんだ」という潜在的ニーズを満たすことにつながる ・いかに共感をよぶ文脈・コトづくりができるか ・既存の文脈を編集し再構築することで新しい価値を創造する ・ガラパゴス化⇔キュレーション ということを述べている 出だしは新鮮な捉え方を魅力に感じたが、途中から冗長な事例が続き、特に筆者が好んでいるセブンの鈴木氏を称賛する内容が多すぎるのが気になる。
Posted by
カバーの裏にこうある 『20世紀は、送り手の発想で「より多くの価値」「より高い価値」を追求する時代でした。 いっぽう21世紀は、受け手の視点で目利きし、再編集して「より善い価値」「より適した価値」を実現していく、キュレーションの時代に入ろうとしているのです。』 そうだと思う。...
カバーの裏にこうある 『20世紀は、送り手の発想で「より多くの価値」「より高い価値」を追求する時代でした。 いっぽう21世紀は、受け手の視点で目利きし、再編集して「より善い価値」「より適した価値」を実現していく、キュレーションの時代に入ろうとしているのです。』 そうだと思う。言い替えるとキュレーションの時代とは「編集の時代」ということだ。 スティーブ・ジョブスもそういう意味では偉大なキュレーターだったんだとおもう。彼はこう言う。 『「顧客が望むモノを提供しろ」という人もいる。僕の考え方は違う。顧客が今後、なにを望むようになるのか、それを顧客本人よりも早くつかむのが僕らの仕事なんだ。ヘンリーフォードも似たようなことを言ったらしい。「何が欲しいかと顧客にたずねていたら、【足が速い馬】と言われたはずだ」って。欲しいモノを見せてあげなければ、みんな、それが欲しいなんてわからないんだ。だから僕は市場調査に頼らない。歴史のページにまだ書かれていないことを読み取るのが僕らの仕事なんだ。」
Posted by
- 1
- 2