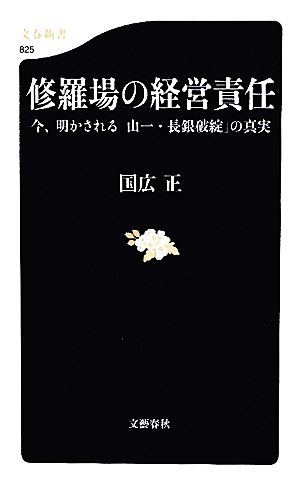修羅場の経営責任 の商品レビュー
八田先生の本に紹介されていたので、読んでみた。 国広先生は内部統制に関するセミナーで講演聞いたことがある程度だけど、本質しっかり掴んでるなあと感じた覚えあり。 で、この本読んで知ったけど、山一破綻のときに活躍された弁護士先生だったんですね。山一破綻については、日経ビジネス人文...
八田先生の本に紹介されていたので、読んでみた。 国広先生は内部統制に関するセミナーで講演聞いたことがある程度だけど、本質しっかり掴んでるなあと感じた覚えあり。 で、この本読んで知ったけど、山一破綻のときに活躍された弁護士先生だったんですね。山一破綻については、日経ビジネス人文庫で読んだ、当事者として破綻劇を目の当たりにしていた石井茂(ソニーフィナンシャルホールディングス社長に)さんの本が面白い。 当事者と外から関わった弁護士、ふたつの側面で読み比べるのも面白そうだけど、国広さんの本はどこかに書棚のどこかにしまってしまった。 石井さんの本は、すぐに取れる場所にある。 いまパラパラ読み返すと、意思決定の基準については、「自己都合という基準」だけがあったという一節が目についた。他人(上司は部下の、部下は上司の判断)に依存し、意思決定の基準は借り物。自分という判断軸がない。Ⅴ、Ⅵは読み応えがある。
Posted by
まえがきの一文が、最も印象に残りました。 最も大切なことは、不祥事という危機に正面から立ち向かう姿勢である。
Posted by
山一と長銀の訴訟に関わった熱き国広弁護士の著書。 「経営責任」と「法的責任」の違いに改めて気付かされた。 <個人メモ> 山一証券の破たん(自主廃業)の1997年11月当時は大学3年生・シューカツ直前のタイミングで、今にして思うと自分自身の職業観・キャリア形成に多大な影響があった...
山一と長銀の訴訟に関わった熱き国広弁護士の著書。 「経営責任」と「法的責任」の違いに改めて気付かされた。 <個人メモ> 山一証券の破たん(自主廃業)の1997年11月当時は大学3年生・シューカツ直前のタイミングで、今にして思うと自分自身の職業観・キャリア形成に多大な影響があったと思われ。
Posted by
タイトルはあまり内容に即しておらず、山一證券と長銀の破綻後の処理に関わった弁護士による回顧録といった趣き。そのあたりに興味がある人にとってはものすごく面白いけど、たぶんいろんなしがらみで書けなかったことも同じくらいたくさんあったのではないかと推察しています。少なくとも長銀では政治...
タイトルはあまり内容に即しておらず、山一證券と長銀の破綻後の処理に関わった弁護士による回顧録といった趣き。そのあたりに興味がある人にとってはものすごく面白いけど、たぶんいろんなしがらみで書けなかったことも同じくらいたくさんあったのではないかと推察しています。少なくとも長銀では政治に絡む話とか根源にあったはずなのだけどそこには言及ないし、人間ドラマとして描くことに終始しているのかな。まぁそれはそれで面白いキャラが多いけど。
Posted by
著名な國廣先生が関わった山一粉飾の調査委員会での経験,そして,長銀事件弁護の苦闘を活写する大変面白い本です。記録文学としても,読み物としても,非常に興味深い。長銀事件での特捜型捜査,国策捜査に触れる部分は,自分が関与した特別背任事件の経験を思い起こさせて感慨無量です。
Posted by
山一の時は学生、長銀の時は社会人1年目だったので全然わけわかっていなかったのですが、両“事件”の内容と歴史上の位置づけ(?)を今更ながら初めて知りつつ、ドラマのような展開内容に、いっきに読み通してしまいました。
Posted by
山一証券の社内調査委員会の一員として、また長期信用銀行の弁護側としての記録。真の経営責任とは何か、冷静に筆者が考察する過程及びそれぞれの経営者の行動の記録を拝見するにつれ目頭が熱くなった。『企業は生き物であり、社会の進化や経済変動によって倒産などで退場を余儀なくされることは往々に...
山一証券の社内調査委員会の一員として、また長期信用銀行の弁護側としての記録。真の経営責任とは何か、冷静に筆者が考察する過程及びそれぞれの経営者の行動の記録を拝見するにつれ目頭が熱くなった。『企業は生き物であり、社会の進化や経済変動によって倒産などで退場を余儀なくされることは往々にしてある。これは経済活動の新陳代謝ともいえる生理現象である。しかし山一の死は経済活動に巻き込まれたことによるやむを得ない生理現象ではなかったー第1章山一証券破綻〜より』 『主文 原判決及び第一審判決を破棄する。被告人はいずれも無罪。 最高裁は不良債権に対して、母体責任に基づく実務慣行が存在してたことを認めたうえ、98年3月には税効果会計が導入されていなかったこと、新基準を適用したのは4行に過ぎないことをあげ98年3月期は過渡的な状況であり、税法上の処理は排除されておらず、したがって長銀の決算は公正な会計慣行に反する違法なものとはいえない。 そして被告を有罪とした第一審判決と高裁判決について事実を誤認して法令の解釈適用を謝ったものであり、破棄しなければ著しく正義に反する。ー第2章長銀破綻〜より』
Posted by
山一証券の自主廃業に際し外部弁護士として社内調査委員会による調査報告書をまとめ、長銀の破綻においては国策捜査による旧経営陣を被告とした粉飾決算疑惑に対し、被告側弁護人として無罪を勝ち取った、その過程についての記述。 会社の不祥事にも色々種類があると思うけれど、「危機管理において...
山一証券の自主廃業に際し外部弁護士として社内調査委員会による調査報告書をまとめ、長銀の破綻においては国策捜査による旧経営陣を被告とした粉飾決算疑惑に対し、被告側弁護人として無罪を勝ち取った、その過程についての記述。 会社の不祥事にも色々種類があると思うけれど、「危機管理において最も大事なのは不祥事に正面から取り組む覚悟と姿勢」とのこと。肝に銘ず。危機管理は正解がないし、お手本もなく、何をやっても非難されるのだから困難極まりない。(だから、本書でも、危機管理を如何に行うかという部分には触れていない。) この本のおもしろいところは、山一でいえば、飛ばしを指揮命令した人など、原因の直接的経営責任にかかわる部分ではなく(山一の調査委員会に関していえば経営陣在任中の調査書なので取締役会の経営責任の一端ではあるとおもうけれど)、自主廃業に追い込まれた山一、破綻して国有化となった長銀の、それぞれ「最終ランナー」と著者が直接かかわっているところ。どちらも、著者から言わせれば「バトンタッチ受けた人」「真実を明らかにしようと立ち向かった誠実な人」。これが実際の責任ある人、山一の社内調査委員会で有責とされた人の弁護とかだったら引き受けたのか、ちょっと気になる。 長銀の方は、引当が妥当であったか、公正な会計慣行に基づいていたかどうかが争点で、10年かけて最高裁までいき、最高裁で原判決・第一審判決を破棄して逆転無罪を勝ち取った法廷闘争についてなので、裁判官の訴訟指揮や、弁護団側の戦略、マスコミ対応など、法律的観点からはとても興味深い。 最終弁論における裁判官・検察への痛烈なあてこすりが秀逸。 「検察官は、実態に目を閉ざして、長銀の最終走者として誠実に難局に立ち向かった被告人らを『粉飾をやるような一握りの悪い経営者』に仕立て上げて処罰し、国民の溜飲を下げさせようとするものである。この検察官の姿勢に迎合する原判決が維持されれば、わが国経済の将来に重大な禍根を残すことになるだろう」
Posted by
破綻企業における経営責任の所在というテーマで、山一証券の社内調査報告書作成と、長銀の弁護を担当した弁護士が、それぞれの経緯を綴った本。 山一と長銀の破綻処理スキームに関する解説を期待して手に取ったが、そういった観点の記述は非常に少ない。その意味では個人的に"失敗&qu...
破綻企業における経営責任の所在というテーマで、山一証券の社内調査報告書作成と、長銀の弁護を担当した弁護士が、それぞれの経緯を綴った本。 山一と長銀の破綻処理スキームに関する解説を期待して手に取ったが、そういった観点の記述は非常に少ない。その意味では個人的に"失敗"だったが、十分な情報も知識もないのに関係者に責任を取れと迫る世論の安易さ、これに乗っかり国策捜査を行う検察のずさんさ・強引さを、非常にシンプルな文章で世に問うており、記録として大変貴重。 ただし、経営責任の所在という中心テーマの掘り下げはほとんどなされていない。単に、『経営責任に絡んだ二つの事案の具体的経緯を、著者の散発的な所感を散りばめながら、記述しただけ』で終わっているのは、残念。
Posted by
山一・新生の破綻に関連した有名弁護士の回顧録のようなもの。興味深かったし読みやすかった。が、特に得るもの無し。
Posted by
- 1
- 2