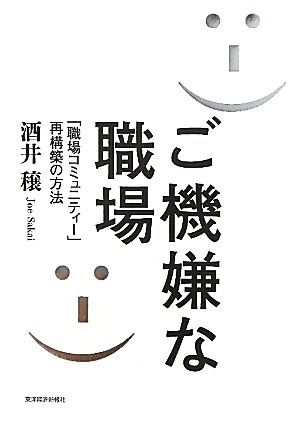ご機嫌な職場 の商品レビュー
酒井さんは多作だ。しかも単に焼き直しだったり、手軽な対談ものであったりすることはほとんどない。ざっと見てみる。 ①『はじめての課長の教科書』 2008年2月 ②『あたらしい戦略の教科書』 2008年7月 ③『英会話ヒトリゴト学習法』 2008年10月 ④『「日本で最も人...
酒井さんは多作だ。しかも単に焼き直しだったり、手軽な対談ものであったりすることはほとんどない。ざっと見てみる。 ①『はじめての課長の教科書』 2008年2月 ②『あたらしい戦略の教科書』 2008年7月 ③『英会話ヒトリゴト学習法』 2008年10月 ④『「日本で最も人材を育成する会社」のテキスト』 2010年1月 ⑤『これからの思考の教科書』 2010年9月 ⑥『リーダーシップでいちばん大切なこと』 2011年3月 ⑦『ビジネス英会話のプロがやっているシンプル英語学習法』 2011年7月 そしてこの本が2011年8月だ。 更にはこの本の後にも ⑨『料理のマネジメント キッチンを制する者がビジネスを制す!』 2011年11月 ⑩『君を成長させる言葉』 2012年1月予定 が続く。 2009年の著作がないが、ここは④でも紹介されたフリービットでの人材育成プログラムに関わっていた時期なのではないだろうか。 とにかく、できる人という印象がある。まわりのことに問題意識を持ってそれを整理することに長けている人なのかもしれない。そのこと自身を学ぶべきなのかもしれない。 ⑨なんかまだ読んでないが手を広げ過ぎでは?と思う。 本書では、「職場コミュニティ」の重要性を説いている。明るい職場が絶対的に必要だと。コミュニティ、コミュニケーションの喪失が根本的な問題であるという問題提起といくつかの解決策、実践案を提案している。実際には社内コミュニケーションに対しては消極的な冷めた立場を取る人も多いだろうけれども、もっと見直されてもいいだろう。 そう言えば入社したての頃は、課レクで伊豆に一泊旅行をしたこともあったな。ああいう制度はなかなか受け入れられないんだろうな。 当時、進んで参加していたわけではなかったが。 --- 紹介された読書手当の支給はうらやましい。最後に置かれた読書の重要性のコラムも秀逸。 --- 「書くことは、僕だ」 - 著者のブログ http://nedwlt.exblog.jp/17260814/ そういうことなんだ。
Posted by
新著は必ず買うことに決めている酒井穣さんによる「職場コミュニティ」再構築の方法論。 明るい職場をつくることは経営課題として絶対に必要なのだ、という筆者の主張とそのための具体論が満載。 それにしても、かつて地域コミュニティは職場コミュニティにとって代わられて廃れた。いま職場コミュ...
新著は必ず買うことに決めている酒井穣さんによる「職場コミュニティ」再構築の方法論。 明るい職場をつくることは経営課題として絶対に必要なのだ、という筆者の主張とそのための具体論が満載。 それにしても、かつて地域コミュニティは職場コミュニティにとって代わられて廃れた。いま職場コミュニティは崩壊の危機にあるが、それは無数のインターネットを通じたSNSなどのコミュニティが発達したことの裏腹であるという見立ては慧眼である。 僕も「こんないい本よんだよ!」ってこうしてブクログやブログで共有したりするけど、職場でオフィシャルにやることはないものなぁ。
Posted by
ご機嫌な職場が失われた理由と職場コミュニティ回復の為の開発理論と方法が纏められた一冊。グローバル化(同一職業、同一賃金、フラット化)とSNS、NPOの台頭の中で、職場のコミュニケーションスタイル(情報伝達、問題対応、対話、個別対応、人間関係維持の5つの形)のバランス再考とモチベー...
ご機嫌な職場が失われた理由と職場コミュニティ回復の為の開発理論と方法が纏められた一冊。グローバル化(同一職業、同一賃金、フラット化)とSNS、NPOの台頭の中で、職場のコミュニケーションスタイル(情報伝達、問題対応、対話、個別対応、人間関係維持の5つの形)のバランス再考とモチベーションとの関係を示した上で、インターネットを介した競合コミュニティーへの対応、理念への議論の活性化、仲の良い職場がもつ意義と非公式なコミュニケーションを念頭に置かせた打ち手(懇親会のデザイン、中だるみを防止するファシリテーション、ピークエンドの法則等)を紹介していく。メモ(1)学習と自らの行動の基準や行動の前提となる理論を変更したり修正したりすること。学習のモードには2つ、①問題を発見し、問題を解決改善するために行動の基準となる理論の公立や効果を高めようとするシングルループ学習、②問題を解決する為に、理論自体を変えるダブルループ学習、がある。(2)表現力というものは読解力があって初めて養われる。高度に圧縮された文字情報は干し椎茸と同様であり、読書は解凍、圧縮のトレーニングになる
Posted by
職場は目的をもった組織であり、人間にとって重要なコミュニティ。集団への親和欲求の薄れ、他人への関心度の低下から、ネットを通じて職場外に無数のコミュニティが形成され始めた。フリービットがコミュニティ科学や心理学の理論を踏まえて設計し実践する9つの対策を紹介する。明るい職場はなんとな...
職場は目的をもった組織であり、人間にとって重要なコミュニティ。集団への親和欲求の薄れ、他人への関心度の低下から、ネットを通じて職場外に無数のコミュニティが形成され始めた。フリービットがコミュニティ科学や心理学の理論を踏まえて設計し実践する9つの対策を紹介する。明るい職場はなんとなく生まれるのではなく、一人ひとりが意識して作り上げるもの。従業員間で意義を浸透させ協力を得ることが重要だと説く。
Posted by
酒井さんの著書を読むのは3作品目だが、それぞれその視点や分析内容、説明の分かりやすさになるほどと思わされる。 昨今、職場の雰囲気が良くならないのは、社内のコミュニケーションが不足しているためで、対策として社内コミュニケーションを良くしようという類のことをよく耳にするが、その...
酒井さんの著書を読むのは3作品目だが、それぞれその視点や分析内容、説明の分かりやすさになるほどと思わされる。 昨今、職場の雰囲気が良くならないのは、社内のコミュニケーションが不足しているためで、対策として社内コミュニケーションを良くしようという類のことをよく耳にするが、その本当の原因や対策についてはほとんど納得できるものは見当たらなかった中で、本書から大きなヒントを得たような気がしている。 本書では「明るい職場」は「絶対につくる必要があるもの」であるが、実際には職場コミュニティーが弱体化しているとして、その原因を欲求理論、イノベーション理論、コミュニケーション理論などの視点から明らかにしている。そしてその原因についての対策を、9つの理論(仮説)を用いて説明している。そのうえで、理論だけでなく著者が役員を務める会社で実践されている内容を結構具体的に紹介してくれている。 もちろん、著者の述べていることが他の会社にそのまま当てはまることはないだろうが、ヒントにはなると思う。 また色々な理論を駆使して説明されているが、要は人間が持つ「自分勝手に振る舞いたいが、他者からも好かれたい」という矛盾した欲求を理解し、ケアしていくことが大事なのではないかと感じた。著者も書いておられるが、経営学とは結局のところ人間学なんですね。
Posted by
以前酒井さんの講演で衝撃を受けた内容が本になりました。読んでみて何故衝撃を受けたのかを考えさせられました。私が社会人になった頃は自分の周りは、家族と会社と地域でほぼ100%だったでしょう。ただ、Internetが出てきた事で、今そしてこれからは+αで"思いを同じくする仲...
以前酒井さんの講演で衝撃を受けた内容が本になりました。読んでみて何故衝撃を受けたのかを考えさせられました。私が社会人になった頃は自分の周りは、家族と会社と地域でほぼ100%だったでしょう。ただ、Internetが出てきた事で、今そしてこれからは+αで"思いを同じくする仲間"が、自分のコミュニティの一つとして含まれます。その時に、これまでは会社の中で、積極的にまたは折り合いをつけながら"やりたい事"を見つけてきた人々が、会社という枷を超えて自己実現を目指して行動し始めるでしょう。故にその人にとって会社・職場にいる意味は、日々の糧を稼ぐため、になっても何らおかしくはないはずです。その時に、今の私が感じている会社観や職場観が通用するのか…、そんな環境に自分はついていけるのか…、正直コワくなりました。考えすぎかもしれませんが、イノベーションのジレンマにあるように、水面下の変化は急激に広がり、今の価値観を破壊します。自分に起こすべき変化は何か、改めて考えたいと思いました。
Posted by
酒井さんの本はいつも通り読みやく、わかりやすかった。 職場を学習する場としてとらえたとき、助け合う(互酬性)が大事だということ。いっぽうで、企業組織のコミュニティーが危機を迎えていることが、理論をまじえて説明されている。 酒井さんが実際にどのような対応を行っているかの対策案も、...
酒井さんの本はいつも通り読みやく、わかりやすかった。 職場を学習する場としてとらえたとき、助け合う(互酬性)が大事だということ。いっぽうで、企業組織のコミュニティーが危機を迎えていることが、理論をまじえて説明されている。 酒井さんが実際にどのような対応を行っているかの対策案も、アイデアとして面白い。もちろんこれが万能な処方箋ということではないが。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・「絶対に明るい職場を作る必要がある」そう断言する著者は、職場コミュニティーが弱体化する現状を踏まえ、その原因と解決について話を進めていく。 ・特に興味深かったのは、その原因において、大きく3つのコミュニティ破壊が起こっていると言う。それは、人間の欲求の間に起こるジレンマ、イノベーションのジレンマ、職場の公式コミュニケーションと非公式コミュニケーションのジレンマである。フィルムカメラからデジタルカメラに市場が取って代わる「破壊的イノベーション」が、移動手段のイノベーション(電車や車など交通機関の発達からインターネットや情報手段)に重ねることができる。イノベーションとはどのような流れの中で発生するのか、とても理解しやすく述べられていた。 ・そのイノベーションの中で自分がどのように、新しいものを捉えていく必要性があるか、気づかされた。 ・第3章で紹介されている社内のミニブログで書評を勧める運用に触発され、私も個人的に短文でも良いから、書録をしていこうと思い実施することにした。 ・巻末のコラム「読書重要性」については、テレビ、インターネットを代表とした情報収集手段が多様化する中、読書の差別化について、納得させられるコラムだった。
Posted by
ご機嫌な職場がなぜ必要なのか、なぜご機嫌な職場が失われたのか、どうすればご機嫌な職場が作れるのか、そんな内容について具体的実践例を交えてわかりやすく記載されている。 著者である酒井さんは、日々の業務で感覚的につかんでいることを論理的に文章にすることができる天才だと思う(笑)。どの...
ご機嫌な職場がなぜ必要なのか、なぜご機嫌な職場が失われたのか、どうすればご機嫌な職場が作れるのか、そんな内容について具体的実践例を交えてわかりやすく記載されている。 著者である酒井さんは、日々の業務で感覚的につかんでいることを論理的に文章にすることができる天才だと思う(笑)。どの著書を読んでもそう思う。個人的には合間に記載があるコラムが好きだったりします。そこだけ立ち読みしてもいいかも・・・
Posted by
尊敬する人の考え方、大事にしている言葉がたくさん出てきて、自分の頭の中の整理ができた。また、いくつかの「なるほど、そういうとらえ方をすればいいのか」というヒントをいただいた。
Posted by